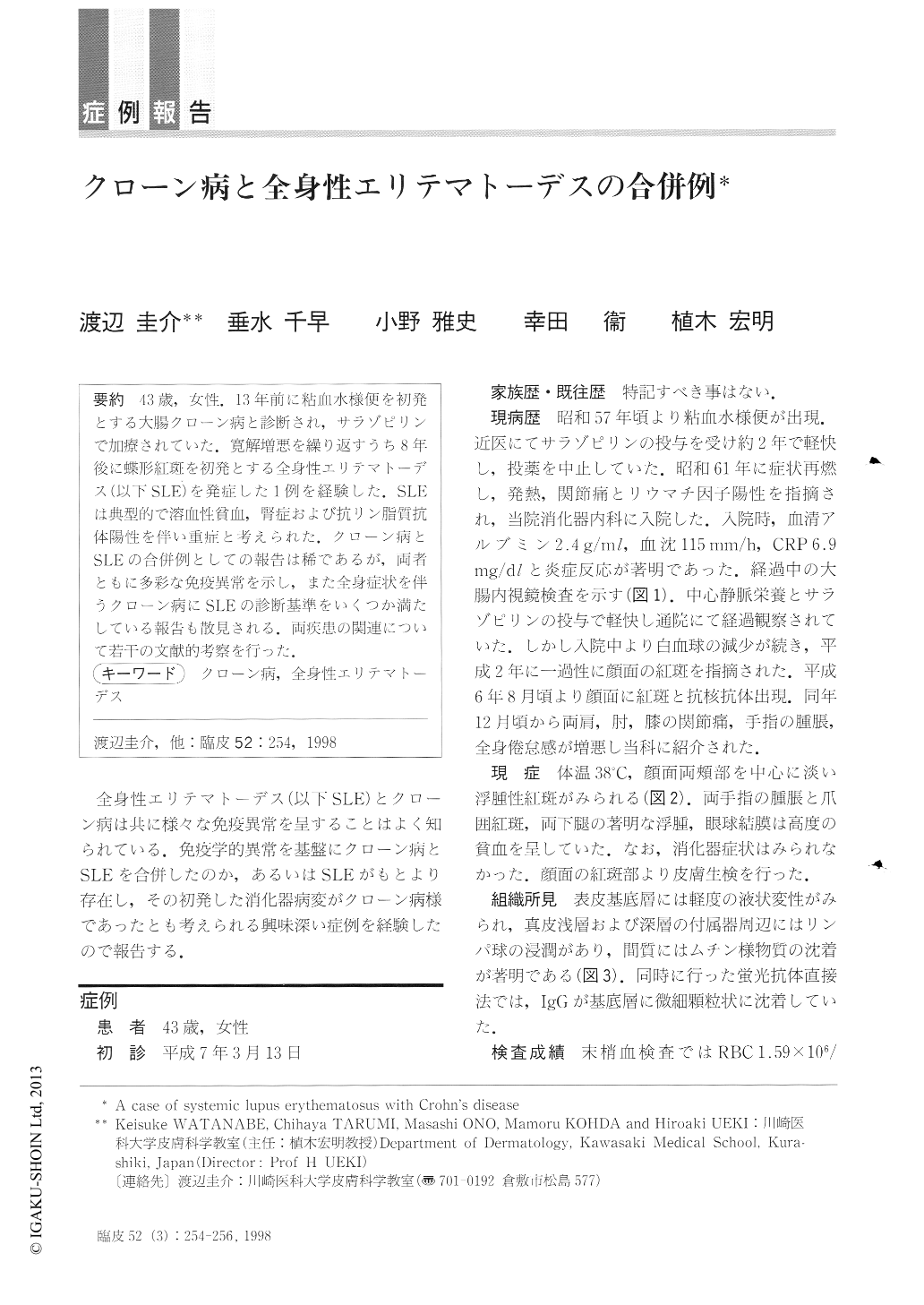1 0 0 0 OA 色落ち海苔の多糖を活用した免疫機能性食品素材の開発
海苔の色落ちは天候やその他の要因で発生するが商品とはならずほとんどが廃棄されている。これを有効利用するため海苔の細胞壁に多量に含まれる粘性のある酸性多糖であるポルフィランを効率的かつ短時間で調製した。精製ポルフィランの免疫細胞に与える影響をマウスのマクロファージ培養細胞(J774. 1)とリポ多糖(LPS)に対する応答性が高いC3H/ HeN系マウスの脾臓細胞で検討した結果、細胞性免疫を増強するサイトカインであるインターロイキン(IL)-12とンターフェロン-γの産生誘導が乳酸菌やLPSと同様に認められ、マクロファージ上のToll様受容体4を介してLPSと同様にIL-12の産生を増強していることが示唆された。また、腫瘍壊死因子あるいは過酸化水素で刺激したヒト腸管上皮様細胞株Caco-2細胞で産生増強される炎症性サイトカインであるIL-8の産生をポルフィランと乳酸菌は抑制し、経上皮電気抵抗値で測定した腸管のバリア損傷に対する抑制効果もポルフィランに認められた。以上のことから、食物として摂取している海苔中のポルフィランには細胞性免疫の賦活化作用と腸管細胞での抗炎症作用といった乳酸菌と同様な健康機能効果があると考えられた。
- 著者
- 篠原 主勲 奥田 洋司
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 最適化シンポジウム講演論文集 2008.8 (ISSN:24243019)
- 巻号頁・発行日
- pp.25-30, 2008-11-26 (Released:2017-06-19)
To obtain the optimal shape of a 3D object minimizing the fluid traction, an adjoint variable method based on the variational principle is formulated and applied to the finite element method. The optimality condition of the present method consists of the state equations, the adjoint equations, and the sensitivity equations. In high Reynold's number cases, shape optimization methods are demanded that the initial shape be sufficiently close to the optimal shape and that Korman vortices not be present in the computational domain. Therefore, these methods were geneally applied to the steady state of the flows. In the present paper, the 3D adjoint variable method used to decrease the traction force of an object in unsteady flow is formulated by using FEM. The particularity of this method resides in the fact that both the start of the test time and the end of the test time in the optimization are determined by the stationary condition of the Lagrange function. The state variable is calculated from the start of the test time to the end of the test time in forward time and this data is saved, while the adjoint variable is calculated in backward time by using the saved data. The algorithm of the method is implemented using HEC-MW. By using the prepared algorithm, robust convergence of the cost function can be attained. This robustness makes possible the shape optimization even under unsteady flow containing Karman vortices.
1 0 0 0 建設機械
- 著者
- 建設機械編集委員会 編
- 出版者
- 日本工業出版
- 巻号頁・発行日
- vol.2(2), no.7, 1966-02
1 0 0 0 OA 大師御請来梵字真言集
1 0 0 0 OA 梵文普賢行願讃
- 著者
- 泉 芳璟
- 出版者
- 大谷学会
- 雑誌
- 大谷学報 = THE OTANI GAKUHO (ISSN:02876027)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.152-208, 1929-06
1 0 0 0 OA 南アフリカ共和国Witwatersrand盆地のシュードタキライト
- 著者
- 久田 英子
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.1, pp.1-16, 2001-02-25 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 103
The Vredefort Dome, located in the central part of the Witwatersrand Basin in South Africa, is the type locality for pseudotachylite. Pseudotachylite at the Vredefort Dome is generally regarded to be of impact origin. Pseudotachylites which are closely associated with faults are, however, also known to be common along the northern and northwestern edges of the Witwatersrand Basin. In order to compare pseudotachylites from the Vredefort Dome and from the surrounding Witwatersrand Basin, different studies were undertaken in the past. Mode of occurrence, microscopic textures, geochemical analyses and chronological measurements of pseudotachylites are briefly reviewed in this paper.In the Vredefrot Dome, pseudotachylites are commonly observed except in the central part of its core. In the surrounding Witwatersrand Basin, they are reported from drill core sections and in underground workings. The matrix in pseudotachylite from the Vredefort Dome is mostly a recrystallized melt phase, while those from the surrounding Witwatersrand Basin seem to be composed of clastic material. Pseudotachylites both from the Vredefort Dome and the surrounding Witwatersrand Basin are geochemically closely related to their host rocks. Although evidence for more than one generation of pseudotachylite has been presented, both in the Vredefort Dome and the surrounding Witwatersrand Basin, it is widely believed that most of them were formed as a result of the Vredefort impact event (ca. 2.0 Ga). Other fault rocks reported from the surrounding Witwatersrand Basin are older than the pseudotachylites and therefore not related to their formation.
1 0 0 0 OA 議事録未作成問題の経緯と現状 : 東日本大震災・原発事故対応会議から閣議へと展開
1 0 0 0 OA 鰹節について
- 著者
- 宮下 章
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 食生活総合研究会誌 (ISSN:0917303X)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.30-33, 1993-03-30 (Released:2011-01-31)
1 0 0 0 OA オランウータンの代理母は子供の面倒を見るのか?
- 著者
- 川上 礼四郎 伊藤 太郎 本田 豊 黒田 峻平
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement 第33回日本霊長類学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.78-79, 2017-07-01 (Released:2017-10-12)
東京都動物園協会の多摩動物公園では,育児放棄されたボルネオオランウータン(Pongo pygmaeus,以下オランウータン)のチェリア(メス,2歳)に代理母であるジュリー(メス,51歳)を充てるという国内初の試みが行われている。そのため,代理母を充てた血縁関係のない親子の行動を血縁関係のある親子の行動と比較して考察していこうと考えている。過去に行った血縁関係のある親子間におけるオランウータンの社会的行動に関する研究では,ワカモノ以下の個体は母親だけでなく血縁関係のない個体とも身体接触を伴う社会的交流を行うのに対し,オトナは自身の子供としか交流を行わないという結果になった。また,ワカモノ以下の個体の方がオトナの個体に比べ単独行動時間が短く,また,血縁関係のない個体と個体間距離が短くなる時間が多いと考えられた。そこで本研究では「血縁関係がある親子,ない親子でも交流時間や個体間距離が短くなる時間は大きく変わらない」という仮説を立て,それを検証するために「母親(子供)と交流する時間」「母親(子供)と個体間距離が短くなる時間」を記録し,その結果を血縁関係がある親子(2組)と血縁関係がない親子(1組)で比較する予定である。調査は東京都動物園協会の多摩動物公園において4/23~6/18まで計13回,9:45~16:45まで行う予定である。調査対象は血縁関係がないジュリー(オトナメス,51歳)とチェリア(アカンボウ,2歳)の親子,血縁関係があるチャッピー(オトナメス,43歳)とアピ(アカンボウ,3歳)の親子,同じく血縁関係があるキキ(オトナメス,16歳)とリキ(コドモ,4歳)の親子である。収集したデータをもとに,代理母を充てることによる子供の行動変化について考察を行う予定である。
1 0 0 0 「保守革命」宣言 : アンチ・リベラルへの選択
- 著者
- 栗本慎一郎 安倍晋三 衛藤晟一著
- 出版者
- 現代書林
- 巻号頁・発行日
- 1996
1 0 0 0 クローン病と全身性エリテマトーデスの合併例
- 著者
- 渡辺 圭介 垂水 千早 小野 雅史 幸田 衞 植木 宏明
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床皮膚科 (ISSN:00214973)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.254-256, 1998-03-01
43歳,女性.13年前に粘血水様便を初発とする大腸クローン病と診断され,サラゾピリンで加療されていた.寛解増悪を繰り返すうち8年後に蝶形紅斑を初発とする全身性エリテマトーデス(以下SLE)を発症した1例を経験した.SLEは典型的で溶血性貧血,腎症および抗リン脂質抗体陽性を伴い重症と考えられた.クローン病とSLEの合併例としての報告は稀であるが,両者ともに多彩な免疫異常を示し,また全身症状を伴うクローン病にSLEの診断基準をいくつか満たしている報告も散見される.両疾患の関連について若干の文献的考察を行った.
1 0 0 0 OA How Do Japanese EFL Learners Elaborate Sentences Complexly in L2 Writing? Focusing on Clause Types
- 著者
- Yoshito NISHIMURA Yu TAMURA Kazuhisa HARA
- 出版者
- The Japan Society of English Language Education
- 雑誌
- 全国英語教育学会紀要 (ISSN:13448560)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.209-224, 2017-03-31 (Released:2018-04-10)
- 参考文献数
- 27
Syntactic complexity has traditionally been measured by “macro-perspective measures,” which provide a paucity of angles from which to examine how learners actually elaborate a sentence. Mixing up a large variety of clauses with only “the number of clauses” or “subordination ratios” could lead to overlooking desired relationships between complexity and proficiency or task manipulation and linguistic performance. The current study attempted to capture the features of writing syntactically complex sentences through “micro-perspective measures,” such as clause types (main clauses, coordinate clauses, adverbial clauses, relative clauses, complement clauses, and non-finite clauses), and differences in learner proficiency levels. Participants were 28 Japanese EFL learners. Proficiency was operationalized via argumentative essay scores. To elicit syntactic knowledge, we offered the participants a specialized task that restricted the number of sentences in describing a plot consisting of six related illustrations. The results revealed that coordinate clauses, relative clauses, and non-finite clauses are more frequently produced in elaborating syntactic structures, irrespective of the writer’s proficiency level. Our findings also indicated that non-finite clauses are a more practical expedient for proficient learners than less proficient ones. Some pedagogical implications are also discussed.
1 0 0 0 OA 水田における表層剥離の発生機構
- 著者
- 村岡 哲郎 鴨居 道明 則武 晃二
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.227-232, 1997-11-25 (Released:2009-12-17)
- 参考文献数
- 8
水田における表層剥離の発生機構を明らかにするために, 外見的な土壌剥離膜の変化と剥離膜内における藻類の構成割合の変化との関係を経時的に調べた。さらに剥離膜形成の初期段階における珪藻類 (Bacillariophyceae) の役割を調べた。水稲栽培圃場において, 剥離膜は次のような段階を経て形成された。まず, 代かきによって地表面に浮上した微細な土壌粒子が, 珪藻類の運動によって速やかに凝集し, 淡い褐色を帯びた薄膜が形成された。その後, 珪藻類が急速に増殖し優占化することにより, 土壌粒子の凝集が更に進むとともに, 藻類の光合成作用によって生じた酸素が膜上で気泡となって浮力が生じ, 膜の浮上が始まった。次に, この浮上膜内でユレモ類 (Osillatoria sp.) 等の糸状の藍藻類 (Cyanophyceae) の増殖が始まり, やがて, これらが優占化した。その結果, 剥離膜の表面は緑色の繊維状を呈し, これら糸状の藍藻類が凝集した土壌粒子を緊縛することにより, 剥離膜の強度はさらに増加することが判明した。
1 0 0 0 OA 可溶性ピロリン酸第一鉄塩に関する研究
- 著者
- 高橋 強
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.6, pp.469-473, 1970-12-05 (Released:2010-02-22)
- 参考文献数
- 5
硫酸第一鉄にピロリン酸ナトリウムを反応させてコロイド状のピロリン酸第一鉄塩を生成させる際に, 硫酸第一鉄に添加するピロリン酸ナトリウム量を種々に変えたときの可溶性鉄量を調べた. ピロリン酸ナトリウム添加量が反応当量点付近のときに, 可溶性鉄量は最も少ない. 反応当量点付近で得られたピロリン酸第一鉄液は, コロイド状であり, 熱およびpHの変化に安定であり, かつまた可溶性鉄量が少ないからタンニンに対する反応性が少なく, 油脂に対する酸化触媒として作用することが少ないことを示唆するものと考えられる. しかしこのコロイド状ピロリン酸第一鉄液をろ過風乾すると, コロイド性がまったく失われ, しかも大部分の鉄が第二鉄に酸化されてしまう.このコロイド状ピロリン酸第一鉄液をそのコロイド性を失わせることのないように粉末化させるために, デンプンの酸分解または酵素分解によって調製した溶性多糖類溶液に添加して, 熱風噴霧乾燥を行なうことによって, 粉末状のピロリン酸第一鉄塩を得た. このものは水に溶かしたとき, コロイド状に復元し, かつ第一鉄の形を保持している. この粉末状ピロリン酸第一鉄塩がコロイド性を保持しているのは, 噴霧乾燥時にコロイド状鉄塩が一部含水の形で微粉化されると共に, デンプン分解物の粘度と還元力が一部関与しているものと考えられる.この粉末状ピロリン酸第一鉄塩を粉乳ならびにホットケーキに強化したときの影響について調べたが, これら食品に悪影響を与えなかった.
1 0 0 0 OA Personal CGMおよびProfessional CGMの測定精度の検討
- 著者
- 楠 宜樹 勝野 朋幸 中江 理絵 渡邉 佳穂里 角田 拓 越智 史浩 徳田 八大 赤神 隆文 美内 雅之 宮川 潤一郎 難波 光義
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.9, pp.715-720, 2015-09-30 (Released:2015-09-30)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2
血糖自己測定(SMBG)に加えて持続血糖モニター(CGM)が血糖変動の評価に使用されている.本試験ではProfessional CGM(Pro-CGM)とPersonal CGM(Per-CGM)によるグルコース値の測定精度を評価する.1型糖尿病患者8名にPro-CGMおよびPer-CGMを同時に装着してセンサーグルコース値(SG)を測定し,SMBGで得られた血糖値(BG)との相関について検討.Pro-CGMおよびPer-CGMで得られたSG値とBG値とはそれぞれ強い正の相関を示した.Pro-CGMのSG値とBG値での平均絶対偏差は12.3±13.8 %,Per-CGMのSGとBGでの平均絶対偏差は13.7±12.6 %と両CGMの精度は同程度であった.日本で使用可能なPro-CGMとPer-CGMともにBGと強い相関を示し,血糖変動の評価に有用である.
1 0 0 0 埼玉県川越市郊外の水田産珪藻類
- 著者
- 安藤 一男
- 出版者
- 埼玉県立自然の博物館
- 雑誌
- 秩父自然科学博物館研究報告 (ISSN:05291305)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.1-5, 1966-03