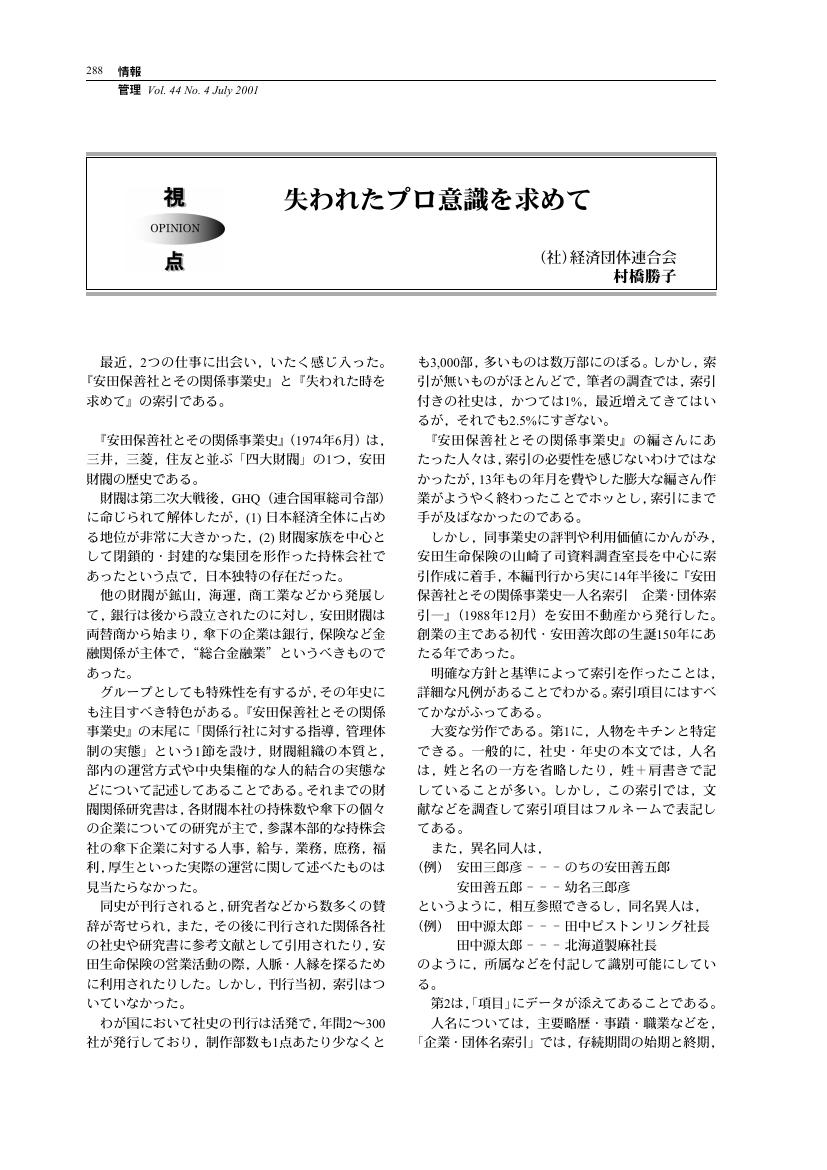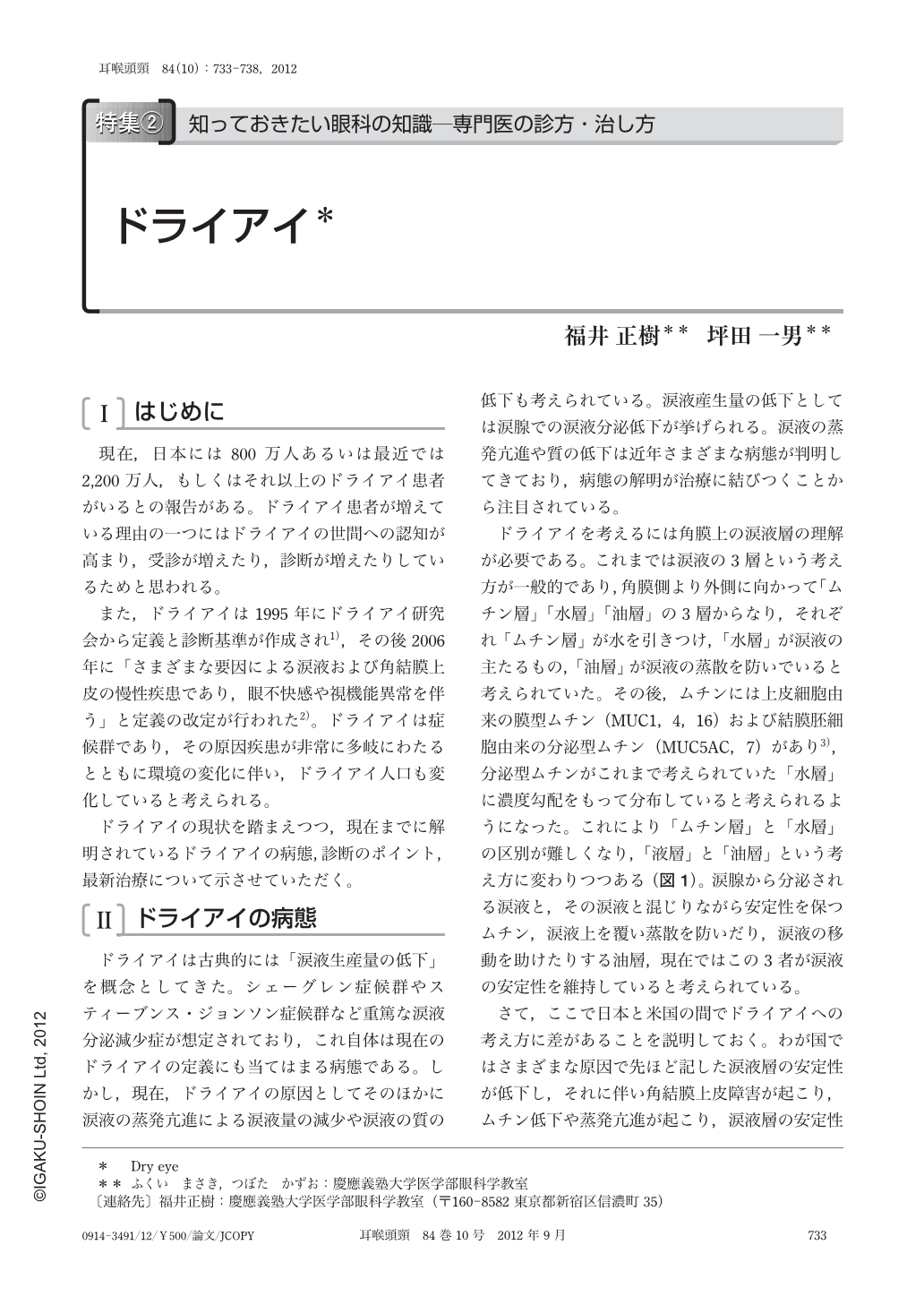1 0 0 0 OA 進化心理学の夜明け(1995年度日本基礎心理学会第2回フォーラム発表要旨)
- 著者
- 長谷川 寿一
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.46-48, 1996-09-30 (Released:2016-11-16)
1 0 0 0 OA Significant Species Differences in Intestinal Phosphate Absorption between Dogs, Rats, and Monkeys
- 著者
- Yasuhiro ICHIDA Naoto HOSOKAWA Ryushi TAKEMOTO Takafumi KOIKE Tasuku NAKATOGAWA Mayumi HIRANUMA Hitoshi ARAKAWA Yukihito MIURA Hiroko AZABU Shuichi OHTOMO Naoshi HORIBA
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.60-67, 2020-02-29 (Released:2020-02-29)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 9
A treatment for hyperphosphatemia would be expected to reduce mortality rates for CKD and dialysis patients. Although rodent studies have suggested sodium-dependent phosphate transporter type IIb (NaPi-IIb) as a potential target for hyperphosphatemia, NaPi-IIb selective inhibitors failed to achieve efficacy in human clinical trials. In this study, we analyzed phosphate metabolism in rats, dogs, and monkeys to confirm the species differences. Factors related to phosphate metabolism were measured and intestinal phosphate absorption rate was calculated from fecal excretion in each species. Phosphate uptake by intestinal brush border membrane vesicles (BBMV) and the mRNA expression of NaPi-IIb, PiT-1, and PiT-2 were analyzed. In addition, alkaline phosphatase (ALP) activity was evaluated. The intestinal phosphate absorption rate, including phosphate uptake by BBMV and NaPi-IIb expression, was the highest in dogs. Notably, urinary phosphate excretion was the lowest in monkeys, and their intestinal phosphate absorption rate was by far the lowest. Dogs and rats showed positive correlations between Vmax/Km of phosphate uptake in BBMV and NaPi-IIb expression. Although phosphate uptake was observed in the BBMV of monkeys, NaPi-IIb expression was not detected and ALP activity was low. This study revealed significant species differences in intestinal phosphate absorption. NaPi-IIb contributes to intestinal phosphate uptake in rats and dogs. However, in monkeys, phosphate is poorly absorbed due to the slight degradation of organic phosphate in the intestine.
1 0 0 0 IR 合理性についての規範的アプローチ : 経済的・社会的規範と合理的選択について
- 著者
- 喜治 都
- 出版者
- 玉川大学経営学部
- 雑誌
- 論叢 : 玉川大学経営学部紀要
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.41-59, 2013
経済学における経済主体の合理的選択は,果たして個人の厚生や社会的厚生に寄与しているのであろうか。本稿では経済学で主要な役割を果たしてきた合理的経済人に見られる「合理性」の概念について,経済学の誕生以来の人間観の変遷から辿り,その限界について考察するとともに,規範的経済学の観点からより広義の合理性の概念の可能性について考察することを目的とする。第1節では,合理性の概念について概観し,自己利益追求のみを目的とした合理的選択の限界について明らかにする。続く第2節では,経済学誕生以来の人間観の変遷をたどり,自己利益が行動目的としてどのように位置づけられてきたか,また他者との相互依存関係を考慮した場合にそれが自己利益にどう影響するかなど,他者を配慮した経済主体について見ていく。最後に3節では,経済的規範と社会的規範に従う社会的存在としての人間に焦点を当て,社会的厚生について考える際の規範的アプローチの重要性を示していく。教育サービスを価値財の例として取り上げ,社会的厚生を高めるようなしくみを構築する上で,共通の価値観や信念に基づいた規範が重要な役割を果たすことを明らかにする。
1 0 0 0 OA J・D・シンガー編『戦争の相関研究』
- 著者
- 黒川 修司
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.1981, no.67, pp.159-163, 1981-05-25 (Released:2010-09-01)
1 0 0 0 OA ネットワーク分析による政治的つながりの可視化
- 著者
- 土屋 大洋
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.155, pp.155_109-125, 2009-03-20 (Released:2011-07-10)
- 参考文献数
- 30
This paper analyzes political connections using a method based on network theory. Recent developments in network theory, which have been accelerated by advances in computers and data collection, can be applied to various research areas including physics, information society studies, sociology and other social sciences.This paper uses network theory to analyze networks among U.S. senators who submitted bills related to Japan in the 109th Congress, focusing on cosponsorship of bills. Senators sometimes submit bills with other senators to make them more prospective, to gain more attentions, or just to deal with political bargains. This paper assumes that senators who co-submit bills more often have tighter connections and organize wider networks. Although it is difficult for an outsider to know who has what kinds of connections with whom in politics, it is easier to track who acted with whom in co-sponsoring bills in Congress.The results of the analysis show that Japan-related bills were led by influential leaders in the senate such as Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton and Joseph Lieberman, who played important roles in the 2008 Presidential election. They were active in submitting and co-sponsoring bills and had higher scores in network indexes such as degree, between centrality, and closeness centrality. This implies two possible hypotheses. First, those influential leaders themselves were interested in Japan-related issues. Second, no specific senators were interested in the issues and that is why the influential senators seemed to be leading. These hypotheses should be tested in combination with other analytical methods.Network analysis has three advantages. First, it focuses more on relationships among actors instead of looking at the characters of individual actors. Most of conventional analysis methods look at who actors are and what they do. In contrast, network analysis focuses on who is connected to whom and how. Second, the development of network analysis and data collection could give us alternative perspectives and new results based on large amounts of data. Third, network analysis could be used not only for proving hypotheses, but also for finding new ones.Network analysis can be applied both to case studies in international relations and to enriching the theories of international relations. Actors in international relations vary from nation states (or governments), multi-national or global corporations, non-profit or non-state organizations, and even to individuals. Network analysis tells how they are connected and how they are interacting. It should reveal more dynamic relations rather than stable structures.
1 0 0 0 OA 生活質の定量化に基づく社会資本整備の評価に関する研究
- 著者
- 林 良嗣 土井 健司 杉山 郁夫
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.751, pp.55-70, 2004-01-20 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 11 3
近年, 社会資本整備に際しては費用便益分析法などの評価手法が定着しつつあるが, 一方で市民が持つ多様な価値観を反映できる総合的な評価指標が必要とされている. 費用や便益の最終帰着先である市民生活の状態を測るための指標である Quality Of Life (QOL) は, 広範囲な分野をカバーする性質上, 要素毎の評価を総合する段階で相互の重み付けを避けて通れない性質を持つ. 本論文ではQOLを5つの評価要素から説明し, これを市民の充足度に基づき計測する方法を提案している. その際, 要素の重みと代替弾力性の推定により充足度の総合化を可能とし, 加えて充足度の変化に伴う重みの補正機能を内包させている点に特徴がある, 本研究ではこの方法を広域交通社会資本の評価に適用し, QOLの with/without 比較に基づく整備効果の計測を試みている.
1 0 0 0 OA 大腿骨骨腫瘍を初発症状とした非分泌型多発性骨髄腫の1例
- 著者
- 片江 祐二 島田 佳宏 松本 康二郎 近藤 秀臣 森 俊陽 西田 茂喜 山下 信行 山元 英崇
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.185-188, 2018-03-25 (Released:2018-05-21)
- 参考文献数
- 14
【症例】77歳,女性.主訴:なし.現病歴:約2ヵ月前当院呼吸器外科で肺腫瘍を疑われた.PET-CTで左大腿骨に集積を認め,骨転移を疑われ当科紹介受診となった.肺腫瘍は生検で炎症性病変であり,大腿骨CTでは異常を認めなかったため,大腿部の骨生検は行わなかった.初診5ヵ月後のMRIで大腿骨の病変の増大を認め,腰椎MRIでは年齢の割には脂肪髄が少なかった.内科受診し,血液検査でM蛋白,尿中Bence Jones(以下BJ)蛋白は検出されなかったが,κ/λFLC比の異常を認め,γ-グロブリンは低値だった.胸骨生検を行い,病理診断と臨床像を合わせて非分泌型多発性骨髄腫と診断された.現在,血液内科で薬物治療中である.【考察】非分泌型多発性骨髄腫は多発性骨髄腫の数%の稀な疾患である.血清M蛋白や尿中BJ蛋白は検出されず,診断確定までに時間を要することが多い.原発不明の多発性骨病変があり,MRIで年齢の割に脂肪髄の減少をみたときは骨髄腫を考え,非分泌型も念頭に置くべきである.
1 0 0 0 OA 鈴木基史著『国際関係』
- 著者
- 河野 勝
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.126, pp.218-221, 2001-02-23 (Released:2010-09-01)
1 0 0 0 周期・非周期信号を用いたDNNに基づくリアルタイム音声ボコーダ
- 著者
- 大浦 圭一郎 中村 和寛 橋本 佳 南角 吉彦 徳田 恵一
- 雑誌
- 研究報告音声言語情報処理(SLP) (ISSN:21888663)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019-SLP-127, no.34, pp.1-6, 2019-06-15
本稿では,ニューラルネットワークに基づく音声ボコーダにおいて,周期信号と非周期信号を入力とする音声生成の枠組みを提案する.近年,ニューラルネットワークを用いて音声波形を直接モデル化する手法として WaveNet [1] が提案された.WaveNet は音声波形を高精度にモデル化することができ,自然な音声を直接生成することができるため,特に音声ボコーダ [2] として様々な研究で利用されている [3],[4],[5].しかし,過去の音声サンプル列から次の音声サンプルを生成する自己回帰構造を持ち,合成時に並列演算ができないことから,実時間で合成できない問題があった.また,WaveNet を学習する際のデータベースに無い音高の再現ができない問題や,補助特徴量として指定したピッチ情報の音高を再現しないことがある問題があった.これらの問題に対し,本稿では明示的に周期信号と非周期信号の列を入力として用い,対応する音声サンプルの列を一度に生成する手法を提案する.提案手法を用いることで,実時間より高速に音声を生成できること,および,学習データの範囲外のピッチを持つ音声波形を生成できることを確認した.また,自然性に関する主観評価実験を行い,WaveNet と比較して合成音声品質の向上を確認した.
1 0 0 0 OA オブジェクト指向デザインと形式手法
- 著者
- 中島 震
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.5, pp.499-528, 2001 (Released:2002-07-13)
- 参考文献数
- 157
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 井上 浩
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 月刊労働問題 (ISSN:04310985)
- 巻号頁・発行日
- no.268, pp.p37-44, 1979-12
1 0 0 0 OA 新しき亞酸化銅整流眞空管に就て
- 著者
- 佐々木 六郎
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.11, pp.539-541, 1936-11-01 (Released:2009-02-20)
1 0 0 0 OA 視点
- 著者
- 村橋 勝子
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.288, 2001 (Released:2001-07-01)
1 0 0 0 OA 飛騨国中案内
- 著者
- 上村木曽右衛門満義 編
- 出版者
- 住伊書院
- 巻号頁・発行日
- 1917
1 0 0 0 ドライアイ
Ⅰ はじめに 現在,日本には800万人あるいは最近では2,200万人,もしくはそれ以上のドライアイ患者がいるとの報告がある。ドライアイ患者が増えている理由の一つにはドライアイの世間への認知が高まり,受診が増えたり,診断が増えたりしているためと思われる。 また,ドライアイは1995年にドライアイ研究会から定義と診断基準が作成され1),その後2006年に「さまざまな要因による涙液および角結膜上皮の慢性疾患であり,眼不快感や視機能異常を伴う」と定義の改定が行われた2)。ドライアイは症候群であり,その原因疾患が非常に多岐にわたるとともに環境の変化に伴い,ドライアイ人口も変化していると考えられる。 ドライアイの現状を踏まえつつ,現在までに解明されているドライアイの病態,診断のポイント,最新治療について示させていただく。
- 著者
- 瀬戸山 雅人 嶋田 正和
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会大会講演要旨集 第51回日本生態学会大会 釧路大会
- 巻号頁・発行日
- pp.302, 2004 (Released:2004-07-30)
昆虫において、一見すると人間の脳のように高度な情報処理能力がなければ実現できないような精錬された行動を示すものがいる。発表者は、その行動の裏にある「昆虫でも実現できるようなシンプルな情報処理によるシンプルな行動決定のルール」の観点から、ヨツモンマメゾウムシの産卵時にみられる均等産卵分布について、どのような行動決定のルールがこの分布をもたらしているのかを研究してきた。雌のヨツモンマメゾウムシは、すでに卵を多く産みつけられた豆に対して産卵を避け、卵のついていない豆を選んで産卵することにより、豆当りの卵数が均等になる。その結果、豆内での幼虫の種内競争が均等に軽減される。本研究では、卵の均等分布をもたらすこの行動がどのような知覚情報をどう用いて実現されているかを、ニューラルネットワークモデルを利用して解析した。具体的には、単純なフィードフォーワード型のニューラルネットワークモデルを用意して、これに実際のヨツモンマメゾウムシの行動パターンを教師信号として誤差逆伝播法を用いて学習をさせた。このときヨツモンマメゾウムシが意思決定に用いている情報として、現在いる豆の卵数、1つ前の豆の卵数、2つ前の豆の卵数、蔵卵数、前回の産卵からの経過時間、他の雌との遭遇回数を使用した。ニューラルネットが教師信号を十分に学習したのを確認した後は、モデルの汎化性のテストを行った。汎化性のテストは、学習済みのニューラルネットを搭載した仮想のヨツモンマメゾウムシを豆を配置した仮想環境に置き、その環境で均等産卵が達成できるかで評価した。汎化性のテストの結果としてモデルが産卵行動の特徴を実現できていることが確認されたら、ニューラルネットの中で各情報がどのように重み付けされているかを解析した。
1 0 0 0 都市史研究
- 著者
- 都市史学会編
- 出版者
- 山川出版社 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1942年07月13日, 1942-07-13
1 0 0 0 猫の下痢症への猫コロナウイルスの関与
- 著者
- 望月 雅美 大澤 直子 石田 卓夫
- 出版者
- 社団法人日本獣医学会
- 雑誌
- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.9, pp.1071-1073, 1999-09-25
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 10
猫の消化器疾患に関係するウイルスの検索のために猫糞便を調べた. 特に逆転写酵素遺伝子増幅法を用いて猫コロナウイルス(FCoV)に焦点を当て検索した. 最も高頻度に検出されたのは猫汎白血球減少症パルボウイルス(FPLV;陽性率28.5%)で,次がFCoVであった(10.7%).FCoV陽性の猫に共通した症状は嘔吐, 下痢および脱水で, 多くは間もなく回復した. しかし, FPLVが混合感染していた猫は重症であった.