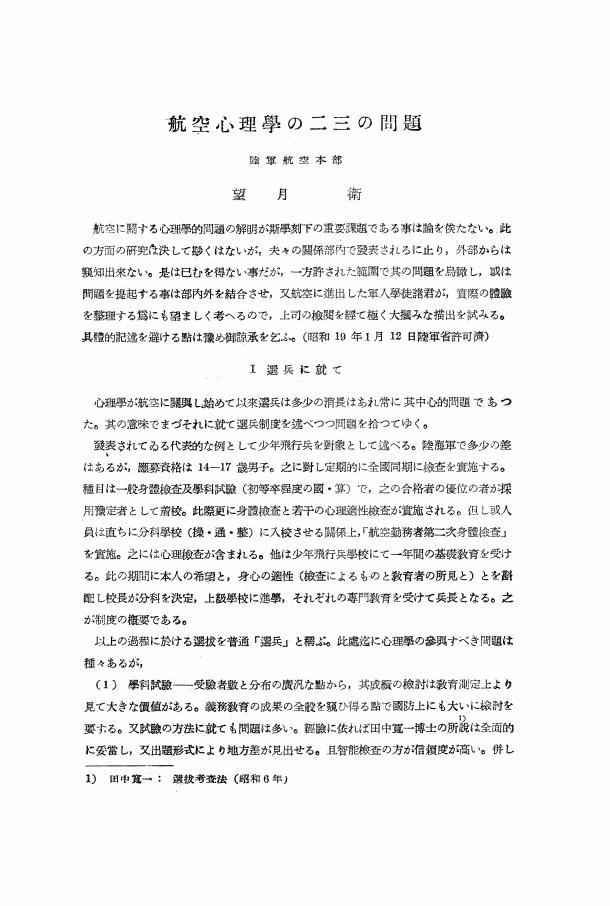- 著者
- NAKAMURA Genki NARIMATSU Kaori NIIDOME Yasuro NAKASHIMA Naotoshi
- 雑誌
- Chemistry letters (ISSN:03667022)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.9, pp.1140-1141, 2007-09-05
7 0 0 0 福島が映し出すリスク管理の日本的課題
- 著者
- 中西 準子
- 出版者
- 一般社団法人日本リスク研究学会
- 雑誌
- 日本リスク研究学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.1-2, 2015
7 0 0 0 井上馨論:日本外交史研究 外交指導者論
- 著者
- 安岡 昭男
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.1-9, 1967
7 0 0 0 ウクライナ国民の微量元素摂取状況と健康影響
- 著者
- 白石 久二雄 サフー サラタ・クマール 幸 進 木村 真三
- 出版者
- 独立行政法人放射線医学総合研究所
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2003
1986年のチェルノブイリ事故は世界に与えた環境汚染程度ならびにその後の放射線被ばくによる健康影響についても大きなインパクトをのこした。多くの研究が実施され結果も報告されているが、本研究では汚染地域を含むウクライナ国民の健康維持の観点から、放射性核種ならびに非放射性核種の摂取量について研究し、他の要因との関連性を、特に"住民の元素摂取量"に関連した健康影響因子に関して調査・解明を現地研究者と共同で行った。食事試料は陰膳方式で約300試料をウクライナ全国(25洲)から収集した。牛乳等の主要食品試料も収集した。試料は化学処理後、微量元素(I, U, Th, Co, Cs, Sr, Rb, Ba, Tl, Bi等)並びに主要、中間元素(Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Mn, Cu, Zn等)をICP-MS(誘導結合プラズマ・質量分析法)ないしICP-AES(誘導結合プラズマ・発光分光法)にて定量した。灰化した試料については放射性核種(^<134>Cs, ^<137>Cs, ^<40>K等)の分析をγ-スペクトロメータで測定した。ウクライナ人の一日摂取量はBa O.51mg, Bi O.37μg, Br 3.Omg, Ca O.70g, Cd 8.0μg, Co 9.7μg, Cr 113μg, Cs 3.8μg, Cu O.70mg, Fe 7.9mg, 145μg, K 2.9g, Mg O.25g, Mn 2.3mg, Na 4.1g, P 0.99g, Pb 33μg, Rb 2.2mg, Sr 1.9mg, Tl 0.37μg, Zn 6.6mg, ^<60>Co ND-0.28 Bq, ^<134>Cs N.D.-0.59Bq, ^<137>Cs 0.5-570 Bq, ^<40>K 89 Bq, ^<226>Ra N.D.-11mBq, ^<232>Th 2.1mBq, ^<238>U 12mBqであった。日本人や世界の報告値と比較すると、Br, Cu, I, Mn, Znの摂取量が低い。元素間の相関を調べた所、高い相関を示す物もあり、環境汚染時を含めた食物連鎖における元素挙動の観点から重要である。興味が持てる。ウクライナには克山病やモリブデン毒等の著名な風土病はみあたらないが、特に、ヨウ素摂取量は栄養所要量、100μg以下であり、平素からの欠乏状況とチェルノブイリ事故の甲状腺異常との因果関係があると推察された。これらの精度の高い莫大なデータはウクライナの研究者から重要なデータとして賞賛を受けた。今後の事故対策、栄養・医学研究に役立つ基礎データを本研究で提供することができた。
- 著者
- Nobuyuki Horita Satoru Hashimoto Naoki Miyazawa Hiroyuki Fujita Ryota Kojima Miyo Inoue Atsuhisa Ueda Yoshiaki Ishigatsubo Takeshi Kaneko
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.12, pp.1473-1479, 2015 (Released:2015-06-15)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 8 28
Objective The impact of corticosteroids on acute respiratory distress syndrome (ARDS) mortality remains controversial following the publication of numerous trials, observational studies and meta-analyses. An updated meta-analysis is warranted, as a few original studies on this topic have been published since the last meta-analysis. Methods We searched for eligible articles using four databases. In particular, we included full-length original articles providing sufficient data for evaluating the impact of corticosteroid treatment on adult ARDS mortality in the form of odds ratios. A fixed model with the confidence interval method was used. An assessment of publication bias and sensitivity analyses were also conducted. Results We included 11 of 185 articles. The pooled odds ratio for corticosteroids with respect to all-cause mortality involving 949 patients was 0.77 [95% confidence interval (CI): 0.58-1.03, p=0.079] with strong heterogeneity (I2=70%, p<0.001). The results of the sensitivity analysis, Begg-Kendall test (τ=0.53, p=0.024) and funnel plot consistently suggested the existence of strong publication bias. After six potentially unpublished cohorts were filled using Duval's trim and fill method, the pooled odds ratio shifted to 1.11 (95% CI 0.86-1.44, p=0.427). In addition, the sensitivity analyses suggested that corticosteroid treatment has a different impact on mortality depending on the comorbidities and trigger events. Conclusion We were unable to confirm, based on the data of published studies, the favorable impact of corticosteroid therapy on mortality in overall ARDS cases. Published articles exhibit strong publication bias, and previous meta-analyses may be affected by this publication bias. Further research focusing on pathophysiology- or trigger event-specific ARDS is anticipated.
7 0 0 0 IR 特別企画 川崎恭治インタビュー:ボルツマンメダル受賞記念
- 著者
- 早川 尚男 川崎 恭治
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:05252997)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.3, pp.299-327, 2001-06
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
7 0 0 0 『うつほ物語』論 : 書かれたものの機能
1. 問題意識と研究の目的本論は、『源氏物語』より数十年前に成立したとされる『うつほ物語』における「書かれたもの」に着目し、その機能について考察するものである。これまでの『うつほ物語』の研究は、巻々の論や人物論、琴や学問、羅列される物の論考といったものが主であった。しかし、『うつほ物語』には、これらとはまた別の、固有の特徴として挙げられる事項がある。それは、物語の最初から最後まで、紙だけではなく物に文字を書きつけるという行為が多くみられ、かつ物語の展開の中でこの行為が重要な役割を担っていることである。これまで、物に文字を書きつけるというこの物語独自の人物間のコミュニケーションについて述べた論考は少ない。本論では、物に文字を書きつけるという行為を中心に据え、『うつほ物語』において贈与される言葉と、それに付随する物について見ていき、過去に「稚拙」の一言で片づけられていた本物語において行なわれてきた「言葉」を贈る行為について考える。そして、これを発端として、この特徴的な行為を行なう藤原仲忠という人物について見ていくことで、「清原一族」が作り出した三つの〈系譜〉を考察する。2. 本論の構成と方法本論では、九つの観点から『うつほ物語』における「書かれたもの」の機能を考察しており、それぞれの観点を章としている。各章の概要については、以下の通りである。第一章では、紙以外の物に文字(和歌)を書く場面が多くあることが『うつほ物語』独自のものであることに着目し、物語内で一貫して物に文字を書き続ける藤原仲忠に焦点を合わせる。この検討から、『うつほ物語』における物に文字を書きつけるという行為が一定の論理の元に描かれている可能性があることを指摘した。第二章では、源実忠が文字を書きつけた物を取り上げ、第一章で見た仲忠と比較した。また、あて宮との意思疎通に成功した仲忠の方法を詳細に見てゆくことで、「書きつける」ことから見えるこの物語の言語認識が、文字に対する『うつほ物語』独特の認識を根底に置いた上で成り立っていることを示した。第三章では、人物たちの筆跡、すなわち〈手〉に着目した。筆跡は、書いた人物を特定するものであると共に称賛の対象となっている。特に素晴らしいとされるのが仲忠である。このことは、「蔵開・上」巻の冒頭において仲忠が俊蔭伝来の蔵を開き、清原俊蔭や俊蔭の父母といった人々の書物を手にし、その学問を習得したことと関係があることを示した。第四章では、手紙の機能について述べた。『うつほ物語』に出てくる全ての手紙についてその特徴を七つに分けた。『うつほ物語』では、人物関係の補強・拡大、もしくは信頼の獲得として手紙が機能しているといえる。またそのことから、『うつほ物語』における手紙の「安定性」が見えてくる。第五章では、仲忠が藤壺の若宮に献上した「手本四巻」について論じた。俊蔭伝来の蔵を開いた仲忠の筆跡は称賛されるものであった。仲忠の「手本」は、受け取り手から見れば至上のものである。しかし、仲忠にとっては「手本」は至上のものではない。このことから、至上のものとして「手本」を認識し、またしたがって、それに続く〈琴〉を求める藤壺と、「手本」は「手本」でしかなく、〈琴〉を教えるつもりのない仲忠の思惑がすれ違うことが明らかになるのが、若宮への手本献上の場面であると指摘した。第六章では、俊蔭伝来の蔵から書物が出て来てからの仲忠の行動を追った。仲忠は、俊蔭伝来の蔵を開いたことにより、「清原氏」としての自覚を持った。そして、母屋に八ヶ月間籠って〈学問〉を継承するとともに〈手〉も継承した。またいぬ宮を〈琴〉の継承者とした。このことから、〈琴〉のみならず、〈学問〉においても、「籠る」ことによって継承者が継承者たりえることを示した。第七章では、「蔵開・中」巻における朱雀帝の御前での〈学問〉の進講に着目した。従来、菅原道真の「献家集状」との関連のみが指摘されてきたこの進講を、本論では史実の進講とも比較し捉え直している。「清原家」の学問が、一氏族の学問でしかないものであるにも拘わらず、それを公のものにするべく、『日本紀』の進講と同じ形式を採っていたことを指摘した。さらに、『日本紀』の進講と同じ形式を採ることにより、春宮の権威付けと、清原家の学問の家としての権威付けを図っていることを示した。第八章では、〈琴〉と〈学問〉の公開の場を比較し、時刻表現・〈香〉・空間の三点において、この二つの場の構造が相似関係にあることを指摘した。また、秘曲を披露する前に必ず学問披露の場があることから、〈琴〉の公開の場と〈学問〉の公開の場が一対のものであるといえることを示した。第九章では、清原家の系譜――〈琴〉・〈学問〉・〈手〉――の全てを担っている仲忠に着目し、これらの継承されるものが、どのようにして次世代に伝わっていくのかについて考察した。〈琴〉はいぬ宮が継承者となっているが、〈学問〉を伝える先は決まっておらず、また、手本は春宮と藤壺の若宮という、清原家とは無関係の人々へと伝わっていく。また、「楼の上・下」巻での秘琴披露において、俊蔭の娘の体調が思わしくないことも踏まえ、「清原家」の継承されてきたものが、消えていくことを示した。過去の論考において、〈琴〉の系譜について述べたものは多く、また、「蔵開・上」巻において、仲忠が清原家の「学問」を継承したことを述べたものも多い。しかし、仲忠が継承した〈学問〉を「系譜」として捉え、また、「学問」から仲忠が独自に作成した手本もまた、「清原家」を負うものとして位置付けられていると述べるものは見られない。本論が、『うつほ物語』の「清原氏」を「書かれたもの」から捉えるという、新たな知見を示すものとなれば幸いである。
7 0 0 0 OA 戦前期地域交通と政党・軍部の経済的関係の研究
本研究では、戦前期において軍事に関係する輸送を行っていた博多湾鉄道汽船および朝倉軌道という二つの地域交通事業者を取り上げ、軍事輸送がその経営にどのような意味を持っていたのかという点を明らかにした。具体的には、次の二点が判明している。一点目は、地域交通事業者が軍事輸送から得られる利益は、必ずしも常に大きいものではなかったという点である。二点目は、軍部や行政は軍事輸送の必要上、事業者にとっては採算性の低い輸送事業の実施を期待したが、その期待は事業者側も認識していたという点である。この二点から、軍事輸送に対する事業者と軍部の利害が、必ずしも一致しているとはいえないことを明らかにした。
- 著者
- 阪 彩香 伊神 正貫 富澤 宏之 福澤 尚美(追加資料作成)
- 出版者
- 科学技術・学術政策研究所
- 巻号頁・発行日
- 2015-04 (Released:2015-04-09)
最新データに基づき2013年までのWoS-KAKEN論文の状況を分析した資料を追加しました(2017年4月11日)。本調査研究では、論文データベース(Web of Science、自然科学系)と我が国の代表的な競争的資金の1つである科学研究費助成事業の成果データベース(KAKEN)を論文単位で連結させ、日本の論文産出構造の分析を行った。その結果、科学研究費補助金の関わる論文数やTop10%補正論文数は近年上昇傾向にあることが分かった。また、科学研究費補助金は、2006-2008年における日本の論文数の47%、Top10%補正論文数の62%に関与しており、日本の論文産出において量的にも質的にも関与していることが明らかとなった。また、日本の論文産出構造において、①科学研究費補助金以外の研究費による論文産出が著しく低下していること、②科学研究費補助金による研究成果が世界における日本全体の存在感を維持させるほどの伸びを生み出していないことが問題点として浮かび上がってきた。This Research Material reports the result of the analysis of the structure of Japan’s scientific publication production using linkage data of bibliographic database (Web of Science) and database of Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKEN), which is one of the representative competitive funds in Japan. Using those linkage data, it was found that the number of scientific papers and of top 10% highly cited papers that are related to the Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) has been increased in the past decade; and outputs of KAKENHI were related to 47% of scientific papers and 62% of top 10% highly cited papers in 2006-2008. These results suggest that KAKENHI plays a large role in the knowledge creation of Japan in not only quantitative aspects but also qualitative aspects. Moreover, following two issues in the structure of Japan’s scientific publication production were revealed. 1) The number of scientific paper that is not related to KAKENHI has been decreased dramatically. 2) Outputs of KAKEN have not shown enough increase for keeping Japan’s presence in the world.
7 0 0 0 OA 北海道留萠線全通記念
- 著者
- 鉄道院北海道建設事務所 編
- 出版者
- 鉄道院北海道建設事務所
- 巻号頁・発行日
- 1910
7 0 0 0 OA お山の雪 : 童話集
- 著者
- 堀 千晶
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.159-170, 2010
Deleuze, au debut de Empirisme et Subjectivite : Essai sur la Nature humaine selon Hume, pose l'identite de l'esprit et de l'imagination, et ne cesse de la reaffirmer tout au long du livre. La valeur de cette affirmation est constatee quand Deleuze definit l'empirisme de Hume comme <<philosophie de l'imagination>>. Et cependant, cette identification, Hume a son tour ne la dit jamais, du moins de facon manifeste : l'esprit selon Hume est toujours l'ensemble d'impressions et d'idees, l'imagination n'etant que la collection des idees. De sorte que dans Empirisme et Subjectivite, il existe implicitement deux definitions divergentes de l'esprit, celle authentique de Hume (impressions et idees) et celle transposed de Deleuze (idees ou imagination). Deleuze ote l'impression presente a la definition de l'esprit, et cette reticence reiteree lui permet d'introduire, dans sa lecture de Hume, la theorie bergsonienne du passe et de l'habitude, qui agissent independamment de l'impression presente. Le frivole chez Hume - theme constant et serieux de sa philosophie morale, croyance en ce qui n'a jamais ete present, voire en ce qui n'est meme pas presentable dans l'imagination - est fonde selon Deleuze sur la conjonction de la presence et de la non-presence, de l'experience et de l'habitude. Cette conjonction ouvrira, au cceur meme de la subjectivite, la possibility generale de la fiction, de la fabulation et de la tromperie.
7 0 0 0 座談会「物理学の明日」
- 著者
- 齋藤 純一
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法律時報 (ISSN:03873420)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.8, pp.59-61, 2015-07
7 0 0 0 OA 航空心理學の二三の問題
- 著者
- 望月 衛
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.5-6, pp.471-484, 1943 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 8
7 0 0 0 31C-07 桂皮含有タンニンにおける内皮依存性血管弛緩作用
7 0 0 0 OA 森山至貴著『「ゲイコミュニティ」の社会学』
- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.729-730, 2013 (Released:2015-03-31)