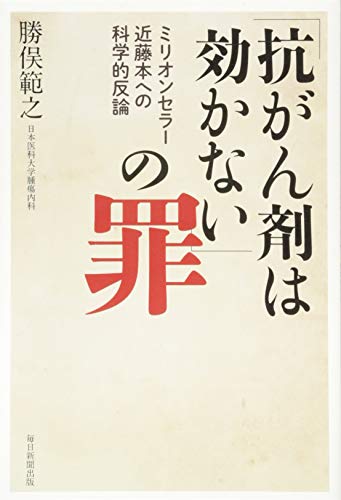1 0 0 0 OA 電場中における線香花火の振る舞い
- 著者
- 溝口 勝
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2018年大会
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-14
2011年3月に福島第一原子力発電所から放出された放射性セシウムは表層に5cm以内の水田に集積していた。この放射性セシウムを除去するために、国は一斉に表層土を剥ぎ取る除染工事を実施した。そのため、福島県飯舘村の水田には汚染土が詰め込まれた黒いレコンバックが山積みになっている。一方、国の方法とは別に、私は放射性セシウムが粘土粒子に固定される性質に着目し、農家自身が手軽にできる農地除染法をNPOや農家と協力して開発してきた。2012年12月、福島県飯舘村の佐須地区の水田で汚染土壌の現場埋設実験を行った。我々は水田の汚染された表土(10m×30m)5cmを剥ぎ取り、水田の中心にトレンチ(幅2m、長さ30m、深さ1m)を掘って、深さ50~80cmに汚染土を入れ、厚さ50cmの非汚染土を被せた。この水田で、2013年から毎年米を育て、この除染法で安全な米を生産できることを確認した。さらにこの水田から放射性セシウムが漏出しないことを証明するために、2014年5月に水田に底付のPVCパイプ(内径10cm、長さ200cm)の井戸を設置し、2015年3月から半年間ごとに土壌放射線量を測定している。その結果、土壌放射線量は深さ70cm辺りでピークを持つガウス分布となることが観測されている。そのピークを持つ深さはこの3年間ほとんど変化していない。この結果は、田面水が地中に浸透していても放射性セシウムが移動しないことを示している。
- 著者
- 松田 昌幸
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.1065-1067, 2006-10-21
これからの日本の生きる道は先進的なアイデアにより日本を取り巻く諸国に先んじて開発を行い、知的財産の強化を進めなければならない。本日の講演は、開発現揚で実際に実施して顕著な効果を確認された集団による新技術、新製品、新事業のアイデアを創生した手法を具体的に提案するものである。この方法は技術の分野に限らず職場での人間関係の改善の提案をするばあいなどにも応用できる多分野、多目的に応用できるもので、所謂KJ法とブレインストームとを組み合わせたものである。従来のものと大きく異なるのは、従来は発言してアイデアを発表するものであったが、MKJ法は紙に書いて提案するものである。MKJ法の基本的なルールは、(1)カードにアイデアと名前と提案時間とを書く(2)特許請求範囲に採用された提案者は発明者になる(3)特許請求範囲を支える具体的な実施の例を提案した者も発明者とする(4)同じ内容の提案が有った場合は最先の者が採用される(5)提案グループは一定期間守秘義務を負う(6)提案行為は同じグループ・メンバーで一定期間継続する(7)一定期間を経過した後は、他のグループ・メンバーに情報を開示しアイデアの拡がりを促進する。MKJ法の本質は提案者のオリジナリティを尊重することにある。
1 0 0 0 ヒマラヤ冒険物語
- 著者
- クリス・ボニントン著 田口二郎訳
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 1992
1 0 0 0 平子氏の西遷・北遷 : 鎌倉御家人 : 特別展
- 著者
- 霜触 智紀 笠巻 純一 中台 桂林
- 出版者
- 日本教育保健学会
- 雑誌
- 日本教育保健学会年報 (ISSN:18835880)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.23-38, 2017
1 0 0 0 IR 民意と現代政治分析 : ロバート・A・ダールのデモクラシー理論
- 著者
- 鵜飼 健史
- 出版者
- 早稲田大学社会科学学会
- 雑誌
- 早稲田社会科学総合研究 (ISSN:13457640)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.25-44, 2014-03
1 0 0 0 OA <一般論文>歴史学における状況証拠による推論はいかなる時に信頼できるのか
- 著者
- 苗村 弘太郎
- 出版者
- 京都大学文学部科学哲学科学史研究室
- 雑誌
- 科学哲学科学史研究 (ISSN:18839177)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.21-42, 2018-03-31
Circumstantial (indirect) evidence is supposed to be unreliable in historical research. Historians, however, sometimes succeed in establishing a fact based on circumstantial evidence. The reason why circumstantial evidence can achieve it despite its infamous reputation is a question left to be answered. I will give an answer to this question by arguing that credibility of inference in historical research does not depend on whether it is based on circumstantial evidence but on whether its hypothesis is a good explanation in terms of IBE (inference to the best explanation). McCullagh(1984) argues that there are seven explanatory virtues that concern IBE in historical research: some explanation to evidence, explanatory scope, explanatory power, plausibility, ad-hocness, disconfirmation, relative superiority. This criteria can help us understand historical inference based on circumstantial evidence, but it has some problems. Therefore, I will try to modify his criteria in terms of Bayesiansim. I will argue three points. First, plausibility should be interpreted as prior probability in terms of Bayesianism. Second, ad-hocness should be turned into a virtue reflecting degree of unification. Third, how much weight is put on each of explanatory virtues depends on individual historian’s judgement. I will demonstrate these points by a case study.
1 0 0 0 OA 車体装架型軌道検測装置の開発
- 著者
- 矢澤 英治
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.11, pp.980-984, 2014-11-05 (Released:2014-11-05)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 サリドマイドに起因したと思われる上肢海豹肢症について
- 著者
- 内野 滋 坂川 邦彦 南条 典昭 成田 豊福 内野 碩
- 出版者
- 日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科学会雑誌 (ISSN:03009165)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.11, 1962-09
1 0 0 0 日本産ムヨウラン属の検討
- 著者
- 橋本 保
- 出版者
- 国立科学博物館
- 雑誌
- 筑波実験植物園研究報告 (ISSN:02893568)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-40, 1990-12
- 被引用文献数
- 5
Lecanorchis (ムヨウラン属)は小形の腐生ランで,宮城県以南の日本,台湾,およびシッキムからニューギニアにかけて分布が確かめられている。これまで発表された学名は新組合わせと命名上の新名を除き24種5変種であるが,それらのうち11種3変種が日本からのものであった。これらは主として常緑林の林床に生え,個体数が比較的少なく,開花株に出合う例も少なく,花や株の色も目立ち難く,姿も単純で,開花株以外はあたかも樹木のひこ生えが立ち枯れているようにみえる。これらの条件がおそらく主な理由で,これまで本属の分類研究は極めて不充分であった。そこで日本産の材料を主として用い,本属における植物体全体の特徴を含め,花部を解剖して種類の特徴の詳細を明らかにしようと試みた。日本産のLecanorchisをここでは7種6変種認識し,これらの種類への検索表を作り,記載を行った。すでに示した3種類(Hashimoto 1989)を除く,すべての分類群の花部を図解した。またこれらを4節に大別した。唇弁の大脈の数については,これまで注目されたことがなかったが,ここではじめて分類形質としてとりあげた。LecanorchisおよびTrilobae両節の大脈が偶数であることは注目に値する。唇弁の緑の単細胞毛,葯の裂開口周辺の毛などはこれまで分類上の特徴とされたことがなかったが,ここでは種の異同を認識する形質として取り上げた。
1 0 0 0 OA 下谷浅草辺 : 宝暦年中之頃
- 出版者
- 写
- 巻号頁・発行日
- vol.[1],
1 0 0 0 アクパトーク島(ハドソン海峽)
- 著者
- 國分 安吉
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.12, pp.1006-1009, 1932
- 著者
- Suzuki Atsushi Sekiguchi Sahoko Asano Shogo ITOH Mitsuyasu
- 出版者
- The Japanese Pharmacological Society
- 雑誌
- Journal of pharmacological sciences (ISSN:13478613)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.4, pp.530-535, 2008-04-20
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 3 21
The prevention of osteoporotic fracture is an essential socioeconomical priority, especially in the developed countries including Japan. Estrogen, selective estrogen-receptor modulators (SERMs), and bisphosphonate are potent inhibitors of bone resorption; and they have clinical relevance to reduce osteoporotic fractures in postmenopausal women. However, we can prevent at most 50% of vertebral fractures with these agents. For the better compliance of aminobisphosphonate, the use of a daily bisphosphonate regimen is moving to a weekly or monthly bisphosphonate regimen. Both cathepsin K inhibitors and modulators of the RANK-RANKL system, which can reduce bone resorption, are the candidates for the future treatment of osteoporosis. As well as bone resorption, we need to increase bone formation to prevent osteoporotic fractures, particularly in elderly patients with low bone turnover. In the U.S., Europe, and Australia, they have already started intermittent parathyroid hormone injection and/or oral strontium ranelate to stimulate bone formation. We still need to discover new agents to reduce osteoporotic fractures for the better quality of life without fractures.<br>
1 0 0 0 OA 鋳造工場の粉じん対策事例
- 著者
- 高柳 弘明 岡本 守
- 出版者
- 公益社団法人 日本鋳造工学会
- 雑誌
- 鋳造工学 (ISSN:13420429)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.12, pp.1050-1053, 1997-12-25 (Released:2014-12-18)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 野原 博淳
- 出版者
- The Health Care Science Institute
- 雑誌
- 医療と社会 (ISSN:09169202)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.71-89, 2007
フランスの医薬品産業は,サノフィとアベンティスが合併して世界3位のフランス系多国籍医薬品グループを生み出すなど,近年ダイナミックな展開を見せている。その反面,フランス医薬品産業の将来を危惧する声も大きく聞かれる。フランスの医薬品企業グループについては,その国際的事業基盤整備の遅れが指摘されており,またゲノム応用創薬研究分野への進出でも遅れ気味である。多くの家族経営的企業は,いまだに古くからの製品分野に固執して,多角化戦略に消極的である。また,色々な企業再編にも拘らず,国内中堅医薬品企業層は相対的に脆弱であり,医薬品国内生産の半分以上が外資系多国籍グループの手によって行われている。本稿では,新旧色々な潮流が交錯する現代フランス医薬品産業界を対象として,M&Aや企業提携が産業再編において果たす役割を具体的な事例を使って浮き彫りにすることを試みる。