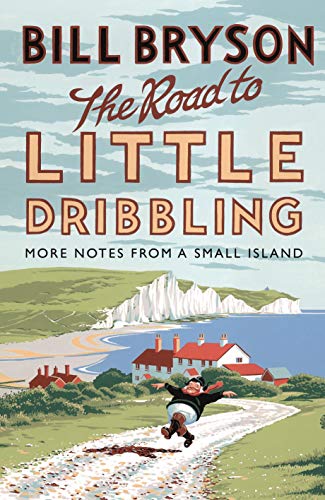1 0 0 0 概日時計の分子機構
- 著者
- 池田 正明 熊谷 恵 中島 芳浩
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.S13-2, 2017
概日リズムは、地球が24時間で自転しながら太陽の周りを回ることにより地球上に起こる明暗の光環境リズムを、地球上の生物が体内に取り込む形で形成されたと考えられている。地球上の生物は、生体内に概日リズムシステムを獲得したことにより、24時間周期の明暗変化を予測して体内を変化させ、恒常性の維持や環境適応を有利にしていったと考えられている。概日リズムが遺伝子レベルで制御されていることは、1971年にベンザーらがショウジョウバエからリズム変異体<i>period</i>を発見したことを端緒に、これが1984年の<i>period</i>遺伝子の発見へつながり、1997年の<i>Clock, Bmal1, Per</i>などの哺乳類の時計遺伝子の発見、1998年のCLOCK/BMAL1/PER時計遺伝子群の転写翻訳によるフィードバック機構からなるコアフィードバックループの同定へと続き、20世紀末に明らかにされた。コア時計遺伝子であるCLOCK/BMAL1/PERは転写因子として機能しているが、これらの分子にはPASドメインというドメイン構造があり、PASドメインは転写因子間の相互作用のインターフェースとして機能している。CLOCK/BMAL1はこのPASドメインを介してヘテロダイマーを形成し、<i>Per, Cry</i>時計遺伝子のプロモーターにあるE-boxに結合してこれらの遺伝子の転写を促進、産生された産物はCLOCK/BMAL1の転写促進活性を抑制することによって約24時間のリズムを形成している。時計遺伝子は概日リズムの発振という機能を生体内の殆どの細胞で発現することに加えて、CLOCK/BMALが、時計制御遺伝子(<b>clock controlled genes</b> (CGG))を直接転写制御することにより、生体内の代謝リズム発現を起こし、生体内の恒常性維持に働いている。本シンポジウムでは概日リズムの分子機構を概説するとともに、毒物代謝との接点についても論考したい。
- 著者
- 安達 奈緒子 安達 知郎
- 出版者
- 弘前大学教育学部
- 雑誌
- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, pp.159-168, 2017-10-13
「居場所」という言葉は,それぞれの人がそれぞれに意味を見出しうる重層的な言葉である。居場所の多義性は心理臨床において重要であると考えられる。本研究では,その多義性を保持して実証的研究を行うねらいから,「居場所がある」「居場所がない」という意識(居場所意識)に注目し,居場所意識の基本的性質(性差・時期差,精神的健康・心理的居場所感との関連,時間的安定性)を明らかにすることを目的とした。居場所意識,精神的健康,心理的居場所感を測定する質問紙調査を3回,実施した(協力者は大学生計497名であった)。その結果,第一に,居場所あり意識と居場所なし意識は対極に位置するものではないこと,第二に,居場所あり意識は必ずしも精神的健康と関連するものではなく,女性では精神的な不健康と関連していること,第三に,女性は男性に比べて居場所なし意識が時期を越えて維持されやすいことが明らかにされた。一方で,居場所意識測定項目の時間的安定性については評価基準が明確でなく,この点についてさらに検討が必要と考えられた。 This study investigated the consciousness of‘ I have IBASHO’ or‘ I don't have IBASHO’ and aimed to clarify theproperty of these‘ IBASHO’ consciousness. University student( total n=497) completed questionnaires about‘ IBASHO’consciousness, mental health, and psychological‘ IBASHO’ in three surveys. The results were followings;( a) Theconsciousness of‘ I have IBASHO’ and‘ I don't have IBASHO’ were not opposition.( b) The consciousness of‘ I haveIBASHO’ was not related to mental health in males, and it was related to mental ill health in females.( c) Females kept theconsciousness of‘ I don't have IBASHO’ across time more than males. In addition, the time stability of measurement items about‘ IBASHO’ consciousness didn't become clear.
- 著者
- Bill Bryson
- 出版者
- Doubleday
- 巻号頁・発行日
- 2015
1 0 0 0 IR <論文>余暇と消費行動
- 著者
- 小川 一夫 岡村 和明
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 經濟研究 (ISSN:00229733)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.132-142,190, 2001
本稿では「家計調査」収録の費目別消費データに基づいて,余暇と消費の間の弱分離性を統計的に検証する.弱分離性が棄却されれば,余暇水準は支出行動に直接的な影響を及ぼすことになる.われわれは,条件付き需要関数に基づき,家計にとって余暇水準が与えられた下で,家計の支出行動に検討を加えた.実証分析の結果,総支出弾力性は余暇時間の大きさに依存することが明らかとなり,消費と余暇時間の間の弱分離制は棄却された.消費サービスを享受する行為に時間が必要とされる「教養・娯楽」,「住居」といった費目への総支出弾力性は,余暇時間が増加するにつれて上昇する傾向が観察される.逆に,労働と密接に結びついて消費費目である「被服及び履物」,「保険医療」といった費目への総支出弾力性は,余暇時間の増加につれて低下していくことが見いだされる.We examine the effects of leisure on household commodity demands using data on monthly expenditure from Japanese Household Expenditure Survey during 1970 to 1996. Specifically we test the separability of commodity demands from leisure based on conditional demand functions. Separability is decisively rejected and it is found that as the time allocated to leisure increases, the total expenditure elasticity of recreation and housing rises, while that of clothing and medical care falls.
1 0 0 0 交換・企業家・社会変化 : 日本村落社会の過程論的分析の試み
- 著者
- 三浦 敦
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.149-171, 1990
本稿では, 日本の一村落の政治過程とその背景となる社会秩序との分析を通して, そこに働く権力過程やその相互関係を, F.Barthの企業家モデルのアイデアを使って明らかにすることを試みる。こうした日本における政治現象の過程論的視点からの人類学的研究はまだ十分とはいえない。ここで対象とするZ村は主要産業である漁業と林業の不振と過疎化に直面して新たに農業の商品化を試みようとしているのであるが, それを推進する現村長と農協理事長への支持は, その活発な活動にもかかわらず芳しくない。この不支持の理由は交換関係に基く村の社会秩序の考察を通して明らかになる。村には贈与交換と商品交換という二つの交換関係が, それぞれ異なる権力過程によって維持されている。役場と農協の活動はここに新たな交換関係を導入し村社会を変化させるものとして考えられるが, そこでの彼等の権力過程は社会秩序によって制限されるのである。
1 0 0 0 OA ギシギシ属植物のリンとアルミニウムに対する生育反応の種間差異
- 著者
- 堀江 秀樹 根本 正之
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.340-345, 1990-12-25 (Released:2009-12-17)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
アレチギシギシ, ナガバギシギシ, ギシギシ, エゾノギシギシの4種におけるリンおよびアルミニウムの生育への影響を比較した。1) リンを4水準で施肥し, 栽培試験を行った結果, 4種はすべて無リン条件での生育は極めて不良であるが, リンを与えるとその生育量は著しく増加した。土壌中の可給態リン濃度が低い場合の全乾物重はギシギシ, エゾノギシギシ, アレチギシギシ, ナガバギシギシの順であった (Figs. 1, 4)。2) ナガバギシギシではT/R比は最小であったが (Fig. 2), 側根の占める割合が小さく, 根長は最も短かった (Fig. 4)。ナガバギシギシでの低リン耐性が低い要因は根長が短いことによると考えられる。3) アルミニウムを20ppm添加して4種を水耕栽培した結果, エゾノギシギシの全乾物重は他の3種より有意に大きかった (Table 1)。4) 日本の人工草地ではリン欠乏やアルミニウムの害が問題になるが, このような土壌条件下では低リン耐性および高アルミニウム耐性にまさるエゾノギシギシがナガバギシギシよりも生育しやすいと考えられる。
1 0 0 0 OA 国立国会図書館オンラインの目次データを使用した資料の検索方法
- 著者
- 阿部幸江
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 参考書誌研究 (ISSN:18849997)
- 巻号頁・発行日
- no.79, 2018-03-30
1 0 0 0 OA 天蚕絹タンパク質の機能性利用への実用的可能性
- 著者
- 瓜田 章二
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.2, pp.2_79-2_84, 2013 (Released:2013-10-11)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 OA 室戸ユネスコ世界ジオパークにおけるサイト見直し
- 著者
- 中村 有吾 高橋 唯 仙頭 杏美 和田 庫治
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2018年大会
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-14
室戸ジオパークは、2008年に日本ジオパークに認定されてから、今年で満10年となる。2018年には、今後10年間の活動計画(マスタープラン)を策定し、今後のジオパーク活動を推進する上で主要な活動場所となるサイトおよび拠点施設を見直し、新たに指定することになる。その際、2015年のGGN再審査による指摘事項(Recommendation)に対応するため、次の条件を満たすサイトを設定する:内陸のサイトを増やす、地質サイトとそれ以外(生態・文化)をわける、自然の家展望台などツーリストの関心を引く施設も活用する、構造地質学的要素(断層など)をとりいれる、施設や道を「サイト」としてはいけない。ただし、大前提として、室戸ジオパークのテーマ(「海と陸が出会い 新しい大地が誕生する最前線」)およびそこから派生するジオストーリーに沿った地点を、サイトとして設定する。新たなサイト設定には、従来「ジオサイト」として活用してきた地点を再定義するとともに、市民から要望のあったサイトでテーマとの関連するものを新たにサイトとして定義した。そのほか、専門員による野外調査・文献調査に基づいて、室戸ジオパークに分布する主要な地層(Formationレベル。場合によってはMemberレベル)や地形(海成段丘や海食地形など)は代表的な地点をサイトとして認定する。その際なるべく、室戸半島の東海岸・西海岸でそれぞれ認定する。その結果、51のジオサイト、10のエコサイト、17のカルチュラルサイトを「サイト」として、また、展示施設や展望台などの10施設を「拠点施設」として、設定した。
- 著者
- 平松 良浩 松原 誠 中川 和之
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2018年大会
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-14
はじめに 日本各地のジオパーク活動の支援ならびに地震学の知識の普及、学術研究の促進を目的として発足した日本地震学会ジオパーク支援委員会では、ジオパーク専門員に対する勉強会として、地震学習会「ジオパーク活動で使える地震学1」を昨年度に実施した。さらに参加者に対してアンケートを実施し、地震学習会に対する評価や今後のテーマについて調査を行なった。本講演ではそれらについて紹介する。 地震学習会「ジオパーク活動で使える地震学1」 日本地球惑星科学連合2017年大会期間中の5月22日に地震学習会を実施した。 (1) 「ジオパーク活動で使える地震学 −地震観測データの活用方法−」(防災科研:松原 誠)および (2) 「日本周辺の沈み込み帯における海底地形」(海上保安庁:西澤あずさ)と題した講演が行われ、地震観測網、地震データや震源分布図に関する解説、地震データの展示例、各ジオパーク内の地震観測点の分布や、日本周辺の3D海底地形図に見られる海底地形と地震の関係や海上保安庁の各管区の海の相談室の利用やwebで公開されている海洋台帳に関して解説された。地震学習会には、事前申込のあった10ジオパークの他に、飛び込みで8ジオパークおよびJGN事務局から計32名の参加者があり、紹介されたデータの具体的な利用法など活発な質問がなされた。 参加者アンケートによる地震学習会の評価と要望 講演内容の理解度や今回紹介されたデータの活用事例の有無、開催時期や時間の長さ、今後のテーマへの要望に関して、参加者に対してアンケート調査を実施した。講演内容及び各ジオパークにおける地震観測点や海上保安庁が所有するデータの利用方法については、概ね理解でき、今回紹介されたデータについても活用したいという意見が多かった。開催時期については、日本地球惑星科学連合大会開催期間中を望む声が多かった。時間の長さについては、ちょうど良いとの意見と短いとの意見に分かれ、参加者の予備知識が反映された結果と推測される。今後のテーマについては、地震防災、地震教育、地震活動や日本列島の地震学的構造など多様な意見があり、地震学習会を継続的に実施する必要性があると考えられる。 謝辞:地震学習会の実施にあたり、日本ジオパークネットワーク事務局に多大なるご協力をいただきました。記して感謝します。
1 0 0 0 暗黒物質を捉える (特集 暗黒物質に異説)
- 著者
- 中島 林彦
- 出版者
- 日経サイエンス ; 1990-
- 雑誌
- 日経サイエンス (ISSN:0917009X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.10, pp.48-55, 2015-10
太陽系には暗黒物質の風が常時,はくちょう座の方向から吹き付けているとみられている。地球は太陽の周りを回っているので,地球から見ると,その風速は公転速度の分だけ,1年周期で変化すると考えられる。
1 0 0 0 OA 東京高等商業学校一覧
- 出版者
- 東京高等商業学校
- 巻号頁・発行日
- vol.明治44-45年, 1912
1 0 0 0 OA 下仁田ジオパークの二重ナップ構造の形成時期とその起源
- 著者
- 高木 秀雄 新井 宏嘉
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2018年大会
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-14
ジオパークのストーリーとしてジオガイドが説明する時,複雑で難しいものの一つが地質構造発達史であろう.今回は下仁田ジオパークの構造発達史について,跡倉層に関する新しい情報も踏まえつつレビューし,ナップの移動を可能にした圧縮場をもたらしたテクトニックイベントにも触れたい.二重ナップの構成要素跡倉ナップ:御荷鉾緑色岩を基盤とする跡倉ナップを構成する地質体は跡倉層が大部分を占め,その他四ツ又山などに白亜紀前期花崗岩類・変成岩類が存在する.跡倉層の時代は以前より不明確で,アンモナイト等によりサントニアン階:Matsukawa and Obata, 2012)という報告がなされているが,近年ジオパークの化石発掘体験で得られたアンモナイトから,下部白亜系バレミアン階下部の可能性が指摘された(生野ほか,2016).また跡倉層を貫くとされている花崗岩類の角閃石K−Ar年代は112+/-3Ma(竹内・牧本,2003)という報告もある.一方,下仁田や寄居地域の跡倉層中の砕屑性ジルコンの最も若い年代は119+/-11Ma(中畑ほか, 2015)であるが,誤差を考慮するとその年代がバレミアン(129−125 Ma)であることを否定するものでもない.逆に,それより若い砕屑性ジルコンの年代が全く確認されていない.金勝山ナップ:跡倉ナップの上構造的上位に存在するナップで,ペルム紀の石英閃緑岩とホルンフェルスから構成され,下仁田では川井山,ふじ山に分布する.寄居地域や皆野町金沢地域にも同じ岩体があり,それらは御荷鉾緑色岩の上に直接乗る場合と,跡倉ナップを挟んでその上に乗る場合がある.関東山地におけるこのナップ境界露頭は,下仁田の大北野川でのみ認められる.対比と復元モデル ペルム紀の岩体は南部北上−黒瀬川帯に存在する花崗岩礫に,白亜紀前期の岩体は,阿武隈帯や肥後帯にそれぞれ対比されている(高木・柴田,2000).つまり,ナップの起源はである東北日本の要素が,御荷鉾緑色岩とナップ構造を北縁で切断している中央構造線(MTL)と御荷鉾緑色岩との間にかつて広く分布していた.それらの南への押し被せ(新井・高木,1998;Arai et al., 2008) が,最も重要なナップのイベントである.その断層活動に先立ち大規模な横臥褶曲が発生し,例えば四ツ又山以北の2 km四方もの跡倉層の大部分の地層の逆転をもたらしたと考えられる(新井・高木,1998).その後もナップ境界は上盤西の走向移動や最終時期には上盤北の正断層的な運動を重複した(Kobayashi, 1996).ナップの移動距離も中央構造線(MTL)以南での移動のみを考慮すると,数km程度のオーダーであったと推定される.南北圧縮をもたらしたテクトニックイベント 大規模な南への押し被せが発生した時期については,下盤の御荷鉾帯の変成年代である後期白亜紀以降,北側の下仁田層(約20Ma)を切断しているMTLによってナップ境界断層が切断されていることから,そのMTLの最終活動時期よりは前となる.日本海拡大に伴う西南日本の時計回りの回転を元へ戻した時のMTLの走向(西南日本の帯状構造の方向)をN30°Eとした時に,ナップ構造をもたらした圧縮テクトニクスの背景を考察すると,一つの可能性として太平洋プレートの移動方向がWNWのハワイ諸島の方向へと転換したイベントである50 Ma前後 (O’Connor, et al., 2013) が考えられる.この南への押し被せの時期については,解明すべき重要な課題として残されている.文献 新井宏嘉・高木秀雄,1998,地質雑,104,861-876.Arai, H., Kobayashi, K. and Takagi, H., 2008, Gondwana Res., 13, 319-330.生野賢司ほか,2016,日本古生物学会第165回例会講演要旨P.29.Kobayashi, K., 1996, Jour. Struct. Geol., 18, 563-571.Matsukawa, M. and Obata, I., 2012, Bull. Tokyo Gakugei Univ., Natr. Sci., 64, 143-152.Miyashita, A. and Itaya, T., Gondwana Res., 5, 837-848.中畑浩基ほか,2015,地学雑, 124, 633−656.O'Connor, J. M. et al., 2013, Geochem. Geophys. Geosyst., 14, 4564-4584.高木秀雄・柴田 賢,2000,地質学論集,no. 56, 1-12.竹内圭史・牧本 博,2003, 日本地質学会第110年学術大会講演要旨,69.
- 著者
- Dirican Melahat Sarandol Emre Ulukaya Enjin
- 出版者
- 徳島大学
- 雑誌
- The journal of medical investigation : JMI (ISSN:13431420)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.169-172, 1999
- 被引用文献数
- 1
Cigarette smoking is one of the major risk factors for cardiovascular disease.The mechanism responsible for this association is still unknown. We measured the activity of lecithin:cholesterol acyltransferase (LCAT), a key factor in the esterification of plasma cholesterol and reverse cholesterol transport, and the levels of lipids and apolipoproteins in the serum of 27 cigarette smoking and 31 non-smoking (control) men. We could not find any significant difference among these parameters between the groups. Serum LCAT activity was lower in smokers, but the difference was statistically nonsignificant. We also classified the two groups in respect to their serum lipid levels as hyper- and normolipidemic, we observed that normolipidemic-smokers had lower (p<0.05) high density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) and HDL-ester cholesterol levels compared to the normolipidemic-nonsmokers. While there were no any significant differences between hyperlipidemic-smokers and nonsmokers with respect to any of the parameters.In the end we have got the idea that smoking seems to affect HDL-C and HDL-ester cholesterol levels in the normolipidemic-smokers group, only, Also, LCAT activity tended to be lower in smokers compared to nonsmokers.
1 0 0 0 OA 康富記 36巻
- 著者
- [中原]康富 [著]
- 巻号頁・発行日
- vol.[33], 1000
1 0 0 0 lcm(エル・シー・エム)
- 著者
- 牧野 智哉
- 出版者
- 一般社団法人 画像電子学会
- 雑誌
- 画像電子学会研究会講演予稿
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.69-70, 2006
周期の異なるサウンドループを仮想の惑星の公転運動に見立てて視覚化した、映像+音響インスタレーション作品。各惑星は、それぞれに割り当てられたサウンドループが一周する時間で太陽のまわりを一周し、公転周期(サウンドループの長さ)の差によって音の重なり方は常に変化していく。鑑賞者はコントローラーで宇宙船を操作して、音の太陽系を探索する。
- 著者
- 尾方 隆幸
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2018年大会
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-14
Geoparks require effective outreach and education based on academic terminology. Science Council of Japan (SCJ) reported terminological variation on all geoscience textbooks used in senior high schools. Such a situation also leads to terminological confusion in lifelong education and geoscience outreach. Geoscientific terms are likely to vary among many geoparks in Japan. Geoparks should consider terminological problems, and use academically appropriate terms for geoscientific education and geotourism.
1 0 0 0 気球における二次元日食画像の採取とその記録
- 著者
- 磯部 [シュウ]三 狛 豊 宮木 末雄
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.35, pp.27-32, 1983
1983年6月11日のインドネシア・ジャワ島での日食時に, 太陽外層コロナの観測を気球を使って行った.この観測により, 太陽周辺に微粒子の密度が高いリング状の構造が存在していることを明らかにした.日食という短時間の現象をしかも空の明るさが刻々変化する中での微弱光の観測であるので, 技術的にむつかしい面が多かった.そのため, 二次元で高感度しかも比較的時間分解能のよいSIT受光器を用いた.多量のデータを上空30kmの気球上で採取し, その一部を地上に送信し, 大部分のデータをビデオ・コーダーに記録した.これらのデータを地上で再生して, 十分に雑音レベルの低い像を得る事ができた.そして, 太陽のまわりに存在する微粒子の輪という天文学的に意義のある結果を得ることができた.