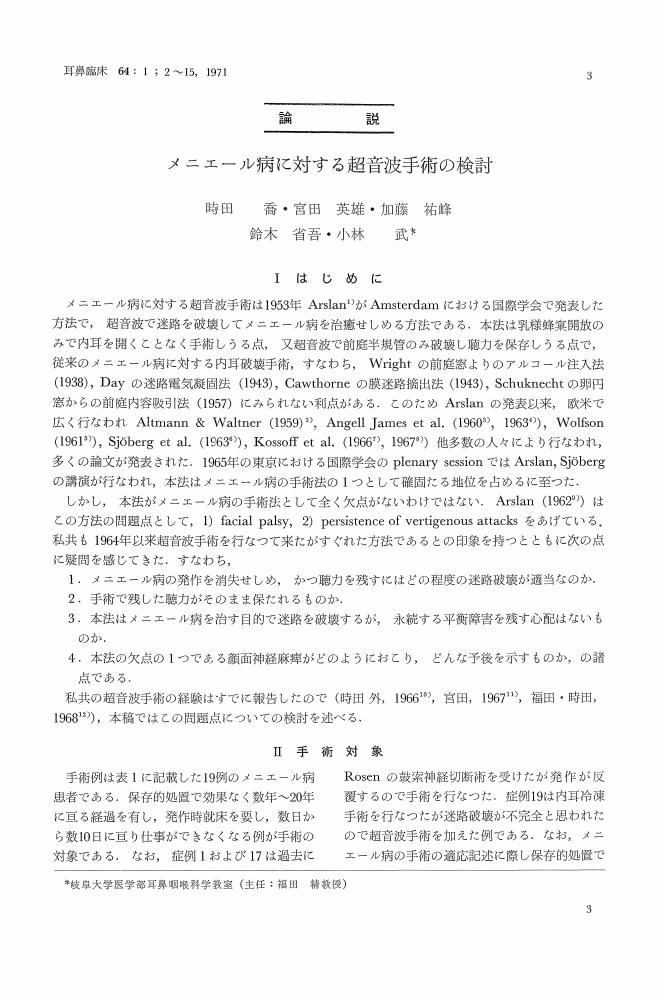1 0 0 0 広島原爆早期入市者の疾病記録と誘導放射能による外部被曝量の評価
- 著者
- 今中 哲二 遠藤 暁 川野 徳幸 田中 憲一
- 出版者
- Journal of Radiation Research 編集委員会
- 雑誌
- 日本放射線影響学会大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.146-146, 2009
広島・長崎の原爆直後に爆心地近辺に入った早期入市者については、入市直後にさまざまな疾病が現れたことが知られている。従来より誘導放射線による被曝影響の可能性が指摘されているものの、その因果関係を検討するには、個々の入市被爆者に関する情報が不十分であった。2008年8月に放映されたNHKの番組の中で、早期入市者の病状について1950年頃にABCCが聞き取り調査を行った個人記録が紹介された。その記録によると、嘔吐、下痢、脱毛といった、急性放射線障害と同様の症状が起きていたことが確認されている。我々は、そのような記録がある2名に入市時の行動についてインタビューを行い、行動経路に基づいて誘導放射能からの外部被曝を計算した。8月7日に入市し、爆心から900mの自宅に立ち寄り、一週間ほど文理大グラウンド(1400m)で寝泊まりしたAさんの被曝量は9.40mGyとなった。不確定さを考慮しここでの見積もりは約30mGyとした。Aさんは、8月13日に発熱、下痢、口内痛を発症、1ヵ月後に歯齦出血、脱毛があった。8月7日に、比治山から電車通り沿いに爆心近くを通って己斐駅まで歩いたBさんの被曝量は2.6mGyとなったが、不確定さを考慮し約8mGyと見積もった。Bさんは、9月12日に嘔吐、下痢で病臥、10月5日頃に脱毛がはじまった。AさんやBさんの病状は急性放射線症状を想定させる一方、従来の知見に基づくと、かれらの被曝量の見積もりは放射線症状を引き起こすほどではない。我々としては、以下の3つの可能性を考えている。(1)観察された疾病は、疲労や感染症などによるもので放射線被曝とは関係ない、(2)被曝量の見積もりが大きく間違っている、たとえば、本研究の見積もりには含まれていない内部被曝の寄与が大きかった、(3)原爆被爆という極限的な状況下で、放射線被曝が他の要因と複合的に作用して閾値が大きく下がり急性放射線障害のような症状が現れた。どの説明がより適切であるか今の段階では結論できないと考えている。
1 0 0 0 OA 刑法各論覚書(1) : いわゆる「わいせつ」三要素と「強制わいせつ」罪(一七六条)
- 著者
- 伊藤 司
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- 法政研究 (ISSN:03872882)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.343-350, 1996-11-21
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 私の見た布哇の土地
- 著者
- 山口 君子
- 出版者
- Osaka Urban Living and Health Association
- 雑誌
- 家事と衛生 (ISSN:18836615)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.71-74, 1929
1 0 0 0 OA メニエール病の治療効果の判定
- 著者
- 時田 喬 宮田 英雄 牧 達夫 浅井 徳光 橋本 正彦 前田 正徳 棚橋 聰子
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.6special, pp.1124-1130, 1980-06-25 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 4
We report herein the examinations required for evaluation of the effects of treatment of Meniere's disease. Prior to the discussion, it is indispensable to clarify the design of the treatment. In the treatment, the authors take into consideration the following three subjects: (1) treatment of vertigo, (2) treatment of damage to the inner ear, and (3) treatment of recurrence of attacks of vertigo.(1) For evaluation of effects of treatment of vertigo in attacks and dizziness in the chronic stage of the disease, complaints of vertigo and spontaneous nystagmus as objective evidence of vertigo should be investigated. Furthermore, righting reflex and deviation test should be performed in order to demonstrate the mechanism of improvement of the vertigo. Despite the improvement obtained by inhibitory effects of drugs on the vertigo, the righting function and deviation phenomenon remain unchanged. On the contrary, when the pathological condition of the inner ear is healed there is an improvement of these signs.(2) Effects of the treatment for damage of the inner ear are evaluated by hearing and caloric tests. In cases where the labyrinthine excitability is not reversible, compensatory process of balancing activity of the body should be examined using the standing test, tests for spontaneous nystagmus, deviation and caloric tests and tests for postrotatory nystagmus. Disappearance of spontaneous nystagmus and deviation phenomenon reveal a recovery of static balance of the vestibular system. Disappearance of asymmetry of postrotatory nystagmus indicates a restoration of balance in the kinetic labyrinthine reflexes.(3) Recurrences of attacks of vertigo are treated on the basis of the results of examination of etiologic factors of Meniere's disease in each patient. Effects of this treatment should be evaluated by long-term follow-up of the vertiginous attacks.
1 0 0 0 OA メニエール病に対する超音波手術の検討
- 著者
- 小内 透
- 出版者
- 北海道社会学会
- 雑誌
- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.38-61, 1992
本稿では、旭川市の小中高校生を対象に、子どもたちの生活の全体像を浮き彫りにし、「学歴社会」といわれている現実が、児童・生徒の生活にいかなる問題を生み出しているのかを明らかにした。<BR>その結果、第一に、旭川の子どもたちは、「学歴獲得競争」をそれほど重視せずフォーマルな「学校文化」に背をむけて日々を過ごしていたこと、第二に、「学歴社会」は、(1)学年の上昇にともなう「社会関係からの孤立化傾向」、(2)拡大する親子の間の認識のズレ、(3)「底辺校」の高校生の職業選択の遅れ、(4)「学ぶこと」の真の意義の喪失等々の問題を生み出していたこと、第三に、その中で、学歴獲得競争に比較的積極的な姿勢を示していたのは、管理的職業や専門技術の親をもつ一部の階層の小中学生であったこと、第四に、高校段階になると階層差は進学校と「底辺校」の生徒の出身階層の違いとなって現われていたことが明らかになった。<BR>このことは、一方で、子どもたち全体の生活や意識の変化の中に「学歴社会」の弊害を見いだすことの重要性、他方で、「学歴社会」における学歴獲得が決して平等な形で展開されているものではないという事実を示している。<BR>「学歴社会」の克服は、これらの点をふまえなければ十全な形で実現することはできないといえる。
1 0 0 0 OA 康徳七年滿洲國臨時國勢調査に依る確定人口の發表
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- 人口問題研究
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.10, 1942-10
1 0 0 0 定型表現集の活用を支援する言語処理基盤技術の研究
- 著者
- 原田 武
- 出版者
- 大阪外国語大学
- 雑誌
- Etudes francaises (ISSN:0285984X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.1-23, 1994-03-30
- 著者
- Hoichi Amano Yoshiharu Fukuda Takashi Yokoo Kazue Yamaoka
- 出版者
- Japan Atherosclerosis Society
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- pp.42036, (Released:2018-03-27)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 16
Aim: Shift workers have a high risk of cardiovascular disease (CVD). Systemic inflammation measured has been associated with the risk of CVD onset, in addition to classical risk factors. However, the association between work schedule and inflammatory cytokine levels remains unclear. The purpose of this study was to examine the association between work schedule and interleukin-6 (IL-6)/high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) levels among Japanese workers.Methods: The present cross-sectional study was a part of the Japanese Study of Health, Occupation and Psychosocial Factors Related Equity (J-HOPE). A total of 5259 persons who measured inflammatory cytokine were analyzed in this study. One-way analysis of variance was used to test log-transformed IL-6/hs-CRP differences by work schedule. Multiple regression analysis was used to examine the difference adjusted for other possible CVD risk factors.Results: There were 3660 participants who had a regular work schedule; the remaining schedules were shift work without night work for 181 participants, shift work with night work for 1276 participants, and only night work for 142 participants. The unadjusted model showed that only night workers were significantly related to high levels of IL-6 compared with regular workers. Even in the multiple regression analysis, the higher level of IL-6 among only night workers remained significant (β=0.058, P=0.01). On the contrary, hs-CRP was not.Conclusion: The present study revealed that only night shift work is significantly associated with high levels of IL-6 in Japanese workers. These observations help us understand the mechanism for the association between work schedule and CVD onset.
- 著者
- 大須賀 愛幸 植松 洋子 山嶋 裕季子 田原 正一 宮川 弘之 高梨 麻由 門間 公夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.73-79, 2018-04-25 (Released:2018-04-25)
- 参考文献数
- 12
高タンパク食品中の酸性タール色素分析法について,回収率に優れ,かつ簡便で迅速な試験法を作成した.試薬量等のスケールダウンを行い,さらにポリアミド (PA) カラムに負荷する液の調製法として,溶媒留去の替わりに抽出液を水で希釈し有機溶媒濃度を下げ,色素をPAカラムに保持させることにより,操作の簡便化および迅速化を達成した.またPAカラムで色素を精製する際,負荷する液のpHを汎用されるpH 3~4からpH 8.5にすることで,高タンパク食品における,キサンテン系色素の回収率が大きく向上した.高タンパク食品の中でも特に酸性タール色素の分析が困難とされてきた辛子明太子での11種類の色素の回収率はpH 8.5で精製することで63~101%となり,pH 3.5での精製(回収率18~95%)に比べ大幅な改善が認められた(5 μg/g添加).
- 著者
- 高橋 迪子 安田 祐加 高橋 肇 武内 章 久田 孝 木村 凡
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.89-92, 2018-04-25 (Released:2018-04-25)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4
本研究では,菓子パン等の材料であるフィリング中におけるノロウイルスの生残性と,近年抗ウイルス効果が見いだされた加熱変性リゾチームの有効性を検証した.小売店で購入したチョコレートクリームおよびマーマレードジャムにMurine norovirus-1 (MNV-1) を4.5 log PFU/g接種し,4℃で5日間保存したところ,MNV-1の感染価は5日間ほとんど減少しなかった.一方,加熱変性リゾチームをこれらフィリング中に1%添加することで,フィリングに接種したMNV-1は0.9~1.2 log PFU/g減少した.
1 0 0 0 OA 船舶の航行水域につくられる橋梁の安全対策(<特集>橋と船舶航行)
- 著者
- 庄司 邦昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本航海学会
- 雑誌
- 航海 (ISSN:24331198)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.26-36, 1991-06-25 (Released:2017-07-12)
1 0 0 0 OA 国会法の政党間移動制限規定(109条の2)をめぐる憲法問題
- 著者
- 野畑 健太郎
- 雑誌
- 白鴎大学法科大学院紀要 = Hakuoh law review (ISSN:18824277)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.11-31, 2010-10-01
1 0 0 0 図解スポーツ大百科
- 著者
- フランソワ・フォルタン編著 室星隆吾監訳
- 出版者
- 八峰出版 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2006