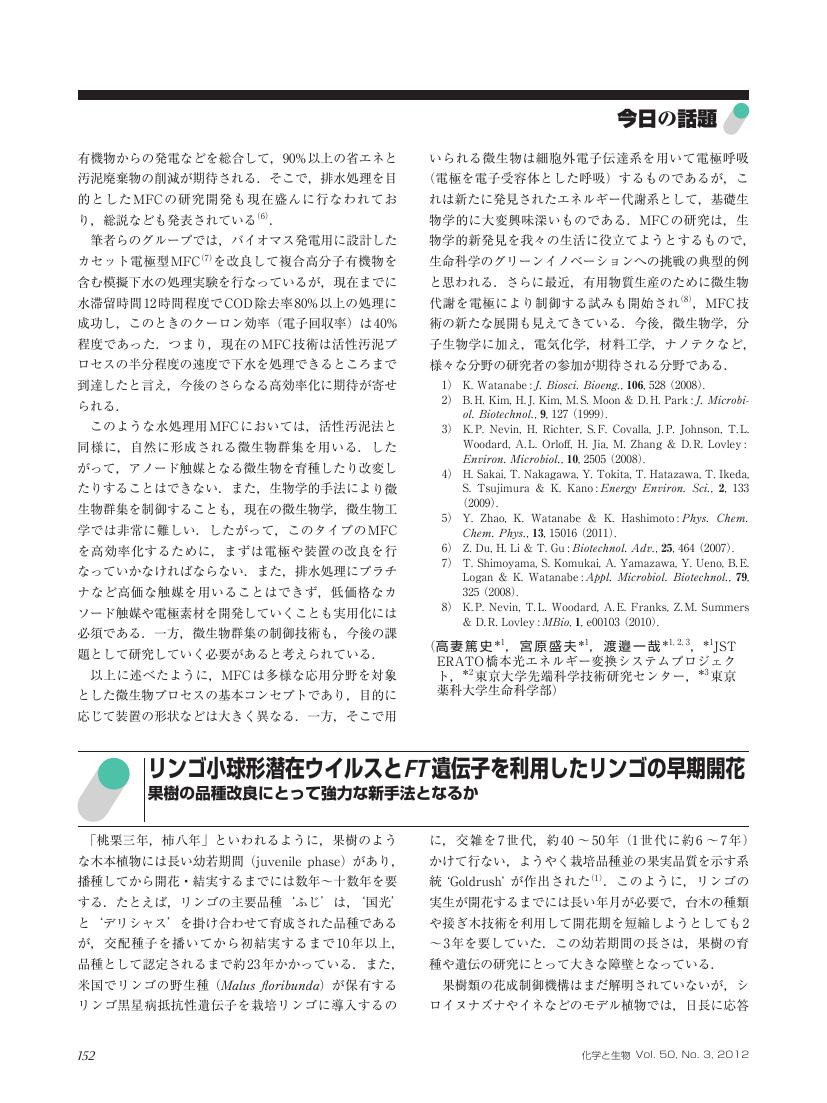5 0 0 0 OA ゲイアイデンティティとゲイコミュニティの関係性の変遷
- 著者
- 森山 至貴
- 出版者
- The Kantoh Sociological Society
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.23, pp.188-199, 2010-08-30 (Released:2015-06-12)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1 1
Gay identity and gay community are both central topics in gay studies and queer studies. However, the relationship between them remains unquestioned. This paper reveals how the relationship between gay identity and gay community has been shifted from the 90's to the present based on an analysis of discourses on coming-out.Coming-out in the 90's included three important elements: aspiration for making a good relationship, high self-reflexivity and entry into the gay community. However, the latter two elements have disappeared and the meaning of coming-out has shifted. This shift demonstrates that the relationship between gay identity and gay community has become more and more irrelevant and independent.
- 著者
- 山田 真紀 藤田 英典
- 出版者
- 椙山女学園大学教育学部
- 雑誌
- 椙山女学園大学教育学部紀要 = Journal of the School of Education, Sugiyama Jogakuen University (ISSN:18838626)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.111-127, 2022-03-01
同じ質問項目を用いた二つの質問紙調査PACT1995とNAPP2018を用いて,この22年間に,教員の意識のうち「同僚との関係性」「学校の役割範囲」「教職観や働き方」の3点においてどのような変化があったのかを統計的に明らかにすることを試みた。その結果,①同僚性については,同僚との関係性が希薄化し,同僚関係を負担に感じる教員が増加しているとともに,他の教師の学級経営について議論の俎上にあげていた風土も,余計な軋轢を避けるための不干渉へと移りつつあること,②学校の役割範囲については,生活習慣・基礎的学力・受験学力・思いやりなどの社会性を学校の役割範囲ととらえる割合が低下し,限定的な教職観を持つ教員が増加していること,③教職観や働き方については,教職のサラリーマン化ともいえる傾向が進み,あまり努力することなく,熱意を持つこともなく,淡々と勤務するタイプの教師が増えていること等を明らかにすることができた。
5 0 0 0 OA 伊曽保物語 3巻
- 出版者
- 伊藤三右衛門
- 巻号頁・発行日
- 1659
イソップ物語を翻訳した仮名草子。前段は伊曽保の伝記、後段は喩言の構成をもつ。慶長・元和から寛永にかけて古活字版数種が刊行されたが、本書は万治2(1659)年刊の整版本。当館所蔵の古活字本(請求記号:WA7-31)と物語の構成、内容は同じであるが、上中下各巻にそれぞれ5図を有する絵入り本である。当館本は、幕末・明治の蔵書家中川徳基(1833-1915)の旧蔵書。裏表紙見返しに、旧蔵者中川及び江戸後期の和学者山崎美成(1796-1856)の識語を記した紙片が貼付されている。
5 0 0 0 OA 関節軟骨の破壊と修復の機序
- 著者
- 久保 俊一 高橋 謙二
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.70-75, 2001-03-31 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 28
- 著者
- 松岡 是伸
- 雑誌
- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 = Hokusei Review, the School of Social Welfare (ISSN:13426958)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.87-101, 2021-03-15
5 0 0 0 OA 広島大学皮膚科外来での蕁麻疹の病型別患者数
- 著者
- 田中 稔彦 亀好 良一 秀 道広
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.134-139, 2006-02-28 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 9
【背景】蕁麻疹の病態・原因は多様であり,これまでに様々な分類法が用いられてきた.平成17年に日本皮膚科学会より「蕁麻疹・血管性浮腫の治療ガイドライン」が作成され,必要となる検査の内容と意義,治療内容,予後の視点を重視した病型分類が示された.【方法】平成15年から17年に広島大学病院皮膚科外来を受診した260名の蕁麻疹患者をこの分類法に準拠して病型を診断し,その内訳を調査した.【結果】物理性蕁麻疹10.0%,コリン性蕁麻疹6.5%,外来物質による蕁麻疹は6.5%であり,残りの76.9%が明らかな誘因なく生じる特発性の蕁麻疹であった.また38.8%の患者で複数の病型が合併しており,特に慢性蕁麻疹と機械性蕁麻疹あるいは血管性浮腫との合併が多く見られた.【結語】多くの蕁麻疹は丁寧な病歴聴取と簡単な負荷試験により病型を診断することができ,それを踏まえて検査,治療内容の決定および予後の推定を行うべきであると考えられる.
5 0 0 0 OA Transformer-based Siamese and Triplet Networks for Facial Expression Intensity Estimation
- 著者
- Motaz SABRI
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- International Journal of Affective Engineering (ISSN:21875413)
- 巻号頁・発行日
- pp.IJAE-D-22-00011, (Released:2022-12-13)
- 参考文献数
- 76
- 被引用文献数
- 1
Recognizing facial expressions and estimating their corresponding action units’ intensities have achieved many milestones. However, such estimating is still challenging due to subtle action units’ variations during emotional arousal. The latest approaches are confined to the probabilistic models’ characteristics that model action units’ relationships. Considering ordinal relationships across an emotional transition sequence, we propose two metric learning approaches with self-attention-based triplet and Siamese networks to estimate emotional intensities. Our emotion expert branches use shifted-window SWIN-transformer which restricts self-attention computation to adjacent windows while also allowing for cross-window connection. This offers flexible modeling at various scales of action units with high performance. We evaluated our network’s spatial and time-based feature localization on CK+, KDEF-dyn, AFEW, SAMM, and CASME-II datasets. They outperform deep learning state-of-the-art methods in micro-expression detection on the latter two datasets with 2.4% and 2.6% UAR respectively. Ablation studies highlight the strength of our design with a thorough analysis.
5 0 0 0 OA 重度上肢麻痺患者の麻痺手を生活に転移させるための方略 ―インタビューを用いた質的研究―
- 著者
- 萩原 祐 丸山 祥 長山 洋史
- 出版者
- 一般社団法人 神奈川県作業療法士会
- 雑誌
- 神奈川作業療法研究 (ISSN:21860998)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.10-18, 2022 (Released:2022-07-29)
- 参考文献数
- 19
本研究は,セラピストが重度上肢麻痺患者の麻痺手を生活に転移させるための方略について明らかにすることを目的として実施した.対象者はCI療法の経験がある作業療法士とし,計8名(平均臨床年数10.6±4.0年)とし,個別インタビューを実施した.データから,Steps for Coding and Theorizationを用いて分析した.結果,麻痺手を生活に転移させるために,1)心理的支援として成功体験が積めるよう難易度の調整を行うこと,2)生活面の工夫として自助具を使用すること,3)導入方法の工夫として目標設定ツールの使用や家族の協力を得ること,4)目標設定の工夫として具体的な目標設定を敢えて行わない可能性があることが示唆された.
5 0 0 0 OA 気分障害,統合失調症のWAIS-Ⅲのプロフィール傾向について
- 著者
- 滑川 瑞穂 横田 正夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第76回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.3PMC07, 2012-09-11 (Released:2020-12-29)
5 0 0 0 OA 歴史家の見た御伽草子『猫のさうし』と禁制
- 著者
- 上田 穰 Minoru UYEDA
- 雑誌
- 奈良県立大学研究季報 = NARA PREFECTURAL UNIVERSITY KENKYUKIHO (ISSN:13465775)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2・3, pp.9-18, 2003-12-10
5 0 0 0 OA 日本語アクセント史研究とアクセント観(<特集>音韻史研究の現状と課題)
- 著者
- 上野 和昭
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.47-57, 2003-04-30 (Released:2017-08-31)
In the historical studies of Japanese accent, especially in those using the written texts, the pitch accent is often described with the discreet levels. Since this 'level' view is sometimes subject to criticism, I review the discussions concerning the notions such as 'tone-bearing units' or 'compound accent' and examine their validity. The purpose is not to argue against the 'non-level' view, but to develop further the insights obtained both by the level and non-level approaches. The discussion here would contribute toward establishing the method of the historical research of Japanese accent which is more practical both for the text and field researches and which at the same time can approach the true nature of Jananese accent.
5 0 0 0 OA マイノリティ言語の保全政策の規範理論 : 言語の公共的機能からの基礎づけ
- 著者
- 辻 康夫
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.55-89, 2022-07-29
- 著者
- 吉川 信幸 山岸 紀子
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.152-154, 2012-03-01 (Released:2013-03-01)
- 参考文献数
- 6
5 0 0 0 OA 本棟造民家の分布と信濃小笠原氏支配地域の関連について
- 著者
- 中尾 七重
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.603, pp.147-154, 2006-05-30 (Released:2017-02-17)
- 参考文献数
- 51
In this paper we argue the coincidence of distribution area of Honmune style minka and the territory controlled by the Ogasawara, the Constable of Shinano. The factors of the coincidence are as follows: 1. The Ogasawara made it their policy to give members of the local gentry permission to erect decorative gables in the Sengoku period. 2. Under the peasant proprietorship of the Edo period, these of jizamurai descent and village officials expressed their status through minka design. 3. The feudal lord allowed this because it was conducive to stability and smooth collection of land tax. In conclusion, the Honmune style originated in medieval times and revived at the Edo period.