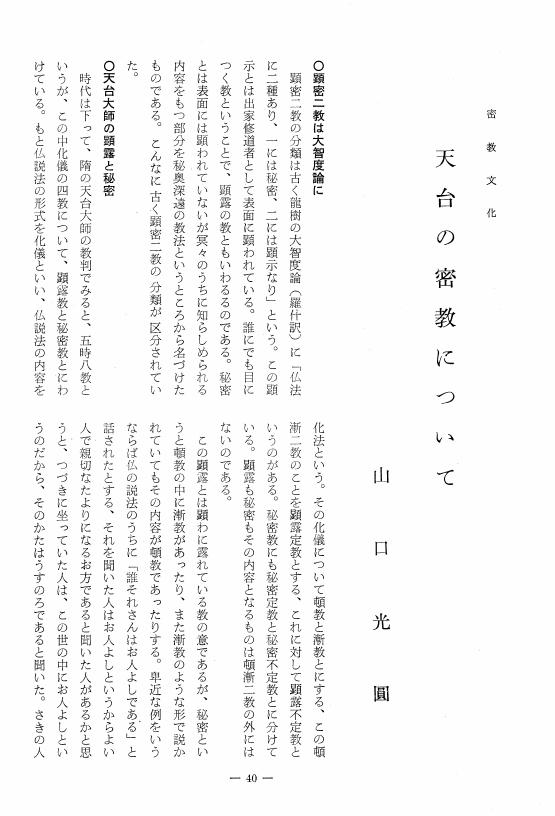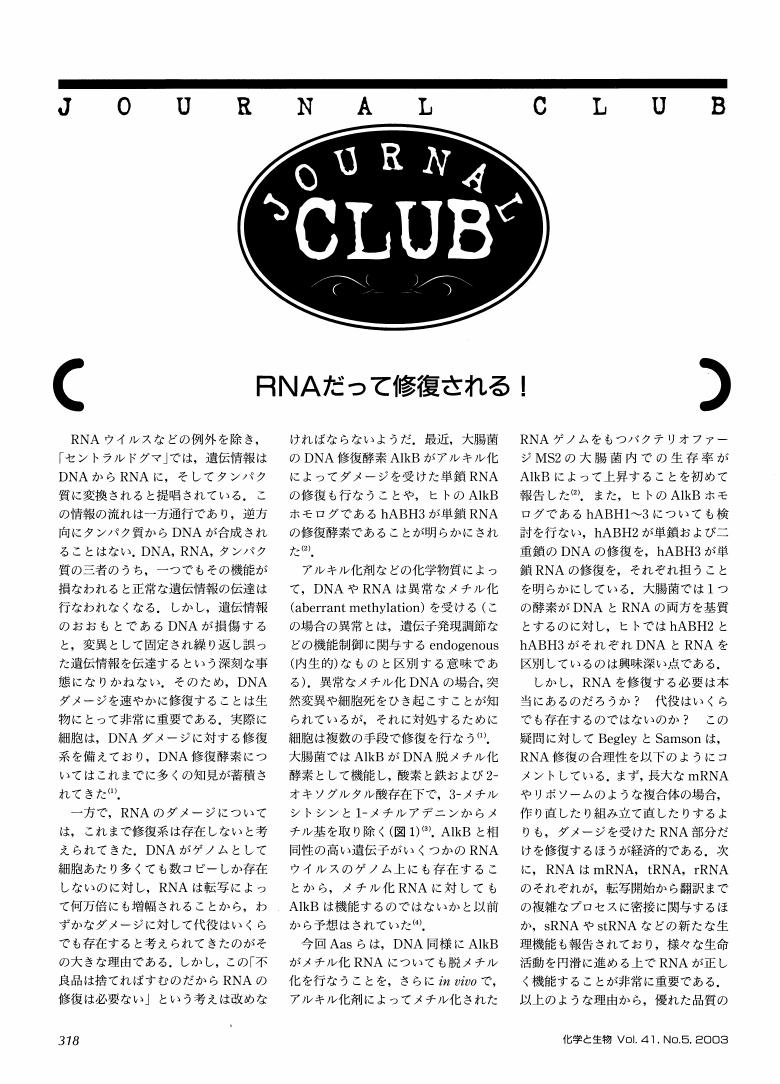5 0 0 0 OA 天台の密教について
- 著者
- 山口 光圓
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1964, no.69-70, pp.40-60, 1964-11-30 (Released:2010-03-12)
5 0 0 0 IR ディズニー版『白雪姫』のりんごをめぐる物語の変容 : 「毒」から「かわいい」への変遷
- 著者
- 川村 明日香 Kawamura Asuka カワムラ アスカ
- 出版者
- 大阪大学大学院言語文化研究科
- 雑誌
- 言語文化共同研究プロジェクト
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, pp.21-32, 2018-05-30
表象と文化 (15)
5 0 0 0 OA 受賞のことば
- 著者
- アンドルー・ゴードン 大網白里市教育委員会 沖縄アーカイブ研究所 久米川 正好 チーム カルチュラル・ジャパン 東京大学学術資産アーカイブ化推進室 中村 覚 青池 亨 木下 貴文 里見 航 川島 隆徳 大井 将生 永崎 研宣 柳 与志夫
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.147-150, 2021-07-01 (Released:2021-08-30)
5 0 0 0 OA 受賞者一覧と授賞理由
- 著者
- デジタルアーカイブ学会事務局
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.144-146, 2021-07-01 (Released:2021-08-30)
5 0 0 0 OA 美と民族の祭典 : オリンピア写真集
5 0 0 0 ヘビPLA2遺伝子の加速深化-I型PLA2遺伝子による検証-
ヘビ毒および哺乳類の膵液に含まれるいわゆる外分泌性ホスホリパーゼA2(PLA2)は、その一次構造が明らかになったものが多くある。両酵素間には一次構造におけるホモロジーがあるほか、X線結晶構造解析により明らかになった立体構造においても類似性がある。外分泌性PLA2は7個のジスルフィド結合の位置の違いにより2群(I型、II型)に分類される。I型PLA2はコブラ科、ウミヘビ科に属するヘビの毒や膵液に含まれるもので、Cys11とCys77間のジスルフィド結合が存在するのがその特徴である。さらにI型は、哺乳類膵臓由来のPLA2に存在する"pancreatic loop"の有る(IB)、無い(IA)により2つのサブグループに分類される。II型はマムシ科、クサリヘビ科に属するヘビの毒や炎症部由来の非膵臓型PLA2がこれに含まれる。一般に、ヘビ毒中のPLA2は神経・筋接合部の神経側に作用してアセチルコリンの放出を阻害することで毒性を発現する。コブラ科のヘビ毒中に存在するI型PLA2は、PLA2活性の強いもの、弱いもの、毒性の全くないもの、強いものまでいろいろで、なかにはtipoxinγやOphiophagus hannnahの毒由来PLA2のように、"pancreatic loop"を持つものも知られている。沖縄産エラブウミヘビの毒液中にはI型PLA2が存在することが既に明らかになっている。本研究では、エラブウミヘビ毒腺並びに膵臓で発現しているIA及びIB型PLA2遺伝子(cDNA、genome DNA)の構造を明らかにした膵臓由来I型(IB)PLA2と毒腺由来I型(IA)PLA2の遺伝子を比較したところ、イントロンは互いに良く保存されていたが、膵臓由来I型に存在する"pancreatic loop"および第4エクソンの後半部分が毒腺由来I型では欠損していた。毒腺が唾液腺から変化した器官であることを考慮すると、毒腺由来I型PLA2は膵臓由来I型のprototypeを祖先遺伝子として進化してきたと考えられる
5 0 0 0 OA 私の大学時代 -新世界に踏み出す皆さんへ-
- 雑誌
- 情報処理
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.363, 2015-03-15
- 著者
- 笹尾 俊明
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会論文誌 (ISSN:18835856)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.75-87, 2020 (Released:2020-11-07)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
持続可能な廃棄物処理を行う上で,廃棄物の収集運搬や処理の方法が費用に与える影響を把握することは重要である。廃棄物処理費用に関する既存の計量経済分析では,収集運搬・中間処理・最終処分の部門ごとの分析や,単独で事業を行う市町村と一部事務組合等との比較検討は不充分であった。本研究では,収集運搬・中間処理・最終処分の部門ごとに,単独で廃棄物処理事業を行う市町村と一部事務組合等の違いも考慮して,一般廃棄物の収集運搬・処理費用に関する計量経済分析を行った。分析の結果,収集運搬・中間処理・最終処分の全部門で規模の経済が確認され,特に中間処理と最終処分でそれが顕著であることがわかった。単独で収集・処理を行う市町村と比べ,組合等では収集運搬に係る平均費用が低く,また全部門で規模の経済の効果がより大きいことを明らかにした。組合等における費用削減要因として,委託費抑制による可能性を指摘した。
- 著者
- 遠藤 智世 エンドウ トモヨ Tomoyo Endo
- 出版者
- 立教大学グローバル都市研究所
- 雑誌
- グローバル都市研究 (ISSN:18838006)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.25-41, 2017
5 0 0 0 OA 芳譚
- 著者
- 遠藤総越 (金美) , 加藤桃蹊 (政憲) 編
- 出版者
- 東京書院
- 巻号頁・発行日
- 1909
5 0 0 0 OA 撤回:教授・学習研究の動向
- 著者
- 植木 理恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.298-298, 2014 (Released:2014-12-24)
本論文は掲載取り消しとなりました。
- 著者
- 平野 貴大 Takahiro Hirano
- 出版者
- 同志社大学一神教学際研究センター(CISMOR)
- 雑誌
- 一神教世界 = The world of monotheistic religions (ISSN:21850380)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.99-119, 2019-03-31
本稿の目的は、現在のイランの最高指導者であるハーメネイーのシャイフ・ムフィード観を分析することで、現代のシーア派学者が同派とムウタズィラ派との教義上の類似性をどのように説明するのかを解明することである。その分析を通じて、ハーメネイーをムフィードの学統に繋がる中道的な法学者・神学者として位置づけることも目指す。欧米研究者の通説によれば、ムフィードはムウタズィラ派をイマーム派に導入した、もしくはムウタズィラ派に強く影響を受けた合理主義者であるとされる。ハーメネイーは欧米研究者のムフィード観を批判し、ムフィードは法学と神学における伝承主義と合理主義の中道的な学統の創始者であると主張した。シーア派がムウタズィラ派を導入したという主張を否定することは、ハーメネイー独自の学説ではなく、シーア派学者の間の定説となっていた。以上より、保守派/原理主義者とみなされる傾向にあったハーメネイーはムフィードの学統に繋がる中道的な法学者・神学者として再評価されるべきであるといえる。
- 著者
- 金城 克哉 Kinjo Katsuya
- 出版者
- 琉球大学法文学部国際言語文化学科(欧米系)
- 雑誌
- 琉球大学欧米文化論集 (ISSN:13410482)
- 巻号頁・発行日
- no.57, pp.23-42, 2013-03
This paper tries to statistically analyze a Japanese singer and songwriter Noriyuki Makihara's original lyrics appeared in his seventeen albums from two view points. The first is to clarify the categorical ratio of the whole vocabulary. And the second point is to apply two cluster analyses (the hierarchical clustering and the centroid-based clustering) to see if these albums could form some clusters. The results show that,(i) the number of verbs outnumbers nouns in both types and tokens,and (ii) the centroid-based clustering shows that the albums before 2000 and after 2000 are divided except one album,and (iii) the hierarchical clustering shows that the first two albums forms one cluster,which could be supported by Makihara' s own words. Moreover,it is shown that the third cluster in the hierarchical clustering contains such words as ikiru (to live) and kokoro (heart) which displays Makihara' s ways of creating his lyrics after 2000.この論文は査読により、「研究論文集-教育系・文系の九州地区国立大学間連携論文集-」第1巻第1号(通巻第12号)に採択されたものである。
5 0 0 0 OA 高機能広汎性発達障害児・者をもつ親の気づきと障害認識 : 父と母との相違
- 著者
- 山岡 祥子 中村 真理
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.93-101, 2008-07-31 (Released:2017-07-28)
- 被引用文献数
- 1 2
本研究では、HFPDD児・者をもつ父母の障害の気づきと障害認識の相違を明らかにすることを目的とし、父母80組を対象に質問紙調査を行った。その結果、診断前後とも父母の障害の気づきと障害認識に有意な違いがあった。診断前、母親は父親よりも子どもの問題に幼児期早期から気づき深刻に悩んでおり、受診に対しても能動的であった。しかし、成長に伴い問題は解消すると考える傾向は父母で相違がなかった。診断時において、告知は父母どちらにも精神的ショックを与えていたが、障害認識は父母で違いが認められた。母親の多くは肯定・否定の両面的感情をもち、障害であると認めたのに対し、父親の多くは否定的な感情のみをもち、障害を認めにくかった。診断後は父母とも1年以内に障害を認めたが、母親は父親よりも積極的に障害を理解しようとしていた。
5 0 0 0 OA 金志成:破壊のエクリチュール トーマス・ベルンハルト『アムラス』のフラグメント性
- 出版者
- 日本オーストリア文学会
- 雑誌
- オーストリア文学 (ISSN:09123539)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.13-24, 2000 (Released:2021-04-03)
- 著者
- 友田 豊 友田 清 安藤 不二夫 梅津 朋和 水上 元
- 出版者
- FFIジャーナル編集委員会
- 雑誌
- Foods & food ingredients journal of Japan : FFIジャーナル (ISSN:09199772)
- 巻号頁・発行日
- vol.222, no.4, pp.327-332, 2017
5 0 0 0 OA RNAだって修復される!
- 著者
- 井沢 真吾
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.5, pp.318-319, 2003-05-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- Eri Toda Kato Shinya Goto
- 出版者
- Japan Atherosclerosis Society
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- pp.RV17049, (Released:2021-04-13)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
Atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) is the leading cause of morbidity and mortality across the world, warranting continuous research in this field. The elucidation of the atherogenesis mechanism is considered one of the most relevant scientific accomplishments of the last century. This has led to the clinical development of various novel therapeutic interventions for patients with or at risk of ASCVD, in which randomized clinical trials played a crucial role.The Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) Study Group was initially established to conduct a clinical trial studying thrombolysis for treatment of myocardial infarction. However, over the years, the TIMI Study Group has expanded their research interests to include antithrombotic therapy, lipid lowering, anti-diabetes, anti-obesity, and even heart failure. By leading large-scale, international, randomized, controlled trials of novel therapeutics, the TIMI Study Group has helped shape the very practice of cardiovascular medicine for over a quarter of a century, and decades of research continue to provide future promise for further advancement. Through a mutual goal to improve the care of ASCVD patients, the Japanese scientific community has become one of the important contributors to the TIMI Study Group's clinical research.In this review article, the authors aim to summarize major research lead by the TIMI Study Group in the ASCVD field.