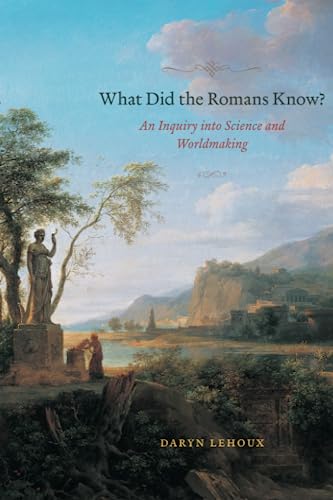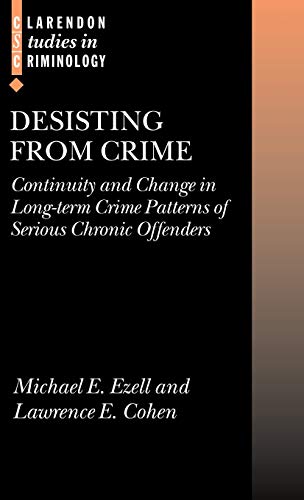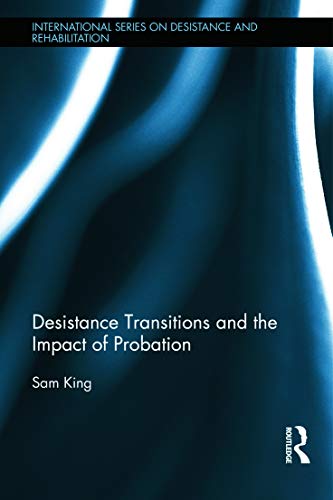1 0 0 0 トリの視覚世界から見える,ヒトの視覚世界
- 著者
- 中村 哲之
- 出版者
- The Japanese Psychonomic Society
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.96-101, 2014
Visual illusions in animals are important to study because they magnify how the perceptual system in each animal works. This paper reviews comparative studies on visual illusions in birds (pigeons and bantam chickens) and humans. Not only similarities but also dissimilarities in the perception of illusory figures between these animals have been shown, suggesting that the same physical environments may induce different visual worlds among the species.
1 0 0 0 脳波コミュニケーション技術の開発における脳科学と心理学の融合
- 著者
- 長谷川 良平
- 出版者
- The Japanese Psychonomic Society
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.86-90, 2014
An EEG-based brain–machine interface (BMI), "Neurocommunicator" has been developed by the authors research group in AIST in order to support communication of patients with severer motor deficits. The user can select one of registered messages in real time from electroencephalography (EEG) data and express it via his/her avatar. Integration of neuroscience and psychology will contribute to the future development, at hardware, software and service levels, of Neurocommunicator toward a commercial product.
- 著者
- 前川 和也
- 出版者
- 公益社団法人日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 咸臨 : 日本船舶海洋工学会誌 (ISSN:18803725)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.16-17, 2007-09-10
1 0 0 0 著作権法の一部を改正する法律(平成26年法律第35号)の解説
- 著者
- 文化庁長官官房著作権課
- 出版者
- 商事法務
- 雑誌
- NBL (ISSN:02879670)
- 巻号頁・発行日
- no.1038, pp.39-45, 2014-11-15
1 0 0 0 OA 住民が抱く犯罪不安の社会地理
- 著者
- 齊藤 知範
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2009年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.48, 2009 (Released:2009-12-16)
先行研究の問題点 先行研究によれば、犯罪不安とは、「犯罪や、犯罪に関連するシンボルに対する情緒的反応」、被害リスク知覚は、「犯罪被害に遭う主観的確率」とそれぞれ定義することができ、別々の構成概念として捉えることが可能である。 阪口(2008)が用いている、2000年のJGSS(日本版総合社会調査)における分析指標は、「あなたの家から1キロ(徒歩15分程度)以内で、夜の1人歩きが危ない場所はありますか(1 ある、0 ない)」である。アメリカのGSSが”afraid”という言葉を用いて「夜の1人歩きが不安な場所があるか」と尋ねており犯罪不安の指標に近いのに対して、JGSSの指標は「夜の1人歩きが危ない場所はあるか」と尋ねているためリスク知覚に近く、犯罪不安の指標としては不適切であると考えられる。先行研究においても、犯罪不安を測るためには、JGSSの指標を今後「夜の1人歩きが不安な場所があるか」という指標に変更することも検討すべきであるといった重要な問題点が指摘されている(阪口 2008:475)。阪口(2008)などの先行研究においては、犯罪不安を測る上ではワーディングをはじめとする調査設計に大きな問題点があり、データの制約上、犯罪不安の要因構造に関して充分な検討をすることが困難である。さらに、犯罪不安に関する調査設計や分析に際して、地理的な観点は、これまでわが国の諸研究においてはほとんど考慮されてこなかった。 本研究のアプローチ これに対して、本研究においては、住民調査を実施し、犯罪不安に関する指標を心理的な側面と行動に関する側面とに切り分けて測定することにより、分析に使用する。行動に関する側面については、具体的にどのエリアに対して犯罪不安に由来する回避行動を取っているかを、白地図を用いて記入してもらう調査を併用している。 住民調査についての概要を記す。神戸市須磨区のニュータウン地区と既成市街地地区からそれぞれ2小学校区、3小学校区を任意に選定し、これら5校区の20歳から69歳までの成人住民の縮図になるように、住民基本台帳にもとづき、確率比例抽出法によってサンプリングした。1つの調査地点につき50名ずつを抽出し、50の調査地点の合計2500名を対象に、2009年1月から2月にかけて、郵送法により調査を実施した。回収率の向上を目的とする、督促とお礼状を兼ねたリマインダー葉書は、1回送付した。1086票が回収され、回収率は、43.4%であった。回答に不備のあった4票を除外し、1082票を分析対象とした。 当日は、その分析結果の一部について報告し、社会学的、地理学的視座から、いくつかの考察を加えることとしたい。
1 0 0 0 IR 自然と教育. 第24号
- 著者
- ナラキョウイクダイガクシゼンカンキョウキョウイクセンター 奈良教育大学自然環境教育センター
- 出版者
- 奈良教育大学自然環境教育センター
- 雑誌
- 自然と教育
- 巻号頁・発行日
- vol.24, 2014-12-01
奈良教育大学自然環境教育センターの20年(前編)/「雪への憧れ」から「雪の科学者・中谷宇吉郎」へ/国際交流と奈良実習園/奈良教育大学自然環境教育センター公開セミナー「最近の森林を見つつ、人と自然のかかわりを考える」を受講して/自然環境教育センターの新センター長の紹介/平成25年度自然環境教育センター事業報告/編集後記
1 0 0 0 位相コヒーレンスとアンダーソン転移の数値的研究
- 著者
- SLEVIN K.M
- 出版者
- 大阪大学
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2001
シンプレクティックな対称性をもった2次元系のアンダーソン転移の臨界指数を、いわゆるSU(2)モデルのシミュレーションにより正確に決定した。今まで数多くのシミュレーションが行われてきた安藤モデルと比べて、このSU(2)モデルではスケーリングの補正が特に小さい。この特徴によりスケーリング補正を無視することが可能となり、従来に比べて非常に正確な臨界指数の決定が可能となった。本研究はPhysical Review Letters誌の2002年12月号に載された。MacKinnon-Kramer法による局在長の計算を改良し、並列計算機を効率的に利用できるようにした。東京大学物性研究所の並列計算機を利用することにより、3次元系SU(2)モデルの臨界指数の決定を現在進めている。磁性不純物を含んだランダム系におけるdephasingの問題を研究するプログラムを、このプロジェクトの初年度に開発した。しかしながら期待したよりもはるかし小さいdephasingの効果しか得られなかった。この理由は今後の研究課題である。
1 0 0 0 IR 「原爆投下理由」の再検証--スミソニアン原爆展論争から
- 著者
- 小室 憲義
- 出版者
- 愛知淑徳大学大学院コミュニケーション研究科異文化コミュニケーション専攻・言語文学研究所
- 雑誌
- 異文化コミュニケ-ション研究 (ISSN:13440837)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.163-180, 1998-02
- 著者
- Daryn Lehoux
- 出版者
- University of Chicago Press
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 OA 懐疑主義に対する或る古代の批判 ー アリストクレス「哲学について」より
- 著者
- 金山 弥平 Kanayama Yasuhira (Yahei)
- 出版者
- 名古屋大学文学部
- 雑誌
- 名古屋大学文学部研究論集 (ISSN:04694716)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.65-76, 1997-03-31 (Released:2006-02-14)
- 著者
- ハッサニン アミン 桑原 佐知 ヌルヒダヤット 塚本 康浩 小川 和重 平松 和也 佐々木 文彦
- 出版者
- 社団法人日本獣医学会
- 雑誌
- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.10, pp.921-926, 2002
- 被引用文献数
- 3 57
エストロジェン様化合物の魚への影響を研究する目的で,2つの汚染河川(石津川と和田川)と対照地域に生息する成熟雄性コイのゴナドソマチックインデックス([精巣重量/体重]×100:GSI)と精巣の形態を1998年6月〜2001年3月までの期間調べた.石津川のノニルフェノール,ビスフェノールAと17β-エストラジオールの含有濃度は和田川の3〜4倍高かった.繁殖前期と繁殖期では,3地域のコイの体重に有意の差はなかった.石津川のコイの体重は繁殖後期でのみ和田川のものより小さかった(P<0.05).石津川に生息するコイのGSIと精巣重量は精巣周期の全期間で対照のものより小さく(P<0.05),和田川のコイと比較すると繁殖前期と後期でより小さかった(P<0.05).組織学的な異常は調べた全精巣で見られなかった.精巣の組織学的な所見から,石津川のコイの精子形成開始時期は他の地域のものに比べて遅延していた.これらの結果は,石津川の水中に含有するエストロジェン様化合物がコイの精巣の発達に有害な影響を与えているということを明らかに示している.
1 0 0 0 OA 本草図譜
- 著者
- 岩崎常正<岩崎潅園>//著
- 巻号頁・発行日
- vol.第2冊 巻20湿草類8,
- 著者
- Toshiro Tango Toshiharu Fujita Takeo Tanihata Masumi Minowa Yuriko Doi Noriko Kato Shoichi Kunikane Iwao Uchiyama Masaru Tanaka Tetsunojo Uehata
- 出版者
- 日本疫学会
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.83-93, 2004 (Released:2005-03-18)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 14 34
BACKGROUND: Great public concern about health effects of dioxins emitted from municipal solid waste incinerators has increased in Japan. This paper investigates the association of adverse reproductive outcomes with maternal residential proximity to municipal solid waste incinerators.METHODS: The association of adverse reproductive outcomes with mothers living within 10 km from 63 municipal solid waste incinerators with high dioxin emission levels (above 80 ng international toxic equivalents TEQ/m3) in Japan was examined. The numbers of observed cases were compared with the expected numbers calculated from national rates adjusted regionally. Observed/expected ratios were tested for decline in risk or peak-decline in risk with distance up to 10 km.RESULTS: In the study area within 10 km from the 63 municipal solid waste incinerators in 1997-1998, 225, 215 live births, 3, 387 fetal deaths, and 835 infant deaths were confirmed. None of the reproductive outcomes studied here showed statistically significant excess within 2 km from the incinerators. However, a statistically significant peak-decline in risk with distance from the incinerators up to 10 km was found for infant deaths (p=0.023) and infant deaths with all congenital malformations combined (p=0.047), where a “peak” is detected around 1-2 km.CONCLUSION: Our study shows a peak-decline in risk with distance from the municipal solid waste incinerators for infant of deaths and infant deaths with all congenital malformations combined. However, due to the lack of detailed exposure information to dioxins around the incinerators, the observed trend in risk should be interpreted cautiously and there is a need for further investigation to accumulate good evidence regarding the reproductive health effects of waste incinerator exposure.
1 0 0 0 OA 地球観測フロンティアシステムの現状と将来について
- 著者
- 菱田 昌孝
- 出版者
- 公益社団法人日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- Techno marine : bulletin of the Society of Naval Architects of Japan : 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)
- 巻号頁・発行日
- no.856, pp.687-699, 2000-10-25
1 0 0 0 OA これからの光合成研究 : 生物物理の視点から
- 著者
- 三室 守
- 出版者
- 一般社団法人日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.88-96, 2008-03-25
Several essential points of photosynthetic light reactions were reviewed for future development of this scientific field and a general interest of biophysicists. Historical backgrounds of the reaction systems were also stated for the continuity of problems. Main points are reaction schemes and mechanisms of photochemical reactions in reaction center complexes, oxygen evolution, i.e. water cleavage and a high redox potential for water oxidation, and structures of reaction center complexes. These points will be solved by combination of spectroscopy and molecular biology. Photosynthesis will be utilized for our survival in the 21st century through their potentials in food supply, solar energy conversion and sustainable environmental preservation.
1 0 0 0 OA 精神疾患を呈する成人の家族を持つ者への認知行動論的アプローチの現状と課題
- 著者
- 長野 恭子 野村 和孝 嶋田 洋徳
- 出版者
- 早稲田大学人間科学学術院心理相談室
- 雑誌
- 早稲田大学臨床心理学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.129-139, 2014-01
1 0 0 0 IR 社交不安における回避行動を誘発する他者の表情刺激の処理に関する展望
- 著者
- 山下 歩 佐藤 友哉 千先 純 嶋田 洋徳
- 出版者
- 早稲田大学人間科学学術院心理相談室
- 雑誌
- 早稲田大学臨床心理学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.161-169, 2014-01
- 著者
- Michael E. Ezell and Lawrence E. Cohen
- 出版者
- Oxford University Press
- 巻号頁・発行日
- 2005