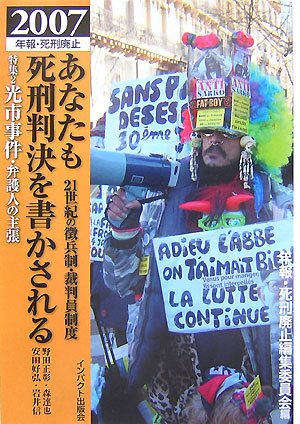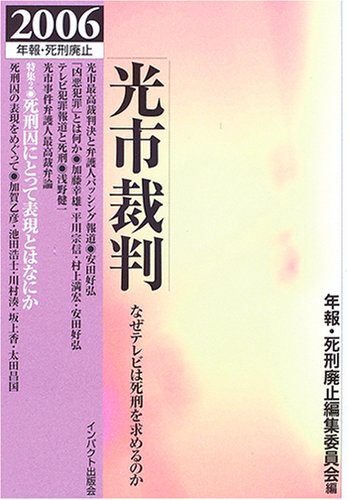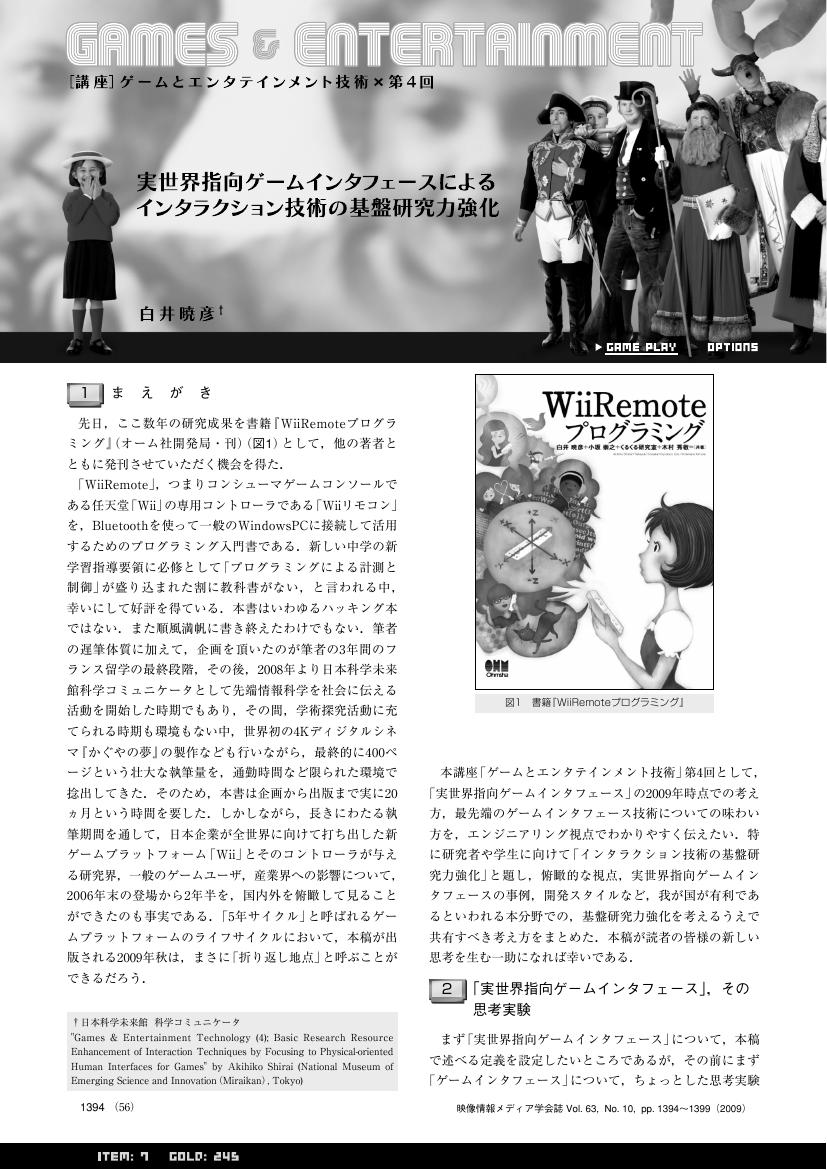3 0 0 0 OA 死刑の適用基準(最三小判平成18年6月20日判タ1213号89頁)
- 著者
- 諏訪 雅顕
- 出版者
- 信州大学
- 雑誌
- 信州大学法学論集 (ISSN:13471198)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.141-153, 2007-03-22
3 0 0 0 あなたも死刑判決を書かされる
- 著者
- 年報・死刑廃止編集委員会編集
- 出版者
- インパクト出版会
- 巻号頁・発行日
- 2007
3 0 0 0 光市裁判 : なぜテレビは死刑を求めるのか
- 著者
- 年報・死刑廃止編集委員会編集
- 出版者
- インパクト出版会
- 巻号頁・発行日
- 2006
3 0 0 0 高等裁判所刑事裁判速報集
- 著者
- 法務大臣官房司法法制調査部編
- 出版者
- 法曹会
- 巻号頁・発行日
- 1982
3 0 0 0 OA あいまいさと統合失調症
- 著者
- 岩満 優美
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.409-413, 2010-08-15 (Released:2018-01-26)
3 0 0 0 OA 花びら作りの分子メカニズム
- 著者
- 武田 征士
- 出版者
- 日本植物形態学会
- 雑誌
- PLANT MORPHOLOGY (ISSN:09189726)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.95-99, 2013 (Released:2014-09-26)
- 参考文献数
- 44
植物にとって,花は次世代へ遺伝情報を伝える重要な生殖器官である.雄しべと雌しべは生殖そのものに関わる一方,萼(がく)は花器官を外環境から守り,花びらは虫や鳥などの花粉の運び屋を惹き付ける.花びらはこの役割を果たすため,最も多様性に富む植物器官に進化してきている.モデル植物のシロイヌナズナの研究を中心に,花器官作りのメカニズムが遺伝子レベルで明らかにされてきた.最近の報告を含め,植物にとって重要な「花びら作り」に関わる遺伝子とメカニズムについて述べる.
3 0 0 0 OA 日本におけるパーソンセンタード・アプローチに関する文献リスト (2021)
- 著者
- 田中 秀男 並木 崇浩 青木 剛 坂中 正義
- 出版者
- 南山大学人間関係研究センター
- 雑誌
- 人間関係研究 = Human relations (ISSN:13464620)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.65-84, 2022-10-31
3 0 0 0 OA 脳死下臓器提供を行う子どもと家族へのケアと支援
- 著者
- 日沼 千尋 荒木 尚 種市 尋宙 西山 和孝
- 出版者
- 日本脳死・脳蘇生学会
- 雑誌
- 脳死・脳蘇生 (ISSN:1348429X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.82-90, 2022 (Released:2022-08-26)
- 参考文献数
- 6
〔目的〕脳死下臓器提供をする子どもと家族へのケアと支援の実際を明らかにし,体制整備に関して検討すること。〔方法〕小児の脳死下臓器提供を経験し,施設名が公表されている10医療施設の11例のドナーを担当した医療チームメンバーに子どもと家族に行った支援,ケアについてインタビューを行った。インタビューデータの中から子どもと家族に行ったケアに注目してデータを抽出し,質的に分析した。〔結果〕【子どもの尊厳を守りいつもと変わらずていねいに終末期のケアをする】【家族が子どものためにしてあげたいことは,できるだけ叶える】【自由に面会してもらい,ともに過ごす時間を十分にとる】【子どもと家族の物語りに耳を傾け,感情の揺れを受け止める】【家族の意思決定を支える】【きょうだいへのケアと説明を担う】【多職種チームでケアする体制を整え,カンファレンスで情報共有と検討を重ねる】【最期まで大切な子どもとしてケアする】【家族とともに体験を振り返る機会をもつ】の9つのカテゴリーが抽出された。〔考察〕脳死下臓器提供をする子どもと家族のケアにおいては,家族が子どものためにできるだけのことをやれたと思える丁寧な看取りのケアを基盤に,意思決定支援としては,子どもと家族のこれまでと,これからに描いていた物語に耳を傾けることの重要性が示唆された。課題としては,脳死下臓器提供時のケアに当たる医療スタッフの精神的な支援と学習機会の提供があげられた。
3 0 0 0 OA 人文学不要言説の分析 : 冨山和彦の『AI経営で会社は甦る』より
- 著者
- 石綿 寛
- 雑誌
- 総合福祉研究 = Social welfare research bulletin (ISSN:18818315)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.115-128, 2018-03-31
本論は,人文学不要言説の分析を実施した.既存の人文学を擁護する人文学擁護言説は,人文学の危機を人文学を聴く人々の無理解を巡る問題として議論していた.これに対し本論は,人文学の危機を人々の人文学からの撤退として議論する.この立場を取るならば,人文学の危機は,人々に人文学の意義を語ることでは解決されない.取り組むべきは,人々がなぜ人文学から撤退することが可能なのかという人文学と人々の距離を問うことである.このような問題意識にもとづき,本論は,人文学から距離を取り既存の人文学を不要とする冨山和彦の議論を分析した.冨山の論考から明確になったことは,社会構造を巡る理解の違いである.冨山にとって,技術革新などによって実現される社会構造は所与であり,その中でいかに効率的に政策を実施するかが重要な課題になっている.この理解の枠組みの中では,人間が社会構造を変えていくことを所与とする人文学は必要がないものとなる.
3 0 0 0 OA 新渡戸稲造の朝鮮(韓国)観
- 著者
- 田中 愼一
- 出版者
- 北海道大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- 經濟學研究 (ISSN:04516265)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.9-18, 2005-03-10
近代日本の人傑をとらえ、これを論評するのは容易であるはずはないだろう。高尚偉大なる人物にして且つ文筆家であれば、その一代の文業に精通することが期待されるだけに、余計そうなるであろう。1984 年制定の五千円札以来にわかに族生の感ある新渡戸稲造研究家、その一員に達していない私としては、いわゆる群盲象を評す、にとどまることを危惧しつつ書いたのがこの小論である。焦点は新渡戸稲造の朝鮮(韓国)観、それが年代を経るなかでどのように推移していったのか、を追跡しようとした。しかも、関連する事柄で興味が湧いた際には、追求していく本来の大通りから、時には註をステップ台にして横町へ飛び込み、場合によってはさらに横町から左右の細い路地を覗き込みながらあわただしく出入りしたかのごとき叙述もしたのであった。文化的架橋者たらんことを使命にしていたとおぼしき新渡戸稲造は、その生きた多端な時代の運命をよく担っていた方なのではないか、というのが私の擱筆感の一つである。
3 0 0 0 OA おさえておきたい基本判例 : 第6回
- 著者
- 木村恵子
- 出版者
- 労働者健康福祉機構
- 雑誌
- 産業保健21 : 産業医・産業看護職・衛生管理者の情報ニーズに応える
- 巻号頁・発行日
- vol.17(3), no.67, 2012-01-01
3 0 0 0 OA 書評 会田弘継著『破綻するアメリカ』
- 著者
- 山城 雅江
- 出版者
- 中央大学英米文学会
- 雑誌
- 英語英米文学 (ISSN:02867710)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.151-156, 2019-02-28
3 0 0 0 IR 幸せな生活の視座
- 著者
- 楠 幹江 山田 俊亮 Mikie Kusunoki Shunsuke Yamada
- 出版者
- 安田女子大学大学院
- 雑誌
- 安田女子大学大学院紀要 = The journal of the Graduate School, Yasuda Women's University (ISSN:24323772)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.171-182, 2018-03-31
衣・食・住などの生活は,生きる基本であり,幸せの基盤でもある。家政学はこの人間の生活を研究対象としており,生活の向上と人類の福祉を目的としている。「人類の福祉」の「福」「祉」は,共に幸せを意味する言葉であり,このため,家政学そのものを,幸せを追求する学問として捉えることができる。幸せとは何か?を検討する場合,健康をキーワードとすることは意味があることだと考える。ここでの健康は,WHO 憲章における内容を意味している。すなわち,「肉体的,精神的,社会的に完全に良好な状態である」ことが,健康の意味する内容である。したがって,衣・食・住それぞれの生活において,肉体的,精神的,社会的に良好な状態を維持することが,幸せな生活に繋がると考える。そのために,個人でできることは,家庭生活の営み行動を重視することである。
3 0 0 0 OA 更生施設の利用者の実態と支援課題に関する考察~全国更生施設実態調査結果を通して~
- 著者
- 川原 恵子
- 出版者
- 東洋大学社会学部
- 雑誌
- 東洋大学社会学部紀要 = The Bulletin of Faculty of Sociology,Toyo University (ISSN:04959892)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.131-149, 2019-12
3 0 0 0 OA 日露戦争-大東亜戦争間日本陸軍夜間攻撃戦例集 : [旧日本陸軍の夜間戦斗] 別冊
- 出版者
- [米極東陸軍司令部]
- 巻号頁・発行日
- 1954
3 0 0 0 OA 内外集団の比較の文脈が黒い羊効果に及ぼす影響 社会的アイデンティティ理論の観点から
- 著者
- 大石 千歳 吉田 富二雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.6, pp.445-453, 2001-02-25 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 1
Based on social identity theory (Tajfel, 1978), it is expected that black sheep effect occurs only in cases where ingroup members are compared with outgroup individuals. In study 1, 112 female student nurses were divided into two groups, and evaluated both outgroup and ingroup individuals (outgroup-ingroup condition), or ingroup members only (ingroup-only condition). Black sheep effect was found only in the outgroup-ingroup condition. Ingroup members in the condition were evaluated more extremely than those in the ingroup-only condition, and there was no significant difference between the evaluations of outgroup individuals in the outgroup-ingroup condition and ingroup members in the ingroup-only condition. The results confirmed the ingroup-outgroup comparison prediction. In study 2, in addition to rating four individuals, desirable or undesirable and ingroup or outgroup, 86 female student nurses were asked to indicate the importance of their own social identity. Mack sheep effect was observed, with perception of ingroup homogeneity strengthening ingroup identification, thereby facilitating black sheep effect. These findings support Turners self categorization theory (1982) as an explanation of the mechanism for black sheep effect.
3 0 0 0 OA 実世界指向ゲームインタフェースによるインタラクション技術の基盤研究力強化
- 著者
- 白井 暁彦
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.10, pp.1394-1399, 2009-10-01 (Released:2011-10-01)
3 0 0 0 OA 上杉博物館蔵林泉文庫旧蔵『源姓系図』の特徴について
- 著者
- 佐々木 紀一
- 出版者
- 山形県立米沢女子短期大学
- 雑誌
- 山形県立米沢女子短期大学紀要 (ISSN:02880725)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.1-27, 2016-12-26