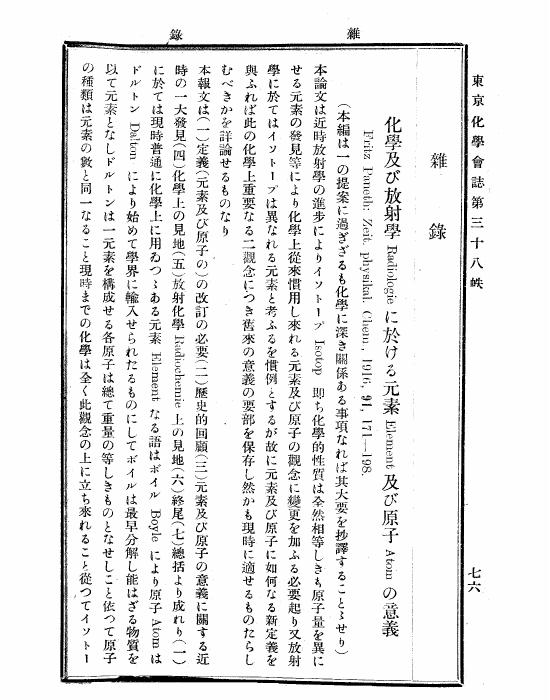- 著者
- 小谷 利明
- 出版者
- 日本史研究会
- 雑誌
- 日本史研究 (ISSN:03868850)
- 巻号頁・発行日
- no.510, pp.55-79, 2005-02
2 0 0 0 OA よみがえる江戸時代の村田 : 山田家文書からのメッセージ
- 著者
- 高橋 陽一 佐藤 大介 小関 悠一郎
- 出版者
- 東北大学東北アジア研究センター
- 雑誌
- 東北アジア研究センター報告 = CNEAS Report
- 巻号頁・発行日
- no.15, 2014-11-28
2 0 0 0 OA 人工血液(まねる化学 2)
- 著者
- 西出 宏之
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.116-119, 2000-02-20 (Released:2017-07-11)
- 参考文献数
- 4
空気から酸素分子を選択的に取り込み運搬するヘモグロビンは, 中心に鉄をもつ分子「ヘム」を含むタンパク質である。ヘモグロビン中のヘムの構造と, 酸素の結合平衡反応をもとに設計された全合成ヘムは, タンパク質なしでも酸素運搬できるので, 酸素運搬輸液(いわゆる人工血液)としての試験が進んでいる。全合成ヘムを組み込んだフィルムによる(酸素/窒素)分離など, ヘモグロビンを超える全合成ヘムの機能も紹介する。
2 0 0 0 OA 説明文における読解方略の構造
- 著者
- 犬塚 美輪
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.152-162, 2002-06-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 22 8
本研究の目的は, 説明文読解方略について, 具体的な認知的活動を表す構造を示し, その併存的妥当性および交差妥当性を検討するとともに, 学年による方略使用の違いを検討することである。調査1では, 読解方略は,「意味明確化」「コントロール」「要点把握」「記憶」「モニタリング」「構造注目」「既有知識活用」の7カテゴリに分類できることが示され, これらのカテゴリは,「部分理解方略」「内容学習方略」「理解深化方略」の3因子のもとにまとめられることが示唆された。これらの因子は, さらに上位の因子である「読解方略使用傾向」のもとにまとめられた。調査2では, 発話思考法を用いて, 上述のカテゴリの併存的妥当性を示した。最後に, 調査3では, 方略構造の交差妥当性が示され, さらに, 学年間の比較から「要点把握」「構造注目」「既有知識活用」において学年による方略使用の違いを見出した。このことから, これら3つのカテゴリに属するような方略が, 年齢によって発達するものであることが示唆された。
- 著者
- 村上 龍
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.25-36, 2012-06-30 (Released:2017-05-22)
Although rarely pointed out, in his The Two Sources of Morality and Religion (1932), Henri Bergson (1859-1941) briefly discusses sensibilite in a very interesting way. The purpose of this paper is to examine minutely the bergsonian notion of sensibilite. In The Two Sources, Bergson analyzes sensibilite into two components; the purely passive one called infra-intellectuel for the one hand, and the passive-active one called supra-intellectuel, which is characterized by unity-multiplicity, on the other. In comparison to his contemporaries, his argument is original to the degree that he pays attention to the supra-intellectuel component. In my opinion, this originality has been fostered around the turn of the century in the course of reorganizing his thought, particularly redefining duree and intuition based on the unity-multiplicity opposition. And again in my opinion, this reorganization or redefinition is nothing but a dialogue with the Kantism. From what is mentioned above, I would like to conclude that Bergson, after tackling the Kantism, has comes to his own notion of sensibilite, firstly characterized by passivity-activity in contrast to the kantian Sinnlichkeit which is solely passive, and secondly characterized by unity-multiplicity in contrast to the kantian Sinnlichkeit which is exclusively multiple.
2 0 0 0 OA 超多視点裸眼立体ディスプレイのためのインタラクティブコンテンツの制作および実行環境の構築
- 著者
- 吉田 俊介 岩澤 昭一郎 奥井 誠人 井ノ上 直己
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.7, pp.J158-J165, 2016 (Released:2016-06-24)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
超多視点式のような裸眼立体ディスプレイのコンテンツ制作時には,通常はその原理と仕様の熟知が重要であり,知識の習熟には困難が伴う.本論文では,そのような裸眼立体ディスプレイ向けのコンテンツを,一般のクリエータでも容易に制作しやすくし,より広く利活用するためのフレームワークの設計手法と実装について述べる.実装の検討は,運用を見据えたハードウェアの選定手法と,コンテンツ制作環境と運用手法に係わるソフトウェア開発手法の両面から行った.実装したフレームワーク上にて,超多視点裸眼立体ディスプレイについて特段の知識を有しないクリエータが,既存のコンテンツを改修し,超多視点裸眼立体ディスプレイで再生可能な,インタラクティブコンテンツを開発できることを実証した.
2 0 0 0 OA 教育工学におけるオンライン教育
- 著者
- 森田 裕介
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.593-600, 2023-02-02 (Released:2023-02-11)
- 参考文献数
- 40
本稿では,教育工学におけるオンライン教育の研究動向を概観することを目的とした.まず,オンライン教育に関連する研究のキーワードとして,遠隔教育,e ラーニング,ブレンディッドラーニング,オンライン教育に焦点を絞り,海外並びに日本の研究動向についてまとめた.次に,日本の高等教育のオンライン化を10年ごとに分け,1990年代を黎明期,2000年代を発展期,2010年代を拡張期,2020年以降を革新期とし,オンライン教育に関する研究の変遷を考察した.
2 0 0 0 OA アスベストの鉱物学
- 著者
- 神山 宣彦
- 出版者
- 東洋大学自然科学研究室
- 雑誌
- 東洋大学紀要 自然科学篇 = Journal of Toyo University Natural science (ISSN:13468987)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.115-135, 2011-03
2 0 0 0 視線の対決--坂口安吾「夜長姫と耳男」論
- 著者
- 加藤 達彦
- 出版者
- 日本文芸研究会
- 雑誌
- 文芸研究 (ISSN:02875829)
- 巻号頁・発行日
- vol.152, pp.64-78, 2001-09
2 0 0 0 OA 五味川純平『人間の條件』に関する序論的考察
- 著者
- 高橋 啓太
- 出版者
- 花園大学文学部
- 雑誌
- 花園大学文学部研究紀要 = Annual Journal Faculty of Letters Hanazono University (ISSN:1342467X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.77-91, 2020-03-17
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1928年03月13日, 1928-03-13
2 0 0 0 OA 日本の難民認定制度の現場から
- 著者
- 古川 浩司 君塚 宏 浅川 晃広 新海 英史
- 雑誌
- 社会科学研究 = SHAKAIKAGAKU-KENKYU
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.35-130, 2018-10-31
2 0 0 0 OA シランの物性と安全な取扱い
- 著者
- 野中勲加藤芳久
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.163-168, 1983-06-15 (Released:2018-01-31)
シランの消費量は近年の半導体の進歩と発展に伴い急速に増加しつつある.シランは特異な性質を持ち,その取扱いを一つ誤まると災害につながるおそれがある、本稿ではシランの物性と安全な取扱いについて,初歩的でしかも保安の基本である事柄について概略紹介する.
2 0 0 0 OA 古保利古墳群の基礎的研究(2) : 前方後方墳の検討
- 著者
- 丸山 竜平 マルヤマ リュウヘイ Ryuhei MARUYAMA
- 雑誌
- 名古屋女子大学紀要. 人文・社会編 = Journal of Nagoya Women's University. Humanities・social science
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.67-78, 1999-03-05
- 著者
- Hiroaki SHIMIZU Takahiro ONO Takatsugu ABE Masaaki HOKARI Yusuke EGASHIRA Koji SHIMONAGA Masahiko KAWANISHI Kyoko NOMURA Yusuke TAKAHASHI
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-0249, (Released:2023-01-05)
- 参考文献数
- 21
Intracranial carotid artery dissection causing cerebral ischemia is a rare but important cause of cerebral infarction in children and adolescents. Although endovascular therapy has been reported to be effective, questions regarding the indications for intervention are yet to be addressed. Therefore, this study aimed to evaluate factors related to clinical outcomes through a nationwide survey. Overall, 35 neurosurgical centers reported patients within 2 weeks after ischemic onset due to intracranial carotid artery dissection causing cerebral ischemia treated between January 2015 and December 2020. Data on clinical and radiological findings were statistically analyzed. Twenty-eight patients met the inclusion criteria. The median age was 36 years (range, 7-59 years), without sex differences. Headache at onset was documented in 60.7% of the patients. Dissection findings were categorized into stenosis (71.4%) or occlusion (28.6%). Initial treatments, including various antithrombotic agent combinations in 23 (82.1%) patients, effectively improved or prevented aggravation in half of the patients. The patients with stenotic dissection were significantly more likely to experience aggravation during the initial treatment than did those with occlusive dissection (P = 0.03). In addition, the patients with moderate to severe neurological deficits on admission had poorer outcomes at discharge more frequently than did those with mild neurological deficits on admission. Eight patients undergoing endovascular therapy had no procedural complications or further aggravation after intervention. In conclusion, patients with intracranial carotid dissection causing cerebral ischemia who had a stenotic dissection were at risk of further aggravation, and endovascular therapy effectively improved or prevented aggravation.
2 0 0 0 OA 息切れの評価法
- 著者
- 中村 健 岡村 正嗣 佐伯 拓也
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.12, pp.941-946, 2017-12-18 (Released:2018-01-10)
- 参考文献数
- 10
息切れは,健常者においても急激な激しい運動を行うと起こるが,安静時や軽微な運動によって息切れが起こる場合には,病的な状態であることが考えられる.息切れの程度を評価するための代表的な評価法には,修正Borgスケール,Visual Analogue Scale(VAS),Fletcher, Hugh-Jones分類,modified British Medical Research Council(mMRC)息切れスケール,Baseline Dyspnea Index(BDI)およびTransition Dyspnea Index(TDI),Oxygen Cost Diagram(OCD)などがある.さらに,病的な息切れであると判断した場合は,息切れの原因となっている疾患を診断することが重要である.息切れの原因には,呼吸器疾患,循環器疾患,神経筋疾患,廃用症候群などが考えられる.まず,呼吸数・呼吸様式,呼吸音,心音,心拍,血圧,胸郭・四肢所見などの身体所見から,息切れの原因疾患を判断することが重要である.
2 0 0 0 セクシュアル・マイノリティ (特集 性と生のデータ集(2))
2 0 0 0 OA The SOLA Award in 2022
- 著者
- Tetsuya Takemi
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.ii-iii, 2023 (Released:2023-02-11)
- 参考文献数
- 2
The Editorial Committee of Scientific Online Letters on the Atmosphere (SOLA) presents the SOLA Award to one or two outstanding papers published each year. We are pleased to announce that the SOLA Award in 2022 will be given to the paper by Dr. Yasumitsu Maejima et al., entitled “Observing system simulation experiments of a rich phased array weather radar network covering Kyushu for the July 2020 heavy rainfall event” (Maejima et al. 2022), and to the paper by Dr. Tomoe Nasuno et al., entitled “Impacts of midlatitude western North Pacific sea surface temperature anomaly on the subseasonal to seasonal tropical cyclone activity: Case study of the 2018 boreal summer” (Nasuno et al. 2022).
2 0 0 0 OA 化學及び放射學Radiologieに於ける元素Element及び原子Atomの意義
- 著者
- 平田
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 東京化學會誌 (ISSN:03718409)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.76-86, 1917 (Released:2009-02-05)
- 著者
- 木村 直弘 KIMURA Naohiro
- 出版者
- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター
- 雑誌
- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 (ISSN:13472216)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.107-129, 2013