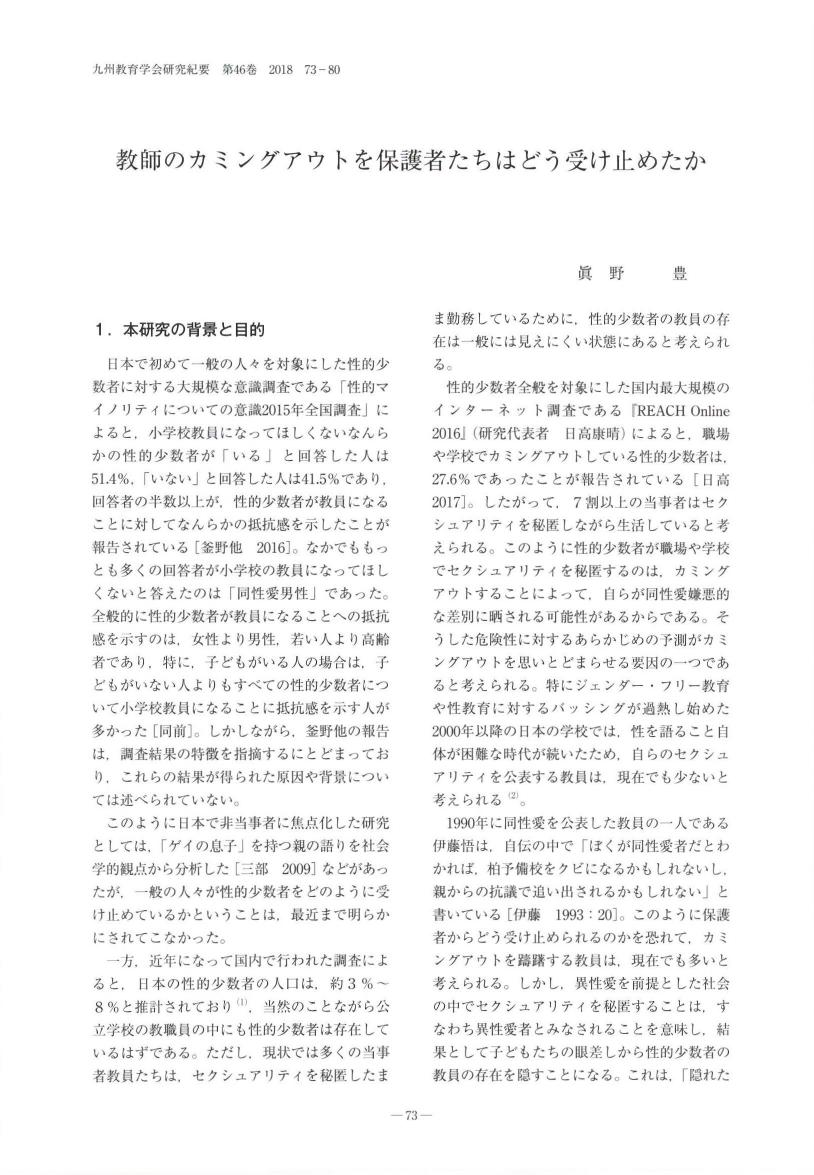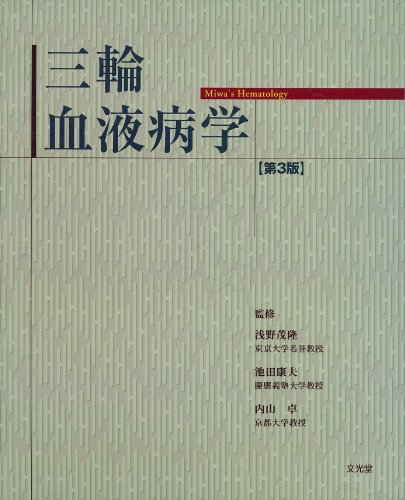2 0 0 0 OA 教師のカミングアウトを保護者たちはどう受け止めたか
- 著者
- 眞野 豊
- 出版者
- 九州教育学会
- 雑誌
- 九州教育学会研究紀要 (ISSN:02870622)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.73-80, 2019 (Released:2020-10-14)
- 著者
- Pramote Khuwijitjaru Shuji Adachi
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- pp.FSTR-D-22-00215, (Released:2023-01-13)
- 被引用文献数
- 4
In a batch reactor, 0.01 mol/L arginine, lysine, or histidine, which are natural basic amino acids, was used as an environmentally friendly, “green”, catalyst to isomerize 0.2 mol/L ribose to the corresponding ketose, ribulose, at 110 °C. The changes over time in the conversion of ribose, the yield of ribulose, pH, and the absorbance of the reaction mixture at 280 and 420 nm were measured. The yield of ribulose was highest (ca. 8.5 %) when arginine was used as a catalyst, followed by lysine. Ribulose was also produced with histidine, but the yield was very low (ca. 1.5 %). On the other hand, the coloration, which was evaluated by the absorbance of the reaction mixture at 280 and 420 nm, was highest when lysine was used, followed by arginine. Therefore, arginine was the most suitable green catalyst for isomerizing ribose to ribulose among the three basic amino acids tested.
2 0 0 0 OA <研究ノート>伏見作事板の廻漕と軍役(二)
- 著者
- 中川 和明
- 出版者
- 弘前大学國史研究会
- 雑誌
- 弘前大学國史研究 (ISSN:02874318)
- 巻号頁・発行日
- no.79, pp.58-83, 1985-10-30
- 著者
- Keisuke Shibata Akihiro Tokushige Yuki Hamamoto Koji Higuchi Masakazu Imamura Yoshiyuki Ikeda Mitsuru Ohishi
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- pp.CR-22-0112, (Released:2023-01-27)
- 参考文献数
- 24
Background: Cancer-associated thrombosis (CAT) is a common complication of cancer and has received increasing attention; the Khorana Risk Score (KRS) is a recommended but insufficient risk assessment model for CAT. We propose a novel Kagoshima-DVT score (KDS) to predict preoperative deep vein thrombosis (DVT). This scoring method scores D-dimer ≥1.5 μg/mL, age ≥60 years, female sex, ongoing glucocorticoids, cancer with high risk of DVT, and prolonged immobility. The purpose of this study was to compare the performance of the KDS and KRS in predicting CAT in patients with gastrointestinal cancer.Methods and Results: In all, 250 patients without a history of thrombosis who received their first chemotherapy for gastrointestinal cancer were divided into low- (48.0%), intermediate- (38.8%), and high-risk (13.2%) groups for CAT development by the KDS. The patients’ median age was 67 years and 63.2% were men. In all, 61 (27.1%) patients developed CAT (17.6%, 35.3%, and 36.4% of patients in the low-, intermediate, and high-risk groups, respectively; log-rank P=0.006). The area under the time-dependent receiver operating characteristic curve for CAT occurrence within 1 year was larger for the KDS than KRS (0.653 vs. 0.494).Conclusions: A high KDS at the start of first chemotherapy is a risk indicator for CAT development during chemotherapy. Moreover, the KDS is more useful than the KRS in predicting CAT risk.
2 0 0 0 OA <研究ノート>伏見作事板の廻漕と軍役(1)
- 著者
- 中川 和明
- 出版者
- 弘前大学國史研究会
- 雑誌
- 弘前大学國史研究 (ISSN:02874318)
- 巻号頁・発行日
- no.78, pp.17-40, 1985-03-20
2 0 0 0 動画コンテンツ制作入門
- 著者
- 斎賀 和彦
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.44-48, 2022-02-01 (Released:2022-02-01)
カメラの普及,その動画ファイルを編集,加工するパソコンの低価格化と普及により,動画制作はプロだけのものではなく身近になった。時を同じくするように拡大したコロナ禍におけるオンライン授業の流れは,教育における講義用の動画コンテンツ制作を加速し,多くの教育関係者が動画制作に関与せざるを得なくなった。しかし,動画作成と言っても,その範囲は広く何億ドルというハリウッド映画からTikTokのような数十秒に満たないショートビデオまで含むと,その制作思想も手法も多岐に渡る。本稿では主に大学での発信を想定した広報(インフォメーション),講義配信を基本として制作フローの解説と基礎知識のまとめを行う。
2 0 0 0 OA 独立した音楽と映像に対する印象評価と音楽動画の印象の関係性に関する研究
- 著者
- 大野 直紀 土屋 駿貴 中村 聡史 山本 岳洋
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.929-940, 2018-03-15
音楽動画の印象に基づく検索や推薦,音楽動画の類似判定のためには,音楽動画の印象推定に関する技術が必須となる.しかし,音楽に対する印象評価や映像に対する印象評価に関する研究は多数なされている一方で,音楽と映像が組み合わされた音楽動画に対する印象評価の研究は十分になされていない.我々は,音楽と映像の印象がどのように音楽動画の印象に影響するのかを調べるため,「音楽のみ」「映像のみ」「音楽動画」の3つの関係性に着目し,これらに対する8印象軸の印象評価データセットを構築した.また,それらを分析することで,音楽と映像の印象評価の組合せによる音楽動画の印象推定の可能性について検討を行った.またデータセット内の音楽動画の音楽と映像を任意に合成した音楽動画を生成し,印象評価を行ってもらうことで,音楽印象と映像印象の組合せが音楽動画の印象とどのように関係しているのかの分析を行った.その結果,音楽と映像の印象を組み合わせることによる印象推定の可能性があること,また各印象によって印象の組合せ方が異なることを明らかにした.
2 0 0 0 OA 統合失調症と自閉スペクトラム症の連続性─ゲノムコピー数変異の観点から
- 著者
- 久島 周
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.2-5, 2022 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 13
DSM‐5の診断基準では,統合失調症と自閉スペクトラム症(ASD)は,臨床症状に基づいて異なる精神疾患として区別される。しかし,最近の疫学研究や臨床研究の知見から両疾患には連続性が存在することが指摘されている。ゲノム研究においても,両疾患の発症にかかわる疾患横断的な変異が多数同定されている。なかでも,ゲノムコピー数変異(CNV)(欠失・重複を含む)では,22q11.2欠失,15q11.2‐q13.1重複,3q29欠失をはじめ,低頻度で存在するCNVが統合失調症とASDの両方に関与することが報告されている。CNVデータの詳細な解析からは,両疾患の病態メカニズムの共通性も指摘されている。今後の研究では,統合失調症・ASDに関連するCNVをもつ被験者を対象に,幼少期から成人期まで臨床症状を追跡することで,両疾患の関係性について明らかになるかもしれない。また,CNVに基づくモデルマウスや患者由来iPS細胞を用いた神経生物学的な解析から,両疾患の神経基盤の解明が期待される。
2 0 0 0 OA 北里柴三郎:第1回ノーベル賞候補,脚気論争,ペスト菌真贋論争
- 著者
- 河野 俊哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.50-53, 2021-02-20 (Released:2022-02-01)
- 参考文献数
- 5
新型コロナウイルスが席巻する現在,北里柴三郎の営為は益々再評価される機運にある。また,北里と言えば第1回ノーベル賞候補,ペスト菌真贋論争,脚気論争,伝染病研究所移管騒動などエピソードに事欠かない人物でもあるが,それらを精査する時期にも来ている。そこで最新の科学史研究の成果を基に北里の上記エピソードの現在の状況を確認すると共に北里研究所・北里柴三郎記念室や東京大学医科学研究所・近代医科学記念館など白金周辺の探索の成果も併せて紹介したい。
2 0 0 0 OA 世界のハンセン病政策に関する研究Ⅰ -ハワイにおける絶対隔離政策の変遷-
- 著者
- 森 修一
- 出版者
- 日本ハンセン病学会
- 雑誌
- 日本ハンセン病学会雑誌 (ISSN:13423681)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.3, pp.189-211, 2018 (Released:2018-08-29)
- 参考文献数
- 20
ハワイでは19世紀半ばからハンセン病の蔓延が始まった。これに対してハワイ王国政府は1865年に公衆衛生政策としての隔離を決定、モロカイ島のカラワオを療養地とし、患者移送を始めた。患者の発見は密告と逮捕により行われ、容赦なくモロカイ島に送られた。政府は当初、カラワオで患者が自給自足する農業コロニーを目指したが、地理的特性や予算不足などが要因となり、農業コロニー構想は失敗し、カラワオは無法地帯となり、多くの混乱が生じた。1873年にはダミアン神父がカラワオに赴き、患者の救済を開始、政府との交渉にも務め、混乱は収拾された。その後、ハンセン病対策費の増加、治安システムの整備などによりカラワオには治安が確保され、療養地は近接するカラウパパへ拡がり、その拡充と制度の整備の過程とアメリカ合衆国の関与の中でハワイでは隔離政策が進展していった。
- 著者
- 蘭 由岐子
- 出版者
- 九州女子大学・九州女子短期大学
- 雑誌
- 九州女子大学紀要. 人文・社会科学編 (ISSN:09162151)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.1-19, 1996-03
This paper discusses how the Leprosy Prevention Law has defined the leprosarium from modern to contemporary Japan. The Japanese government has controlled Hansen's Disease basically by segregating patients from the rest of society by enacting the Leprosy Prevention Law, even though modern medicine can insist that there is no longer a need for segregation. There are many problems in this process, because patients' rights were abused and they were treated as if they were criminal for a long time. Patients have been enclosed in leprosaria for their whole life even after WWII, resulting in ordinary people in society being fearful of Hansen's Disease. This study is an introduct analysis of the leprosrium. Further work will consider sociological aspects of leprosarium.
- 著者
- 伊藤 公雄
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.149-166, 1981-03-31 (Released:2017-04-05)
Che affinita esistono fra il senso comune, che e la coscienza del popolo, e una visione del mondo piu sistematica e coerente? In che modo una determinata visione del mondo arriva a dominare il popolo? Si tratta di problemi di sociologia della conoscenza che trovano nell'opera di Gramsci alcuni suggerimenti interessanti per una loro soluzione. Il presente articolo e un tentativo di ricostruzione del pensiero di Gramsci da questo punto di vista e si articola in tre punti. 1) In primo luogo ho inserito la teoria di Gramsci sugli intellettuali nell'ambito piu generale delle teorie sociologiche sull'argomento. In particolare ho considerato i suoi "intellettuali tradizionali" come "intellettuali reali", costituenti una classe sociale, ed i suoi "intellettuali organici" come "intellettuali funzionali", cioe osservati dal punto di vista dela loro funzione sociale, concetti che ho riutilizzati al momento di affrontare i problemi dell'egemonia e del blocco storico. 2) In secondo luogo ho distinto nelle idee di Gramsci fra teoria della dominazione e teoria della rivoluzione. L'autore ha ricavato quest'ultima teoria, in cui viene affrontato il problema di come possa nascere una nuova forma di dominio, dalle sue ricerche sulla dominazione. Il suo pensiero in questo campo presenta spiegazioni di grande interesse, come quando utilizza i concetti di egemonia, di blocco storico, di intellettuali organici e tradizionali, ma la sua strategia della rivoluzione ha alcuni limiti. Su questo punto infatti Gramsci appare piu dogmatico ed idealistico. 3) Da ultimo ho delineato un quadro dei rapporti intercorrenti fra folclore, senso comune e filosofia. Fra folclore, che e una forma di conoscenza piu incoerente e statica, e filosofia, che e piu sistematica, esiste una gerarchia. Per dominare il popolo i gruppi egemoni hanno sempre teso a mantenere questa gerarchia attraverso i loro apparati (scuola, chiesa ecc.), cioe attraverso i loro intellettuali organici. Gramsci invece pensa che sia necessario elevare il "senso comune", valorizzandone e sistematizzandone gli elementi positivi, e rendere omogenee le conoscenze del popolo alla visione degli intellettuali organici della nuova classe. Da un punto di vista teorico questa strategia sembra chiara, ma nella pratica come e possibile rendere omogenee le conoscenze del popolo e come ci si rapporta rispetto ai suoi desideri materiali ed alla sua sensibilita? A queti problemi l'autore non risponde. Gramsci e stato sicuramente un grande pensatore dell'epoca moderna ma presenta alcuni limiti. Per superare questi limiti spetta a noi risolvere i problemi lasciati aperti in modo da dare concretezza alla "filosofia della prassi".
2 0 0 0 OA 第14回 Veritas In Silico社のmRNA構造解析技術
- 著者
- 中村 慎吾
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.11, pp.1068-1070, 2019 (Released:2019-11-01)
- 参考文献数
- 1
Veritas In Silicoは、あらゆるmRNAに対し効率的に分子標的創薬を実現する機会をパートナー製薬会社へ提供する。この創薬事業の根幹の一つは、mRNAの部分構造を高速に予測・解析・評価するコンピュータ技術である。適切な作業仮説をおいた上で仮想的な測定器として用い、部分構造の存在確率を計算することで標的として利用可能な部分構造を特定する。これにより、標的が枯渇しつつある低分子創薬事業へ大量の新規な優良標的を供給でき、First in Classの創出に貢献する。
- 著者
- Akio Yagi Shinya Hayasaka Toshiyuki Ojima Yuri Sasaki Taishi Tsuji Yasuhiro Miyaguni Yuiko Nagamine Takao Namiki Katsunori Kondo
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.12, pp.451-456, 2019-12-05 (Released:2019-12-05)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 7 8
Background: While bathing styles vary among countries, most Japanese people prefer tub bathing to showers and saunas. However, few studies have examined the relationship between tub bathing and health outcomes. Accordingly, in this prospective cohort study, we investigated the association between tub bathing frequency and the onset of functional disability among older people in Japan.Methods: We used data from the Japan Gerontological Evaluation Study (JAGES). The baseline survey was conducted from August 2010 through January 2012 and enrolled 13,786 community-dwelling older people (6,482 men and 7,304 women) independent in activities of daily living. During a 3-year observation period, the onset of functional disability, identified by new certification for need of Long-Term Care Insurance, was recorded. Tub bathing frequencies in summer and winter at baseline were divided into three groups: low frequency (0–2 times/week), moderate frequency (3–6 times/week), and high frequency (≥7 times/week). We estimated the risks of functional disability in each group using a multivariate Cox proportional hazards model.Results: Functional disability was observed in a total of 1,203 cases (8.7%). Compared with the low-frequency group and after adjustment for 14 potential confounders, the hazard ratios of the moderate- and high-frequency groups were 0.91 (95% confidence interval [CI], 0.75–1.10) and 0.72 (95% CI, 0.60–0.85) for summer and 0.90 (95% CI, 0.76–1.07) and 0.71 (95% CI, 0.60–0.84) for winter.Conclusion: High tub bathing frequency is associated with lower onset of functional disability. Therefore, tub bathing might be beneficial for older people’s health.
2 0 0 0 水熱プロセスによる二酸化炭素からの有機化合物の直接合成
水および二酸化炭素を金属鉄あるいはニッケルとともに水熱条件にさらすと水と二酸化炭素の両者から酸素が金属に引き抜かれ、結果として水から活性に富んだ水素が発生すると同時に二酸化炭素も活性化する。この両者が反応して有機化合物が生成する。この原理を確認し、平成14年度では反応条件と生成物の解析から中性条件では、一酸化炭素を経由するフィッシャートロプシュ反応を主反応とし、メタンからヘキサンまでのアルカン類の生成を確認した。また酸性条件では酢酸を中心としたカルボン酸の生成を、また金属のかわりにマグネタイトを還元剤として使えば、エタノールの生成をそれぞれ確認した。工業化を考えた場合、メタンおよびカルボン酸を高収量で得られることを見出した。工業化では焼却炉あるいは発電所からの廃ガスを直接利用することになる。14年度では反応のプロセスを探求すると同時に工業化のための大量処理を仮定した流通系の連続処理プロセスの小型テストプラントを作成し、非平衡下での反応を調べた。バッチ式オートクレーブを使った平衡系の反応、いいかえれば理想系での実験に比べて流通型オートクレーブは、自然界での現実の反応に近く、また大量処理のための工業化プロセスの主体をなすものであるが、科学的には未踏領域ともいわれる複雑反応系である。ここでは加熱パイプの内部に旋盤による屑状態の鉄を置き、これに塩酸と二酸化炭素を200℃加熱下で流通させ、生成有機物の気体・液体を相互に分離し、それぞれを分析する方法をとった。マイルドな水熱条件下で水起源の活性水素をつくり、二酸化炭素を同時に活性化せしめ、炭化水素を合成、反応条件による反応選択性の可能性を見出し、ついで収量・収率から流通式の非平衡反応で工業化の可能性を提示するという一連の計画を遂行し、流通式非平衡装置の設計・製作および装置の特性試験を行い、それを使って流通系による工業化の可能性を得ることができた。
2 0 0 0 IR パワーハラスメント防止対策が義務化されて
- 著者
- 長見 まき子
- 雑誌
- 関西福祉科学大学EAP研究所紀要 (ISSN:21854947)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.7-11, 2020-03-31
2 0 0 0 三輪血液病学
- 著者
- 浅野茂隆 池田康夫 内山卓監修 大野仁嗣 [ほか] 編集
- 出版者
- 文光堂
- 巻号頁・発行日
- 2006
2 0 0 0 OA 職能武家集団の移住にみる千町野開発の意義と実態
- 著者
- 夏目 宗幸 安岡 達仁
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.189-199, 2020 (Released:2020-07-01)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1 1
千町野開発は,武蔵野台地における初期新田開発の一例であることから,地理学上の新田開発研究のモデルケースとして,これまで種々の学説が提唱されてきた.それらの研究は,対象地の計画地割や土地利用,土地生産力,あるいは土豪名主の役割規定などの視点から千町野開発の実態を把握しようと試みているが,幕府の具体的関与の実態について言及していない.本研究はこの点に着目し,千町野開発におけるその実態を明らかにするために,千町野に移住した武家集団の詳細な来歴を調査した.その結果,千町野に移住した武家集団は,三つの職能集団すなわち,1)代官・代官手代の集団,2)鷹狩・鷹場管理を専門とする集団,3)測量・普請を専門とする集団に分類できることが明らかとなった.これにより千町野開発は,幕府技術官僚としての職能武家集団の関与によって遂行されてきたと結論付けた.
2 0 0 0 OA 第3巻 成長・成熟・性決定—継 カエルW染色体のターンオーバー
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1927年12月05日, 1927-12-05