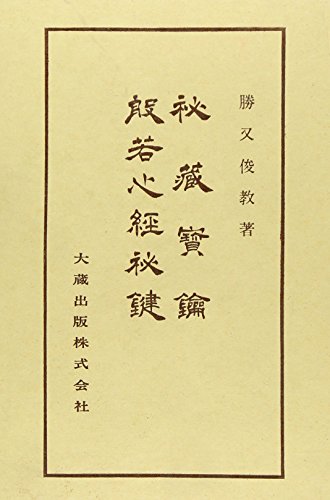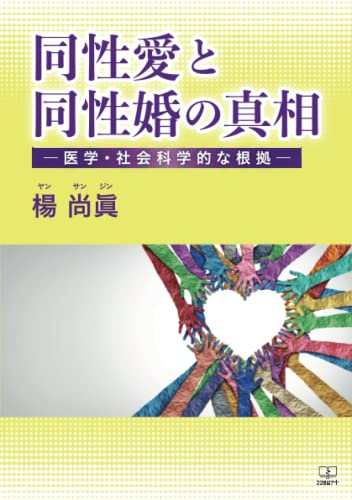2 0 0 0 桑名の民俗
- 著者
- 堀田吉雄 [ほか]編著
- 出版者
- 桑名市教育委員会
- 巻号頁・発行日
- 1987
2 0 0 0 OA 新種エキノコックス包虫病体モデル動物の作成
2005年に中華人民共和国のチベット高地において発見された新種Echinococcus shiquicusの包虫(チベット包条虫)について、(1) BALB/cとNOD/Shi-scidマウスの腹腔にて包虫の発育・増殖に成功した。(2) 包虫を18日間凍結保存後、BALB/cマウスへ接種して包虫の生存・増殖を確認した。(3)それらの嚢包を肝癌細胞H-4-II-Eを供培養にしてEMEM培地にて185日間培養し、直径約二倍に及ぶ嚢包の拡大、クチクラ層の肥厚、顕著な原頭節と石灰小体を形成させることについても成功した。
2 0 0 0 OA 末梢神経障害の基礎と臨床 TN型らいとその鑑別診断
- 著者
- 近藤 喜代太郎
- 出版者
- 日本ハンセン病学会
- 雑誌
- レプラ (ISSN:00241008)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.191-214, 1974-09-30 (Released:2008-12-10)
- 参考文献数
- 105
2 0 0 0 秘蔵宝鑰 ; 般若心経秘鍵
2 0 0 0 OA 入院患者における自覚症状ならびにストレス認知と心理的状態の関係
- 著者
- 林 陽子 森本 美智子 神原 千比呂 中村 珠恵 谷村 千華
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.2_49-2_56, 2011-06-01 (Released:2016-03-05)
- 参考文献数
- 36
本研究の目的は,自覚症状ならびにストレス認知と心理的状態の関係を明らかにすることであった。対象は満20歳以上の入院患者81名であった。自覚症状の測定にはIPQの12項目にCMIを参考にした13項目を組み合わせて用い,ストレス認知の測定には病気関連不安認知尺度,心理的状態の測定にはHADSを用いた。まず自覚症状の因子妥当性と信頼性を確認し,自覚症状,ストレス認知,心理的状態の相関関係を確認した。次に従属変数を心理的状態とし,自覚症状が直接的またはストレス認知を介して影響するとする因果モデルを設定し,関連性を検討した。結果,自覚症状はストレス認知および心理的状態に影響を与えており,ストレス認知は心理的状態により強い影響を与えることが明らかになった。これは,看護師が入院患者の心理的な健康状態を維持するうえで,自覚症状のマネジメントのみならず,ストレス認知についても把握し,介入することの重要性を示唆している。
2 0 0 0 OA お辞儀と顔の外見的特徴が主観的魅力に及ぼす影響
- 著者
- 大杉 尚之 河原 純一郎
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.69-77, 2020-02-29 (Released:2020-03-05)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1 2
日本において,お辞儀は第一印象の形成にポジティブな効果を持つと信じられている.最近,Osugi & Kawahara(2015)は,お辞儀が魅力知覚に及ぼす影響について実験的に検討した.写真上辺を前方に傾け,元の角度に戻すお辞儀条件では顔写真の主観的な魅力が上昇した.本研究では,これらの発見を拡張し,お辞儀の効果の変調要因を検証した.研究1の結果は,顔写真の外見魅力(実験1と2),顔の性別(実験3),人間と人間以外のエージェントの違い(実験4)のいずれともお辞儀の効果は独立であった.これらのことから,さまざまな顔刺激間でお辞儀効果量に違いはなく,外見的特徴とは独立に印象形成に寄与している可能性が示された.すなわち,誰がお辞儀をするかは重要ではなく,お辞儀動作そのものによる効果が加算的に作用することで印象が形成されると考えられる.また,この結果がお辞儀効果に関するメタ認知と一致しているかについて検討した結果(研究2),実験結果とメタ認知の食い違いが生じ,低魅力の人や人間以外のエージェントのお辞儀効果が小さく見積もられることが明らかとなった.
2 0 0 0 OA 歴史認識とアイデンティティ形成
- 著者
- 別所 良美
- 雑誌
- 名古屋市立大学人文社会学部研究紀要 = Journal of humanities and social sciences (ISSN:13429310)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.21-43, 2001-11-30
2 0 0 0 構築環境教育と生涯学習:
- 著者
- コーザー ボウ 木方 十根 鷹野 敦
- 出版者
- Architectural Institute of Japan
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.780, pp.687-696, 2021 (Released:2021-02-28)
- 参考文献数
- 31
This study examines signage and monuments to discover how they may contribute to Built Environment Education (BEE) for self-directed lifelong learning. The site chosen for this study is Ishibashi Memorial Park in Kagoshima, due to its layered historical functions; currently as an educational park for Kagoshima’s stone bridge heritage, but formerly a battleground and religious site. This analysis is conducted using BECK (Built Environment Context of Knowledge) Charts developed in our previous study, which allows us to categorize types of knowledge presented, and to visualize where this knowledge is concentrated. The text and diagrams on 20 signs and 9 monuments are analyzed by coding phrases according to the horizontal and vertical axis of the BECK Chart. These codes were tabulated, the number of occurrences were entered into the corresponding cell on the chart, and each cell was assigned a tonal gradation with darker tones representing higher frequency. This allowed us to see at a glance which types of knowledge were mainly presented on each sign or monument. This analysis demonstrated that technical, political, and social knowledge about the built environment appeared most frequently. The amount of textual information available throughout the park is extensive, and thus it is possible to state that the signs and monuments have potential to contribute to BEE through self-directed lifelong learning. However, some hurdles to learning were also identified. Due to its many uses over time, this site contains a mixture of historic remains, reconstructed historical artifacts, and modern facilities. These are scattered throughout, and there is no clear attempt to integrate these coherently in the overall park design. This makes it difficult for visitors to infer the relationship between these disparate elements through the information on the signs alone. Additionally, reading the signs is time consuming, and depending on the background, motivation, and literacy of the visitor, the amount of effort needed to understand all the information on display is considerable. While the potential for BEE in the park is great, whether this translates into actual learning is questionable. This is an important consideration in relation to the design of parks which are intentionally educational. In terms of applying the BECK Chart, it was found that the original matrix label of ‘building’ was insufficient to address structures which are built, but are not buildings. This was rectified by adding the term ‘structure’ to the label, which allowed for wider application without losing the integrity of the original chart.
- 著者
- Fumihiro CHINA Naoki TAKEUCHI Hideo SUZUKI Yuki YAMANASHI Hirotaka TERAI Nobuyuki YOSHIKAWA
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Electronics (ISSN:09168516)
- 巻号頁・発行日
- vol.E105-C, no.6, pp.264-269, 2022-06-01
The adiabatic quantum flux parametron (AQFP) is an energy-efficient, high-speed superconducting logic device. To observe the tiny output currents from the AQFP in experiments, high-speed voltage drivers are indispensable. In the present study, we develop a compact voltage driver for AQFP logic based on a Josephson latching driver (JLD), which has been used as a high-speed driver for rapid single-flux-quantum (RSFQ) logic. In the JLD-based voltage driver, the signal currents of AQFP gates are converted into gap-voltage-level signals via an AQFP/RSFQ interface and a four-junction logic gate. Furthermore, this voltage driver includes only 15 Josephson junctions, which is much fewer than in the case for the previously designed driver based on dc superconducting quantum interference devices (60 junctions). In measurement, we successfully operate the JLD-based voltage driver up to 4 GHz. We also evaluate the bit error rate (BER) of the driver and find that the BER is 7.92×10-10 and 2.67×10-3 at 1GHz and 4GHz, respectively.
2 0 0 0 国立国会図書館スタッフ・マニュアル
- 著者
- 国立国会図書館総務部 編
- 出版者
- 国立国会図書館
- 巻号頁・発行日
- vol.G-2, 1965
2 0 0 0 OA 明治末期の民営社会資本の挫折と再建 : 高野鉄道のデフォルトと財政整理を中心に
- 著者
- 小川 功
- 出版者
- 滋賀大学経済学部
- 雑誌
- 滋賀大学経済学部研究年報 (ISSN:13411608)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.17-41, 1995
2 0 0 0 OA 清酒酵母の高泡形成に関与する遺伝子AWA1
- 著者
- 下飯 仁
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.7, pp.474-480, 2002-07-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 16
協会701号等の泡なし酵母は, 1970年代に泡あり酵母の変異株として育種され, 現在, 広く清酒醸造に利用されているが, その泡なしとなるメカニズムについては, 長い間不明のままであった。今回, 協会7号の高泡形成に関わるAWA7遺伝子がクローニングされ, 協会7m号のAWA7遺伝子の構造が解析された結果, 高泡形成および泡なし性のメカニズムが分子レベルで解明された。これは近年の分子生物学と酵母遺伝学の発達の腸物であり, その成果は鮮やかで見事である
2 0 0 0 OA 土壌微生物バイオマス窒素の動態に関する研究
- 著者
- 丸本 卓哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.229-232, 1997-06-05 (Released:2017-06-28)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 同性愛と同性婚の真相 : 医学・社会科学的な根拠
- 出版者
- かながわ考古学財団 : 神奈川県立埋蔵文化センター
- 巻号頁・発行日
- 1998
2 0 0 0 OA 中学校用教科書ガイドにおける発音表記の扱い
- 著者
- 河内山 真理 有本 純
- 出版者
- 関西国際大学教育総合研究所
- 雑誌
- 教育総合研究叢書 = Studies on education (ISSN:18829937)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.131-140, 2017-03-31
本研究は、中学校用の教科書ガイドにおいて、どのような発音表記が用いられているかを明らかにすることを目的としている。1 年次用の教科書ガイドのすべてがカタカナによる表記を用いており、またこの表記法は出版社によって差異があった。同様に中学生を主たる対象にした初級英和辞典でも多くが異なったカナ表記を用いているため、ガイドと辞典の出版社が異なると、学習者が混乱する可能性が非常に高いという問題点が浮かび上がった。辞典も併用するなどの熱心な学習者ほど混乱する可能性があり、主として自宅学習に用いられる教材としては、厄介な問題を抱えていると言える。また、学校での指導者たる教員は、こうした学習参考書の現状を補う発音指導を行うことが必要になるだろう。辞典の出版社が共通認識を持つことも必要と考えられる。カナ表記そのものが教科書では用いられておらず、継続性がないという事実が、学習上の大きな問題であり、その点からも発音記号を指導しておくことが必要と考えられる。
2 0 0 0 OA 左再帰に対応するPackrat Parserの実装
- 著者
- 後藤 勇太 木山 真人 芦原 評
- 雑誌
- 夏のプログラミング・シンポジウム2011報告集
- 巻号頁・発行日
- pp.49-55, 2012-01-06
構文解析法でPackrat Parsingという手法がある.Packrat Parsingは,再帰下降構文解析にメモ化を組み合わせた手法であり,バックトラックや無限先読みを用いた解析において,線形時間で解析可能である.しかし,左再帰を含む文法は解析不可能である.そこで,従来は左再帰を含む文法を解析する際,左再帰部分を等価な右再帰に変換し,解析を行っていた.だが文法の変換を行うと構文木の構造が変化してしまう.また,特定の左再帰は変換できない.たとえば,閉路が存在する文法である.よって,この手法では解析できない文法がある.Alessandro Warthらは,左再帰を含む文法を,右再帰への変換無しに解析を可能にした.しかし,Alessandroらの手法では,同一の入力位置で左再帰が複数発生する文法において,特定の入力の解析に失敗する.そこで本研究では,左再帰を含む文法を右再帰への変換無しに解析でき,かつ従来手法の問題点に対応するPackrat Parserを提案・実装し,評価を行った.