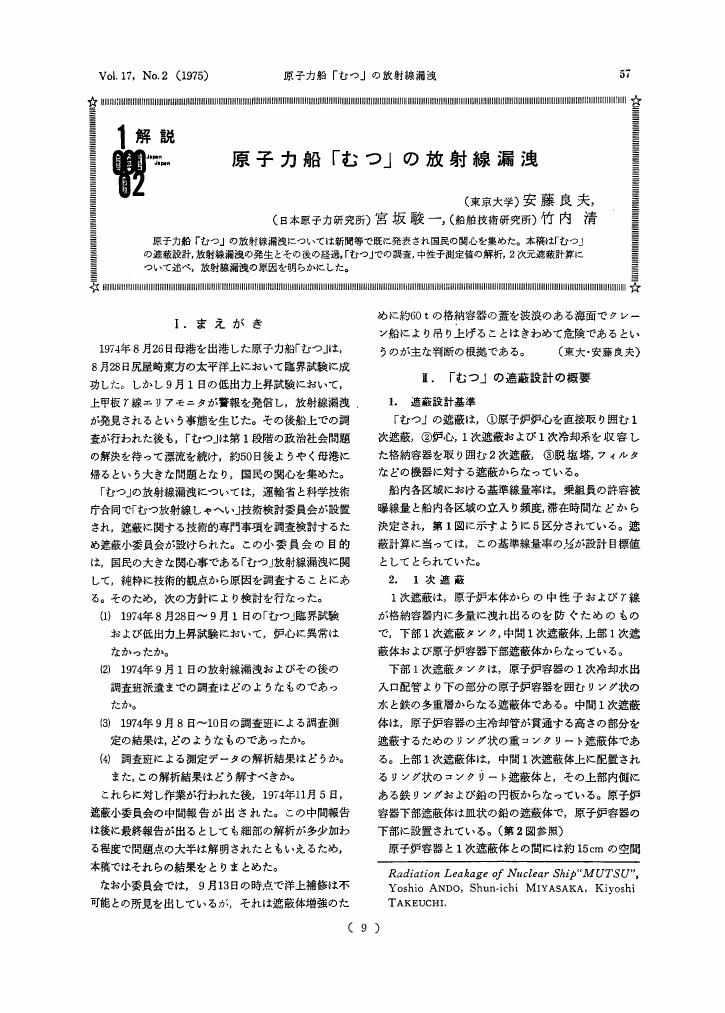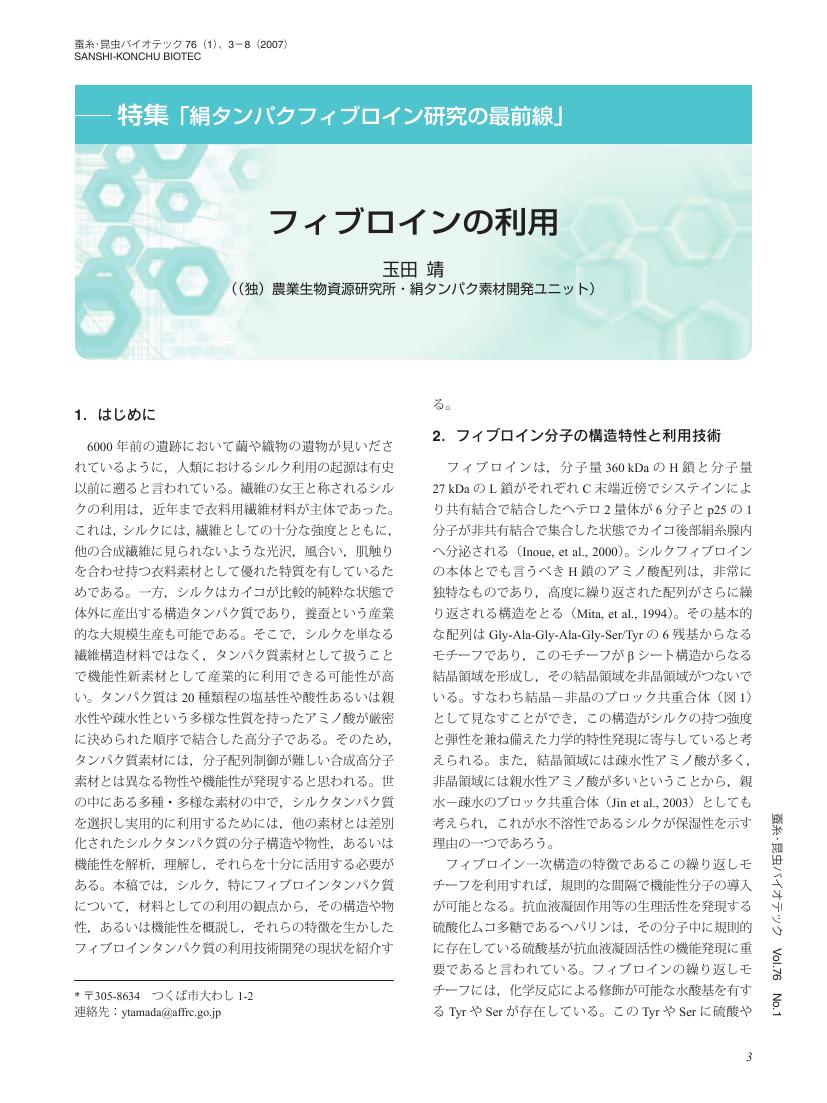2 0 0 0 IR 產死鬼考 : ウブメ傳說の構成要素として
- 著者
- 增子 和男
- 出版者
- 中國詩文研究會
- 雑誌
- 中国詩文論叢 (ISSN:02874342)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.223-235, 2015-12
- 著者
- 任 貞美
- 出版者
- 一般社団法人日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.57-69, 2014-02-28
本研究は,「実践上の高齢者虐待定義の構築」に向けて,介護職員の虐待認識を基とに新たに「準虐待」を加え,その構造と特徴を明らかにすることを目的とした.全国の介護老人福祉施設に勤務する介護職員5,000人を対象に,質問紙調査を行い,1,143人を分析対象とした.調査期間は2012年10月11〜25日までである.因子分析を行った結果,「準虐待」の構造として,「尊厳の侵害」「役割の侵害」「自律の侵害」「交流の侵害」の4因子が抽出された.また,4因子の各「下位尺度得点」の平均値を比較した結果,「尊厳の侵害」「交流の侵害」に対する介護職員の虐待認識は高く,「役割の侵害」「自律の侵害」についての虐待認識は低かった.上記の結果から,(1)高齢者にとって重要な生活,「尊厳・役割・自律・交流」の侵害は「準虐待」であること.(2)介護職員が見逃しがちな高齢者の「自律や役割のある生活支援」の重要性について,介護職員の共通理解を強化する必要性が示唆された.
2 0 0 0 OA 「新体制」 を巡る攻防 : 国策研究会 「新体制試案要綱」 の策定過程
- 著者
- 髙杉 洋平
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.1_270-1_292, 2018 (Released:2021-07-16)
- 参考文献数
- 37
本稿の目的は 「新体制試案要綱」 の策定に関わる民間シンク・タンク国策研究会と陸軍省軍務局幕僚の関係を再評価すると共に, 軍務局幕僚の新体制構想の実像を明らかにすることにある。従来, 国策研究会は陸軍のブレーン・トラストと考えられており, 同会が策定した 「新体制試案要綱」 は, 未発見の陸軍の新体制構想を代替するものと明確な根拠を欠いたまま推測されてきた。しかし 「新体制試案要綱」 の策定過程を確認すると, 同要綱が多様性に富んだメンバーによって立案され, 審議の過程や結論が広く公開されたこと, その内容も議会や旧政党を尊重するものであったことが分かる。この事実は同要綱と軍務局幕僚の関係を一見否定するものである。にもかかわらず, 既存研究はこの矛盾について全く説明しえていない。本稿は, 当該期に軍務局幕僚が陥っていた政治的苦境を指摘し, 軍務局幕僚にとっては国策研究会の 「中立性」 や 「公開性」 にこそ同会の利用価値の本質があったことを指摘する。そしてこの考察の過程で, 当該期の軍務局幕僚の新体制構想が, 議会政治や政党政治に肯定的評価を与えるものであったことを明らかにする。
2 0 0 0 OA 造血器悪性腫瘍に合併したSweet症候群
2 0 0 0 OA アブラムシの警報フェロモン
- 著者
- 西野 親生
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.5, pp.276-285, 1977-05-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1 1
2 0 0 0 OA 原子力船「むつ」の放射線漏洩
- 著者
- 安藤 良夫 宮坂 駿一 竹内 清
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.57-65, 1975-02-28 (Released:2010-04-19)
- 被引用文献数
- 2 2
2 0 0 0 OA 若年労働者のメンタルヘルス不調の特徴と対策 ―自由回答式質問票を用いた横断調査―
- 著者
- 池上 和範 江口 将史 大﨑 陽平 中尾 智 中元 健吾 日野 亜弥子 廣 尚典
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- pp.E13003, (Released:2014-04-02)
- 被引用文献数
- 2 1
目的:本研究の目的は,若年労働者のメンタルヘルス不調の特徴を明らかにし,実効的なメンタルヘルス対策を検討することである.方法:国内の産業医386名に無記名の自由回答式質問票を送付し,109名から回答を得た.質問票は,産業医として対応したメンタルヘルス不調者の年齢階層別の特徴に関する設問と,若年労働者に対して実施しているメンタルヘルス対策とその効果の認知に関する2つのパートで構成された.全ての回答をデータ化し,質問毎に頻出語句とその出現数を数えた.前者に関しては,各年齢階層と頻出語句の関連性を検討するために統計学的処理を加えた.後者では,共同研究者及び研究協力者10名にて,若年労働者に対して実施しているメンタルヘルス対策とその効果の認知に関する記述を整理した.結果:コレスポンダンス分析において,20歳代の周辺には,性格,未熟,他罰的,発達障害,統合失調症,新型うつ病,不適応,入社,社会,上司,同僚などの語句が布置された.30歳代では業務の質的負担,量的負担といった仕事に関する語句,40歳代は家庭,子供,介護といった職場外要因に関する語句が布置された.若年労働者に対して実施した対策は,教育と面談に関する記述が頻出したが,その効果は不明であるという回答が最も多かった.複数名の回答者から,上司や人事担当者,産業医といった職場関係者と若年労働者の家族との連携により家族の支援の向上が認められたという回答が得られた.考察:若年労働者のメンタルヘルス不調は,職場への不適応や未熟で他罰的な性格といった個人的要因や精神障害,労働者の背景や職場組織に関する職業性ストレスといった様々な要因の影響を受けていることが示唆される.職場と家族との連携は若年労働者にとって重要なメンタルヘルス対策となる可能性がある.
- 著者
- 堀 諒雅 篠原 健一
- 雑誌
- 日本化学会 第102春季年会 (2022)
- 巻号頁・発行日
- 2022-01-17
2 0 0 0 OA フィブロインの利用
- 著者
- 玉田 靖
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.1_3-1_8, 2007 (Released:2016-04-12)
- 参考文献数
- 36
2 0 0 0 IR 日本経済の国際化と企業投資
2 0 0 0 OA ネットワーク指向のデザイン・アプローチの提案:情報システムの運用開発事例の分析か
- 著者
- 中村 雅子 上野 直樹
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.627-643, 2008 (Released:2010-04-23)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
In this study, authors participated in the process of re-designing an information system for civil activities. From viewpoint of Actor Network Theory, they mainly pointed out two findings. Firstly, designing an information system inevitably includes (re-)designing related social organization and activity itself. Therefore the requirement engineering approach has its limitations, for it implicitly assumes that activities and social organization are out there independently from information systems, user requirements already exist, and they can be obtained out with various methods. Secondly, the subject of the information system design should not be regarded as an isolated individual or a team. It is a fluid network including artifacts and people with various interests. Moreover, these actors sometimes participate in, and withdraw from, the project. A new approach, the network-oriented approach, is required to make a useful information system, which will not cause serious breakdown.
- 著者
- 小林 義行
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- スターリングサイクルシンポジウム講演論文集 2001.5 (ISSN:24242926)
- 巻号頁・発行日
- pp.73-74, 2001-10-25 (Released:2017-06-19)
2 0 0 0 OA 東語初階 : 韓訳重刊
2 0 0 0 OA 3.高血圧の最新治療
- 著者
- 苅尾 七臣
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.3, pp.514-526, 2019-03-10 (Released:2020-03-10)
- 参考文献数
- 28
- 著者
- 加藤 慶
- 出版者
- 専修大学緑鳳学会
- 雑誌
- 専修総合科学研究 (ISSN:13418602)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.121-128, 2021-10-20
2 0 0 0 OA コロナ禍における教育研修委員会活動 ~学会ウェビナーの立ち上げと今後の展開~
- 著者
- 菊池 宏幸
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.74-77, 2021 (Released:2022-01-23)
2 0 0 0 料理レシピ特徴に基づく料理−器関係の獲得
- 著者
- 福元 颯 高橋 知奈 松下 光範 山西 良典
- 雑誌
- 2022年度 人工知能学会全国大会(第36回)
- 巻号頁・発行日
- 2022-04-07
- 著者
- Hideki YORIMITSU Gregory J. P. PERRY
- 出版者
- The Japan Academy
- 雑誌
- Proceedings of the Japan Academy, Series B (ISSN:03862208)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.4, pp.190-205, 2022-04-11 (Released:2022-04-11)
- 参考文献数
- 83
- 被引用文献数
- 10
Biaryl synthesis continues to occupy a central role in chemical synthesis. From blockbuster drug molecules to organic electronics, biaryls present numerous possibilities and new applications continue to emerge. Transition-metal-catalyzed coupling reactions represent the gold standard for biaryl synthesis and the mechanistic steps, such as reductive elimination, are well established. Developing routes that exploit alternative mechanistic scenarios could give unprecedented biaryl structures and expand the portfolio of biaryl applications. We have developed metal-free C–H/C–H couplings of aryl sulfoxides with phenols to afford 2-hydroxy-2′-sulfanylbiaryls. This cascade strategy consists of an interrupted Pummerer reaction and [3,3] sigmatropic rearrangement. Our method enables the synthesis of intriguing aromatic molecules, including oligoarenes, enantioenriched dihetero[8]helicenes, and polyfluorobiaryls. From our successes in aryl sulfoxide/phenol couplings and a deeper understanding of sigmatropic rearrangements for biaryl synthesis, we have established related methods, such as aryl sulfoxide/aniline and aryl iodane/phenol couplings. Overall, our fundamental interests in underexplored reaction mechanisms have led to various methods for accessing important biaryl architectures.
2 0 0 0 OA デ・サンクティスの自然主義観
- 著者
- 阿部 史郎
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.67-75, 1955-12-30
Lo studio dell'evoluzione del pensiero del De Sanctis sul realismo e in sostanza quella del verismo. E degno di nota che questa evoluzione e divisa dall'anno 1848, in due, l'anno della revoluzione di Parigi. La sua posizione prima della rivoluzione e quella di un dirigente del Romanticismo. Quella dopo il 1848, sotto l'influenza dell' Estetica di Hegel, tradotta dal Bernardo nel 1850, la filosofia di Compte e sopratutto di Zola tende verso il verismo. Le relazioni fra il De Sanctis e lo Zola cominciavano dopo il 1877 ed e un fatto molto interessante e degno di studio, ma io qul prendo in considerazione solo la posizione del De Sanctis circa il realismo.