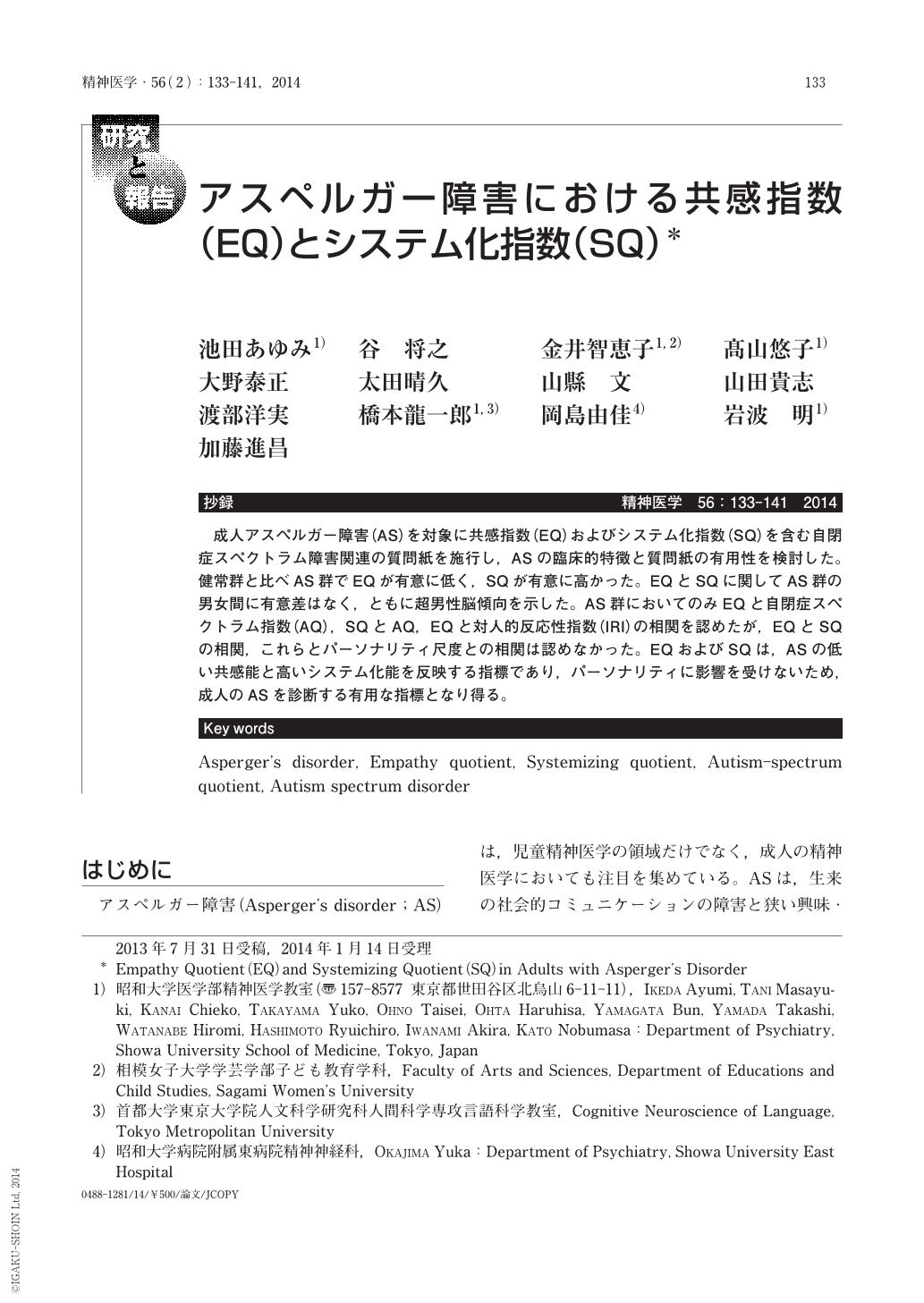2 0 0 0 OA ホロコーストとルーマニア(前篇)
- 著者
- 野村 真理
- 出版者
- 金沢大学経済学経営学系 = Faculty of Economics and Management, Kanazawa University
- 雑誌
- 金沢大学経済論集 = Kanazawa University economic review (ISSN:18840396)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.1-33, 2015-12-01
- 著者
- 佐々木 豊 中嶋 啓雄
- 出版者
- 京都外国語大学国際言語平和研究所
- 雑誌
- Ignis = Ignis (ISSN:24367591)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.149-176, 2021-12
2 0 0 0 多様性の秩序 : 批評の現在
2 0 0 0 OA 歯科領域の標準化 ―海外の状況と日本の標準マスターの位置付け―
- 著者
- 玉川 裕夫 齊藤 孝親 江島 堅一郎 佐々木 好幸 鈴木 一郎 多貝 浩行 冨山 雅史 日高 理智 森本 徳明 紀 山枚 岡峯 栄子 遠藤 明
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療情報学会
- 雑誌
- 医療情報学 (ISSN:02898055)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.183-195, 2014 (Released:2016-04-20)
- 参考文献数
- 74
本論文は,歯科・口腔外科領域の標準化に関する経緯と現状を,具体的な例とともに整理した総論である.歯科医療情報の電子的交換が広がりつつあるなか,国際的な状況も含めて読者の理解を得ることを目的とした. 歯科の標準病名マスターは,齊藤らによってとりまとめられ,医科の標準病名集とともに一般財団法人医療情報システム開発センターでメンテナンスされて,保健医療情報分野の厚生労働省標準規格の一つとなっている.歯式は,標準病名とあわせて歯科・口腔外科領域の病院情報システムに欠かせないことから,日本の歯式表記の特徴を述べ,国際的な表記の具体例を挙げて比較した.また,SNOMEDとISO/TR 13668(矯正歯科領域の規約)を例に,診療情報交換の場で歯式がどのように扱われているかを解説した.そして,現在使われているその他の指標について紹介し,最後に,歯科領域の標準化に関する今後の課題を考察した.
- 著者
- 小林 政子
- 雑誌
- 武庫川女子大学附属総合ミュージアム紀要・年報 = Bulletin of the Mukogawa Women's University Museum
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.13-30, 2022-03-16
- 著者
- 吉村 拓馬 大六 一志
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第52回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.366, 2010 (Released:2017-03-30)
2 0 0 0 OA こだま : 金沢大学附属図書館報
- 著者
- 金沢大学附属図書館広報委員会
- 出版者
- 金沢大学
- 巻号頁・発行日
- no.(135), 1999-10-01
- 著者
- SHOGO KIKUTA JOE IWANAGA BASEM ISHAK AARON S. DUMONT R. SHANE TUBBS
- 出版者
- Kurume University School of Medicine
- 雑誌
- The Kurume Medical Journal (ISSN:00235679)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.1-4, 2020-03-31 (Released:2022-03-11)
- 参考文献数
- 23
Summary: This paper aimed to better describe the anatomy of the superficial anterior atlanto-occipital ligament of the craniocervical junction and discuss this ligament’s potential function and clinical implications. A broad literature review on the anatomical features and findings of the superficial anterior atlanto-occipital ligament was performed. The superficial anterior atlanto-occipital ligament is located anterior to the anterior atlanto-occipital membrane. However, the physiological role of the superficial anterior atlanto-occipital ligament is still unclear due to a lack of anatomical and biomechanical studies although one study has suggested that this ligament is a secondary stabilizer of the craniocervical junction. Further studies are needed to clarify the function and anatomy of the superficial anterior atlanto-occipital ligament.
2 0 0 0 アスペルガー障害における共感指数(EQ)とシステム化指数(SQ)
- 著者
- 池田 あゆみ 谷 将之 金井 智恵子 髙山 悠子 大野 泰正 太田 晴久 山縣 文 山田 貴志 渡部 洋実 橋本 龍一郎 岡島 由佳 岩波 明 加藤 進昌
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.133-141, 2014-02-15
抄録 成人アスペルガー障害(AS)を対象に共感指数(EQ)およびシステム化指数(SQ)を含む自閉症スペクトラム障害関連の質問紙を施行し,ASの臨床的特徴と質問紙の有用性を検討した。健常群と比べAS群でEQが有意に低く,SQが有意に高かった。EQとSQに関してAS群の男女間に有意差はなく,ともに超男性脳傾向を示した。AS群においてのみEQと自閉症スペクトラム指数(AQ),SQとAQ,EQと対人的反応性指数(IRI)の相関を認めたが,EQとSQの相関,これらとパーソナリティ尺度との相関は認めなかった。EQおよびSQは,ASの低い共感能と高いシステム化能を反映する指標であり,パーソナリティに影響を受けないため,成人のASを診断する有用な指標となり得る。
2 0 0 0 OA 賀茂真淵の著述(擬古文)における「から」系のことば
- 著者
- 塚本 泰造
- 出版者
- 熊本大学文学部国語国文学会
- 雑誌
- 国語国文学研究 (ISSN:03898601)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.409-419, 2002-02-23
本稿では、本居宣長の著述に見られる「から」の考察(塚本(二〇〇一)に引き続き、賀茂真淵の著述に見られる「からに」「からは」(以下これを「から」系とする)を取り上げ、擬古文という表現の背後に、日本語の、論理的性格への変貌がどのようにうかがわれるかを考察する。
2 0 0 0 OA 日本における仏教研究の百年(日本の宗教研究の百年, <特集>第六十三回学術大会紀要)
- 著者
- 木村 清孝
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.947-961,iii, 2005-03-30 (Released:2017-07-14)
本論文は、近代日本において、西欧から移入された文献学的な仏教研究の軌跡を辿ることを基軸として、このおよそ百年間における仏教研究の歴史を顧み、その特徴を明らかにするとともに、それがもつ問題点を探り、合わせて今後の仏教研究のあり方について述べようとするものである。明治時代の初め、<近代的>な仏教研究の扉は、少なくとも表面的には伝統的な仏教学と切れたところで、南條文雄によって開かれ、高楠順次郎によって一応定着した。それが、文献学的仏教研究である。この伝統は、のちに歴史的な見方を重視する宇井伯寿によって新展開を見た。さらにその愛弟子の中村元は、宇井の視点と方法を継承しながらも、それに満足することなく、新たに比較思想の方法を導入し、「世界思想史」を構想し、その中で仏教を捉えることを試みた。この比較思想的な仏教研究が、西田哲学を継承する哲学的な仏教研究と並んで、現在も主流である文献学的な仏教研究に対峙する位置にあると思われる。最後に付言すれば、これからの仏教研究は、その中軸として、文献学的研究と、それを踏まえた思想史的研究、さらには、その思想史的研究によって明らかになる重要な「生きたテキスト」をよりどころとする比較思想的研究が遂行されることが望まれるのではなかろうか。
2 0 0 0 OA 高齢層における年齢と時間選好の関係
- 著者
- 福冨 雅夫 安藤 悠人 三谷 羊平
- 出版者
- 行動経済学会
- 雑誌
- 行動経済学 (ISSN:21853568)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.94-104, 2020-11-25 (Released:2020-11-25)
- 参考文献数
- 41
高齢化のさらなる進行が世界各国で続く中,高齢者の経済的意思決定をより良く理解することが重要となっている.時間選好は経済活動や医療健康行動をはじめとする様々な意思決定に影響を与えうるが,高齢者の時間割引率や時間非整合性は十分に検証されていない.本論文では,高齢者を対象として,時間選好に関する経済選択を含むフィールド実験を実施し,高齢者の時間選好と個人属性の関係を考察する.実験結果より,割引の程度は高齢層における年齢に関して逆U字型の形状をとる傾向にあること,高齢者は現在時点から遠い将来になるにつれて近視眼的になるという将来バイアスと整合的な傾向にあることが明らかになった.また,この時間非整合性の一種である将来バイアスと整合的な選択は,健康状態の悪い後期高齢者にてより多く観察された.
2 0 0 0 OA 水溶液から生じたイオン結晶に含まれる不純物
- 著者
- 一国 雅巳
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学教育 (ISSN:24326542)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.297-300, 1978-08-20 (Released:2017-09-15)
2 0 0 0 OA <論文>重田定一と広島高等師範学校
- 著者
- 菅 真城
- 出版者
- 広島大学
- 雑誌
- 広島大学史紀要 (ISSN:13448625)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.91-115, 2001-03-31
2 0 0 0 OA 野球のピッチング動作における再現性
- 著者
- 鈴木 久貴 湯浅 景元 Hisataka SUZUKI Kagemoto YUASA
- 雑誌
- 中京大学体育学論叢 = Research journal of physical education Chukyo University (ISSN:02887339)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.41-46, 2002-11-08
This study investigated pitching motion reproducibility in baseball using two pitchers as subjects, a graduate student and a person on the university ball team. Both were asked to actually throw, and a photograph was taken with a high-speed camera. Analysis was done using 2-dimensional picture. The results revealed that the coefficient of variation of the arm motion [two subjects] increased among the seven items measures. From this, it is thought that the arm motion before release (forearm, upper arm, and elbow) is related to ball control.
2 0 0 0 OA 日本帝国人口静態統計
- 出版者
- 内閣統計局
- 巻号頁・発行日
- vol.明治36年12月31日調, 1911
2 0 0 0 OA ロシア語におけるアイヌ語からの1借用語と地名calque
- 著者
- 村山 七郎
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1970, no.57, pp.22-40, 1970-03-31 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 16
Man unterscheidet in der Ainu-Sprache drei Dialekte: Hokkaido (Yezo)-Dialekt, Sakhalin-Dialekt und Dialekt der nördlichen Kurilen-Inseln. Die ersteren zwei sind ziemlich gut erforscht, während der letztgenannte restlos verschwand, ohne gut beschrieben und erforscht zu werden. Der letzte Dialekt wurde zuerst von S. P. KRASCHENINNIKOV, obgleich auf unvollkommne Weise, in seinem Lebenswerk “Beschreibung von dem Lande Kamtschatka”(russisch, Sankt-Petersburg, 1755) beschrieben. Es ist jetzt klar geworden, dass das Material der Ainu-Sprache in diesem Buch auf der Information eines Ainus aus der Schumusch-Insel und eines Ainus aus der Poromuschir-Insel beruht, die vom 19. bis zum 31. Juli 1738 in Bolscheretsk in Kamtschatka verweilten. Er hatVocabularium Latino-Curilice (Manuskript, Leningrad) hinterlassen, das dem Sprachmaterial in seinem Buch zu Grunde liegt. Dieses MS wurde zum erstenmal von dem Verfasser dieser Zeilen in seinem Aufsatz “Ainu in Kamchatka”(Bulletin of the Faculty of Literature, Kyushu University, No.12, Fukuoka 1968) veröffentlicsht. Das Sprachmaterial der Schumusch-Insel, das der polnische Zoologe (später Professor der Krakower Universität) DYBOWSKI während seines Aufenthaltes in Kamtschatka (1879-1883) gesammelt hat, wurde von RADLINSKI (Forscher des Christentums) veröffentlicht. Dieses Material, das ca.1900 Ainu-Wörter enthalt, ist der Wissenschaft wenig bekannt gewesen. R. TORIIs Sprachmaterial der Ainu auf derselben Insel, das er im J. 1899 auf der Insel Schikotan gesammelt hat (ca. 700 Worter) trägt nicht wenig zur Kenntnis des Dialekts der nördlichen Kuril-Inseln.Anhand dieser Materialien kann man sich jetzt ein Bild des letztgenannten Dialekts verschaffen, was man bisher fiir beinah unmöglich gehalten hat.Von diesem Dialekt ist ein Wort, d. h. urir “Kormoran” ins Russische eingedrungen, und zwar in der Form uvil (ypun) . Dieses Wort wurde zuerst in dem erwahnten Buch KRASCHENINNIKOVs (1755) und dann in dem von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Petersburg im J. 1847 herausgegebenen “Wörterbuch der Kirchen-Slawischen und der Russischen Sprache” und weiter in dem beruhmten Wiirterbuch von DAL' aufgenommen. Dieses Wort bietet ein gutes Beispiel für “Ferndissimilation” im Russischen; Man vergleich Februar февралъ (fevral') , altrussisch ver'bludz “Kamel”, tschechisch velbloud “id.” еерблоб (verbl'ud.) Ein Uebersetzungslehnwort findet man in dem Toponym Lopatka (russisch “Schulterblatt”), Das ist die russische Uebersetzung des Ainu-Toponyms tapéra.-tapére “Schulterblatt”. Die Ainu, die das südlichste Gebiet der Halbinsel Kamtschatka vor der Ankunft der Russen am Ende des XVII. Jahrhunderts bewohnten, hatten dem Kap den Namen tapéra gegeben, den S. P. KRASCHENINNIKOV, wahrscheinlich durch seine Kenntnis der lateinischen Sprache beeinflusst, in kapury (lat. scápulae) verwandelte. Kapury ist eine Kontamination von tapéra.-tapére und scapulae.