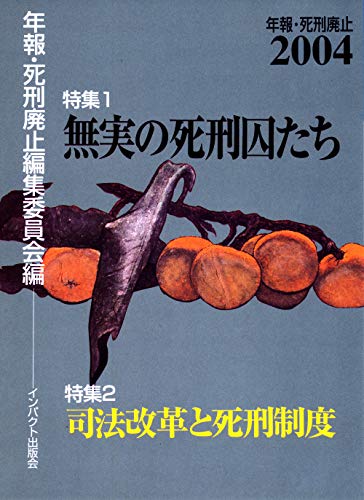- 著者
- 青木 健
- 出版者
- 東京大学東洋文化研究所
- 雑誌
- 東洋文化研究所紀要 (ISSN:05638089)
- 巻号頁・発行日
- vol.158, pp.166-78, 2010-12
- 著者
- Hiroshi Kakeya
- 出版者
- The Japanese Society for Medical Mycology
- 雑誌
- Medical Mycology Journal (ISSN:21856486)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.11-15, 2022 (Released:2022-02-28)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 2
In clinical settings, the number of immune compromised patients have increased as a result of developments in medical technology (e.g., organ transplantation, anticancer drugs, steroids, TNF inhibitors, etc.). However, patients with fungal diseases are also increasing globally. In recent years, the distribution and pathogenicity of fungi worldwide have been changing, with reports that new fungi are emerging, and antifungal-resistant fungi are spreading globally. Global warming, globalization, human activities, and other factors have been suggested as contributing to the emergence of new fungi. Some of the antifungals against which resistant fungi have emerged are commonly used not only for human but also for animal health care and crop protection. Consequently, the occurrence of antifungal-resistant fungi has become a clinical issue. Solving these problems entails continuing the “One Health” approach, which in turn requires updating medical mycology information with regard to the emerging pathogenic fungi. In particular, this paper reviews the recent information on Cryptococcus gattii, Candia auris, and azole-resistant Aspergillus fumigatus.
がん細胞の増殖能や侵潤・転移能はがん細胞をとりまく宿主細胞との相互作用を介して大きく影響されることががん細胞-宿主相互作用として知られてきた。本年度は宿主間質に由来するHGFならびにがん細胞に由来するHGF誘導因子ががん細胞-宿主相互作用のメデイエーターとして、がん細胞の悪性化に関与することを明らかにした。胆のうがんは一般に高転移性で致死率の高い悪性のがんである。ヒト胆のうがん細胞は宿主組織内では高い侵潤能を有するものの、コラーゲンゲル上に培養しても自らゲル内に侵潤することはない。ところが、正常線維芽細胞とコラーゲンゲルをはさんでco-cultureすると胆のうがん細胞はゲル内に侵潤し、液性因子を介した間質細胞との相互作用が胆のうがん細胞の侵潤能を誘導している。しかも、このco-culture系でのがん細胞の侵潤はHGFに対する抗体により完全にブロックされ、間質由来の侵潤因子の実態はHGFであることを明らかにした。さらに胆のうがん細胞のゲル内侵潤はHGF以外での代表的な増殖因子では誘導されず、HGFは強力な侵潤誘導因子であるといえる。一方、興味深いことにがん細胞は間質線維芽細胞に対しHGFの産生を高める因子を産生、このHGF誘導因子(インジュリン)の実体はIL-1βであることを明らかにした。また同様に線維芽細胞が産生する口腔粘膜上皮がん細胞に対する侵潤誘導因子の実体もHGFであることを明らかにした。その他、ヒト肺小細胞がんやオリゴデンドログリオーマの中にはvariant HGFを産生し、しかもこれらの細胞においては、HGFがオートクリン的にがん細胞の運動性や侵潤能を高めていることを明らかにした。一方、HGFによるmotilityの亢進にはp125^<FAK>(focal adhesion kinase)を一過的なリン酸化が関与することを明らかにした。p125^<FAK>はβ1インテグリン結合することが知られており、HGF刺激後、初期のfocal adhesionの形成、細胞骨格の再構成にはp125^<FAK>のリン酸化が関与しており、HGFによる細胞のmotility亢進において細胞-マトリックスとの相互作用はp125^<FAK>を介して調節されていると思われる。これらの観点から、HGFによる侵潤をブロックするアンタゴニストの開発は今後がん治療という点で極めて重要になることが予測される。
2 0 0 0 第13話 柳田昌一の挑戦
- 著者
- 荒田 洋治
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.330-330_1, 2013
2 0 0 0 無実の死刑囚たち
- 著者
- 年報・死刑廃止編集委員会編集
- 出版者
- インパクト出版会
- 巻号頁・発行日
- 2004
2 0 0 0 OA ナスを用いたpH指示薬の教材研究
- 著者
- 島田 秀昭 松本 直也
- 出版者
- 熊本大学
- 雑誌
- 熊本大学教育学部紀要 (ISSN:21881871)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.235-237, 2019-12-16
The red cabbage pigment is used as a teaching material for acid alkaline experiment in lower secondary school science. However, it is difficult to obtain the red cabbage stably throughout the year. Thus, in the present study, to develop a new teaching material for acid alkaline experiment, the extraction method of pigment from eggplant and the color development at each pH of the pigment extracted were examined. Furthermore, the color development at each pH of the pigment extracted from the several eggplants were compared.
2 0 0 0 《追悼》豊後レイコさんを偲んで
- 著者
- 深井 耀子
- 出版者
- 日本図書館研究会
- 雑誌
- 図書館界 (ISSN:00409669)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.6, pp.424-425, 2017
2 0 0 0 空想的平和主義から空想的軍国主義ヘ (現代国家論の条件<特集>)
- 著者
- 猪木 正道
- 出版者
- 中央公論新社
- 雑誌
- 中央公論 (ISSN:05296838)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.12, pp.p62-75, 1980-09
2 0 0 0 IR ろう教育における2つの教育方法--障害学の2つのモデルによる整理
- 著者
- 座主 果林
- 出版者
- 奈良女子大学社会学研究会
- 雑誌
- 奈良女子大学社会学論集 = Nara Women's University sociological studies (ISSN:13404032)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.243-257, 2010
清水新二教授定年退職記念号
- 著者
- Nochlin Linda 松岡 和子
- 出版者
- 美術出版社
- 雑誌
- 美術手帖 (ISSN:02872218)
- 巻号頁・発行日
- no.407, pp.p46-83, 1976-05
2 0 0 0 最高裁判所民事判例集
- 出版者
- 最高裁判所
- 巻号頁・発行日
- 1948
- 著者
- 井野 俊介
- 出版者
- 九州大学大学院人文科学研究院地理学講座
- 雑誌
- 空間・社会・地理思想 (ISSN:13423282)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.15-41, 2012
2 0 0 0 IR 日本の病院の福祉的課題
- 著者
- 佐藤 沙織
- 出版者
- 尾道市立大学経済情報学部
- 雑誌
- 尾道市立大学経済情報論集 (ISSN:21870276)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.53-68, 2021-07-15
2 0 0 0 IR 戦後部落解放運動史ノート(その1)
- 著者
- 村越 末男
- 出版者
- 大阪市立大学
- 雑誌
- 同和問題研究 : 大阪市立大学同和問題研究室紀要 (ISSN:03860973)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.158-199, 1980-03
2 0 0 0 OA 永久気管切開によりQOLが改善された咽頭喉頭腺癌の猫の1例
- 著者
- 桑原 岳 桑原 和江 桑原 光一
- 出版者
- 動物臨床医学会
- 雑誌
- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.65-68, 2013-06-20 (Released:2014-12-06)
- 参考文献数
- 7
症例は日本猫,16歳,避妊雌で進行性の呼吸困難を主訴に来院した。一般身体検査では喉頭部にマスが触知された。一般的に,猫の喉頭部腫瘍の予後は悪いといわれている。その理由として,腫瘍特異的な治療法が確立されていないこと,また全喉頭切除術により深刻な合併症を伴い得ることが挙げられる。本症例では永久気管切開による対症療法を実施し,喉頭部の腫瘍に対して部分切除生検を行った。病理学的検査を実施した結果,咽頭喉頭腺癌と診断された。症例は順調に麻酔から覚醒し,手術3日目に退院した。術後,飼い主による主観的なQOLは改善されたようであったが,手術54日目に嚥下困難による食欲廃絶が認められ,その後に死亡した。死亡直前まで呼吸状態は良好であった。咽頭喉頭腺癌により重度の呼吸器症状を呈する猫では,低侵襲な部分切除生検と永久気管切開術を実施して気道を確保することが,動物のQOLを改善し,なおかつ飼い主の満足度を得るための選択肢のひとつとなり得ることが示された。
2 0 0 0 OA モクレン科の花の匂いと系統進化
- 著者
- 東 浩司
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 分類 : bunrui : 日本植物分類学会誌 (ISSN:13466852)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.49-61, 2004-02-29
- 著者
- Sitaram Bhavaraju Subramanya G. Sreerama David Taylor Steven Rau
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.226-229, 2022-03-01 (Released:2022-03-01)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2
Quantitative proton NMR (qHNMR) methodology was employed for the stoichiometric (free base and the corresponding counterion) assessment of a ticagrelor process impurity, also referred to in the United States Pharmacopeia (USP), Pharmacopeial Forum as Ticagrelor Related Compound A (RC A), [(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropan-1-amine (R)-mandelate], also called as Tica amine mandelate, a critical impurity that, when present during manufacturing, has a limit of not more than 0.0008%. The Tica amine is also a listed impurity E in the Ticagrelor monograph, in European Pharmacopeia. Because there was no existing NMR spectroscopic method in the literature specific to quantify the counterion (mandelic acid) in Ticagrelor RC A, this study aimed to fill the gap. Accurate stoichiometric measurement of this impurity serves to enhance product quality in the manufacturing of the ticagrelor active pharmaceutical ingredient (API). Using ethylene carbonate as an internal standard (IS), the qHNMR analysis on Ticagrelor impurity, revealed many key characteristics of the test mixture composition, including (free base and counterion). The results demonstrate that qHNMR has great potential for addressing several key quality attributes associated with chemical analyses such as detection, identification, quantification, and purity determination, as well as deriving molecular stoichiometry, all from the single proton spectrum.