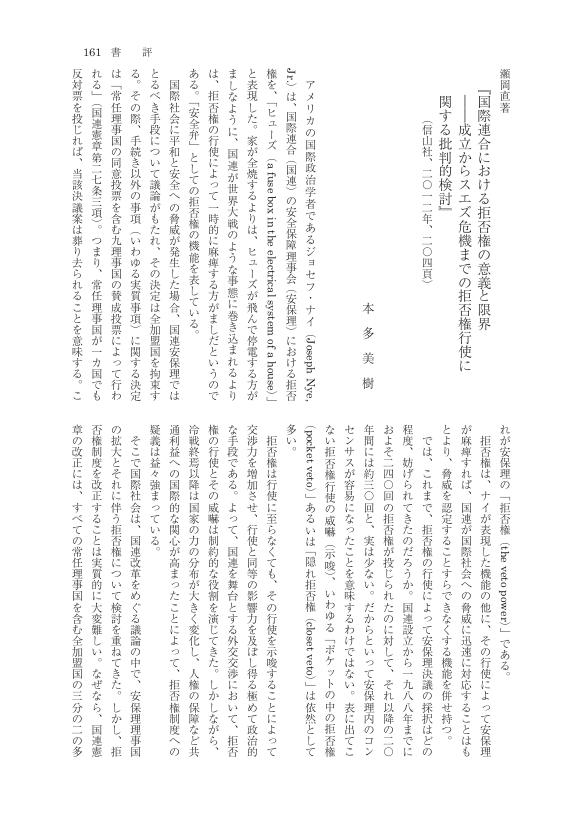- 著者
- 村尾 修 山崎 文雄
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.555, pp.185-192, 2002-05-30 (Released:2017-02-04)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 15 10
A number of building damage surveys were carried out for different purposes after the 1995 Hyogoken-Nanbu Earthquake. The damage surveys by local governments intended its use for property tax reduction while the survey by the CPIJ & AIJ group aimed to get technical records. This paper presents building fragility curves based on the CPIJ & AIJ damage survey data for Nada Ward, Kobe City, and the detailed building inventory, structural type and construction period, provided by Kobe City Government. This paper also compares them with the fragility curves based on the local government's survey for property tax reduction to clarify the relationship between the two evaluations.
- 著者
- 吉田 索 浅桐 公男 朝川 貴博 田中 宏明 倉八 朋宏
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.169-175, 2019 (Released:2019-09-15)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 3
近年,生体電気インピーダンス分析法(以下BIA)は,日常の診療や栄養評価,スポーツなどのさまざまな分野に用いられている.このBIAを利用して算出されるPhase angle(以下PhA)は細胞膜の抵抗を表した角度であり,細胞や細胞膜の栄養状態と関係が深く,体細胞量に反映する.健常者やアスリートなどの構造的完成度の高い細胞膜をもった正常細胞では,PhAは高く計測され,老化やがんなどの細胞膜の構造的損傷や細胞密度の低下した障害細胞では,PhAは低く計測される. PhAは細胞の健常度や全体的な栄養状態を反映することから,各種疾患の予後予測因子や栄養指標として注目されている.また,PhAは人体に微弱電流を流し細胞膜の抵抗値を直接測定して算出する実測値であるため,身長や体重だけでなく体液過剰の影響を直接受けない利点がある.そのため,通常の体成分分析には則さない重症度の高い患者や重症心身障害者などの正確な栄養評価が困難な患者にPhAは有用と思われる.
- 著者
- 本多 美樹
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.175, pp.175_161-175_164, 2014-03-30 (Released:2015-09-05)
2 0 0 0 現代的いじめについての社会心理学的考察
- 著者
- 塩谷 治彦
- 出版者
- 北海道社会学会
- 雑誌
- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.132-149, 1997
いじめが重大な社会問題となっている中で,この論文は現代的いじめをもたらす社会的背景についての解明を試みたものである。いじめを引き起こす原因,または仮説として,家庭の中での過保護や放任,甘やかしなどが指摘される一方,その社会背景として受験競争や管理主義の学校教育の弊害が指摘されてきたが,現代のいじめを引き起こす原因の説明としては不十分の感がある。そこで本論では,いじめを引き起こす社会背景として共同社会から利益社会への変化の中で相互の信頼関係が衰退しており,それが進学競争や管理主義教育の中で青少年の不満や葛藤を強めているという仮説を設定した。現代的いじめを引き起こす要因として家庭や学校での青少年の置かれた抑圧的状況を仮定し,少年たちの欲求不満やストレスの増大がいじめにそのはけ口をもたらしているものと考えられる。ただし,いじめが暴行や恐喝,傷害など陰湿で残酷な行為につながる場合には,管理主義的教育や進学競争の中での緊張や欲求不満ばかりでなく,問題を起こす少年たちの管理・抑圧されることへの「うらみ」の感情があることを仮定することが必要である。いじめが暴力的非行に結び付く場合には,自己主張を抑圧されることのうらみの心理が方向転換されて弱い者いじめに結び付く可能性が高いことを示した。
2 0 0 0 OA 政府のない大使館 1918-1924 : ロシア革命後の在日ロシア大使館
- 著者
- ポダルコ ピョートル
- 出版者
- 日本スラヴ・東欧学会
- 雑誌
- Japanese Slavic and East European studies (ISSN:03891186)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.21-42, 2001-03-31
革命直前、帝政ロシア在日公館は、東京の大使館をはじめ、日本本土(内地)や朝鮮半島、遠東半島に10館の総領事館・領事館があり、その外交官数は約30人だった。1917年10月の社会主義革命直後、新しいボリシエビキ政府の外務大臣に当たる「外務人民委員」トロツキーの、1917年11月26日付(新暦の12月9日)の命令により、ソビエト政権を認めなかった元帝政ロシアの外交官たちは、全員退職させられた。一方、海外諸国で勤めていた外交官たちは、トロツキーの命令に反対し、フランスのパリで集会を行い、元駐ローマロシア大使ミハイル・ギルスを議長とする「大使会議」を設立した。それ以降この大使会議は、海外諸国に在住した元帝政ロシア外交官にとり、彼らの活動の一致をはかるコーディネータ機関になった。駐東京ロシア大使館のスタッフも大使会議との定期的連絡を維持していた。ひきつづき7年間(1918-1924)にわたって、駐日ロシア大使館(「旧大使館」)は、在日ロシア人の代表的な機関であった。例えば、最初から、来日したロシア人亡命者に対して最も面倒をみたのは、本国において正式にロシアを代表するロシア外交官であった。特に、駐日ロシア大使館の経済的・政治的な状況は、他国における帝政ロシアの外交機関と異なっていた。大使館の財政は、第一次世界大戦中に行った軍需発注金をはじめ、義和団乱後の賠償金等からなっていた。また、駐日ロシア大使館のスタッフは、自分たちも亡命生活を送りながらソビエト政権に反対する立場に立っており、極東の各地に居留するロシア人への財政支援の執行をした。外交官は、日本の当局からもロシアの公式の代表的機関として以前通り認められていたので、このような状態にしたがって自分の使命を果たし続けていた。その「政府無しの7年間」にわたって、彼らはシベリアで続いていた反ソビエト闘争を支持したり、シベリア・極東の各地に作られた政府に対する援助を行ったりしたが、日ソ国交樹立の結果、ついに自分たちの活動に終止符を打たざるをえなかった。その直前まで代理大使は、在日ロシア人の地位(「無国籍」)等について、日本政府との話合いを行っていた。1924年末、各領事、副領事、その他の職員は皆3 ヶ月分の給料をもらい、退職させられた。1925年8月4日、日ソ両政府は、大使館や領事館を両国に開設することを決定した。ところが元の外交官は、「新政権」(ソビエト政権)に就職することを希望せず、民間人としての生活を選んだという。
- 著者
- 川田 昌克
- 出版者
- 自動制御連合講演会
- 雑誌
- 自動制御連合講演会講演論文集 第57回自動制御連合講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.598-605, 2014 (Released:2016-03-02)
LEGO MINDSTORMS は PBL 教育の題材として広く教育現場で利用されているが,制御工学教育の活用事例はほとんどない.本報告では,サードバーティの LEGO 用ロータリエンコーダと LEGO Power Functions シリーズのモータを利用して製作した回転型倒立振子を,Simulink Support Package により動作させることにより,制御工学を効果的に教育する事例を紹介する.
2 0 0 0 OA LEGO MINDSTORMSを利用した回転型倒立振子の開発
- 著者
- 川田 昌克
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.192-195, 2015-03-10 (Released:2015-05-26)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 正田 浩由
- 出版者
- 白鴎大学経営学部
- 雑誌
- 白鴎大学論集 = The Hakuoh University journal (ISSN:09137661)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.175-195, 2020-03
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1936年04月10日, 1936-04-10
2 0 0 0 OA 立憲民政党史
- 著者
- 立憲民政党史編纂部 編
- 出版者
- 立憲民政党史編纂部
- 巻号頁・発行日
- 1934
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1911年12月29日, 1911-12-29
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1936年12月07日, 1936-12-07
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1939年07月01日, 1939-07-01
2 0 0 0 IR 沖縄における方言札の出現に関する研究 : 1911年度以前を中心に
- 著者
- 梶村 光郎
- 出版者
- 沖縄大学地域研究所
- 雑誌
- 地域研究 = Regional studies (ISSN:18812082)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.1-16, 2019-04
小論は、沖縄県内の小学校教育のお手本と目される沖縄県師範学校附属小学校が方言札を導入した1911年度を沖縄の方言札の歴史における一つの画期と見なし、それ以前の方言札の事例を調査し、1900年代以前にも方言札が存在したことと、その事実が意味することを考察するものである。考察の対象となる事例が19あることと、方言札の最も古い事例は1903年であるという「通説」を覆す、最も古い事例が1895年度・1896年度頃のものであることを明らかにした。また、1911年度以前の方言札の実態を回想・証言・第一次史料を用いて眺めてみると、時期がまちまちであり、地域も沖縄全県にまたがっており、札の形状も様々であることが確認できた。罰の内容も方言札を手渡されるだけですむ場合と、札を首に掲げられる場合があり、それに加えて立たされたり、掃除当番をさせられたり、修身の点を下げられたりするなどの罰があることが確認された。さらに、方言札は、教師の目が届かない時間や場所で、取り締まりの係や児童・生徒同士によって監視され、札を手渡されたりなどするものであった。そうしたことが日常的に行われていたが、特別に「方言札の日」を設定して行われたりしている場合もあった。方言札の学校への導入については、生徒間の取り決めに基づく事例(県立一中)を除けば、学校・教員側が主体となって行った事例ばかりだった。罰との関係で言えば、方言を使用した場合、①方言札を手渡される罰、②方言札を首にかけられる罰、③方言札とそれ以外の罰を課されること、④方言札をもち続けることに伴う制裁という形が見られた。一方、下級生がいじめを怖れ上級生に方言札を渡せないという事態も起こり、廃止された事例も見られた。その事実は、方言札の教育方法や教具としての欠陥を示すものであった。また、沖縄県師範学校附属小学校の標準語教育実践の例から見ると、この学校では、方言札の使用だけでなく、普通語と対照させた方言集を用意したり、談話会を設けて言語の練習をさせたりすることなど、標準語を正しく使用させるための取り組みや工夫があった。このことは、方言札だけで標準語の教育・励行・普及が図られるとは考えられていなかったことを示している。 以上のことを踏まえ、方言札の出現の時期や出自などの問題を検討し、方言札の出現には、方言を使用させないで標準語を話させようという学校・教員の強い意志が関係していること。その意味で、どの時点でも方言札は出現する可能性があることを指摘した。
2 0 0 0 IR 『おくのほそ道』序文「月日は百代の過客」小攷 : 李白「春夜宴桃李園序」詳解を通して
- 著者
- 澁澤 尚
- 雑誌
- 言文 (ISSN:09110356)
- 巻号頁・発行日
- no.68, pp.15-48, 2021-03
2 0 0 0 OA ミストCVD法により作製したAl2O3薄膜とGaN系MIS-HEMTへの応用
- 著者
- 本山 智洋 Ali Baratov Rui Shan Low 浦野 駿 中村 有水 葛原 正明 Joel T. Asubar 谷田部 然治
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面真空学会
- 雑誌
- 日本表面真空学会学術講演会要旨集 2021年日本表面真空学会学術講演会 (ISSN:24348589)
- 巻号頁・発行日
- pp.2Ca10S, 2021 (Released:2021-12-24)
GaN系パワー・高周波デバイスのゲート絶縁膜として有望なAl2O3薄膜を低コストな酸化物薄膜形成手法であるミストCVD法により作製し評価した。ミストCVD法で作製したAl2O3薄膜は禁制帯幅など、ALD法で作製したAl2O3薄膜と同等の物性値を示した。またAl2O3/AlGaN/GaNキャパシタの容量-電圧特性から、良好なAl2O3/AlGaN界面が形成されていることが示唆された。
2 0 0 0 OA 可視化技術の最近の動向
- 著者
- 福井 希一
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.182-188, 2000-03-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 11
2 0 0 0 OA 郵送調査の効用と可能性
- 著者
- 松田 映二
- 出版者
- 日本行動計量学会
- 雑誌
- 行動計量学 (ISSN:03855481)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.17-45, 2008 (Released:2009-04-07)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 14 8
Many mail surveys have been conducted in Japan since the 1950's. Unfortunately, their response rates have been lower than other methods of administration. Various difficulties that result from the lack of an interviewer are major contributing factors of the lower response rates. This paper provides some guidelines regarding the design of mail questionnaires, the timing of the follow-ups, and other operational details. Mail surveys can potentially achieve high response rates. Further, their response rates in rural and urban areas are very similar. In addition, the response rates of mail surveys were found to be unrelated to the educational level of the respondents. A problem of mail surveys is the omission of questions by some respondents. However, there are usually few omitted questions and the overall quality of answers is usually better. The tendency to leave unanswered some branching questions is discussed and suggestions are provided how to decrease it.
- 著者
- Hiroyuki Matsuoka Gen-ichiro Sano Ryuta Hattori Hiroyuki Tomita Daisuke S. Yamamoto Makoto Hirai
- 出版者
- Japanese Society of Tropical Medicine
- 雑誌
- Tropical Medicine and Health (ISSN:13488945)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.47-53, 2012 (Released:2012-10-05)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 4
It has been proposed that transgenic mosquitoes can be used as a “flying syringe” for infectious disease control. We succeeded in generating a transgenic (TG) mosquito, Anopheles stephensi, excreting and discharging DsRed in saliva. DsRed was deposited on the membrane where the TG mosquito probed with its proboscis. Repeated feeding by the TG mosquitoes induced anti-DeRed as well as anti-SG antibodies in mice. This indicates that the TG mosquitoes can immunize the animal. Moreover, in this report, we employed a pre-immunization method before exposing mice to the TG mosquitoes. We injected DsRed to mice to prepare memory B cells and exposed the mice to bites by the TG mosquitoes excreting DsRed. The mice produced a higher titer of antibody to DsRed, suggesting that the bites from TG mosquitoes act as a booster and that primary immunization with a vaccine protein and exposure to TG mosquitoes excreting the vaccine protein in the saliva produces a synergistic effect.