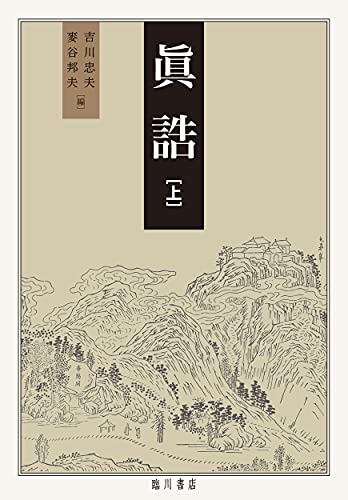2 0 0 0 IR 日本の介護保険制度の導入過程
- 著者
- 何 妨容
- 出版者
- 広島大学法学会
- 雑誌
- 広島法学 (ISSN:03865010)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.180-159, 2020-07
This paper focuses on the discussions about the care services for elderly people during the introduction of Long-Term Care Insurance in Japan.To resolve the problem of nursing care socialization and the associated financial challenges, in 2000, Japan introduced Long-Term Care Insurance under the Ministry of Health and Welfare, through political processes such as agreements with stakeholders, ruling examination, and diet process. Although the Ministry of Health and Welfare initially intended to examine how elderly care should be provided and how to protect financial security and develop a social care system, the discussion mostly focused on financial security and the social insurance system.As a result of the inadequate debate about elderly care service during the introduction of the system, several new social problems occurred, accompanied by the rapid increase in the elderly population, weakened family function, and the increase of new forms of unconventional families. For example, the number of elderly people waiting to occupy the intensive care home is increasing rapidly, especially in the urban areas. The number of family members who have to quit their jobs for family care is also increasing.
- 著者
- 川村 卓 小池 関也 阿江 数通
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.17038, (Released:2019-02-05)
- 参考文献数
- 22
This study examined the flow of energy in the right and left upper limbs of skilled baseball batters during the forward swing motion at different bat head speeds to obtain basic insights that would be useful for batting coaching. The subjects were 23 college baseball outfielders in university teams. The subjects were instructed to hit a ball toward the pitcher from a tee set at a mid-height position. Measurements were taken using 47 points on each subject’s body and 6 points on the bat for a total of 53 points, onto which reflective markers were attached. The 3D coordinates of each marker were measured using a 3D optical motion capture device (Vicon Motion Systems’ VICONMX, 12 cameras, 250 Hz). The variables in the kinetics of each hand were measured using a force detection sensor bat (1000 Hz). The subjects were separated into a faster group of 36.8±0.8 m/s and a slower group of 34.7±1.1 m/s for analysis. In terms of energy transmission, the data revealed that the faster group, in addition to showing additional torque on the knob side shoulder joints, were able to transmit more mechanical energy from the knob side shoulder joints to the end of the upper limbs than the slower group, and that this might be related to an efficient bat head speed. In addition, the faster group showed an increased positive torque power, and transmitted greater mechanical energy to the bat from the hand region. In other words, to prevent mechanical energy from being absorbed while adjusting the bat trajectory near the time of impact, skilled bat control involving movement of the hand joints appeared to determine the bat head speed.
- 著者
- 江頭 満正
- 出版者
- 尚美学園大学総合政策学部
- 雑誌
- 尚美学園大学総合政策研究紀要 = Bulletin of policy and management, Shobi-Gakuen University (ISSN:13463802)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.1-16, 2020-03
音楽フェスティバルの市場は拡大し、様々な理由で観客を引き付けることができる、ユニークで特別なイベントである。しかし、日本では音楽フェスティバルに関する研究は殆ど存在しない。本論の目的は、ロックフェスティバルの初回訪問者とリピーターによる行動の相違点を発見することである。その結果、参加回数による参加動機の違いが明らかになった。初回来場者は音楽を中心とした興味関心が強いが、リピーターは音楽フェスティバル特有の価値を重視していた。この調査の結果から、主催者が大勢の観客を引きつけるために、特定のアーティストだけに頼ることは危険であることが示された。
2 0 0 0 IR 樋口一葉『うもれ木』考
- 著者
- 萩原 進
- 出版者
- 法政大学経済学部学会
- 雑誌
- 経済志林 (ISSN:00229741)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.3, pp.175-194,図版2p, 2009-03
One of Ichiyo Higuchi's early short novels, Umoregi, portrays the tragic life of a Satsuma potter. The protagonist, Raizo Irie, dreams of becoming a great Satsuma potter, but is too poor to build a pottery atelier. He is a dreamer, who will never earn profits from pottery, so his sister Ocho supports him by working as a maid. One day, Raizo is lucky to meet a wealthy sponsor who was a fellow potter during their apprenticeship. Ocho falls in love with this sponsor. Raizo finally succeeds in creating an excellent Satsuma piece. However, he discovers that the true intent of the sponsor is to make Ocho into a prostitute to get money, and he smashes the Satsuma pottery into pieces. This article analyzes this novel by casting light on Satsuma pottery in the Meiji period.
- 著者
- 吉原 直毅
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 経済セミナー (ISSN:0386992X)
- 巻号頁・発行日
- no.646, pp.107-117, 2009-02
- 著者
- 長谷川 伸
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.154_2-154_2, 2017
<p> 本研究では投球速度の異なる野球投手の筋厚を比較し、高い投球速度を示す投手の形態的特徴を明らかにすることを目的とした。2016、2017年の春季オープン戦に登板した投手を対象に全投球の球速上位20%の平均値を算出し、140km/h以上を高速群(n=7)、130km/h未満を低速群(n=9)として抽出した。筋厚測定には超音波診断装置を使用した。撮像部位は両側の前腕部、上腕部(前・後部)、胸部、腹部、側腹部、肩甲棘部(上・下部)、肩甲骨内側部・肩甲下部、腰部、臀部(後・側部)、大腿部(前・後部)、下腿部(前・後部)であり、これらの17部位より29筋を測定の対象とした。部位別の比較において高速群では投球側の前腕部、腰部、臀部、大腿後部、下腿後部、非投球側の腹部、側腹部、大腿前部、臀部、大腿後部、下腿後部において低速群よりも高い筋厚を示した。また、筋別の比較において高速群は投球側の脊柱起立筋、大殿筋、大腿二頭筋、腓腹筋、非投球側の腹直筋、内腹斜筋、脊柱起立筋、大腿二頭筋において低速群よりも高い筋厚を示した。これら結果より投球速度の高速群では体幹、下肢筋群の発達が顕著であることが示唆された。</p>
2 0 0 0 IR 独露通商対立とロシア機械工業
- 著者
- 伊藤 昌太
- 出版者
- 福島大学経済学会
- 雑誌
- 商学論集 (ISSN:02878070)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.29-85, 1971-03
2 0 0 0 OA 性感染症―増加する梅毒―
- 著者
- 髙橋 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.5, pp.931-937, 2018-05-10 (Released:2019-05-10)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
梅毒の罹患率は増加しており,本疾患の疫学,診断及び治療の知識が必要となっている.梅毒の病変は,典型例から非典型例まで多彩であり,典型例ではない場合には,梅毒血清反応の検査が必要になる.また,無症候梅毒も梅毒血清反応の検査によって診断できる.治療は,ベンザチンペニシリンGが世界標準の推奨治療法であるが,我が国では使用できないため,アモキシシリンが投与される.治癒判定は,症例によって複雑な解釈になるが,カルジオリピンを抗原とする抗体検査法が治療経過を反映するので,こちらを追跡することになる.梅毒への対応としては,まずは疑い,検査を依頼することとなる.他の性感染症の罹患や性感染症の既往,不特定の性的パートナーの存在,HIV(human immunodeficiency virus)感染等の梅毒も含めた性感染症感染の危険因子を有する場合には検査が必要であることを伝える必要がある.梅毒を制圧するためには,特定の診療科のみではなく,多くの診療科が連携して立ち向かう必要があることを強調したい.
2 0 0 0 IR 中級日本語学習者が望む学習とは何か : 高等教育機関におけるアンケート調査
- 著者
- 内丸 裕佳子
- 出版者
- 岡山大学国際センター, 岡山大学教育開発センター, 岡山大学言語教育センター, 岡山大学キャリア開発センター
- 雑誌
- 大学教育研究紀要 (ISSN:18815952)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.61-72, 2012-12
本稿は,アンケート調査を通じて高等教育機関で学ぶ学習者の中級レベルに対する学習ニーズを明らかにすることを目的とする。アンケート調査結果は4点にまとめられる。(1)教科書の説明および内容:初級に比べ評価が低くなる。母語による解説が望まれている。(2)学習項目:アカデミックな日本語,日常生活での日本語の両方に対するニーズがある。会話学習への要望が最も多く,次いで文法・文型,語彙が同数だった。(3)教え方に対する要望:①既習表現と比較しながら説明する。②文型・表現は共通する意味・用法でまとめて効率的に教える。③文型・語彙の硬さ・柔らかさの区別を示す。(4)教室活動に対する要望:短い会話練習,作文,ゲーム要素を取り入れた練習も増やす。
2 0 0 0 OA 石垣島名蔵湾に棲息するホシムシアケボノガイ(新称)(ブンブクヤドリガイ科),日本初記録
- 著者
- 小菅 丈治
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- Venus (Journal of the Malacological Society of Japan) (ISSN:13482955)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1-2, pp.67-70, 2009-09-30 (Released:2016-05-31)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
ブンブクヤドリガイ科アケボノガイ属の一種Barrimysia siphonosomae Morton & Scott, 1989を,石垣島名蔵湾から記録した。本種は,香港の砂泥質の干潟に棲息するスジホシムシモドキSiphonosomacumanenseの巣孔内に棲息することが知られ,石垣島名蔵湾でもサンゴ片などの礫混じりの砂泥干潟に棲息するスジホシムシモドキの巣孔内より見出された。日本からは初めての記録であり,ホシムシの一種の巣孔に棲む習性とアケボノガイ属の一種であることに因んで「ホシムシアケボノガイ」の新和名を提案した。模式産地以外から初めての記録でもあり,香港から琉球列島にかけて分布することが明らかになった。2008年8月に行った名蔵湾での観察結果では,採集したスジホシムシモドキの巣孔の15~17%にホシムシアケボノガイが生息していた。ホシムシアケボノガイは,多くの場合単独で生息していたが,2個体の貝が1つの巣孔から見つかる例も少数観察された。
2 0 0 0 OA 条件表現の推移から見る明治・大正期日本語の動態に関する研究
2 0 0 0 眞誥
- 著者
- 吉川忠夫 麥谷邦夫編
- 出版者
- 臨川書店
- 巻号頁・発行日
- 2021
2 0 0 0 OA トンネル施工における地下水環境保全
- 著者
- 西垣 誠
- 出版者
- 公益社団法人 日本地下水学会
- 雑誌
- 地下水学会誌 (ISSN:09134182)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.283-301, 2020-05-28 (Released:2020-08-21)
- 参考文献数
- 83
トンネルや地中構造物を施工することによって地下水環境に与える影響,また,地下水がトンネル施工時に与える影響について,過去の事例を踏まえながらその対応の歴史を解説した。さらに,トンネル施工が地下水環境へ及ぼす悪影響を防ぐために,これまで開発されてきた新しい施工技術の歴史についても概観した。特に,止水方法,水抜き方法それぞれの様々な施工方法とその難しさ,また現場の状況に応じてどのように使い分けるべきか等の考え方について述べた。
2 0 0 0 ミニフォートランについての討論
- 著者
- 西村 恕彦
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.168-169, 1970-03-15
- 著者
- Sho Masui Atsushi Yonezawa Kenji Momo Shunsaku Nakagawa Kotaro Itohara Satoshi Imai Takayuki Nakagawa Kazuo Matsubara
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.323-332, 2022-03-01 (Released:2022-03-01)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 6
Infliximab (IFX) has contributed to the treatment of several chronic inflammatory diseases, including Crohn’s disease (CD), ulcerative colitis (UC), psoriasis (Pso), and rheumatoid arthritis (RA). However, the loss of response in some patients with long-term IFX therapy has been a major problem. Randomized controlled trials (RCTs) are limited in their short duration and lack of generalizability to the real-world population. We aimed to describe the persistence rates of IFX therapy to estimate its long-term effectiveness in clinical practice. Claims data from the Japan Medical Data Center database from January 2005 to June 2017 were used. The study population was identified based on the International Classification of Diseases, 10th Revision and the Anatomical Therapeutic Chemical Classification System. The 5-year persistence rates of IFX therapy were estimated using the Kaplan–Meier method. Overall, 281, 235, 41, and 222 patients with CD, UC, Pso, and RA, respectively, were selected. The 5-year persistence rates for IFX claims were 62.9, 38.9, 22.1, and 28.1% in patients with CD, UC, Pso, and RA, respectively. Patients with CD and UC administered IFX beyond the median dose had higher persistence rates. In patients with RA, female sex and no prior use of other biologics were associated with longer persistence. In conclusion, IFX persistence rates differed across chronic inflammatory diseases, which did not correspond to the results of the major RCTs. Factors associated with longer IFX persistence were identified in each disease group. Our findings may provide useful information to facilitate the proper use of IFX.
- 著者
- Akihiro Hirayama Kittipong Srivatanakul Hideaki Shigematsu Kazuma Yokota Takatoshi Sorimachi Mitsunori Matsumae
- 出版者
- The Japanese Society for Neuroendovascular Therapy
- 雑誌
- Journal of Neuroendovascular Therapy (ISSN:18824072)
- 巻号頁・発行日
- pp.tn.2020-0192, (Released:2021-03-09)
- 参考文献数
- 8
Objective: We report the utility of microcatheter reshaping by referring to fusion images with 3D-DSA and microcatheter 3D images made using non-subtraction and non-contrast (non-SC) rotational images.Case Presentations: Case 1: The patient was a 74-year-old man who had an internal carotid-anterior choroidal artery bifurcation aneurysm with a tortuous proximal parent artery. The initial attempt to introduce the microcatheter into the aneurysm was unsuccessful. During this unsuccessful microcatheter introduction, we created fusion images with 3D-DSA and microcatheter 3D images by acquiring positional information of the microcatheter using the non-SC method. By reshaping the microcatheter with reference to the fusion images, the direction of the distal end of the microcatheter was reshaped to be in accordance with the long axis of the aneurysm, a shape more suitable for coiling. Case 2: The patient was a 47-year-old man who had an anterior communicating (A-com) artery aneurysm with two daughter sacs. We successfully placed two microcatheters in the direction of each sac to make more stable framing by referring to 3D fusion images after the first microcatheter was positioned. In both cases, microcatheter reshaping was necessary because of the vessel and aneurysm anatomy. We have used this technique successfully in 15 patients, for both ruptured and unruptured aneurysms. The average number of microcatheter reshaping was 1.3 times.Conclusion: This method provides effective microcatheter reshaping for coil embolization of aneurysms, particularly those with differences between the axis of the parent artery and the vertical axis of aneurysm, or with a tortuous proximal artery.
2 0 0 0 IR 「内幕もの」の時代と松本清張『日本の黒い霧』
- 著者
- 尹 芷汐
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.137-149, 2016-03
本論は、1950年代の「内幕もの」との相関性において松本清張のノン・フィクション作品集『日本の黒い霧』を考察したものである。松本清張は当作品集の中で、下山事件や松川事件など、占領期に起きた一連の「怪奇事件」を推理し、それらの事件がすべてGHQの「謀略」に関わっていると説明したが、この「謀略論」は1960年に発表されると大きな反響を呼び、「黒い霧」も流行語となった。実は、『日本の黒い霧』の事件の表象は同時代において決して孤立した存在ではなかった。1950年代、様々な社会的事件の「内側」を知りたいという時代の気運があり、その中で「内幕もの」というジャンルのルポルタージュが総合雑誌、週刊誌の中で急速に増加していった。「内幕もの」は、権力層の「内側」の人間が語り手となり、歴史や政治上の秘密を暴露するのが常套である。しかし、そうした「内幕もの」は、「真実の暴露」に見せかけながら、権力側の世論操作の道具として利用されることも多い。例えば「内幕もの」の第一人者で、GHQの「内部」に潜り込んだジョン・ガンサーは、『マッカーサーの謎』を執筆してGHQの秘密を「暴露」している。しかし、その「暴露」は明らかにGHQとマッカーシズムを讃えるために意図されたものである。 松本清張の『日本の黒い霧』は、直接ガンサーの「内幕もの」に反論しながら、「内側」から発された「秘密」の虚偽性を明らかにした。松本清張は、「内側」に入り込んで新たな秘密情報を探るのではなく、「外側」に立つ「一市民」として新聞報道や既存の資料の読み込みを通して真実を見出そうとする手法で、『日本の黒い霧』を書いた。『日本の黒い霧』は、歴史がいかに「作り物」であるかを教え、「公式的見解」の精読、いわゆる「真実」の不自然さの発見を示唆する書物として読まれるべきである。
2 0 0 0 ヒト・アンジオテンシンの単離と構造決定の秘話
- 著者
- 荒川 規矩男 代田 浩之
- 出版者
- Japan Heart Foundation
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.7, pp.831-841, 2009
荒川規矩男先生は世界で初めてヒトアンジオテンシンの単離に成功し, 構造決定を行いました. その後もヒトアンジオテンシン-II生成バイパス, キニン・テンシン系などを発見されました. また, 活躍の場所を福岡大学に移されると運動療法による降圧効果の研究, 食塩と血圧の研究をされてきました. 国際高血圧学会や高血圧治療ガイドラインにも関わられるなど国際的にも高血圧分野において多大なる功績を残されました.<BR>今回のMeet the Historyは, その荒川規矩男先生をゲストに, 本誌編集委員の代田浩之先生をホストとして, 逆境のなかで研究に邁進された荒川先生の半生をお伺いしました.
- 著者
- 吉留 公太 Yoshitome Kota
- 出版者
- 神奈川大学経営学部
- 雑誌
- 神奈川大学国際経営論集 = Kanagawa University international management review (ISSN:09157611)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.45-85, 2018-03
研究論文
2 0 0 0 OA 計測震度と最大加速度および最大速度に関する一考察
- 著者
- 宮崎 雅徳 尻無濱 昭三 秋吉 卓
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 地震工学研究発表会講演論文集 (ISSN:18848435)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.53-56, 1999 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
1996年に改訂された気象庁震度 (計測震度) と物理量の関係について科学技術庁防災科学研究所の強震ネット (K-NET) の強震記録を用いて検討する。対象とする地震は1996年10月から1998年12月までに九州および周辺地域で観測された159地震、3167記録 (マグニチュードM: 3.2~6.6、震度I:0.0~5.9) を、物理量としては最大加速度および最大速度を用いた。物理量をマグニチュード別に分類して回帰分析を行うことで、中小規模の地震まで適応可能な新たな計測震度と最大加速度および最大速度の関係式を提案した。