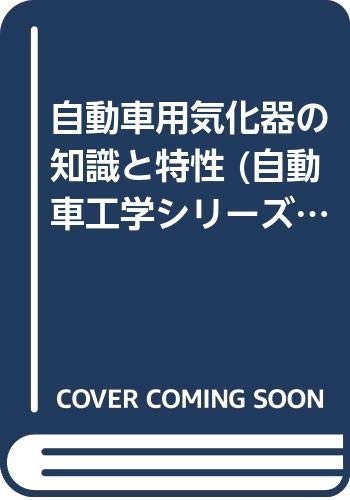2 0 0 0 OA 脊柱の変形を伴う変形性股関節症患者の治療経験
- 著者
- 新井 龍一
- 出版者
- 公益社団法人 埼玉県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法 - 臨床・研究・教育 (ISSN:1880893X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.59-62, 2019 (Released:2019-05-24)
- 参考文献数
- 14
脊柱の変形を伴う右変形性股関節症患者を担当する機会を得た。股関節に対する理学療法を3週間行ったが,歩行時の疼痛がNumerical Rating Scale(以下NRS)4と残存し難渋した。治療内容を再考してシュロス法の治療概念を用いた脊柱に対する理学療法を行い,歩行時の体幹動揺を制御させた結果,12週目で腰椎のコブ角が4°改善した。歩行時の動揺も減少し,14週にはNRS 0へ減少した。脊柱の変形を伴う股関節症患者において,脊柱のアライメントを修正することが股関節の負担軽減に繋がり,さらなる疼痛軽減に効果があることが示唆された。
2 0 0 0 薬師寺文書目録
- 著者
- 奈良文化財研究所 東京大学史料編纂所編
- 出版者
- 東京大学史料編纂所
- 巻号頁・発行日
- 2019
2 0 0 0 意味的関係を利用したSNS上のエンティティの人気度予測
- 著者
- 大澤 昇平 松尾 豊
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.5, pp.469-482, 2014
- 被引用文献数
- 1
In social networking service (SNS), popularity of an entity (e.g., person, company and place) roles an important criterion for people and organizations, and several studies pose to predict the popularity. Although recent papers which addressing the problem of predicting popularity use the attributes of entity itself, typically, the popularity of entities depends on the attributes of other semantically related entities. Hence, we take an approach exploiting the background semantic structure of the entities. Usually, many factors affect a person's popularity: the occupation, the parents, the birthplace, etc. All affect popularity. Predicting the popularity with the semantic structure is almost equivalent to solving the question: What type of relation most affects user preferences for an entity on a social medium? Our proposed method for popularity prediction is presented herein for predicting popularity, on a social medium of a given entity as a function of information of semantically related entities using DBpedia as a data source. DBpedia is a large semantic network produced by the semantic web community. The method has two techniques: (1) integrating accounts on SNS and DBpedia and (2) feature generation based on relations among entities. This is the first paper to propose an analysis method for SNS using semantic network.
2 0 0 0 OA 漢方薬の関与が考えられた薬剤性膀胱炎の2例
- 著者
- 林 麻子 早坂 格 鈴木 秀久 小林 徳雄 佐々木 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児腎臓病学会
- 雑誌
- 日本小児腎臓病学会雑誌 (ISSN:09152245)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.82-87, 2013-04-15 (Released:2013-10-15)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
漢方薬の関与が考えられた薬剤性膀胱炎の2例を経験した。症例1は6歳女児。原因不明の肉眼的血尿と頻尿にて当科受診,検尿にて高度蛋白尿が認められた。MRIを含む画像検査にて一部隆起性の膀胱壁肥厚,粘膜肥厚がみられ腫瘍性病変との鑑別を要した。症例2は11歳女児で,2か月間続く血尿と蛋白尿,無菌性膿尿のため当科紹介受診となった。超音波検査にて膀胱壁肥厚を認めた。症例1は柴胡加竜骨牡蠣湯エキスを約3年前から,症例2は温清飲を約1年前から内服しており,両者とも薬剤中止により膀胱炎症状が徐々に改善し,画像検査所見も正常化した。薬剤性膀胱炎は多彩な臨床症状を呈し得る疾患であり,時に画像検査上,腫瘍病変と類似した膀胱の形態異常を示すことがあり,その診断,治療に際して十分に留意すべきであると思われた。
2 0 0 0 OA 異類婚姻譚の「異類の妻」と「異類の夫」
- 著者
- 難波 美和子
- 出版者
- 筑波大学比較・理論文学会
- 雑誌
- 文学研究論集 (ISSN:09158944)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.117-129, 1993-03-01
2 0 0 0 OA 内的報酬と敵対的学習によるタスク非依存な注意機構の学習
- 著者
- 松嶋 達也 大澤 昇平 松尾 豊
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第32回全国大会(2018)
- 巻号頁・発行日
- pp.3A101, 2018 (Released:2018-07-30)
近年,人工知能の活用による社会の生産性向上への期待が高まっている.この期待の背景として,深層学習が人工知能技術のブレイクスルーになったことが挙げられる.しかし,実世界環境で活用可能な人工知能の構築には,いくつかの課題が残されている.特に,観測が部分的であること,タスクに対する報酬の設計が難しいことの2 点が挙げられる. 部分的な観測を扱うニューラルネットワークのモデルとして,注意機構を持つモデルが提案されている.しかし,これらのモデルでは,注意機構の学習がタスクから定義される外的な報酬信号を用いた強化学習によって行われており,外部からの報酬信号が得られない問題設定下では注意機構の学習を行うことができない. 本研究では,注意機構の学習に外的な報酬を用いる代わりに,観測に対する予測の誤差を注意機構の内的な報酬として与え,観測の予測モデルと注意機構を敵対的な学習により訓練する手法を提案する.
2 0 0 0 OA OSSコミュニティおよびクラウドソーシングの統合によるソフトウェア開発者の評価値予測
- 著者
- 大澤 昇平 松尾 豊
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.A-F24_1-10, 2016-03-01 (Released:2016-02-18)
- 参考文献数
- 22
Success of software developping project depend on skills of developers in the teams, however, predicting such skills is not a obvious problem. In crowd sourcing services, such level of the skills is rated by the users. This paper aims to predict the rating by integrating open source software (OSS) communities and crowd soursing services. We show that the problem is reduced into the feature construction problem from OSS communities and proposes the s-index, which abstract the level of skills of the developers based on the developed projects. Specifically, we inetgrate oDesk (a crowd sourcing service) and GitHub (an OSS community), and construct prediction model by using the ratings from oDesk as a training data. The experimental result shows that our method outperforms the models without s-index for the aspect of nDCG.
2 0 0 0 自動車用気化器の知識と特性
- 著者
- 魚住順蔵 [ほか] 著
- 出版者
- 山海堂
- 巻号頁・発行日
- 1984
2 0 0 0 OA 短時間高光強度照射下におけるサラダナの生育と生理的特性
- 著者
- 石井 雅久 伊東 正 丸尾 達 鈴木 皓三 松尾 幸蔵
- 出版者
- Japanese Society of Agricultural, Biological and Environmental Engineers and Scientists
- 雑誌
- 生物環境調節 (ISSN:05824087)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.103-111, 1995-06-30 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
完全制御型植物工場の電力コストを削減させるために, 一般電力と比べて割安な深夜電力 (11pm~7am) の利用について, 『岡山サラダナ』を供試し, 光強度と照射時間の関係から調査・検討を行った.生育中期までは, PPFDならびに照射時間の増加とともに葉の生体重および乾物重は増加したが, 後期から腋芽葉の発生や葉捲きが多く発生し, サラダナの生育は遅延し, 生産物の品質は低下した.また, 1回の明期に照射する光量子の積算値が等しければ, サラダナの生育や品質も同様になると推察された.以上のことから, 本試験の照射条件のなかでは, PPFDが400~420μmol・m-2・s-1, 照射時間が8時間で生育したサラダナが生育や品質などの面から効率的であることがわかり, 深夜電力の利用による栽培の実用的可能性が示唆された.
2 0 0 0 OA システム制御研究者のためのPython入門
- 著者
- 星 義克 米元 謙介
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.10, pp.412-415, 2017-10-15 (Released:2018-04-15)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA 集合住宅における最新のインターネット動向
- 著者
- 亀崎 満
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.6, pp.377-380, 2015-06-10 (Released:2015-06-10)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA <特集 現代トルコ文学の魅力 : その眺望と知られざる側面>現代トルコ文学概要
- 著者
- 勝田 茂
- 出版者
- 京都大学イスラーム地域研究センター
- 雑誌
- イスラーム世界研究 : Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies (ISSN:18818323)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.145-151, 2013-03
- 著者
- Masafumi AKISAKA Hidemoto ZAKOUJI Makoto ARIIZUMI
- 出版者
- The Japanese Society for Hygiene
- 雑誌
- Nippon Eiseigaku Zasshi (Japanese Journal of Hygiene) (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.481-489, 1997-07-15 (Released:2009-04-21)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 5 4
To obtain basic data on the bone density of high school girls, the bone density of the right heel was measured in principle and their lifestyles were surveyed. The subjects were 142 girls (15-18years, mean±SD=16.5±0.8years old) of a high school in Nagano Prefecture, who accepted our visiting bone health check. Bone density was measured with an' Achilles' ultrasound bone-densitometer (Lunar Co.) and a self-registered questionnaire on their lifestyles was also employed in this study.The main results were as follows:1. There were no significant correlations between Sitffness and, age, grede, bone fracture, family historiy, and regularity of menstruation. However, Stiffness significantly correlated to the age of menophania (r=-0.191, p=0.002)2. High school girls who belonged to a sports club had significantly higher bone density than other girls. Those who did exercises which consist mainly of jumping, had significantly higher bone density than others who participated in running sports or did no exercise. There were also significant differences in the frequency of exercise and the duration of exercise. Mireover, those who had a regular exercise history had higher bone density than those who had no regular exercise histry, and the mean Siffness of the group that did exercises daily was higher than for those who did not.3. There were no significant correlations between Stiffness and food intakes. There also were no significant diffrence for Stiffness concerning intake of calcium-containing food groups. Regarding the cause of weight loss of more than 2kg/month, the mean Stiffness of the group with intense exercise was significantly higher than those in the no-weigh loss group and the group that had reduced dietary intake.4. Regarding the relationships between bone density and the lifestyles of high school girls, a delayed age of menophania had a significantly decreasing effect on Stiffness, whereas three variables of regular exercise habits at present, body weight, and exercise histories had significantly increasing effects on Stiffness in multiple regression analysis.5. It is considered that there may be other important factors in the relationship between bone density and lifestyle of adolescent females who are in a developmental state. Therefore, the measurement of bone density and its assessment need consideration from points of view which are different from those for middle-aged and the elderly people.
- 著者
- 石神 圭子
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.21-40, 2004-01
2 0 0 0 IR 日本語の所有者受動文と大主語構文について
- 著者
- 杉本 武
- 出版者
- 筑波大学文藝・言語学系
- 雑誌
- 文芸言語研究 言語篇 (ISSN:03877515)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.1-12, 2000
日本語の受動文には、次のa.のような、「所有者受動文」などと呼ばれる受動文のタイプが存在する。 (1) a. 太郎は暴漢に頭を殴られた。 b. 暴漢が太郎の頭を殴った。 (2) a. 太郎は先生に息子をほめられた。 b. 先生が太郎の息子をほめた。 これらの受動文は、見かけ上、b.のような文の目的語を修飾する名詞句が主語になっている。 ...
2 0 0 0 OA 紀元2600年勅語奉読(一)
- 著者
- 近衛 文麿
- 出版者
- コロムビア(NHK)
2 0 0 0 IR 内閣官房、内閣府の拡大と議員立法の役割
- 著者
- 宮﨑 一徳
- 出版者
- 法政大学公共政策研究科『公共政策志林』編集委員会
- 雑誌
- 公共政策志林 = Public policy and social governance (ISSN:21875790)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.59-74, 2016-03
2015(平成27)年、第189 回通常国会において、「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案」(以下、「内閣機能強化法案」と言う。)が閣法第54 号として提出され、審議が行われた。中央省庁改革から十数年で、法による見直しを必要とするほど内閣官房及び内閣府に重要な政策課題が集中し問題が生じていたのである。本稿では、どれだけ内閣官房と内閣府が拡大して来たかを、特に第2 次安倍内閣以降、内閣はどのように内閣官房、内閣府を使っているのかということと、議員立法がどう関係しているのかということに焦点を当てて分かり易く図、表を使って示す。そこには安倍内閣が内閣官房、内閣府の拡大を伴う積極的な取組みを行っている様子とともに、「○○基本法」と称する等(以下「基本法等」という。)の議員立法が大きく関わっているという実態が浮かび上がって来る。特に議員立法に関しては、内閣機能強化法案の審査を通じて、政府からもその関わりについて明確な認識が示されることとなった。官庁の垣根を超えた問題に基本法等で担っていく役割が非常に大きくなっていることが、法案審査に関わった多くの議員、政府の職員、国会のスタッフ等にも認知されたと考える。一方、内閣機能強化法案の審査は、今後の内閣官房、内閣府の拡大への対策のスキームも示すこととなった。基本法等のあり方にも、期限設定等の点で影響を与える。しかし、官庁の垣根を超えた問題の解決の必要性自体を減ずるものではないため、当面の間、大きな変化は生じないのではないかと考える。
- 著者
- 小坂 淳子
- 出版者
- 大阪健康福祉短期大学
- 雑誌
- 創発 : 大阪健康福祉短期大学紀要 = Starting anew : annual bulletin of Osaka Junior College of Social Health and Welfare (ISSN:13481576)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.15-29, 2019-03