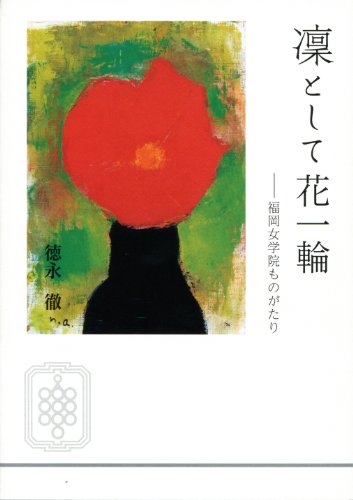- 著者
- 中前 正志
- 出版者
- 京都女子大学国文学会
- 雑誌
- 女子大国文 (ISSN:02859823)
- 巻号頁・発行日
- no.159, pp.1-99, 2016-09
2 0 0 0 OA 「一致」というテーマに関する最適の書
- 著者
- 田中 秀男
- 出版者
- 日本人間性心理学会
- 雑誌
- 人間性心理学研究 (ISSN:02894904)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.145-149, 2017-03-31
[特集]ロジャーズの中核三条件を読む
2 0 0 0 OA 「80年代」というフィクション : 美術史の合間を思考するための「起点」
- 著者
- 霜山 博也 SHIMOYAMA Hiroya
- 出版者
- 名古屋大学大学院人文学研究科附属超域文化社会センター
- 雑誌
- JunCture : 超域的日本文化研究 (ISSN:18844766)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.214-216, 2019-03-25
2 0 0 0 OA 新規開業店舗からみた伊那市中心市街地における 商業機能の変容
- 著者
- 小室 譲 有村 友秀 白 奕佳 平内 雄真 武 越 堤 純 加藤 ゆかり
- 出版者
- Association of Human and Regional Geography, University of Tsukuba
- 雑誌
- 地域研究年報 = Annals of Human and Regional Geography (ISSN:18800254)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.53-71, 2019-02
本稿の目的は,長野県伊那市を事例に2000年代以降の新規店による提供商品・サービス,および顧客変化に着目することで,中心市街地における商業機能の変容を検討することである.伊那市中心市街地では,低廉なテナント料,移住や創業を支援する行政施策が奏功して,①カフェやダイニングバーなどの新たな業態の飲食店,②オーガニック商品やデザイン性の高い服飾雑貨などの物販店,③ピアノ教室や陶芸教室などの教育関連施設やベビーマッサージ店,ライブハウス,ご当地アイドルのイベント事業会社など多岐に渡るサービス店が開業した.それらの店舗経営はIJUターン者が担い,経営者の開業以前の就学・就業経験に裏打ちされた周到な開業計画や高い経営意欲のもと,新たな商品・サービスを提供している.その結果,飲食店や小売店を中心に新たな顧客の掘り起こしと県外におよぶ商圏を獲得する店舗事例が存在するなど,中心市街地における商業機能の向上に寄与しつつある.
2 0 0 0 OA 低線量放射線の健康影響
- 著者
- 米虫 節夫
- 出版者
- 一般社団法人 GPI標準化委員会
- 雑誌
- GPI Journal (ISSN:21893373)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.14, 2016 (Released:2019-01-31)
広島・長崎に対する原爆投下、ビキニ環礁における水爆実験による第五福竜丸事件、さらに東京電力福島原子力発電所の事故と4回も放射線の洗礼を受けた日本においては、国民の多くが強い放射線アレルギーを持っている。一方、火山に恵まれた日本の特性として温泉が各地に噴出し、温泉場における長期療養,特にラジウム温泉の効果は古くから認められている。 東京電力の事故以来、食品の放射線汚染が大きく取りざたされ、低線量の内部被曝が問題とされている。しかしながら、低線量の被曝については、まだ定まった定説がなく、いくつかの異なった説明がなされている。 その様な現状を概観し、低線量放射線の健康影響についての理論を見直すと共に、ラドン温泉である三朝温泉における最新の研究成果を紹介する。 最後に, これらを科学的にとけない不確実性問題・トランスサイエンスとして捉えることの大事さを提案する。
2 0 0 0 OA 日本人の原子力・放射線観に関する調査研究
- 著者
- 辻 さつき 神田 玲子
- 出版者
- 一般社団法人日本リスク学会
- 雑誌
- 日本リスク研究学会誌 (ISSN:09155465)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.2_33-2_45, 2008 (Released:2012-08-22)
- 参考文献数
- 15
Risk assessment of technologies and social activities involves subjective judgment as one of its components, which depends on the perception of risk by individuals. In the present study, we undertook a survey of public perceptions regarding the social issues and risks, the images of radiation, and acceptance of its application and health risk.The majority identified global warming as highly risky among social issues related to technology, and smoking among health-damaging issues, but not radiation-related items such as natural radiation, artificial radiation, and X-ray/CT examinations. In general, a sexual distinction was observed regarding perceptions of sick house and food safety. Forty percent of the public inaccurately believed that the main source of daily exposure was nuclear facilities. Many citizens associated the word of radiation with medical exposure, death/damage/disease and nuclear weapon including A.bomb, and connected the health effects of radiation with cancer and leukemia. However, majority did not bring up any image from the terms of “radiation” and “health effects of radiation”
2 0 0 0 OA ザーヤンデルードの用水配分に関する一考察
- 著者
- 岡崎 正孝
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = The Toyo Gakuho (ISSN:03869067)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3・4, pp.307-335, 1988-03
The waters of the Zāyandeh-rūd in Esfahān had traditionally been distributed among some 500 villages of seven irrigation districts through 105 madis, or main irrigation channels. In the Safavid period, however, a Royal order was proclaimed to abolish the customary water distribution systems and replace them with new regulations. Under the Qājārs, the regulation was altered by certain powerful individuals.The new regulation of the Safavids, known to be drawn up by Sheikh Bahā’ī of Amilī, a distinguished scholar at the court of Shāh ʻAbbās, was intended to gain a monopoly over the river’s summer irrigation water for the rice cultivation in four districts, in which the Crown lands were concentrated. Naturally, this caused the devastation of three other districts when their water supply was stopped.Furthermore, under the Qājār, with the rapid development of the reclamation of lands, the Safavid’s regulation was arbitrarily altered by such influential personages as the Crown Prince Zill al-Soltān, leading mojtaheds and large landlords at the ruinous, selfish sacrifice of the weak.This paper aims to illustrate one of the characteristic features of the land holding system of Iran through examining how irrigation water had been controlled by men of power.
- 著者
- 山梨 淳
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.179-217, 2010-03-31
本論は、一九三一年に公開された無声映画『殉教血史 日本二十六聖人』(日活太秦撮影所、池田富安監督)を取り上げ、一九三〇年代前半期日本カトリック教会の一動向を明らかにすることを目的としている。この映画作品は、十六世紀末、豊臣秀吉の命で、長崎で処刑された外国人神父や日本人信者ら二十六人の殉教者をめぐるものである。長崎出身のカトリック信者で、朝鮮在住の資産家であった平山政十が、この映画の製作を企画し、彼の資金出資のもとに制作された。作品は日本で一般公開されたのち、平山個人によって北米と西欧諸国に、海外興行が試みられている。
2 0 0 0 OA 満洲を見せる博覧会
- 著者
- 山路 勝彦
- 出版者
- 関西学院大学
- 雑誌
- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.43-67, 2006-10
In its efforts to appeal the success of Japanese colonial policies, the Empire of Manchuria joined in various kinds of expositions held in Japan since the Taisho period. The main purpose of joining in these expositions was to display the rich mining and agricultural resources of Manchuria. Under colonial rule by the Japanese militarists, Manchuria was a country situated as a provider of natural resources for Japan. Manchuria had another opportunity to represent itself by showing a different culture from that of the Japanese. When the Chicago world exposition titled "a century of progress" was held in 1933, Manchuria joined in this fair to declare itself as an independent country, displaying its historical and cultural heritage as different from the Chinese and Japanese. In 1934, a unique exposition was held in Dalian (Dairen in Japanese) of Manchuria. In this exposition, not only mining resources but also native folk customs, such as shamanism of the Mongols, Orochen, or Koreans, were displayed as a part of Manchurian culture. Thus, Manchuria showed complicated features in each exposition.
- 著者
- 田口 善弘
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本分子生物学会
- 雑誌
- 第42回日本分子生物学会年会
- 巻号頁・発行日
- 2019-11-08
2 0 0 0 アサと麻と大麻:有用植物から危険ドラッグまで
- 著者
- 船山 信次
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.9, pp.827-831, 2016
アサは古くから人類によって利用され、その繊維は一般に麻と書く。一方、単に麻というと種々の繊維が採れる異なる植物の総称であることから、アサを大麻と称することがある。大麻というと、「大麻取締法」で規制されているドラッグのイメージがあるが、大麻という言葉には本来悪い意味はない。<br>ここではアサの来歴から、アサが大麻取締法にて規制されようになったいきさつ、そして、大麻吸引から派生した危険ドラッグの誕生とその正体について述べる。
2 0 0 0 調理と水道水残留塩素の関係について
(1)残留塩素測定法を検討した結果,o-トリジンで呈色させた後その吸光度を分光光電光度計で測定し,あらかじめ作成しておいた残留塩素標準曲線により残留塩素量を求める方法を考案し,従来の測定法よりも迅速に,かつ正確に測定できることがわかった。(2)残留塩素の時刻的分布をみると1日の中で水道水を比較的多く使用する昼前から午後にかけて多くなっている。反対に朝水道水を出しはじめた直後はほとんど残留塩素は存在せず,それから1~2時間は非常に低い値となっている。(3)水道水を放置,攪拌するだけで残留塩素は減少していく。攪拌の場合その減少の仕方は攪拌しはじめた時急激に減少し,ある程度減少するとそれ以後は攪拌に時間をかけてもあまり変化がない。(4)調味料を添加した場合の残留塩素の減少は食塩の場合はかなり大である。蔗糖の場合は蔗糖濃度が高くなるほど減少の割合は大となる。酢酸添加の場合はあまり減少しない。また酢酸濃度を高くしてもその減少に変りはなかった。このことから食酢を用いる調理には残留塩素の残存はかなりあることが予想される。終りにのぞみ本実験に際し,御丁重なる御教示をいただきました大阪市水道局水質試験所,近藤正義,八木正一の両氏に深甚なる謝意を表する次第である。なお,本報告は昭和41年10月,日本家政学会関西支部総会にて口述発表したものである。
2 0 0 0 OA 詩人のFelt Meaning : 荒川修作、マドリン・ギンズの遺稿研究にむけて
- 著者
- 三村 尚彦
- 出版者
- 関西大学東西学術研究所
- 雑誌
- 関西大学東西学術研究所紀要 (ISSN:02878151)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.A79-A100, 2018-04-01
Shusaku Arakawa (1936-2010) - a modern artist - and Madeline Gins (1942-2014) - a poet - interacted with numerous scientists, thinkers and philosophers, attempting to integrate science and philosophy into art. Among such scientists was Eugene Gendlin (1926-2017), a world-renowned advocate for focusing-oriented psychotherapy. Although it was known that Gendlin was writing a paper on Arakawa and Gins, until recently little was understood about what kind of interests Arakawa and Gins had in the Gendlin philosophy. In 2017, I examined manuscripts by Arakawa and Gins, which revealed that Eugene Gendlin had close academic relationships with Arakawa and Gins. Arakawa and Gins were interested in the function of blanks in poetry studied by Gendlin and David Kolb; Arakawa and Gins made notes on this, to which I succeeded in gaining access. This article focuses mainly on the arguments between Gendlin and Kolb, discussing the function of blanks in poetry and expanding on descriptions of the reasons for their different views on it. My purpose is to further advance the study of manuscripts by Arakawa and Gins. Kolb believes that the two categories of 1) symbols and 2) blanks represent felt meaning, and that they are independent discrete concepts that interact with each other, whereas Gendlin believes that these two categories are presented a priori, and that they do not interact with each other or provide support as discrete entities.
- 著者
- 福井 次郎
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D2(土木史)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.28-41, 2017
大正後期から昭和前期に多数の橋梁を設計した増田淳は,個人ではなく設計事務所で設計業務を行っていた.しかし,この設計事務所の組織体制や,増田が全ての橋の設計の中心的立場であったかどうか等は不明であった.今回,旧独立行政法人土木研究所で発見された設計計算書,設計図に記入されている担当者のサイン,日付を分析し,設計事務所の組織体制,活動状況等を調査した.調査の結果,設計事務所の技術スタッフは約10名で,各職員の氏名や担当した構造物等が明らかとなった.その中で,稲葉健三は増田に劣らない設計技術を有しており,稲葉が設計事務所の中心的立場であったこと等が明らかとなった.
2 0 0 0 IR 戦後の小牧実繁とその地政学観
- 著者
- 柴田 陽一
- 出版者
- 摂南大学外国語学部「摂大人文科学」編集委員会
- 雑誌
- 摂大人文科学 = The Setsudai review of humanities and social sciences (ISSN:13419315)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.71-94, 2019-01
2 0 0 0 凛として花一輪 : 福岡女学院ものがたり
2 0 0 0 OA 『ショレの赤いハンカチ』由来考(1) (濱川祥枝教授退職記念号)
2 0 0 0 OA <論文>「文化集団」の回想
- 著者
- 本多 秋五
- 雑誌
- 日本文學誌要 (ISSN:02877872)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.5-10, 1987-03-03
2 0 0 0 OA 平安時代阿弥陀堂の堂内荘厳とその系譜
- 著者
- 清水 擴
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文報告集 (ISSN:09108017)
- 巻号頁・発行日
- vol.389, pp.136-142, 1988-07-30 (Released:2017-12-25)
The purpose of this paper is to make clear the genealogy of the interior decoration of "Amidado" in Heian era. The conclusions are as follows. (1) The sourse of the interior decoration of "Amidado" exists in halls of Hojoji temple. (2) The method of interior decoration was completed in Hoodo, and the other "Amidado" took Hoodo for a model. (3) "Kuhon-ojo-zu" and "Gokuraku-jodo-zu" were the main themes of the interior painting, and several "Hiten", sculpture or painting, were arranged of the upper walls. (4) The first example of the use of "Raden" (mother-of-pearl-work) existed in "Amidado" of Hojoji, and of "Makie" (lacquer) in Tohokuin of Hojoji. (5) Introduction of the painting of "Ryokai-mandara" on the columns is due to belief in "Komyo shingon".
2 0 0 0 OA 日本人IBD患者における骨塩量減少に関わる臨床的背景と遺伝的背景の同定
- 著者
- 横山 直信
- 出版者
- Tohoku University
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-27
課程