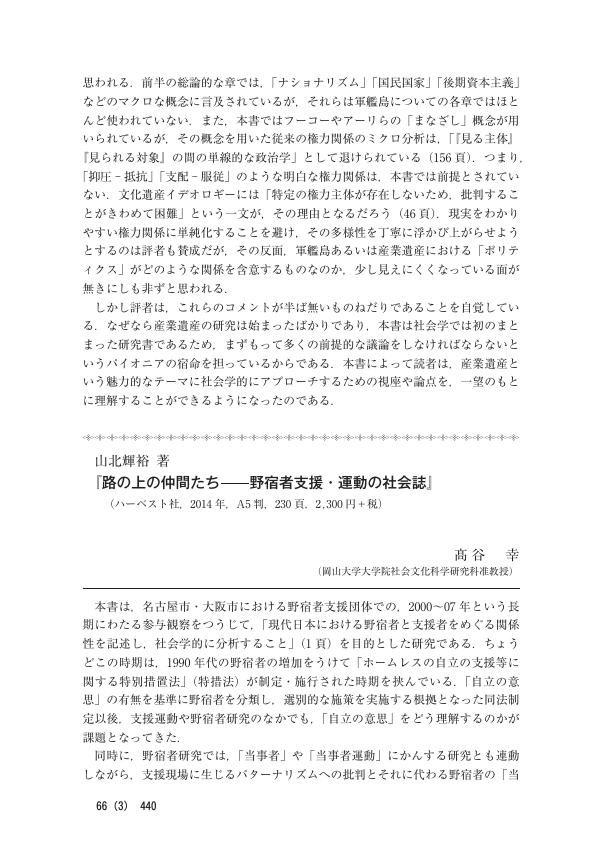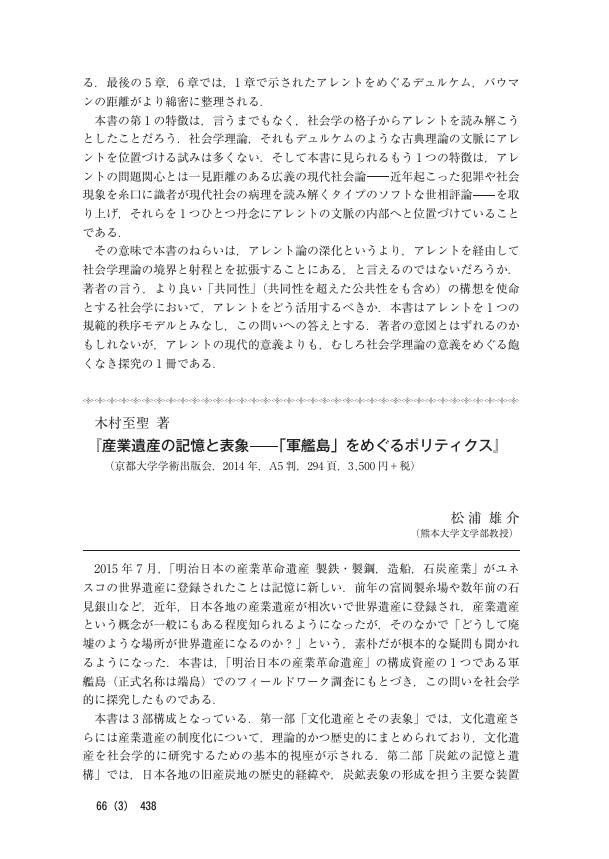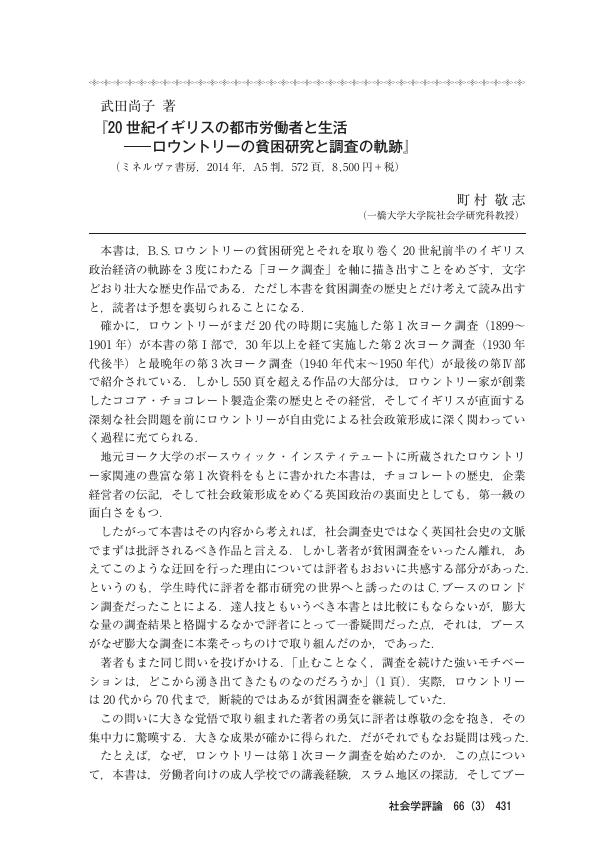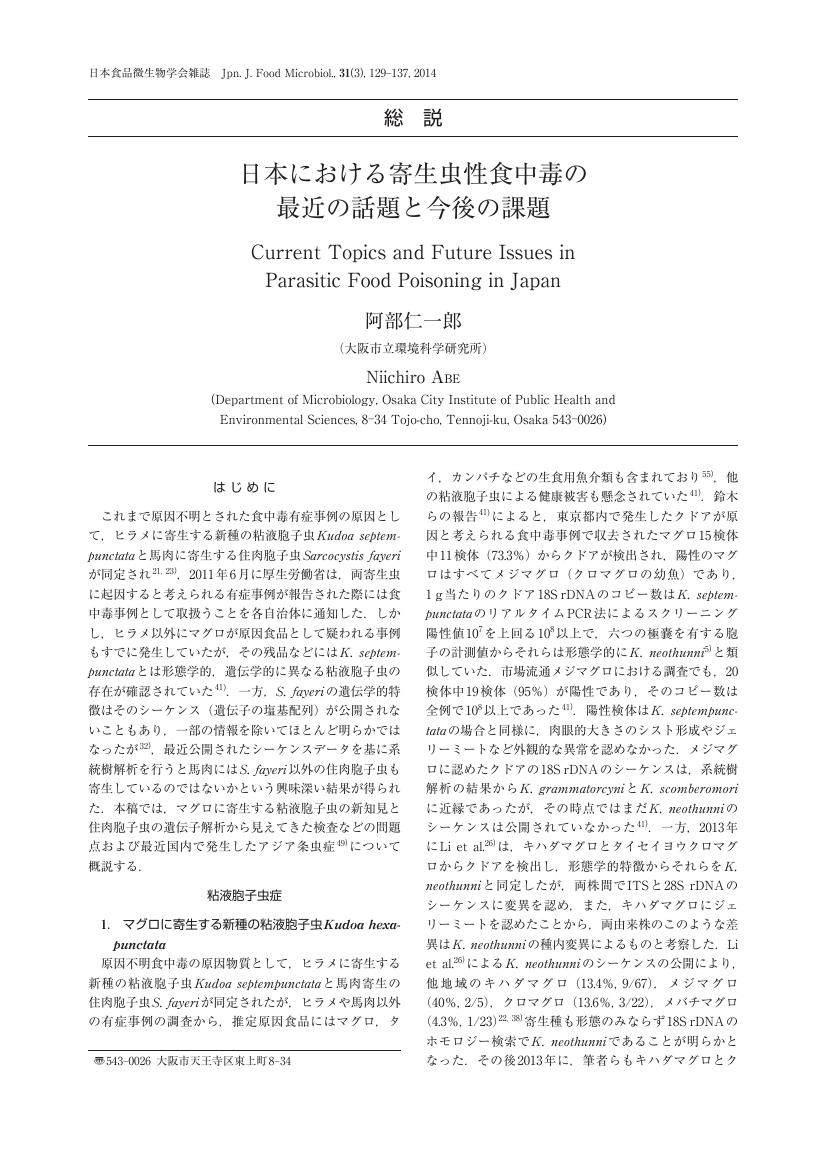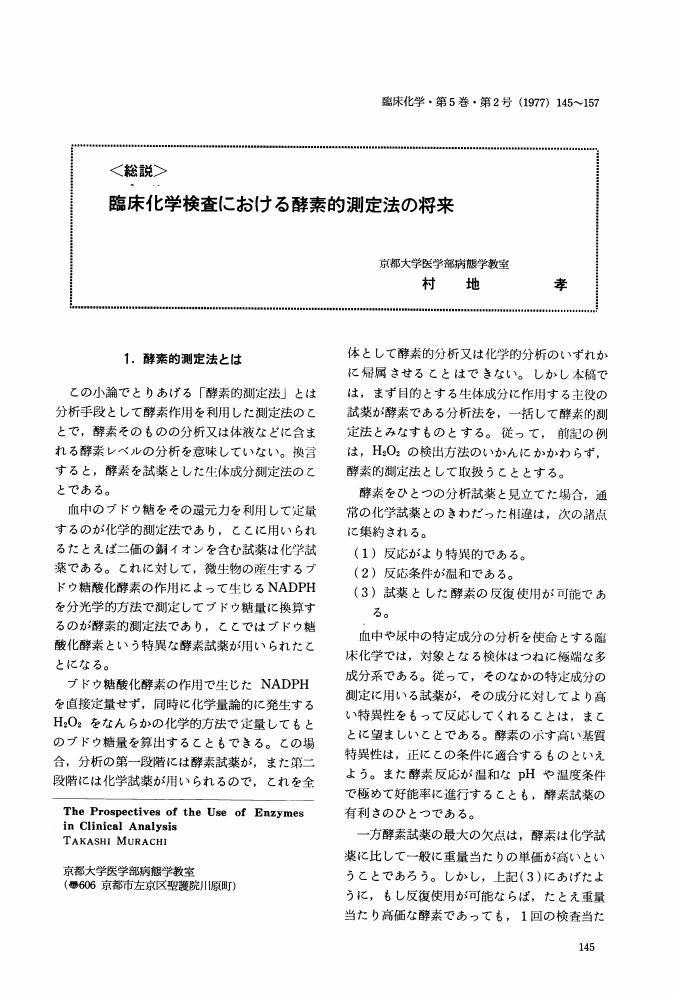1 0 0 0 OA β-展開のエルゴード的性質
- 著者
- 塩川 宇賢
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.45-47, 1971-02-15 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 1992年5月4日白馬大雪渓の大雪崩について
- 著者
- 寺田 秀樹 藤澤 和範 大浦 二朗 小川 紀一朗 臼杵 伸浩
- 出版者
- The Japanese Society of Snow and Ice
- 雑誌
- 雪氷 (ISSN:03731006)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.183-189, 1993-09-30 (Released:2009-08-07)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 磁性エラストマを用いた軸箱支持装置の基礎検討
- 著者
- 梅原 康宏 鴨下 庄吾 小黒 翼 三俣 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.847, pp.16-00523-16-00523, 2017 (Released:2017-03-25)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2
We have devised a steering system in which the magnetic elastomer is used for the elastic members such as rubber bushings in the axle box suspension of railway vehicles. The magnetic elastomer is composed of magnetic particles and the elastomer such as synthetic rubber. This material is characterized by its hardness variation depending on the magnetic field. The axle box suspension using the magnetic elastomer is capable of varying the longitudinal stiffness. In straight sections, the application of this axle box suspension ensures running stability by increasing the longitudinal stiffness by means of applying a magnetic field. On the other hand, in curve sections, it improves curving performance by decreasing the longitudinal stiffness by means of turning off the magnetic field. We made test pieces towards the development of the magnetic elastomer for the steering bogie. In a characteristic test, we confirmed that the Young's modulus of the magnetic elastomer changes in the range of about five times depending on the presence or absence of the magnetic field. In addition, we simulated the vehicle model by applying the longitudinal stiffness change of the magnetic elastomer to the axle box of the bogie. We confirmed that this axle box was capable of reducing the average of the outer wheel lateral force in the circular curve section compared to that of the normal axle box.
1 0 0 0 OA しじみ貝の良否選別装置開発に関する研究
- 著者
- 亀谷 均 内村 和弘 樋野 貴規 山根 勁
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.847, pp.16-00493-16-00493, 2017 (Released:2017-03-25)
- 参考文献数
- 8
In general, manual sorting carries out for the quality inspection of corbicula shells prior to shipment. The inspection worker drops each corbicula shells on the concrete floor, and a shell is assessed as good or bad by the sound of collision with floor. The corbicula shell containing mud or nothing is specified as a bad corbicula. This manual sorting process is time consuming and laborious. In addition, this process is often prone to mistakes. In order to overcome the problem of manual sorting, an inspection probe has been developed. The inspection probe assesses a corbicula shell as good or bad by detecting the transmitted light spectra, and it has been tested that the probe can detect good and bad corbicula shells with an accuracy of 100%. Thereafter, a quality sorting device with the inspection probe has been developed for the commercial use. A laboratory based experiments have been conducted first to evaluate the performance of developed quality sorting device. The test results showed that the sorting device can sort shells with an accuracy of about 99%. Subsequently, a comprehensive evaluation experiment have also been carried out, and the experimental results showed that our developed sorting device is able to sort corbicula shells with an accuracy of 98.6%. This results implies that the present quality sorting device is ready to use for commercial sorting of corbicula shells
1 0 0 0 OA 山北輝裕著『路の上の仲間たち――野宿者支援・運動の社会誌』
- 著者
- 髙谷 幸
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.440-442, 2015 (Released:2017-03-08)
1 0 0 0 OA 木村至聖著『産業遺産の記憶と表象――「軍艦島」をめぐるポリティクス』
- 著者
- 松浦 雄介
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.438-440, 2015 (Released:2017-03-08)
1 0 0 0 OA 武田尚子著『20世紀イギリスの都市労働者と生活――ロウントリーの貧困研究と調査の軌跡』
- 著者
- 町村 敬志
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.431-432, 2015 (Released:2017-03-08)
1 0 0 0 OA 私的所有地のレクリエーション利用をめぐる作法
- 著者
- 北島 義和
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.395-411, 2015 (Released:2017-03-08)
- 参考文献数
- 29
農村アクセス問題とは, レクリエーション活動のため農村地域の土地を利用する人々と, その土地の法的所有者 (おもに農民) の間の対立である. この問題をめぐって生じる, アクセスの地点ごとに対話やシステムが成立したりしなかったりする一方, 問題における不正義を明白に指摘することも難しいという事態は, 複数の主体による自然資源管理をめぐる先行研究の枠内には必ずしも収まりきらない. 本稿は, 農村アクセス問題の深刻化したアイルランドにおける山歩きを事例として, そのような状況下でのレクリエーション利用者の対処のありようを, その活動の多地点性を踏まえたかたちで分析する.現在アイルランドの2つのウォーカーの全国団体は, それぞれ正義と対話の観点から農村アクセス問題を捉え, 互いに対立している. 他方で, 実際にアクセスに問題を抱えた現場で活動する登山クラブへの調査からは, 彼らが「農民との良好な関係」という論理を用いつつ, あるべき姿の山歩きという理想を重視する観点からアクセスに対処していることが判明した. そのような実践は, 農民とできるだけ共存しつつこれまでどおりのレクリエーションをおこなっていくための作法として現場で機能しており, レクリエーションの論理それ自体に他者との共存を可能にするような志向性が内在していることを示している. また, この結論は人々の日常的実践がもつ深みに注視することの重要性を我々に教えている.
1 0 0 0 OA 君主のスペクタクルの知覚様式
- 著者
- 右田 裕規
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.379-394, 2015 (Released:2017-03-08)
- 参考文献数
- 61
近代君主制国家の人びとは, 産業資本制と結びつきスペクタクル化した君主の祝祭をどのように眺め欲望していたか. またその視的経験は, かれらのナショナル・アイデンティティ形成とどのようにかかわりあっていたか. 本稿では, 20世紀初期の日本社会を事例にしつつ, この問いについて社会学的に応答することが目指される. つまり君主の祝祭のスペクタクル化という史的事態がネイション編成とどう関連しあっていたのかが, 同時代人たちの視覚経験から再考される.あきらかにされるのは次の2点である. 第1に, 君主のスペクタクルの見物者たちを特徴づけたのは, 祝祭の景観を刹那的かつ量的に眺め欲望する知覚様式であったこと. 第2に, 資本制に照応したこの知覚様式の拡がりから, 君主のスペクタクルを構成する表象群の ‹国民的› な意味作用が失効する事態が生成されていたことである. 本稿では, この2点をつまびらかにすることで, 君主の祝祭をスペクタクル化する経済主体の運動が君主制ナショナリズム編成に対して含んだ反作用的な契機と機制が呈示される.
1 0 0 0 OA 情報化時代における若者ムスリムの社会統合
- 著者
- 安達 智史
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.346-363, 2015 (Released:2017-03-08)
- 参考文献数
- 21
社会学において「知識」は, 人びとに特有のリアリティを与える社会的フレームを意味し, 宗教はその1つとして考えられている. 従来, 社会の中心的な「知識」は, 宗教的/政治的エリートにより生産され, 人びとの認識や社会関係に大きな影響を与えてきた. だが, 「情報化」のもと, 宗教的知識をめぐる環境は大きな変化の中にある. 情報化の進展は, 人びとが既存の権威から自由に宗教的知識を獲得し, また解釈することを可能にしている. 本稿の目的は, こうした環境変化の中で, 現代イギリスの若者ムスリムがどのようにイスラームの‹知識›と関わり, 社会への統合を果たしているのかを描くことにある. データは, コベントリー市における若者ムスリムへのインタビューを通じて収集され, 主題分析により検討された. 調査の中で, イスラームの‹知識›の探求を促す(親の世代と異なる)3つの環境が指摘された. 第1に, イスラームの‹知識›をめぐるインフラの充実, 第2に, 非イスラーム社会においてムスリムとして生活すること, 第3に, ムスリムをとりまく社会的プレッシャーである. このような環境の中で若者ムスリムは, より広い社会への参加のために, ‹知識›との積極的な関わりを通じて, イスラームの再解釈/再呈示をおこなっている. このことは, 若者が自身の生きる社会的文脈への適応を容易にするために, 宗教的インフラや情報のさらなる充実が求められていることを示している.
1 0 0 0 OA 日本における寄生虫性食中毒の最近の話題と今後の課題
- 著者
- 阿部 仁一郎
- 出版者
- 日本食品微生物学会
- 雑誌
- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.129-137, 2014-09-30 (Released:2015-01-27)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 1 3
1 0 0 0 OA ネオンサインの現況
- 著者
- 坂上 達夫
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.791, pp.991-994, 1954-08-01 (Released:2008-11-20)
1 0 0 0 OA フォトレジスト材料における高分子材料技術
- 著者
- 征矢野 晃雅
- 出版者
- (一社)日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.2, pp.33-39, 2012 (Released:2013-08-02)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 6
Demands for high performance chips have been drastically increased along with the development of smart phones, tablet-PCs and so on. Scaling is an ongoing challenge to fabricate a chip with multi-functions in a limited space for semiconductor manufacturers. In accordance with the design rules, critical dimensions (CD) have shrunk in half every two years. Scaling has been realized by making a photolithography pattern finer and finer by implementing a light source that has a shorter wavelength for lithography. In the development of photoresists for each wavelength, such as g-line, i-line, KrF and ArF, it is necessary to select suitable polymer platforms in order to obtain transmittance of the wavelength being used. This report introduces the history of the development of photoresist material and describes future lithography materials such as nano-imprint lithography (NIL) and direct self-assembly (DSA) technology.
- 著者
- 小河 邦雄 岩澤 まり子
- 出版者
- 情報メディア学会
- 雑誌
- 情報メディア研究 (ISSN:13485857)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.26-37, 2017-03-22 (Released:2017-03-22)
- 参考文献数
- 28
探索調査のためには広い概念でデータベースを検索する場合が多く,大量の検索結果が得られた場合は調査者の過剰な情報負荷となる.本研究では探索的フィルタリングを使用した新しい探索調査の方法を提案する.研究テーマ探索を主題として文献データベースを検索し,得られた文献情報を作成した既知の知識辞書でフィルタリングして低頻度の新奇な情報のみを抽出した.実験では疾病名で文献を検索し,索引情報のフィルタリングで新奇な薬理メカニズムのシーズリストを得た.特に PubMed API を使用した一般語の除去,同義語検出により,大量の情報を半自動的に処理することを可能とした.大量の情報から低頻度で価値のある情報を入手する方法は重要と考える.
1 0 0 0 OA 名誉員 駒井健一郎氏を偲ぶ
- 著者
- 吉山 博吉
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.12, pp.1187-1188, 1986-12-20 (Released:2008-11-20)
1 0 0 0 OA 食物繊維イヌリンによる脂肪代替
- 著者
- 田中 彰裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.312-313, 2013 (Released:2013-10-18)
1 0 0 0 OA 臨床化学検査における酵素的測定法の将来
- 著者
- 村地 孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床化学会
- 雑誌
- 臨床化学 (ISSN:03705633)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.145-157, 1977-06-25 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- Youichi Seto Yukiko Moriyama Daisuke Fujita Mieko Komatsu
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF BENTHOLOGY
- 雑誌
- BENTHOS RESEARCH (ISSN:02894548)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.85-93, 2000-12-31 (Released:2011-11-11)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 4
Abstract: Sexual and asexual reproduction of the fissiparous asteroid Coscinasterias acutispina(Stimpson)was studied in two populations(Kurosaki and Uozu)in Toyama Bay, Sea of Japan, during April 1998-March 1999(Kurosaki)and April 1998-October 1999(Uozu). A total of 96% and 87% of all starfish collected at Kurosaki and Uozu, respectively, showed signs of asexual reproduction by fission. Monthly changes in the ratio of regenerated arm length to maximum arm length revealed that starfish in these populations split most frequently in summer. There was a marked difference in the development of gonads between the two populations. In the Kurosaki population, monthly changes of gonad indices and histological observations on gonads indicated a distinct annual cycle, with a winter spawning season in both males and females. In the Uozu population, gonad indices remained low, and no starfish with mature gonads were observed during the study. An unbalanced sex ratio was observed in both populations; the Uozu population was composed entirely of males. The absence of mature gonads and the extremely biased sex ratio suggest that larval recruitment was low or absent in the Uozu population.
1 0 0 0 OA 各種海産動物によるサザエ稚貝の捕食
- 著者
- 藤井 明彦
- 出版者
- 日本水産増殖学会
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.123-128, 1991-06-30 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2
12種の海産動物を用いてサザエ稚貝に対する捕食実験を行った。1) 9種の海産動物が殻高40mm以下のサザエを捕食し, 捕食された数は20mm以下で多かった。2) ヤツデヒトデの巻貝6種に対する捕食実験から, サザエ稚貝とオオコシダカガンガラに対する選択性が認められた。3) 底面の形状は, サザエ稚貝に対するヤツデヒトデの捕食に影響し, 溝状の底面で最も短期間に捕食された。
1 0 0 0 OA 自殺を二度企図した口臭恐怖症の1例
- 著者
- 山崎 卓 守田 誠吾 扇内 秀樹
- 出版者
- Japanese Society of Psychosomatic Dentistry
- 雑誌
- 日本歯科心身医学会雑誌 (ISSN:09136681)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.17-19, 2005-06-25 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 6
We report a case of school-refusal with two planned attempts at suicide due to halitophobia. The patient was a 20-year-old man whose history of the present illness revealed that he had become concerned about his breath after being bullied in junior high school at the age of fourteen. He had become incapable of having personal contact with other people and refused to go to school. He later graduated without attending junior high school, and subsequently enrolled in a correspondence high school. When he came to our clinic, however, he was currently taking time off from school. He had planned to commit suicide twice, at 17 and 19 years of age, and been admitted to a local psychiatric hospital.The patient was referred to our department by the psychiatrist in charge of his case because no objective evidence of halitosis had been detected during the initial examination. The patient became psychologically stable and hardly concerned about his breath any more after about 6 months of oral cleaning and phased counseling, provided on a regular basis.