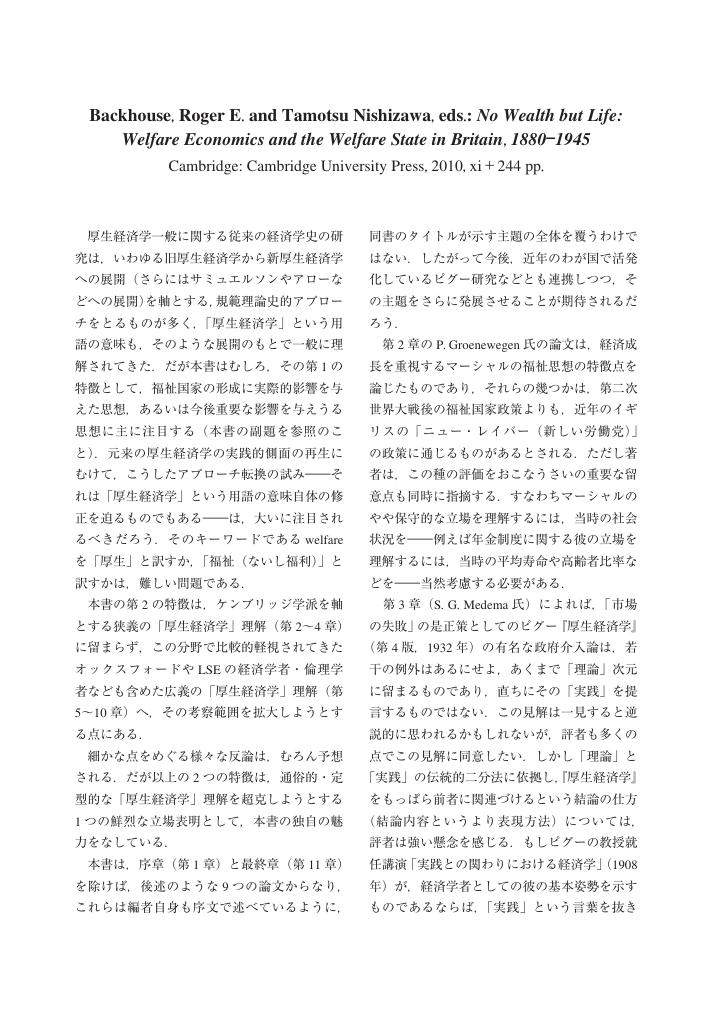- 著者
- 宮内 秀之 米田 卓司 藤原 正和 馬場 崇充 宮澤 昇吾 本郷 良泳 北西 由武 小倉 江里子
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬剤疫学会
- 雑誌
- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.15-26, 2021-06-20 (Released:2021-07-26)
- 参考文献数
- 25
目的:新たな作用機序を有する抗インフルエンザ薬である baloxavir marboxil(以下,baloxavir)のインフルエンザ外来患者における入院及び死亡の発生頻度について,既存の抗インフルエンザ薬であるノイラミニダーゼ阻害剤と比較検討した.研究デザイン:コホート研究方法:急性期医療機関由来のデータベースを用いて,2018/2019 年のインフルエンザシーズンにインフルエンザの診断日(Day 1)を有する 1 歳以上の外来患者を研究対象として抽出し,処方された抗インフルエンザ薬に基づき baloxavir 群,oseltamivir 群,zanamivir 群,または laninamivir 群に群別した.主要なアウトカムとして,Day 2〜14 の入院発生割合を集計し,入院発生の有無を応答としたロジスティック回帰モデルを適用し,年齢カテゴリーによる調整済みオッズ比を算出した.その他,死亡について入院と同様の解析を行った.結果:入院発生割合について,baloxavir 群(1.37%,223/16,309)は,同じ経口剤のoseltamivir 群(1.37%,655/47,843)と同程度であったが,吸入剤の zanamivir 群(0.77%,19/2,474),laninamivir 群(0.91%,234/25,831)よりもわずかに高かった.調整済みオッズ比(対照群/baloxavir 群)[95%信頼区間]は,oseltamivir 群,zanamivir 群及び laninamivir 群との比較において,それぞれ 1.125[0.961−1.317],1.173[0.726−1.897]及び 0.944[0.783−1.140]であり,差は認められなかった.死亡発生割合について,baloxavir 群(0.03%,n=5),oseltamivir 群(0.03%,n=16),laninamivir 群(0.01%,n=3)と同程度であった.一方,zanamivir 群には死亡の発生はなかったが,zanamivir 群の症例数が少ないことの影響が考えられ,他の抗インフルエンザ薬群と死亡発生割合に明らかな差はないと考えられた.結論:Baloxavir 投与によるインフルエンザ外来患者の入院及び死亡の発生頻度は他の抗インフルエンザ薬と同程度であり,インフルエンザ重症化を抑制する新たな選択肢として期待できることが示唆された.
1 0 0 0 野外におけるフクロウによるカブトムシの捕食
- 著者
- 本郷 儀人 金田 大
- 出版者
- 公益財団法人 山階鳥類研究所
- 雑誌
- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.90-95, 2009
- 被引用文献数
- 6
一般にフクロウはネズミなどの小型哺乳類や小型鳥類及び両生類などを主食とし,昆虫類は稀にしか捕食しないと考えられている。しかしながら我々は,フクロウが,餌動物としてはこれまでに報告がなかったカブトムシを捕食することを発見した。さらに,フクロウのカブトムシに対する狩り行動についても観察することができた。そこで,フクロウの詳細な狩り行動についてと,夏季のある時期に非常に頻繁に捕食することを合わせて報告する。
1 0 0 0 OA <翻訳>A.C. ピグー「善の問題」(1908 年) : 邦訳と解題
- 著者
- 本郷 亮 Ryo Hongo
- 雑誌
- 経済学論究 (ISSN:02868032)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.187-205, 2013-06-10
1 0 0 0 IR 昭和二十三年度春期 伊豆山神社見學報告
- 著者
- 本郷 広太郎
- 出版者
- 三田史学会
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.130-131, 1949-10
彙報
- 著者
- 野川 俊彦 ジャン ジュンピル 本郷 やよい 清水 猛 岡野 亜紀子 二村 友史 高橋 俊二 アン ジョンセオ 長田 裕之
- 出版者
- 天然有機化合物討論会実行委員会
- 雑誌
- 天然有機化合物討論会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.56, 2014
<p>放線菌や糸状菌をはじめとする微生物は、多様な構造と活性を有する二次代謝産物を生産することで知られている。それら二次代謝産物は、医薬品や農薬またはそのリード化合物として利用されているものが多い。さらにケミカルバイオロジー研究における生命現象解明のための有用なツール、すなわちバイオプローブとして利用されているものもある。<sup>1</sup>これら代謝産物を効率よく探索・単離するために、我々の研究室ではフラクションライブラリーとスペクトルデータベースを用いる方法を構築し利用している。<sup>2</sup>フラクションライブラリーは、微生物培養液をHPLCや中圧液体クロマトグラフィー(MPLC)により系統的に分画することで作製し、得られたフラクションをPDA-LC/MSにより分析することでデータベースを構築している。データベースは、代謝産物の物性を二次元上の分布として表現したNPPlot(Natural Products Plot)を作成し利用している。今までに、このNPPlotを活用することで特徴的な構造を有する新規化合物を発見・単離してきた。<sup>3</sup>さらに昨年度の本大会において、複数の菌株より作成したNPPlotの分布パターンの比較による新規化合物の探索と単離について報告した。<sup>4</sup>今回、放線菌Streptomyces sp. RK85-270のフラクションライブラリーより作成したNPPlotの分布パターンから菌株特有の化合物群の探索を行い、2種の新規環状デプシペプチド1および2(図1)を見出すことができたので、それらの単離・構造決定について報告する。</p><p>図1.新規環状デプシペプチド1および2の構造</p><p>【微生物代謝産物フラクションライブラリーの作製】</p><p>放線菌Streptomyces. sp. RK85-270の30 L培養液に等量のアセトンを加え撹拌抽出後、吸引ろ過により菌体を除去し含水アセトン抽出液を得た。減圧下でアセトンを留去し、残った水懸濁液を酢酸エチルにより分配することで有機溶媒可溶性画分と水溶性画分を調製した。有機溶媒画分を減圧濃縮することで抽出物37.2 gを得た。このうち28.7 gをシリカゲル順相MPLCにより、クロロホルム/メタノールのステップワイズ溶出を用いて8分画とした。それぞれを逆相HPLCにより移動相にアセトニトリル/0.05%ギ酸水のグラジエント溶出を用いて一定時間で分画することでフラクションを作製した。水溶性画分は、DIAION HP-20によりメタノールに可溶なものを抽出後、得られたメタノール可溶性画分を逆相MPLCによりメタノール/水を移動相として分画することでフラクションを作製した。以上の方法で約400フラクションを作製した。各フラクションをPDA-LC/MSにより分析し、含有成分のUV吸収およびマススペクトルの収集を行い、成分情報の付加したフラクションライブラリーとした。</p><p>図2.放線菌RK85-270のNPPlotと特徴的分布を示した領域の拡大および</p><p>それら化合物のUV吸収スペクトル</p><p>【スペクトルデータベースNPPlot(Natural Products Plot)の作成】</p><p>PDA-LC/MS分析より得られたUV吸収およびマススペクトルデータをもとに化合物探索に利用するためのスペクトルデータベースを作成した。一般的なスペクトルデータベースに加え、研究室オリジナルのデータベースNPPlot</p><p>(View PDFfor the rest of the abstract.)</p>
1 0 0 0 OA 2.糖尿病で感染症が増えるメカニズム
- 著者
- 嶋崎 鉄兵 本郷 偉元
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.10, pp.666-667, 2018-10-30 (Released:2018-10-30)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 次亜塩素酸を用いた高齢者受入施設での空間除菌脱臭機について
- 著者
- 本郷 宏之
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.9, pp.640-643, 2017
- 著者
- 本郷 峻
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.73-74, 2020 (Released:2020-12-23)
1 0 0 0 OA O1-E-11 過敏性腸症候群における認知柔軟性の男女差及び同性間比較(消化器,一般口演,今,心身医学に求められるもの-基礎から臨床まで-,第52回日本心身医学会総会ならびに学術講演会)
- 著者
- 相澤 恵美子 佐藤 康弘 森下 城 金澤 素 本郷 道夫 福土 審
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.539, 2011-06-01 (Released:2017-08-01)
1 0 0 0 (書評)二木謙一著「武家儀礼格式の研究」
- 著者
- 本郷 恵子
- 出版者
- Japan Legal History Association
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.54, pp.123-127, 2004
- 著者
- 本郷 亮
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.171-172, 2016 (Released:2019-11-29)
- 著者
- 本郷 亮
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.112-113, 2012 (Released:2019-10-31)
1 0 0 0 OA ピグーの『失業の理論』
- 著者
- 本郷 亮
- 出版者
- The Japanease Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.63-77, 2006-06-30 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 49
The purpose of this paper is to reexamine the significance for wage policy and theory of The Theory of Unemployment (1933). A. C. Pigou (1877-1959) began to study unemployment problems before World War I. He often advocated “direct state action” to lessen unemployment by increasing government expenditure. After the war, however, increasingly he viewed direct action by government as something to be exercised selectively and with caution. According to Pigou, the causes of unemployment in the 1920s were to be found not in a shortage of aggregate labor demand but primarily in the high wage-rates of some industries.In other words, he shifted the approach to unemployment from the labor demand side to the labor supply side. That change in analytical starting point shows up clearly in Pigou's “Wage Policy and Unemployment” (1927). In that article he maintains, “If it is correct-if, that is to say, post-war wage policy is in fact responsible for adding some 5 per cent to the volume of unemployment which is normally brought about by other factors-the country is confronted with a problem of a type which pre-war economics never found itself called upon study.” Pigou's study of unemployment in relation to wage policies crystallized in 1933 into The Theory of Unemployment, in which his chief objective was to shed light on unemployment as an outcome of causative factors originating in the labor supply side.My main conclusions are three: (1) Pigou's theory of unemployment developed and changed through at least two stages; (2) In the late 1920s Pigou began to emphasize the importance of wage policy as a dominant cause of the unemployment at that time; and (3) The Theory of Unemployment contained some arguments similar to the natural unemployment-rate hypothesis, which was popular in the 1970s.
1 0 0 0 OA 初期ピグーの再評価
- 著者
- 本郷 亮
- 出版者
- The Japanese Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.39, pp.116-127, 2001 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 18
This paper deals with A. C. Pigou's economic thought before the World War I, especially in relation to Liberal Reform (1906-11). Pigou was very interested in the Royal Commission on the Poor Law and Relief of Distress. He submitted “Memorandum on some Economic Aspects and Effects of Poor Law Relief” to the Royal Commission in 1907. In this “Memorandum”, we can distinguish his two welfare criteria: the size and distribution of the national dividend. His motives to write Wealth and Welfare (1912) could be mainly found in those years.The National Insurance Act (1911) was one of the most epoch-making laws during this period. Pigou examined this institution in his book Wealth and Welfare because labour problems, including destitution and unemployment, were an urgent economic theme for him and his contemporaries. In Unemployment (1913) he considered that not only public works as means for relieving unemployment among the poor, but also insurance and National-Minimum were necessary. Liberal Reform was an essential background of Pigou's welfare economics.
- 著者
- 本郷 恵子
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.11, pp.1989-1996, 2009-11-20 (Released:2017-12-01)
1 0 0 0 OA 腱板を構成する筋の筋内腱 -筋外腱移行形態について-
- 著者
- 皆川 洋至 井樋 栄二 佐藤 毅 今野 則和 本郷 道生 佐藤 光三
- 出版者
- 日本肩関節学会
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.103-109, 1996-10-15 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
Each muscle of the rotator cuff is known to have several intramuscular tendons which provide attachment to numerous muscle fiders. The anatomical relationship between intramuscular and extramuscular tendons needs to be determined to know the distribution of the force to the rotator cuff tendon. The purpose of this study was to clarify the morphology of the transitional zone of intramuscular to extramuscular tendons of the rotator cuff.The muscle fibers of cuff muscles of 20 embalmed shoulders without full-thickness rotator cuff tears were removed to examine the transitional zone of the intramuscular to extramuscular tendons macroscopically. Histological sections of the musculotendinous junction were perpared to evaluate the transitional forms microscopically.We defined the intramuscular tendon as the tendon inside the muscle belly and the extramuscular tendon as the tendon outside the muscle. The extramuscular tendons from the rotator cuff tendon distally. Location was expressed as the % position of the anterior and posterior margins of the musculotendinous junction. The intramuscular tendons of the infraspinatus, teres minor, and subscapularis were contiguous to the whole extramuscular tendons and that the supraspinatus was located in the anterior one-third of the extramuscular tendon(0±0% to 28±15%). Microscopically, the intramuscular tendon of the supraspinatus formed a tendon fiber bundle and was continuous with the second of five layers of the extramuscular tendon (Clark and Harryman,1992).Conclusion: The connection of intramuscular tendon to extramuscular tendon was specific to each cuff muscle. The intramuscular tendon of the supraspinatus was attached to the anterior one-third of the extramuscular tendon and was contiguous to the second layer.
1 0 0 0 OA 糖尿病患者における胃排出能のインスリン需要動態と血糖に及ぼす影響
- 著者
- 真山 享 赤井 裕輝 渡辺 力夫 阿部 茂樹 門伝 昌巳 本郷 道夫 豊田 隆謙 後藤 由夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.11, pp.1017-1022, 1987-11-30 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
糖尿病性自律神経障害による胃排出能の異常が食事摂取後のインスリン需要動態および血糖コントロールに与える影響について検討した. 胃排出能正常な糖尿病者 (N群) 4名, 胃無力症 (胃排出能高度異常) の糖尿病者 (G群) 7名の計11名を対象とした.胃排出能は99m-Tc-Tin colloidにより標識した試験食摂取後のアイソトープ胃内残存量をガンマカメラにて経時的に測定し, 全例に人工膵島 (Biostator®) によるfeedback controlを行い, インスリン注入動態を観察した.G群では食後のアイソトープ胃内残存率がN群に比較して高値であり, 150分後ではG群, 74.1±7.4%(M±SD), N群21.3±5.4%であった (p<0.01). 食後インスリン需要量はN群でG群よりも高値であり, 150分後ではN群11.7±5.3単位, G群5.6±2.1単位であった (p<0.05).prokinetic agentの投与により, 胃排出能が著明に改善した6例では, 血糖日内変動, HbA1ともに明きらかに改善し, 良好なコントロールが得られた.胃排出能の異常は血糖の不安定性の原因の1つであり, インスリン需要動態に大きな異常をもたらす. 胃排出能の改善により, 食後インスリン需要量が適正化し, 良好な血糖コントロ一ルを得ることが可能となる.
- 著者
- 本郷 峻
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- pp.36.012, (Released:2020-11-26)
1 0 0 0 霜月騒動再考
- 著者
- 本郷 和人
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.12, pp.1899-1935, 2003
The present article offers a new view of the important political disturbance within the Kamakura Bakufu that occurred during the eleventh month (shimotsuki霜月) of 1285 in an attempt to clarify the political situation within the Bakufu during its later years.The conventional political history of the incident is based on the assumption that the warrior class was unconditionally one composed of natural administrators.However,the author is not convinced that they were all that knowledgeable about the art of governance at the time the Bakufu was founded.At that time,the local land proprietors of the Kanto region formed a political mechanism known as a "bakufu" to protect their rights,which led to start their carrers as administrators.They learned how to govern only through experience over time.An analysis of the amendments and revisions made to the Seibaishikimoku成敗式目 code shows that the Bakufu only became serious about politics and governance after the civil war of 1221.An excellent example of this is the "welfare" measures to nurture the people (bumin撫民) adopted during the Kencho建長 era (early 1250s).On the other hand,the order issued during the Einin永仁 era concerning debt remission was aimed solely at Bakufu vassals (gokenin御家人) and can hardly be looked upon as an act of governing the country.In this sence,the Bakufu should be looked upon as having two different aspects : people forming the mechanism for the Bakufu to govern the country,and those forming an organization to protect the interests of gokenin.Focussing on the remission of debt issue,we can observe political conflict arising within the Bakufu at the time of the Mongol invasion,which can be interpreted in terms of opposition between the above "administrator" and "gokenin interest" groups,the former being represented by Adachi Yasumori安達泰盛,the latter by Taira Yoritsuna平頼綱.The clash that occurred between them known as the Shimotuski incident resulted in the defeat and decline in influence of the "administrator" group who felt the Bakufu should be involved in governing the whole country.The resulting Bakufu organization,which became over-concerned with protecting the interests of its gokenin constituency,would sooner or later lose the support if the other elements of society,resulting in its eventual fall.