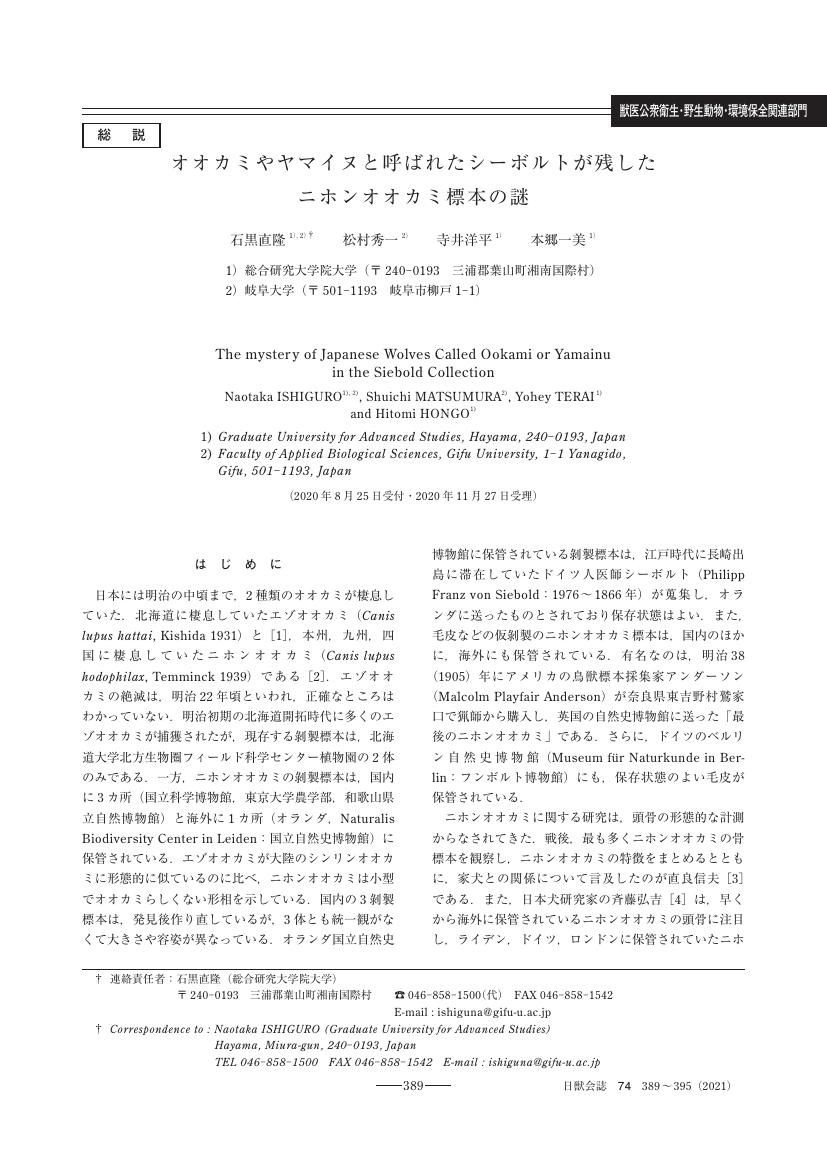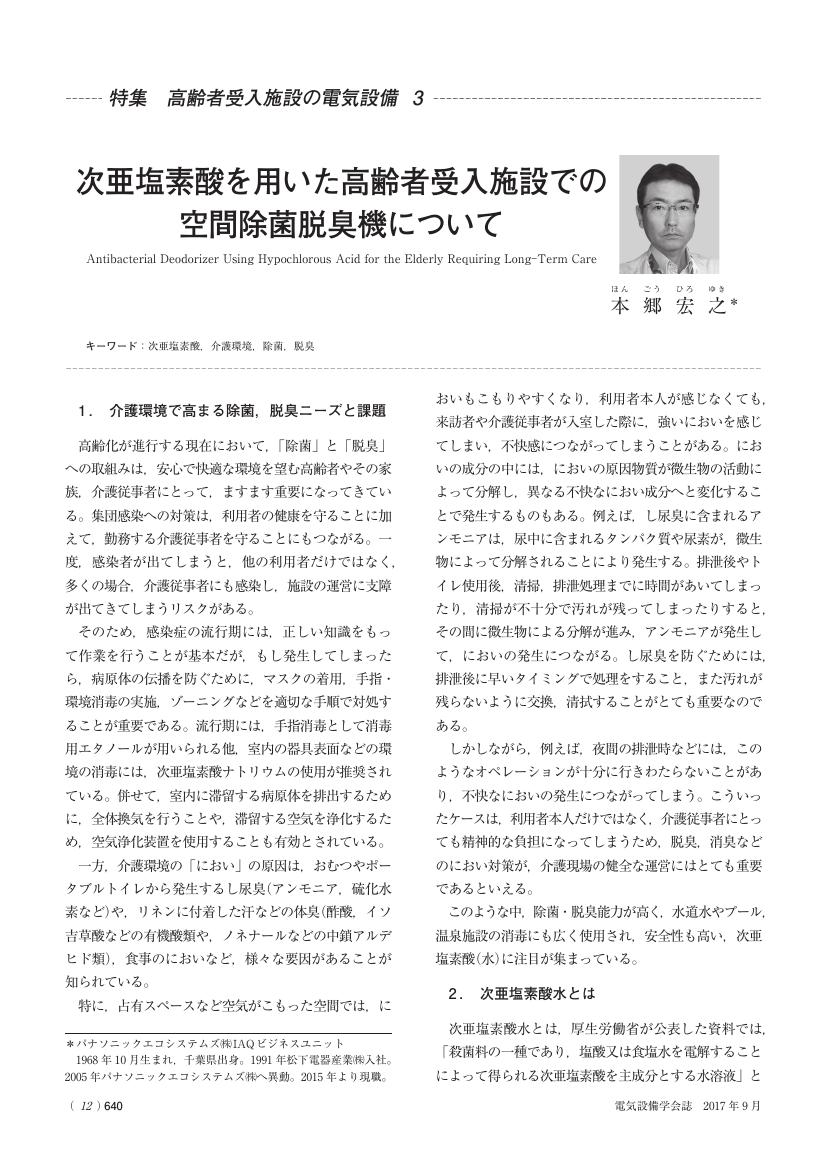78 0 0 0 OA オオカミやヤマイヌと呼ばれたシーボルトが残したニホンオオカミ標本の謎
- 著者
- 石黒 直隆 松村 秀一 寺井 洋平 本郷 一美
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.6, pp.389-395, 2021-06-20 (Released:2021-07-20)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
17 0 0 0 OA 絶滅したエゾオオカミとニホンオオカミの起源と系譜を探る形態的および遺伝学的研究
絶滅した日本のオオカミ(エゾオオカミとニホンオオカミ)の分類学上の位置をミトコンドリア(mt)DNAのゲノム解析により明らかにし、両オオカミの起源と系譜を海外の考古資料から調査した。エゾオオカミは、大陸のオオカミと遺伝的に近く、ニホンオオカミとは大きく異なっていた。ロシアおよび中国の古代サンプル143検体を解析したが、ニホンオオカミのmtDNA配列に近い検体は検出できなかった。また、モンゴルのオオカミ8検体および国内の現生犬426検体を解析し、ニホンオオカミのmtDNAの残存を調査したが見つからなかった。これらの結果は、ニホンオオカミはオオカミ集団の中でもユニークな系統でることを示している。
13 0 0 0 OA 目録学の構築と古典学の再生-天皇家・公家文庫の実態復原と伝統的知識体系の解明-
- 著者
- 田島 公 山口 英男 尾上 陽介 遠藤 基郎 末柄 豊 石上 英一 藤井 譲治 金田 章裕 西山 良平 坂上 康俊 西本 昌弘 本郷 真紹 加藤 友康 武内 孝善 田良島 哲 渡辺 晃宏 石川 徹也 石川 徹也 山口 和夫 藤原 重雄 稲田 奈津子 遠藤 珠紀 三角 洋一 月本 雅幸 吉川 真司 小倉 慈司 綾村 宏 杉橋 隆夫 桃崎 有一郎 島谷 弘幸 猪熊 兼樹 馬場 基
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 学術創成研究費
- 巻号頁・発行日
- 2007
禁裏(天皇家)や主要公家文庫収蔵史料のデジタル画像約100万件、東山御文庫本・伏見宮家本の1画像毎の内容目録約20万件を作成し、編纂所閲覧室での公開準備を進めた。木簡人名データベースと漢籍の受容を網羅した古代対外交流史年表を公開した。『禁裏・公家文庫研究』3・4、研究報告書4冊等を刊行し、禁裏・主要公家文庫の家分け蔵書目録を公開した。「陽明文庫講座」「岩瀬文庫特別連続講座」等市民向け公開講座を約百回開催し講演内容の一部を一般向けの本として刊行した
11 0 0 0 OA ニホンオオカミとイヌとの交雑種?いわゆるヤマイヌの存在を探る動物考古学的研究
10 0 0 0 OA フント則の起源は何か?(最近の研究から)
- 著者
- 本郷 研太 小山田 隆行 川添 良幸 安原 洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.10, pp.799-803, 2005-10-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 2
フント則の交換エネルギーによる解釈は誤りである.2電子系, 軽分子の低励起状態についてこの事実が指摘されて以来, 既に20年以上経つ.スピン最多重度状態の安定性は, 運動エネルギーはもちろん電子間斥力エネルギーをも増加させる代償として得られる原子核電子間引力エネルギーの低下に起因する.本稿は, 炭素, 窒素, 酸素原子の基底状態について同結論を拡散量子モンテカルロ法によって初めて検証し, 相関の役割を解析した.
8 0 0 0 OA 霜月騒動再考
- 著者
- 本郷 和人
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.12, pp.1899-1935, 2003-12-20 (Released:2017-12-01)
The present article offers a new view of the important political disturbance within the Kamakura Bakufu that occurred during the eleventh month (shimotsuki霜月) of 1285 in an attempt to clarify the political situation within the Bakufu during its later years.The conventional political history of the incident is based on the assumption that the warrior class was unconditionally one composed of natural administrators.However,the author is not convinced that they were all that knowledgeable about the art of governance at the time the Bakufu was founded.At that time,the local land proprietors of the Kanto region formed a political mechanism known as a "bakufu" to protect their rights,which led to start their carrers as administrators.They learned how to govern only through experience over time.An analysis of the amendments and revisions made to the Seibaishikimoku成敗式目 code shows that the Bakufu only became serious about politics and governance after the civil war of 1221.An excellent example of this is the "welfare" measures to nurture the people (bumin撫民) adopted during the Kencho建長 era (early 1250s).On the other hand,the order issued during the Einin永仁 era concerning debt remission was aimed solely at Bakufu vassals (gokenin御家人) and can hardly be looked upon as an act of governing the country.In this sence,the Bakufu should be looked upon as having two different aspects : people forming the mechanism for the Bakufu to govern the country,and those forming an organization to protect the interests of gokenin.Focussing on the remission of debt issue,we can observe political conflict arising within the Bakufu at the time of the Mongol invasion,which can be interpreted in terms of opposition between the above "administrator" and "gokenin interest" groups,the former being represented by Adachi Yasumori安達泰盛,the latter by Taira Yoritsuna平頼綱.The clash that occurred between them known as the Shimotuski incident resulted in the defeat and decline in influence of the "administrator" group who felt the Bakufu should be involved in governing the whole country.The resulting Bakufu organization,which became over-concerned with protecting the interests of its gokenin constituency,would sooner or later lose the support if the other elements of society,resulting in its eventual fall.
8 0 0 0 IR 青年女子の身体計測値に関する研究 (第1報)
- 著者
- 山田 民子 本郷 美枝 長塚 こずえ 玉田 清美 橋詰 静子
- 出版者
- 東京家政大学
- 雑誌
- 東京家政大学研究紀要. 2, 自然科学 (ISSN:03851214)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.79-88, 1991-02
6 0 0 0 古代西アジアに生息した未知のライオンの研究
従来、古代西アジアのライオンは「インドライオン」と考えられてきた。しかし新アッシリア時代のライオン狩り浮彫には、異なる2種類のライオンが描き分けられ、ライオンの身体的特徴と連動して身体のサイズが異なることから、両者の違いは個体差ではなく、異なる亜種か品種であった可能性が浮上する。古代の文献には「平原生まれ」と「山生まれ」のライオンが登場し、ライオンを意味するシュメール語とアッカド語には2種類ずつの語彙がある。ここからこの地域のライオンが必ずしも単一種ではなく、未知のライオンが生息していた可能性が浮上する。本研究は古代西アジアのライオンの実態を、図像・文献・動物考古学の学際的視角から探究する。
6 0 0 0 OA 初等中等教育におけるプログラミング教育の教育的意義の考察
- 著者
- 山本 利一 本郷 健 本村 猛能 永井 克昇
- 出版者
- 日本教育情報学会
- 雑誌
- 教育情報研究 (ISSN:09126732)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.3-12, 2016 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 31
本研究は,プログラミング教育に関する教育的意義やその効果を先行研究から整理し,今後それらを推進するための基本的な知見を得ることを目的とする.そのために,初等中等教育におけるプログラミング教育の位置づけを学習指導要領で確認した後,先行研究を整理した.その結果,プログラミング教育の教育的意義や学習効果は,①新たなものを生み出したり,難しいものに挑戦しようとする探究力,②アルゴリズム的思考,論理的思考力,③物事や自己の知識に関する理解力,④自分の考えや感情が発信できる表現力や説得力,⑤知恵を共有したり他者の理解や協力して物事を進めたりする力,⑥プログラミングを通して情報的なものの見方や考え方を身に付けることができる,ことであることが示された.
成人の高機能自閉スペクトラム症(High-functioning Autism spectrum disorder:HF-ASD)者 は「自分は異端である」などのスティグマを持ちやすく,そのため定型発達者の社会に過剰適応する「社会的カモフラージュ行動」を取りやすいが,その行動はメンタルヘルスに負の影響をもたらすことが指摘されている.本研究では,成人のHF-ASD者の社会的カモフラージュ行動の要因について解明する.その知見をもとに,成人のHF-ASD者に対する新たな対処方略の構築を目的とした認知行動療法を開発・施行し,その効果を検証する.
5 0 0 0 OA 道路上の糞を探す踏査で明らかになった屋久島のニホンザルの全島分布(2017‐2018年)
- 著者
- 半谷 吾郎 好廣 眞一 YANG Danhe WONG Christopher Chai Thiam 岡 桃子 楊木 萌 佐藤 侑太郎 大坪 卓 櫻井 貴之 川田 美風 F. FAHRI SIWAN Elangkumaran Sagtia HAVERCAMP Kristin 余田 修助 GU Ningxin LOKHANDWALA Seema Sheesh 中野 勝光 瀧 雄渡 七五三木 環 本郷 峻 澤田 晶子 本田 剛章 栗原 洋介
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- pp.36.014, (Released:2020-11-30)
- 参考文献数
- 23
We studied the island-wide distribution of wild Japanese macaques in Yakushima (Macaca fuscata yakui) in May 2017 and 2018. We walked 165.4 km along roads and recorded the location of 842 macaque feces. We divided the roads into segments 50 m in length (N=3308) and analyzed the effect of the areas of farms and villages or conifer plantations around the segments and also the presence of hunting for pest control on the presence or absence of feces. We divided the island into three areas based on population trend changes over the past two decades: north and east (hunting present, population decreasing); south (hunting present, no change) and west (hunting absent, no change). According to conditional autoregressive models incorporating spatial autocorrelation, only farms and villages affected the presence of feces negatively in the island-wide data set. The effect of hunting on the presence of feces was present only in the north and east and the effect of conifer plantations was present only in the west. Qualitative comparisons of the census records from the 1990s with the more recent census indicated that feces were no longer found in the private land near the northern villages of Yakushima, where macaques were previously often detected in the 1990s. In other areas, such as near the southern villages or in the highlands, macaques were detected both in the 1990s and in 2017-2018. Our results further strengthen the possibility that the macaques have largely disappeared around the villages in the northern and eastern areas. Since the damage of crops by macaques has recently reduced considerably, we recommend reducing hunting pressure in the north and east areas and putting more effort into alternative measures such as the use of electric fences.
- 著者
- 本郷 亮 Ryo Hongo
- 雑誌
- 経済学論究 = The journal of economics of Kwansei Gakuin University (ISSN:02868032)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.225-250, 2017-06-20
- 著者
- 山口 惠三 大野 章 石井 良和 舘田 一博 岩田 守弘 神田 誠 辻尾 芳子 木元 宏弥 方山 揚誠 西村 正治 秋沢 宏次 保嶋 実 葛西 猛 木村 正彦 松田 啓子 林 右 三木 誠 中野渡 進 富永 眞琴 賀来 満夫 金光 敬二 國島 広之 中川 卓夫 櫻井 雅紀 塩谷 譲司 豊嶋 俊光 岡田 淳 杉田 暁大 伊藤 辰美 米山 彰子 諏訪部 章 山端 久美子 熊坂 一成 貝森 光大 中村 敏彦 川村 千鶴子 小池 和彦 木南 英紀 山田 俊幸 小栗 豊子 伊東 紘一 渡邊 清明 小林 芳夫 大竹 皓子 内田 幹 戸塚 恭一 村上 正巳 四方田 幸恵 高橋 綾子 岡本 英行 犬塚 和久 山崎 堅一郎 権田 秀雄 山下 峻徳 山口 育男 岡田 基 五十里 博美 黒澤 直美 藤本 佳則 石郷 潮美 浅野 裕子 森 三樹雄 叶 一乃 永野 栄子 影山 二三男 釋 悦子 菅野 治重 相原 雅典 源馬 均 上村 桂一 前崎 繁文 橋北 義一 堀井 俊伸 宮島 栄治 吉村 平 平岡 稔 住友 みどり 和田 英夫 山根 伸夫 馬場 尚志 家入 蒼生夫 一山 智 藤田 信一 岡 三喜男 二木 芳人 岡部 英俊 立脇 憲一 茂龍 邦彦 草野 展周 三原 栄一郎 能勢 資子 吉田 治義 山下 政宣 桑原 正雄 藤上 良寛 伏脇 猛司 日野田 裕治 田中 伸明 清水 章 田窪 孝行 日下部 正 岡崎 俊朗 高橋 伯夫 平城 均 益田 順一 浅井 浩次 河原 邦光 田港 朝彦 根ケ山 清 佐野 麗子 杉浦 哲朗 松尾 収二 小松 方 村瀬 光春 湯月 洋介 池田 紀男 山根 誠久 仲宗根 勇 相馬 正幸 山本 剛 相澤 久道 本田 順一 木下 承晧 河野 誠司 岡山 昭彦 影岡 武士 本郷 俊治 青木 洋介 宮之原 弘晃 濱崎 直孝 平松 和史 小野 順子 平潟 洋一 河野 茂 岡田 薫
- 出版者
- 日本抗生物質学術協議会
- 雑誌
- The Japanese journal of antibiotics (ISSN:03682781)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.428-451, 2006-12-25
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 37
5 0 0 0 OA 日本目録学の基盤確立と古典学研究支援ツールの拡充-天皇家・公家文庫を中心に-
- 著者
- 田島 公 尾上 陽介 遠藤 基郎 末柄 豊 吉川 真司 金田 章裕 馬場 基 本郷 真紹 山本 聡美 伴瀬 明美 藤原 重雄 稲田 奈津子 黒須 友里江 林 晃弘 月本 雅幸 三角 洋一 川尻 秋生 小倉 慈司 渡辺 晃宏 桃崎 有一郎 北 啓太 吉岡 眞之 山口 英男 金子 拓 遠藤 珠紀 原 秀三郎 神尾 愛子 名和 修 名和 知彦 内海 春代 飯田 武彦
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 基盤研究(S)
- 巻号頁・発行日
- 2012-05-31
東京大学史料編纂所閲覧室で東山御文庫本、陽明文庫本、書陵部蔵九条家本・伏見宮家本など禁裏・公家文庫収蔵史料のデジタル画像約100万件を公開した。高松宮家伝来禁裏本・書陵部所蔵御所本の伝来過程を解明し、分蔵された柳原家本の復原研究を行い、禁裏・公家文庫収蔵未紹介史料や善本を『禁裏・公家文庫研究』や科学研究費報告書等に約30点翻刻・紹介した。更に、日本目録学の総体を展望する「文庫論」を『岩波講座日本歴史』22に発表し、『近衞家名宝からたどる宮廷文化』を刊行した。
4 0 0 0 OA 腸内細菌と精神神経疾患からみる腸脳相関
- 著者
- 本郷 道夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.451-457, 2022 (Released:2022-11-01)
- 参考文献数
- 26
腸内細菌は,多種にわたり大量に腸管内に存在する.腸管粘膜は,上皮細胞間のタイトジャンクションにより緊密に結合し,表面は粘液により被覆される.粘液はその物理的性状,粘液中に分泌されるs-IgAおよび抗菌蛋白により免疫学的に管腔内物質の生体への侵入を予防し,上皮内の樹状細胞,上皮下の免疫細胞およびs-IgAによってより強固な防御機構を形成する.加齢や心理社会環境ストレスは粘液産生低下および免疫機能低下により腸管バリア機能が低下したleaky gutを誘発する.その結果,精神神経系,消化器系,代謝系,免疫系の多彩な腸内細菌関連疾患を誘発する.その主要な機序は,炎症,細菌代謝物などの侵入もしくは吸収,免疫反応である.精神神経疾患の病態においては,精神疾患は主として炎症反応が脳血液関門を障害し,神経炎症を引き起こすこと,神経変性疾患では腸管で吸収された物質が求心性神経を経由して中枢神経系で凝集すること,がその主要な病態と推測される.
4 0 0 0 OA 極超音速統合制御実験(HIMICO)の提案
- 著者
- 佐藤 哲也 田口 秀之 津江 光洋 土屋 武司 松尾 亜紀子 藤川 貴弘 鈴木 宏二郎 中谷 辰爾 渡邉 保真 森田 直人 手塚 亜聖 石村 康生 宮路 幸二 増田 和三 廣谷 智成 高橋 英美 今村 俊介 大木 純一 西田 俊介 本郷 素行 小島 孝之 SATO Tetsuya TAGUCHI Hideyuki TSUE Mitsuhiro TSUCHIYA Takeshi MATSUO Akiko FUJIKAWA Takahiro SUZUKI Kojiro NAKAYA Shinji WATANAB Yasumasa MORITA Naoto TEZUKA Asei ISHIMURA Kosei MIYAJI Koji MASUDA Kazumi HIROTANI Tomonari TAKAHASHI Hidemi IMAMURA Shunsuke OKI Junichi NISHIDA Shunsuke HONGOH Motoyuki KOJIMA Takayuki
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)
- 雑誌
- 観測ロケットシンポジウム2020 講演集 = Proceedings of Sounding Rocket Symposium 2020
- 巻号頁・発行日
- 2021-03
第3回観測ロケットシンポジウム(2021年3月24-25日. オンライン開催)
4 0 0 0 OA 次亜塩素酸を用いた高齢者受入施設での空間除菌脱臭機について
- 著者
- 本郷 宏之
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.9, pp.640-643, 2017 (Released:2017-09-14)
4 0 0 0 OA 歴史歴史に向き合う心――韓国・中国歴史教科書の分析――
- 著者
- 本郷 隆盛
- 出版者
- 日本思想史研究会
- 雑誌
- 年報日本思想史 (ISSN:13472992)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.75-101, 2011-06-25
4 0 0 0 OA 2種の日本新産ハラタケ目菌類について
- 著者
- 本郷 次雄
- 出版者
- 日本きのこセンター菌蕈研究所
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.28-31, 2002 (Released:2011-03-05)
Phaeocollybia lugubris(新称:アカアシナガタケ)およびRussula melliolens(新称:ヨヘイジモドキ)のハラタケ目の2種を日本新産種として報告した。