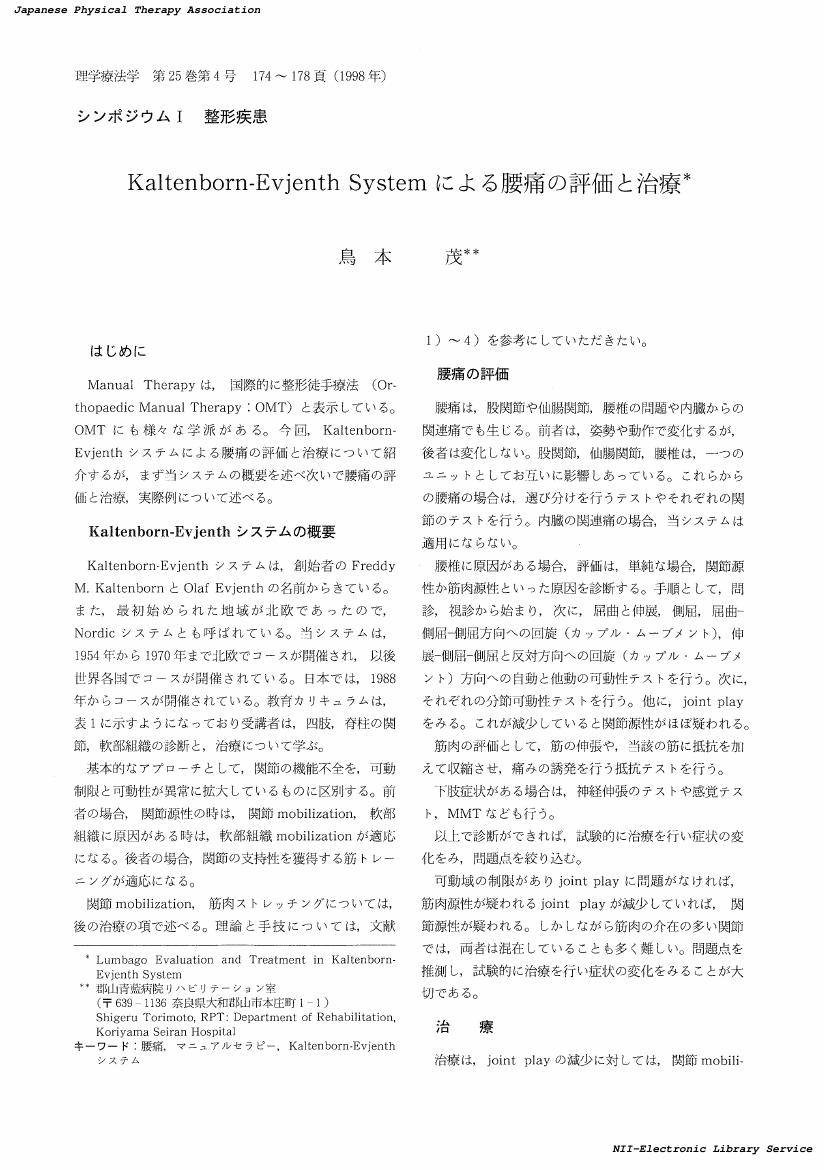1 0 0 0 OA サルコペニア 予防と改善
- 著者
- 山田 実
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.8, pp.580-582, 2013-12-20 (Released:2017-07-04)
1 0 0 0 OA 中高年女性における腹圧性尿失禁症状とインナーユニット機能との関係性
- 著者
- 生方 瞳 丸山仁司 霍 明
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.5, pp.348-356, 2017 (Released:2017-10-20)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
【目的】本研究は,中高年女性における腹圧性尿失禁とインナーユニットの関係について検討した。さらに,動作課題の妥当性について,骨盤底拳上量による腹圧性尿失禁検出度を比較した。【対象と方法】中高年女性101 名を対象とした。質問紙表にて尿失禁群と非尿失禁群に群分けした。握力,CS-30 テストに加え超音波画像診断装置を用いて腹横筋厚,多裂筋横断面積,骨盤底拳上量を測定した。【結果】尿失禁群はすべての筋で,同時収縮および抵抗運動で非尿失禁に比べ有意に低値を示した。尿失禁を従属変数としたロジスティック回帰分析で選択された因子は,抵抗運動時の骨盤底挙上量であった。【考察】インナーユニットは協同運動しており,特に抵抗運動時の骨盤底挙上量の低下は腹圧性尿失禁のリスクファクターであることが示唆された。さらに,抵抗運動時の骨盤底挙上量が4.88 mm 以下である場合は腹圧性尿失禁の可能性が著しく高いことが示唆された。
1 0 0 0 大胸筋と小胸筋の筋線維の走行からみた運動療法
- 著者
- 荒川 高光
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.263-265, 2010
- 参考文献数
- 11
1 0 0 0 運動・動作・行動の流れの中の「意志」と意識:―状況理論に向けて―
- 著者
- 久保田 新
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.199-201, 2006
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 OA 足位が中殿筋活動に及ぼす影響 ―距骨下関節の内外反運動との関係―
- 著者
- 入谷 誠 山嵜 勉 大野 範夫 山口 光国 内田 俊彦 筒井 廣明 黒木 良克
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.35-40, 1991-01-10 (Released:2018-10-25)
- 被引用文献数
- 3
今回,我々は足位,すなわちFOOT ANGLEの変化が,骨盤の側方安定性に関与する中殿筋活動の動態と距骨下関節の内外反角度にどの様に影響をするかをX線学的及び筋電図学的に検索した。その結果,X線学的には,TOE-OUTで距骨下関節は内反し,TOE-INで距骨下関節は外反した。筋電図学的分析では,中殿筋の活動はTOE-OUTからTOE-INに向かって,明らかに増加した。さらに中殿筋の活動量が最も大きかったTOE-IN 30°でアーチサポートを挿入すると,中殿筋の活動量が明らかに低下したことから,中殿筋の活動量はFOOT ANGLEの変化のみならず,足部アーチの状態も大きく影響を及ぼしていることを示唆した。
- 著者
- 小澤 和夫 白石 久富 大野 恭子 西川 隆 田伏 薫
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.21-25, 1990-01-10 (Released:2018-10-25)
顔面運動においてMotor Impersistence(MI)が認められる患者では,車椅子駆動のような複合的な動作に関して,健側上下肢いずれかの肢における連続動作や上下肢の同時動作においても障害が認められる。この病態をより要素的に分析する目的で,手足の等尺性運動の維持能力を検討した。MI陽性左片麻痺群(6例)と対照群であるMI陰性右・左片麻痺群(各7例)の3群について,指腹つまみ単一動作,踏みつけ単一動作,指腹つまみと踏みつけの同時動作,の3種類の動作を各20秒間行わせ,圧力とその変動および保持時間を調べ各群を比較検討した。その結果,顔面運動でみられるような動作の中断はみられなかったが,上肢ではMI陽性左片麻痺群の圧力が他の群に比べ,時間の経過とともに有意に減衰していた。このことは,顔面と上肢および下肢の運動制御の水準の段階的な差を反映しており,より意図的な努力を要する動作において,定常的な運動の維持が困難になるものと考えられる。
1 0 0 0 OA 両側性運動における一側筋力調節時の対側最大筋力への影響
- 著者
- 竹林 秀晃 宮本 謙三 宅間 豊 井上 佳和 宮本 祥子 岡部 孝生 滝本 幸治 八木 文雄
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.82-87, 2006-04-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 2
筋力評価や筋力トレーニングは,徒手筋力検査法や等速度運動機器など,一側を対象として行われることが多い。しかし,身体運動の多くは,左右の四肢を非常に巧みに協応させて行われており,左右肢間の相互作用を考慮した両側性運動を考慮する視点も必要と思われる。本研究では,一側に筋力調節課題を与えることで注意の方向を統一し,その調節水準を変化させることによる対側との相互干渉の変化を,下肢運動課題を用いて検討した。対象は健常成人9名とし,運動課題には右膝伸展筋筋力の筋力調節下(等尺性収縮による100%最大随意収縮 : Maximal Voluntary Contraction(MVC),75%MVC,50%MVC,25%MVC)で,対側である左膝伸展最大等尺性筋力を発揮するという両側性運動を用いた。加えて,左側単独での膝伸展最大等尺性筋力も測定した。測定に際しては右膝伸展筋力の調整量保持を絶対条件とし,注意の方向性を統一した。データ分析対象は,各運動課題遂行時の左膝伸展最大筋力の変化とした。その結果,右膝伸展筋力を調整することによる左膝伸展最大筋力への影響は,右膝伸展筋力の調節水準が低くなるに従い,左膝伸展最大筋力も同様に低下するという同調的変化を示した。これは,両側性機能低下のメカニズムの一つである認知・心理レベルでの注意の分割が関与しており,神経支配比が大きい下肢筋での筋力調節の要求は,課題の難易度が高く,運動の精度を高めるためより多くの注意が必要性であるため,左膝伸展最大筋力が低下したと考えられる。
1 0 0 0 OA 夜間痛を有する肩関節疾患保存治療例に対する理学療法効果と関節注射による影響
- 著者
- 伊藤 創 葉 清規 松田 陽子 室伏 祐介 川上 照彦
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11772, (Released:2020-08-05)
- 参考文献数
- 21
【目的】本研究目的は,肩関節疾患保存例に対して理学療法を行い,初回時の夜間痛の有無における治療経過,また,関節注射による影響を調査し,理学療法の有用性を示すことである。【方法】対象は,肩関節疾患保存例72 例である。初回時の夜間痛の有無で2 群に分類し,また,夜間痛あり群のうち,初診時に関節注射実施の有無で2 群に分類し,治療開始1,3 ヵ月後までROM,動作時VAS,アテネ不眠尺度(以下,AIS)の治療経過の差について解析した。【結果】 夜間痛あり,なし群の経過に交互作用がみられ,夜間痛あり群でROM,動作時VAS,AIS の高い改善度が得られた。また,関節注射併用例で初回から1 ヵ月後で動作時VAS の高い改善度が得られた。【結論】肩関節疾患保存例に対する理学療法により,夜間痛の有無にかかわらずROM,VAS,AIS の改善が得られ,夜間痛を有する場合,関節注射を併用することで早期に疼痛の改善が得られる。
1 0 0 0 OA 離床が循環器系に及ぼす影響について
1 0 0 0 当院での癌終末期理学療法の取り組みについて
- 著者
- 赤尾 健志 寺林 恵美子 大場 正則 水島 朝美 城戸 恵美 高橋 秀幸 山上 亨 八野田 純
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.D1218, 2008
- 被引用文献数
- 1
【目的】当院の癌終末期理学療法では、1.患者・家族のニーズに答える、2.患者・家族の信頼を得る、3.チーム医療を重視することを目標に取り組んでいる。今回、癌終末期理学療法の取り組みを現状と患者・家族のコメントをもとに検討したので報告する。<BR><BR>【対象】2006年4月から2007年9月の間、癌終末期で理学療法を施行し入院中死亡した22名、男性11名、女性11名、平均年齢73.8歳、現疾患は、肺癌16名、大腸癌2名、胃癌2名、肝細胞癌1名、胆嚢癌1名であった。<BR><BR>【方法】理学療法開始時と終了時の理学療法内容とADLレベル、理学療法実施期間、理学療法終了日から死亡までの期間について調べた。また対象者を、理学療法を死亡まで継続可能であった群(以下継続可能群)14名、患者の希望により理学療法を途中で中止した群(以下希望中止群)3名、合併症等の発症により理学療法を中止した群(以下合併症発症群)5名に分類した。それぞれの群に対し、患者・家族のコメントをカルテ等から抽出した。<BR><BR>【結果】理学療法内容は、開始時は、ADL練習19名、肺理学療法5名、筋力運動10名、関節他動運動7名、疼痛緩和・浮腫改善2名であった。終了時は、関節他動運動14名、肺理学療法12名、疼痛緩和・浮腫改善6名、ADL練習1名であった。ADLレベルは、理学療法開始時は歩行レベル7名、車椅子レベル11名、ベット臥床レベル4名であった。終了時は、車椅子レベル2名、ベット臥床レベル20名であった。理学療法実施期間は平均42.6日(7日~170日)であった。理学療法終了日から死亡までの期間は平均4.3日(0日~20日)であった。患者・家族のコメントは継続可能群では、呼吸が楽になった、むくみがとれて足が軽くなった等の身体的改善感の他に、自分の体を触ってもらうことで温もりを感じる、雑談等ゆっくり話ができる、リハビリをするのが生きる支えとなっている等、精神面に関するコメントが見られた。希望中止群では、触ると痛い、歩く練習をすると疲れる等であった。合併症発症群では、脳梗塞発症、消化管出血、呼吸急性増悪等で、急激に全身状態が変化した場合が多かった。<BR><BR>【考察】癌終末期理学療法の現状としては、全身状態が自然経過として次第に悪化していくにも関わらず、理学療法を継続している症例が多く見られた。その理由として、一時的でも身体的改善感が得られること、厳しい現実から少しでも逃避できる癒しの効果、精神的支え等が考えられた。以上より、当院での癌終末期理学療法の取り組みは患者・家族に対し、身体・精神的に良い効果を与えることができているのではないかと思われた。また途中中止になった症例から、患者の状態に応じて少数・頻回のより細かな理学療法内容の検討、また合併症の発症等から、一日一日のリスク管理を含めたチーム医療での情報共有等がより重要だと思われた。<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>
1 0 0 0 OA 長期人工呼吸器管理患者における肺コンプライアンスの関連因子について
- 著者
- 小ノ澤 真一 染矢 富士子 塗谷 栄治
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.411-419, 2020 (Released:2020-10-20)
- 参考文献数
- 42
【目的】長期人工呼吸器管理患者の肺コンプライアンス関連因子を検討すること。【方法】静肺コンプライアンス(以下,Cstat),動肺コンプライアンス(以下,Cdyn)を測定し,無気肺,胸水,自発呼吸の有無に分け2 標本t 検定を行い,換気状態,患者基本データ,血液生化学所見について相関分析を行った。【結果】無気肺がある患者のCstat が有意に低下し,Cstat とCdyn ともにBMI,Rapid shallow breathing index(RSBI),肺胞気動脈血酸素分圧較差,人工呼吸器管理日数に有意な相関を認めた。またCstat では年齢,CRP,肺炎発症回数においても有意な相関を認めた。【結論】Cstat,Cdyn に対する体格の影響は大きく,またCstat は無気肺,肺炎発症回数,炎症性変化に影響を受ける可能性が示唆された。またCstat,Cdyn の低下が換気効率に影響を与える可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 我が国の統合失調症患者に対する運動介入効果に関する文献的考察
- 著者
- 細井 匠 小枩 武陛 石橋 雄介
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11679, (Released:2020-05-27)
- 参考文献数
- 56
【目的】我が国の統合失調症患者に対する運動介入の効果に関して,身体機能の向上,精神症状の改善,ADL の向上,これら3 点についてこれまでの知見を検証すること。【方法】4 種類の電子データベースを用いて,2017 年までの全年代を対象に複数の検索式で検索した。検索結果を統合し,2 回のスクリーニングを実施して採択文献を決定した。【結果】38 編が対象となり,身体機能の向上について記述した30 編,精神症状の改善について記述した24 編,ADL の改善について記述した9 編の内容を検討した。【結論】対応の工夫や精神科治療と併用する必要はあるが,運動介入は統合失調症患者の身体機能の向上,精神症状の改善,ADL の向上に寄与し得ることが示唆された。
1 0 0 0 OA Kaltenborn-Evjenth Systemによる腰痛の評価と治療
- 著者
- 鳥本 茂
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.174-178, 1998-05-31 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA 端座位における側方重心移動動作の運動学的分析
- 著者
- 藤澤 宏幸 星 文彦 武田 涼子
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.268-274, 2001-10-20 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 5
本研究の目的は端座位における側方重心移動時の筋活動と運動力学的関係を明らかにすることである。被験者は健常成人男性10名とし,右側へ側方重心移動した際の左右脊柱起立筋および大殿筋活動,圧中心変動,体幹アライメントを測定した。側方重心移動動作を3分類し,各動作とも速度条件を1)可能な限り速く,2)普通の2条件とした。可能な限り速く側方重心移動した場合,各動作とも初期に圧中心は一旦左側へ移動し,その後急速に移動方向である右側へ移動した。普通の速度という指示で側方重心移動した場合は約半数でこのような機構がみられなくなった。このことより側方重心移動動作における動き始めには各動作に共通する機構が存在すること,またその機構が速度依存性に機能することが示唆された。また,制動に関しては移動側の大殿筋活動および反対側の脊柱起立筋活動が重要であった。脊柱起立筋は高位による活動の違いがみられ,特に下部腰椎部は初期の骨盤運動にも深く関与していると考えられた。
1 0 0 0 OA 苦手な英語で論文をどう書くか:5 つのステップ
- 著者
- 佐藤 春彦 Paul Andrew
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.379-385, 2019 (Released:2019-10-20)
- 参考文献数
- 9
- 著者
- 桑原 知佳 柴 喜崇 坂本 美喜 佐藤 春彦 金子 誠喜
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.7, pp.505-515, 2011-12-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 22
【目的】発達に伴い変化する背臥位からの立ち上がり動作の完成までの,動作パターンおよび動作所要時間の変化を縦断的に調査し,発達に伴う健常児の立ち上がり動作の変遷を明らかにする。【方法】健常児11名を対象とし,平均年齢4歳0ヵ月から1年ごとに6年間継続して立ち上がり動作を観察し,動作パターン,個人内の動作パターンの一致率,動作所要時間の変化を調査した。【結果】立ち上がり動作パターンは,階段状に難易度が高い動作に変化し,8歳10ヵ月以降変化が生じなかった。動作が変化した時期には,個人内でも様々な動作パターンが観察された。また,動作所要時間は発達に伴い短くなり,動作パターンの変化が終了後も短くなった。【結論】縦断調査により,立ち上がり動作は,非線形に変化をしながら9歳頃に完成することが明らかになった。動作獲得においては,個人内・個人間の多様性に富み,個々に適切な動作を選択しながら発達していくことが示唆された。
1 0 0 0 OA 環境・運動・姿勢と自律神経系
- 著者
- 梅原 拓也 梯 正之 田中 亮 恒松 美輪子 村中 くるみ 井上 純子 村上 恒二
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.1-10, 2016 (Released:2017-02-20)
- 参考文献数
- 32
【目的】本研究は,脳卒中患者のADL 回復の対策として,PT,OT およびST の介入量の増加が有効であるかどうかを検討することである。【方法】入院時FIM 運動項目により患者を低群,中群,高群に分類した。各群のFIM 利得に影響する因子の検討のために,ロジスティック回帰分析を行い,抽出された因子ごとにカットオフ値や診断性能を算出した。【結果】対象者と抽出因子数は,低群297 名・5 因子,中群190 名・2 因子,高群170 名・3 因子であった。3 群に共通の因子は,PT とOT の総単位数であった。各群におけるこのカットオフ値・陽性尤度比・陰性尤度比・事後確率は,低群で747 単位以上・2.26・0.63・71.0% であり,中群で495 単位以上・1.5・0.67・62.0% であり,高群で277 単位以上・1.86・0.45・65.0% であった。【結論】重症の者ほど回復は予測しやすいが,より多くの因子でなければ精度の高い予測は難しい。
1 0 0 0 OA 立位大腿拳上動作における体幹・骨盤・大腿リズムの加齢変化
- 著者
- 本島 直之 関屋 昇 山本 澄子
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11570, (Released:2019-09-28)
- 参考文献数
- 34
【目的】立位での大腿拳上運動は日常生活動作と密接な関わりがある。そこで,立位大腿拳上運動を三次元的に解析し,大腿挙上,骨盤傾斜および体幹運動の関係と,それらへの加齢の影響を明らかにすることを目的とした。【方法】対象は健常成人20 名(若年者,高齢者各10 名)とし,運動課題は静止立位と立位からの片脚大腿拳上運動とした。三次元標点計測により体幹傾斜,体幹屈曲,骨盤傾斜,大腿傾斜角度および骨盤と体幹の位置を,床反力計測により足圧中心位置を求め,それらの関係を検討した。【結果】立位姿勢は両群に差は認められなかった。骨盤後傾,骨盤側方傾斜および体幹前屈運動は若年者,高齢者ともに大腿挙上角度に対して一定の割合で直線的に増大し,その割合は高齢者において小さかった。【結論】立位での大腿挙上運動における体幹・骨盤・大腿リズムの存在と加齢の影響が明らかとなり,大腿挙上運動を評価する際に体幹も含めて行う必要性が示唆された。
1 0 0 0 OA 超高齢者大腿骨頸部骨折の歩行自立と自宅退院における問題点
- 著者
- 辻村 康彦 高田 直也
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.5, pp.303-306, 2006-08-20 (Released:2018-08-25)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
超高齢者大腿骨頸部骨折の治療目標である,歩行自立能力の獲得や自宅退院は,身体・精神機能や社会的要因などの諸問題により困難を極めているのが現状である。そこで,当院にて治療を行った90歳以上の29例を対象に,退院時歩行能力,自宅退院率,自宅退院患者のADL能力の経時的推移につき調査し,その問題点を検討した。退院時歩行自立能力の獲得には,認知症の有無が大きな影響を与えていたが,合併症数は,ほぼ全例が複数の合併症を有していたことからそれによる影響はなかった。また,認知症に関しては,単に計画的な術後リハビリテーションの遂行が困難であることのみではなく,徘徊の危険性から患者家族の多くが,患者の積極的な歩行を望んでいないという特徴があった。また,自宅退院を困難とする原因は,歩行自立の可否よりも,超高齢者世帯における介護者自体が高齢者であることや,介護可能者数不足などの受け入れ体制の不備であった。一方,ADL自立レベルにて自宅退院した症例に対しては,家庭環境整備や外来通院での経過管理がその能力維持に有効であった。