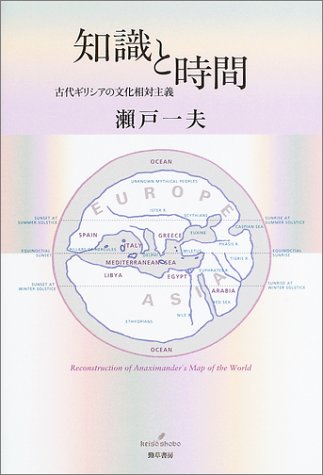- 著者
- 久保田 健市 吉田 富二雄
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.116-124, 1995
Two studies using the minimal group paradigm were conducted to investigate the intergroup discrimination in an experimentally created minority and majority groups. In both studies, subjects were divided into the minority and the majority group by drawing lots, and asked to allocate points between other ingroup members and outgroup members. In the first study, it was found that the minority group showed significant ingroup favouritism whereas the majority group did not. The minority group was more aware of their membership in the group than their counterpart. In the second study, subjects were led to believe that the minority group and the majority group had either similar or different social attitude. On the whole, both the minority and the majority group favoured a similar group and discriminated against a dissimilar group. The effects of attitudinal similarity in minimal groups were discussed.
1 0 0 0 IR 東儀兼頼撰『龍笛吹艶之事』と江戸時代初期の龍笛の系統
- 著者
- 寺内 直子
- 出版者
- 神戸大学大学院国際文化学研究科
- 雑誌
- 国際文化学研究 (ISSN:13405217)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.1-43, 2010-07
1 0 0 0 舞楽《還城楽》の舞踊構造の複相性--舞譜の譜字分析より
- 著者
- 上野(一柳) 智子
- 出版者
- 比較舞踊学会
- 雑誌
- 比較舞踊研究 (ISSN:13440578)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.12-23, 2009-03
- 著者
- 杉田 英明
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻
- 雑誌
- Odysseus (ISSN:13450557)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.1-29, 2014
- 著者
- 三牧 聖子
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 日本政治學會年報政治學 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.1_306-1_323, 2008
This thesis revisits “Twenty Years’ Crisis” and considers what E. H. Carr means by “realism.” Since the 1990s, many works have challenged the stereotyped picture of a “realist Carr.” Now we know much about a “non-realist” Carr, but there still remain a lot of questions about Carr's “realism.” Contrary to the prevailing image of anti-idealism, Carr's “realism” is a “weapon” to demolish the inequalities between nations, and to rebuild a more equal order. <br> During the 1930s, the “idealists” such as Norman Angell and Leonard Woolf abandoned their optimistic beliefs in public opinion, and advocated the League sanctions against the fascist countries. Together with the pacifists, Carr criticized the League sanctions as a superficial solution, and insisted that the fundamental problem was the inequalities between the “have” and “have-not” countries. His criticisms toward the League were not a denial of the League itself. He criticized the “Coercive League,” which was hostile to the “have-not” countries, but supported the “Consultative League,” which functioned as a forum between the “have” and “have-not.” <br> Now we are in the long fight against terrorism. Global terrorism is, in part, a reaction to global inequalities. Carr's “realism” tells us that military actions alone never beat global terrorism.
- 著者
- 貴堂 嘉之
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.39, pp.21-42, 2005
1 0 0 0 IR 南極湖沼における藻類群集の光生理・生態学的研究
- 著者
- 河村 徳士
- 出版者
- 城西大学
- 雑誌
- 城西大学経済経営紀要 (ISSN:03866947)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.43, pp.23-62, 2020-03
通巻第43号
- 著者
- 成戸 浩嗣
- 雑誌
- 愛知学泉大学紀要 = Aichi Gakusen University Review (ISSN:24344923)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.97-114, 2020-03-25
1 0 0 0 科学的な嘘でも嘘はやっぱり嘘であることについて(時評)
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.11, pp.758-759, 1958
1 0 0 0 OA 第14回 薬学から官庁データサイエンティストへ
- 著者
- 服部 雄太
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.242-243, 2018 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 5
筆者は6年制薬学課程の2期卒業生にあたる.学部時代は環境毒性学の実験研究をし,卒業後は博士課程に進んだ.その後,国家公務員総合職試験合格を機に,より大きい調査とデータを求めて総務省へ入省した.行政官として働く傍ら,ヘルスケアIoT コンソーシアム(internet of things: IoT)への参画など、統計に軸をおく公衆衛生学者としての活動も続けている.本稿では,大学院での研究生活と総務省での統計の仕事についてつづり,薬学から大学院,そして公衆衛生や行政・社会科学の分野に進むキャリアパスの一例としてご紹介したい.
1 0 0 0 OA 鳥居川流域の河川災害と地形
- 著者
- 松岡 保正
- 出版者
- 長野工業高等専門学校
- 雑誌
- 長野工業高等専門学校紀要 (ISSN:02861909)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.27-36, 1995-12-28
There lie two quiescent volcanoes and three canyons in the basin of the Torii River. In time of heavey rainfall, driftwoods and gravels are produced in theese areas. Sometimes they cause hydrospheric disaster. On the other hand, these areas are kept in reratively good condition. So we must pay due regard to natural river ecosystems. A good cooperation between engineers, ecologists, and similar experts paired with the work of good service team is essential to water resources management and maintainance.
1 0 0 0 IR 鳥居川流域の河川災害と地形
- 著者
- 松岡 保正
- 出版者
- 長野工業高等専門学校
- 雑誌
- 長野工業高等専門学校紀要 (ISSN:02861909)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.27-36, 1995
There lie two quiescent volcanoes and three canyons in the basin of the Torii River. In time of heavey rainfall, driftwoods and gravels are produced in theese areas. Sometimes they cause hydrospheric disaster. On the other hand, these areas are kept in reratively good condition. So we must pay due regard to natural river ecosystems. A good cooperation between engineers, ecologists, and similar experts paired with the work of good service team is essential to water resources management and maintainance.
1 0 0 0 OA 「美術」と「美術教育」の距離 : 近代以降の展開を辿って
- 著者
- 神野 真吾
- 出版者
- 美術科教育学会
- 雑誌
- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.205-218, 2006-03-31 (Released:2017-06-12)
明治期に,西欧の制度を移入し,美術という言葉が生まれて以降,日本においては,美術家たちによって実践される「美術」と,教育現場で行われる「美術教育」の間に,次第に距離が生じ,断絶した状況が生じている。その一方で生涯学習をはじめ,一般市民の美術は,「美術」「美術教育」いずれともほとんど関わりを持たずに,盛んに取り組まれている現実がある。こうした混沌とした状況の中,現在,美術・美術教育をとりまく環境は大変厳しいものとなっている。今こそ,我々は近代化の中で美術と美術教育が辿ってきた道程を顧み,私たち日本人にとって必要な美術の在り方を,構築する必要があるのではないだろうか。
1 0 0 0 知識と時間 : 古代ギリシアの文化相対主義
1 0 0 0 OA 合意形成問題における“計画修正可能性”と“謝罪”の決定的役割
- 著者
- 藤井 聡
- 出版者
- 一般財団法人 運輸総合研究所
- 雑誌
- 運輸政策研究 (ISSN:13443348)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.002-009, 2004-10-29 (Released:2019-05-31)
- 参考文献数
- 17
交通ネットワーク整備をはじめとする様々な交通政策を実施する際に近隣住民の合意が得られず,それ故にその政策を実施できないという局面は年々増加しているものと考えられる.こうした合意形成の問題に対処すべく,本稿では,社会的ジレンマ(藤井,2003)の理論的枠組を用いて社会状況を捉えることで,人々が特定の政策に対して合意する傾向を促進できる可能性を,社会心理学的アプローチに基づいて探る.特に,行政手続きに対する公正感(i.e. 手続き的公正)と行政に対する信頼の重要性を指摘するとともに,それらの高揚を目指すためには計画の修正可能性を担保すること,そして,計画上の誤りが明らかとなった場合には行政側の謝罪が決定的な役割を演ずることを理論的に指摘する.
1 0 0 0 OA 日中対照研究方法論(3) : “V+O+给・N”表現をめぐる日中対照(上)
- 著者
- 成戸 浩嗣
- 雑誌
- 愛知学泉大学現代マネジメント学部紀要 = The Gakusen contemporary management review
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.25-40, 2017-03
1 0 0 0 OA 歯科医療用機能水の氷結保存前後における諸性質の変化
- 著者
- 吉田 康一 吉田 隆一 伊東 智美 殿内 利夫 斎藤 達哉 瀧谷 佳晃 河野 哲 吉田 隆一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
- 雑誌
- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.6, pp.456-473, 2015 (Released:2016-01-06)
- 参考文献数
- 37
目的 : 強酸性水中の塩素酸や次亜塩素酸は大気に触れると反応し分解する. 水が凝固する際は食塩等溶解物を析出し純水に近い形で凍結するが, 電解機能水を氷結して固体で保存すれば対流はなく酸素との接触面は固定化され, 内部成分を保護でき, 殺菌力を維持した長期保存が可能になると考えた. 装置での機能水生成条件を変えて獲得した, さまざまな強酸性電解水と強アルカリ性電解水を氷結し, 保存条件を変えて解凍液の諸性質の変化を調べ, 最適な使用条件を求めた. 材料と方法 : 可変電圧 (0~90V), 直流電流 (0~10A, 整流), 貯留式の二室型機能水製造装置を試作した. 装置は生成される機能水の性状を大幅に変えることができる. 食塩水の電解により得られた酸性水とアルカリ性水を氷結前に10ml採取し, pHとORP値 (mV), 残留塩素濃度 (ppm) の測定を行った. 両水溶液は容器 (80ml) に各60mlを注入し, −17°Cの冷凍庫にて氷結した. 24, 168時間後に容器を取り出し, 室温 (23°C) で約2時間放置して解凍し, 性状を再度計測した. 分析は, 食塩添加率 (要因A) ; 3水準 (0.3, 0.6, 0.9wt%), 電解電流 (B) ; 2水準 (2, 4A), 保存方法 (C) ; 2水準 (容器の密閉の有無), 氷結時間 (D) ; 2水準として, ランダムに繰り返し3回行い, 測定値を項目別に四元配置分散分析した. さらに, 氷結保存の方法と期間が水溶液に与える影響のみを, 同データからWelchのt-testによって検定した. 機能水生成直後の諸性質の測定値に対して, 同一液で氷結解凍後に得られた値を直線方程式にて回帰分析した. 成績 : 分析から酸性電解水では, pHは解凍液でも2.2以内の酸性度を維持した. ORP値は容器の密閉を行う短期間保存で高い値を維持したが, いずれの条件でも解凍液は1,100mV以上だった. 塩素濃度 (ppm) は氷結保存の前後で263ppmから経時的に減少したが, 食塩添加率と電解電流値を高くし, 容器の密閉でこれを抑制できた. 密閉保存, 168時間氷結の解凍液でy=0.5251x−36.212 (r=0.919**) であった. 開栓でも多種の生成・保存条件の解凍液で, 薬事法上の殺菌料としての強・弱酸性次亜塩素酸水に近似した性状を獲得した. アルカリ性水では, pHは生成時の電解電流が高ければ解凍液でもわずかにアルカリ側に傾いた. ORP値は−849.2から解凍後に+224.94~301mVに転じたが, 容器の密閉によって上昇を抑制できた. 結論 : 生成・保存条件の調節により, 容器を開栓し168時間の氷結保存で解凍した酸性電解水でも十分な殺菌能が維持されており, 密閉保存すればこれが向上した. 解凍アルカリ性電解水では, 市販清掃用アルカリ性水に近似した性状であった. 氷結保存法により解凍後も殺菌能をもつ機能水を獲得でき, 人体への臨床応用の可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 「事業仕分け」をきっかけに思う
- 著者
- 堀 浩一
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-2, 2010 (Released:2010-10-22)