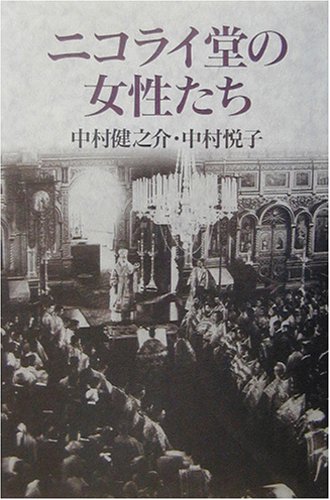2 0 0 0 OA ロシアと第一次世界大戦の原因
- 著者
- 今野 茂充 Shigemitsu KONNO
- 出版者
- 東洋英和女学院大学大学院
- 雑誌
- 東洋英和大学院紀要 = The Journal of the Graduate School of Toyo Eiwa University (ISSN:13497715)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.21-41, 2013-03-15 (Released:2013-07-08)
The debate on the origins of the First World War remains one of the most contested issues in the study of International History and International Relations (IR). Considering that almost a century has passed since the outbreak of the war, it is remarkable that the latest historiography, based on newly available primary sources, can still revitalize the debate and undermine some of the orthodoxinterpretations of the origins of the war. The controversy over the share of responsibilities for the outbreak of the war is typical of this trend. Instead of excessively focusing on Germany as the single prime mover in 1914, many recent historical researches consider a reapportionment of responsibilities among the European great powers for starting the Great War. Taking recent developments into account, this article seeks to examine and evaluate the role of Russia in the origins of the war from a theoretical perspective. The first section of the article traces the development of tensions between Russia and the Central Powers. The second section examines whether major IR theories, such as the offense-defense theory and the preventive war theory, can apply to the Russia's case from the defeat of Russo-Japanese war to the outbreak of the First World War. This article does not intend to demonstrate that Russia should bear the sole responsibility forstarting the First World War. However, even this brief study proves convincingly that Russia played a greater role on the outbreak of the First World War than is generally acknowledged in the recent literature of IR theories.
東北地方縄文人のミトコンドリアDNAの遺伝子型を明らかにすべく、東北大学所蔵の東北地方縄文人骨・計35個体を試料としてDNAを抽出し、ミトコンドリアDNA(mtDNA)解析によりこれら人骨の遺伝子型を明らかにすることを目的として研究を進めた。すべての試料について、control regionおよびcoding regionの塩基置換をダイレクトシークエンス法およびamplified product-length polymorphism(APLP)法を用いて検出した。得られた結果をもとに、現代人のデータベースを用いて東北縄文人骨のmtDNAをハプログループに分類した。検査した35個体のうち、14個体について結果が得られた。観察されたハプログループは、N9b(7個体)、M7a(6個体)、D4b(1個体)の3種類であった。前年度までの研究で「縄文的遺伝子型」の有力な候補の一つと推定されたハプログループN9bは全体の50%と高頻度に観察され、北海道縄文人の分析結果と併せ考えれば、このハプログループが「縄文的遺伝子型」の一つであることは、少なくとも北日本においてはほぼ間違いないものと考えられた。しかし、北海道縄文人と比較すると、東北縄文人ではM7aが著しく高頻度であり(北海道で6.4%に対して東北では42.9%)、北海道でみられたD1aおよびG1bが観察されず、現代日本人で主体的なハプログループであるD4bが1個体のみではあるがみられるなど、これらの縄文人集団は遺伝的に必ずしも近縁であるとはいえないと考えられた。なお、東北縄文人の分析結果は既報の関東縄文人の分析結果とも大きく異なっており、今回の結果から縄文時代には既に日本人に遺伝的地域差がみられた可能性が示唆された。
2 0 0 0 OA ストレプトマイシン利用によるブドウの無核果生産技術の確立 (1)
2 0 0 0 ラマ属家畜の国内における飼育管理状況について
2 0 0 0 OA 安定オーステナイト系ステンレス鋼の加工硬化と変形組織に及ぼす炭素および窒素の影響
- 著者
- 吉武 睦海 土山 聡宏 高木 節雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.6, pp.223-228, 2012 (Released:2012-05-31)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3 22
Stable austenitic stainless steels containing 0.1 % carbon and nitrogen (Fe-18%Cr-12%Ni-0.1%C and Fe-18%Cr-12%Ni-0.1%N alloys) were tensile-tested to clarify the difference between the effects of carbon and nitrogen on the work hardening behavior as well as the deformation microstructure development in austenite. The carbon-added steel exhibited a much larger work hardening rate than the nitrogen-added steel in the high strain region (true strain > 0.25) although the dislocation accumulation was more significant in the nitrogen-added steel. EBSD analysis revealed that deformation twins were more frequently formed in the carbon-added steel, which leads to the TWIP effect. The reason why the nitrogen-added steel showed the less twinning behavior seemed to be mainly related with the short range order (SRO) composed of Cr and N atoms.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.453, pp.48-53, 2008-08-08
2008年5月に、大日本コンサルタントの吉岡勉さん(33)が書いた論文「斜材の実損傷による鋼トラス橋の振動特性変化に関する一検討」が、土木学会第54回構造工学シンポジウム論文賞を受賞した。114編ある査読付きの論文のうち、受賞したのはわずか5編だ。 「既設の橋を適切に維持管理するために、モニタリングは重要だ。
- 著者
- Okada Susumu Oshiyama Atsushi
- 出版者
- American Physical Society
- 雑誌
- Physical review B (ISSN:10980121)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.23, pp.235402, 2003-12
- 被引用文献数
- 26
We report electronic structures and stabilities of rhombohedral C60 polymers by using the local spin-density approximation in the framework of the density-functional theory. Owing to hybrid networks of sp2-like (threefold coordinated) and sp3-like (fourfold coordinated) carbon atoms, the electronic structures of these polymers are considerably different from that of a face-centered cubic (fcc) C60. We find that polymerized structures attained at the double bonds are semiconducting whereas polymerized structures attained at single bonds are metallic. Significant overlap of the wave function in the space among three adjacent C60 causes the metallic behavior on the latter polymers. We also find that the stacking ordering strongly affects the conducting properties of the metallic polymers. Despite substantial density of states at Fermi level, the C60 polymers do not exhibit any magnetic ordering. Total energy calculations show that the metallic C60 polymers have higher total energy than the semiconducting C60 polymer phases.
2 0 0 0 OA アンドレ・ブルトンの「狂人の芸術、野の鍵」(2)
- 著者
- 長谷川 晶子
- 出版者
- 千葉大学
- 雑誌
- 千葉大学社会文化科学研究 (ISSN:13428403)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.133-141, 2004-02-01
2 0 0 0 OA 脚本家・水木洋子と映画『あれが港の灯だ』
- 著者
- 内藤 寿子
- 出版者
- 湘北短期大学
- 雑誌
- 湘北紀要 (ISSN:03859096)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.95-107, 2008-03-31
映画『あれは港の灯だ』(今井正監督 水木洋子脚本 1961 年 東映)は、「李承晩ライン」を舞台に、日本漁船で操業する在日韓国人青年の葛藤を描いた作品である。この作品は、日本と朝鮮半島のはざまで生きざるをえない「在日」のアイデンティティーの問題を先駆的にとらえた作品だといえ、現在、高く評価されている。本稿では、『あれは港の灯だ』の脚本を執筆した水木洋子に着目し、映画の製作過程の一端を明らかにした。
2 0 0 0 IR 「名」と「像」の葛藤--「偶像崇拝」の問題をめぐって
- 著者
- 谷口 知子
- 出版者
- 筑波大学哲学・思想学会
- 雑誌
- 哲学・思想論叢 (ISSN:02873702)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.35-47, 2000-01
2 0 0 0 ニコライ堂の女性たち
- 著者
- 中村健之介 中村悦子著
- 出版者
- 教文館
- 巻号頁・発行日
- 2003
2 0 0 0 OA 口絵1:伊東沖海底火山 (手石海丘) の噴火
- 著者
- 加藤 茂
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.2, pp.Plate1-Plate3, 1990-04-25 (Released:2009-11-12)
2 0 0 0 OA アルツハイマー型認知症に対する 半夏白朮天麻湯の有効性
- 著者
- 中江 啓晴 熊谷 由紀絵 小菅 孝明
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.104-107, 2013 (Released:2013-09-13)
- 参考文献数
- 12
アルツハイマー型認知症は認知症の半数を占め,認知機能障害が徐々に進行する。半夏白朮天麻湯をアルツハイマー型認知症患者に投与し,その有効性を検討したので報告する。対象はアルツハイマー型認知症患者72例。初診時に全例に改訂長谷川式認知症スケール(HDS-R)を実施した。同日から半夏白朮天麻湯エキスの内服を開始し,4週間後にHDS-R で再評価を行なった。評価可能であった患者は72例中64例であった。64例の内訳は年齢79.9±6.0歳(63-89歳),性別は男性33例,女性31例であった。半夏白朮天麻湯エキス投与前のHDS-R は15.5±5.2点であり,投与4週間後のHDS-R は16.9±6.2点と有意に改善を認めた(p < 0.01)。家族の目から見て認知機能が改善したものは13例(20.3%)であった。半夏白朮天麻湯のアルツハイマー型認知症の認知機能障害に対する有効性が示唆された。
- 著者
- 岡本 聖 入江 伸
- 出版者
- 大学図書館研究編集委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, pp.33-42, 2012-08
2 0 0 0 平成10年度教養的科目系別非常勤講師率一覧
- 出版者
- 金沢大学
- 雑誌
- 金沢大学教養教育機構研究調査部報 (ISSN:13439049)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, 1999-03
2 0 0 0 非常勤講師の現状から (婦人労働者,その現状とたたかい)
- 著者
- 小沢 京子
- 出版者
- アドバンテ-ジサ-バ-
- 雑誌
- 教育評論 (ISSN:00235997)
- 巻号頁・発行日
- no.309, pp.32-33, 1974-08
- 著者
- 上村 英明
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 世界 (ISSN:05824532)
- 巻号頁・発行日
- no.463, pp.p143-147, 1984-06
2 0 0 0 検討 オーストラリアの大学非常勤講師--雇用問題を中心として
- 著者
- Okada Susumu Otani Minoru Oshiyama Atsushi
- 出版者
- American Physical Society
- 雑誌
- Physical review B (ISSN:10980121)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.20, pp.205411, 2003-05
- 被引用文献数
- 96 93
We report total-energy electronic structure calculations that provide energetics of encapsulation of various fullerenes in carbon nanotubes and electronic structures of resulting carbon peapods. We find that the electron states of the peapods depend on the space in the nanotubes and that they reflect electron states of the encapsulated fullerenes. The deep energy position of the lowest unoccupied state of fullerenes as well as hybridization between π states of the fullerenes and the nearly free-electron states of the nanotubes causes a multicarrier character in the peapods.
2 0 0 0 079 積雪寒冷地における全天候型遊び場の屋根のある公園としての特徴 : 旭川市・カムイの杜公園わくわくエッグを事例として(公共空間・居住,講演研究論文・計画技術報告・研究委員会報告)
- 著者
- 田川 正毅
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会北海道支部研究報告集 (ISSN:13440705)
- 巻号頁・発行日
- no.79, pp.313-318, 2006-07-01