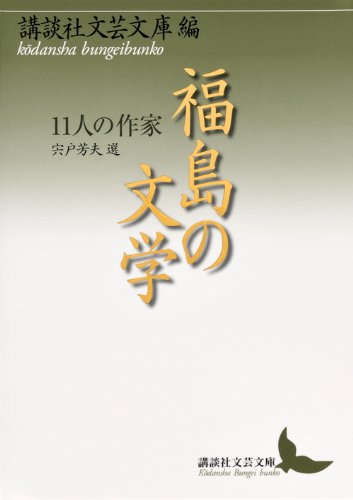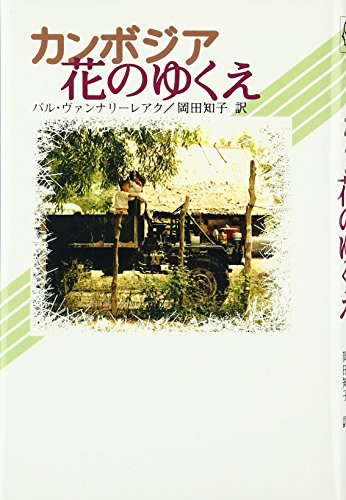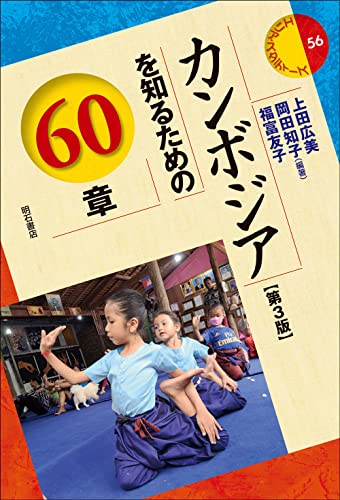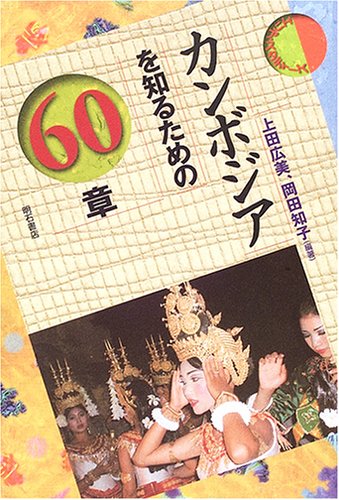1 0 0 0 OA 現代日本の青年期の男女における善悪に関する意識構造と道徳領域判断(2)「善さ」について
- 著者
- 阿部 洋子
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学文学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF LITERATURE (ISSN:13481444)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.A111-A128, 2010-03
子どもたちの道徳心は、誰がどのように育成しなければよいのだろうか。家庭での躾、学校での道徳の授業、地域社会での関係性のあり方などが重要であろう。しかし、現代の日本の青少年を取り巻く環境は、道徳心を育成するための場としての機能をどの程度、果たすことができているのだろうか。また具体的にどのような機能が失われていまったのだろうか。\n Smetana 等(1983)は、道徳・社会的慣習・個人のそれぞれの領域に属すると判断された行為を列挙して貰い、続いてそれらの行為は、規則の有無に関わらず、即ち法律による罰則規定の有無に関わらず、「善い/悪い」と思うかの判断を求めた。その結果、19-20 歳以上になれば、道徳領域に属する行為は、75-100% の範囲で、規則や期待の有無に関わらず(「規則随伴性」と称する)、「善い/悪い」と判断することができるようになる。一方、個人領域に属する行為は、88-100% の範囲で、個人の自由に任せる方がよい(「個人決定権」と称する)と判断されると報告している。ところで、道徳と類似する概念として、社会的慣習があるが、それらの行為は、道徳領域に属する行為における、規則随伴性と善悪の判断の間に見られる強い関係性は見出せなかった。つまり、Turiel(1983)が述べるように、道徳領域と社会的慣習領域は、異なる行為として認識されていると結論づけている。\n これまでも予備的調査を実施(阿部;1996, 1998, 2005)し、現代の日本における道徳構造の特徴を、領域判断、悪さの程度、社会的文脈などから検討してきた。2007 年の報告では、青年期女子を対象としたが、今回は、青年期男女を対象とし、善悪両方の行為について調査を実施した。なお紙数の関係で、前回の結果報告(阿部;2009)は「悪さ」についてのみを行った。今回は「善さ」についての報告を行う。
1 0 0 0 OA 現代日本の青年期の男女における善悪に関する意識構造と道徳領域判断(1)「悪さ」について
- 著者
- 阿部 洋子
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学文学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF LITERATURE (ISSN:13481444)
- 巻号頁・発行日
- no.42(2), pp.A73-A86, 2009-03
子どもたちの道徳心は、誰がどのように育成していけばよいのだろうか。家庭での躾、学校での道徳の授業、地域社会での関係性のあり方などが重要であろう。しかし、現代の日本の青少年を取り巻く環境は、道徳心を育成するための場としての機能をどの程度、果たしているだろうか。また具体的にどのような機能が失われてしまったのだろうか。\n Smetana 等(1983)は、道徳・社会的慣習・個人のそれぞれの領域に属すると判断された行為を列挙して貰い、続いてそれらの行為は、規則の有無に関わらず、即ち法律による罰則規定の有無に関わらず、「善い/悪い」と思うかの判断を求めた。その結果、19-20 歳以上になれば、道徳領域に属する行為は、75-100%の範囲で、規則や期待の有無に関わらず(「規則随伴性」と称する)、「善い/悪い」と判断することができるようになる。一方、個人領域に属する行為は、88-100%の範囲で、個人の自由に任せる方がよい(「個人決定権」と称する)と判断されると報告している。また、道徳と類似する概念として、社会的慣習があるが、それらの行為は、道徳領域に属する行為における、規則随伴性と善悪の判断の間に見られる強い関係性は見出せなかった。つまり、Turiel(1983)が述べるように、道徳領域と社会的慣習領域は、異なる行為として認識されていると結論づけている。これまでも予備的調査を実施(阿部;1996、1998、2005)し、現代の日本における道徳構造の特徴を、領域判断、悪さの程度、社会的文脈などから検討してきた。前回の報告(阿部;2007)では、青年期女子を対象としたが、今回は、青年期男女を対象とし、善悪両方の行為について調査を実施し、性差について比較検討を試みた。なお紙数の関係で、今回の結果報告は「悪さ」についてのみを行う。次回は「善さ」についての報告を行う予定である。
1 0 0 0 OA 攻撃行動に対する中学生の善悪判断と判断に影響を与える要因の検討
- 著者
- 金綱 祐香 濱口 佳和
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.87-102, 2019-06-30 (Released:2019-12-14)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 5 6
中学生のいじめ問題は深刻であり,学校現場における道徳的判断力の育成が求められている。本研究では,中学生に攻撃動機や形態の異なる四つの攻撃場面を提示し,場面の違いによって,加害者の悪さの程度の判断及びその判断理由がどのように異なるかをTurielの社会的領域理論に基づいて検討した。また,そうした善悪判断に影響を与えると考えられる個人要因・環境要因を取り上げ,善悪判断への影響を調査した。はじめに,中学生410名への予備調査をもとに判断理由尺度を作成し,その後,中学生1,022名を対象に,作成した判断理由尺度を用いて本調査を実施した。その結果,仕返しを動機とした攻撃は,慣習領域や個人領域の理由から加害行為が許容されやすいこと,言語的攻撃よりも関係性攻撃の方が道徳領域の理由が多く用いられ,より悪いと判断されることが明らかとなった。また,個人要因では,特に女子における罪悪感特性の高さが,環境要因では,教師の自信のある客観的な態度が,望ましい善悪判断を促進することが明らかとなった。以上の結果から,いじめ抑止に向けた指導や学級運営について議論された。
1 0 0 0 OA 製薬会社における錠剤粉砕または簡易懸濁法に関する医薬品情報の実態調査
- 著者
- 秋山 滋男 新井 克明 輿石 徹 石田 志朗 倉田 なおみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本医薬品情報学会
- 雑誌
- 医薬品情報学 (ISSN:13451464)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.220-226, 2019-02-28 (Released:2019-03-21)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
Objective: We conducted a survey on drug information accumulated by pharmaceutical companies about the adequacy of administration of crushed or simply suspended internal medicines through enteral feeding tube, examination methods to confirm adequacy and inquiries from medical institutions to pharmaceutical companies about the adequacy of these methods.Methods: We sent a questionnaire to 162 pharmaceutical companies that sell internal medicines to collect information. The survey was conducted from May 1, 2016 to March 31, 2017.Results: The questionnaire response rate was 61% (99 companies responded). Eighty and 90 percent of the companies possessed information about the drug crushing methods and simple suspension methods used for administration of internal medicines,respectively. The type of information and examination methods used varied among the companies, was very limited, and was often limited to new drugs. The information acquisition rate about crushing methods was 69.3% in original examination methods of pharmaceutical companies. On the other hand, 90.3% of the information about simple suspension methods was obtained by the unified method of Hand Book of Simple Suspension Method.Conclusions: In the future, medical practice and patients will benefit if examination methods to confirm the adequacy of crushing and administration through feeding tubes are commonly and consistently obtained by pharmaceutical companies. Furthermore, it would be very useful for information of crushing methods and simple suspension methods to be included in package inserts and interview forms.
- 著者
- 足立 眞理子
- 出版者
- 経済理論学会
- 雑誌
- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.6-21, 2010-10-20 (Released:2017-04-25)
- 被引用文献数
- 1
This paper takes a Marxist Feminist perspective to consider how the newly established field of Feminist Economics of the 1990s extended into labor theory. The debate on S. Himmelweit's 1995 extension of feminist economics to labor theory rested on three conditions defining the concept of labor: the generation of opportunity cost, the social division of labor, and third party substitution. According to Himmelweit, if all three conditions are present, one can define the situation as "labor." This serves as the basis of today's feminist economics. The debate, however, centers on the concept of "caring." The concept of caring is in itself a critique of the modernist dualist system of economics that poses "labor" against "non-labor." At the same time, only the concept of care contains the possibility of alienation from the concept of labor because the condition of third-party substitution is not necessarily satisfied. However, this method means simultaneously specified regardless of the criticism to capitalist market economy which the Marxist feminism mainly described. This argument takes the feminist concept of unpaid labor as socially necessary labor to social reproduction. Today we have reached a new concept of reproductive labor. But this concept was arrived at by cutting off the critique of the capitalist market economy which is the source of Marxist Feminist thought. The reason is because the concept of labor was influenced by the English Rubin School's interpretation of labor theory, which was the standard for Marxism in the West. In this paper I will newly elucidate the concept of labor by including the critique of the capitalist market economy which has long been the theme of Marxist Feminism. I do this by clarifying the points of difference in "value" of the labor force for Marx and the classical school's regular equilibrium theory, especially considering the contrast with Ricardo. And, as a response to questions raised by Marxist Feminism, I further argue that unlike classical economics which takes the family unit for its basis, the Marx model is non-converging, based on 'the individual and his/her own child' what one might call the 'single parent model.' I open the argument by a broad discussion of what the Uno School terms as 'muri' in the commodification of labor power in relation to the Marx model. That is, I clarify a theoretical contribution of Marxist feminism, the relative autonomy and articulation between the productive sphere and the reproductive sphere. That is, I argue that 'muri' exists not only in the commodification of labor, but also in the pre-commodification stage as well as in the stage after commodification. One could say that the theorization of history in Marxian analysis is analogous in value to feminist and gender analysis of contemporary globalization.
1 0 0 0 OA 自己回復性高強度ゲルの力学物性
- 著者
- 眞弓 皓一 成田 哲治 Costantino CRETON
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子論文集 (ISSN:03862186)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.10, pp.597-605, 2015-10-25 (Released:2015-10-23)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
高分子ゲルを高強度化する有効な分子設計として,共有結合などの強い結合と水素結合などの弱い結合を架橋点として導入する手法が提唱されている.弱い可逆な架橋点はゲルが変形した際に解離し,その時のエネルギー散逸によってゲルのマクロな破壊を防ぐことができる.また,変形したゲルから外力を取り除くと,強い結合に由来するネットワークの弾性によって,ゲルは元の形状まで復元し,可逆架橋点も再結合して元の状態まで戻る.筆者らは,このような自己回復性高強度ゲルのモデル系として,ポリビニルアルコール(PVA)を共有結合とホウ酸イオンによる可逆結合で同時架橋したDual Crosslink (DC)ゲルを開発し,その力学特性を調べてきた.本報では,可逆架橋点の解離・再結合ダイナミクスがDCゲルの線形粘弾性,ヒステリシスループを含む大変形挙動,および破壊挙動とどのように相関しているのかについて解説する.
- 著者
- 大澤 公一
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.150, pp.71-85, 2011 (Released:2017-02-17)
- 参考文献数
- 10
大学修学能力試験(CSAT),日本留学試験(改定前EJU),日本語能力試験(改定前JLPT)に出題された非音声領域の既出757項目,および日本語Can-do-statements(CDS)尺度60項目によるモニター試験を韓国内で実施した(N=4,647)。項目反応理論の2母数ロジスティックモデルを適用して3試験に共通する一次元の日本語能力を尺度化した結果,各試験の項目困難度の分布の中央値を基準としてCSAT,JLPT4級,3級,2級,1級,EJUのように難易度の序列が付与された。次にCDSの達成困難度と3試験の難易度との対応付けを一般化部分得点モデルによって行った。その結果,韓国語母語話者においては「話す,聴く」課題より「読む,書く」課題の方が達成困難であると考えられていることが判明した。これに加え,3試験の難易度を質的に解釈するための言語4技能別のCDS達成困難度パラメタが付与された。
1 0 0 0 OA 情報科の入試問題に関する一考察
筆者らは、情報処理学会情報入試委員会の委員として、情報入試の問題案や、過去に出題された情報関係基礎の問題の解説などを掲載する情報処理学会会誌note 「教科「情報」の入学試験問題って?」に関わってきた。この連載を通して、筆者らは、情報科の入試問題について、経験的な知見などを得た。過去に出題された「情報関係基礎」の問題、大学入試センターから発表されている試作問題等、その他の各問題について述べ、また、学習と試験の観点、情報科の内容との関係、問題の評価観点との関係、他教科・他科目における状況、他国における状況を議論した。入試で問うべき観点は、「思考力・判断力・表現力」を重視すべきであり、学習指導要領の範囲であっても、範囲外であっても、知っていると簡単に正解を得ることができるような問題は好ましくない、との結論を得た。
- 著者
- 江口 大輔
- 出版者
- 明治大学文学部文芸研究会
- 雑誌
- 文芸研究 : 明治大学文学部紀要 (ISSN:03895882)
- 巻号頁・発行日
- no.120, pp.203-214, 2013
- 著者
- TOMOHITO NAGAOKA AKIO SHIZUSHIMA JUNMEI SAWADA SOICHIRO TOMO KEIGO HOSHINO HANAKO SATO KAZUAKI HIRATA
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- Anthropological Science (ISSN:09187960)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.2, pp.105-113, 2008 (Released:2008-08-27)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 27 33
The purpose of this study was to develop new standards for determining the sex of fragmentary human skeletal remains. We measured height, width, and length of the mastoid process in medieval to early modern Japanese skeletons, from the Yuigahama-minami and Hitotsubashi sites, in order to provide a metric standard for the diagnosis of sex using the mastoid process. We calculated discriminant functions based on these measurements; the accuracy of sex classification was over 80% using a single variable, and reached 82–92% with two variables, mastoid height and width. This accuracy is equal to or better than that reported by some previous studies of sex determination using the cranium. However, when we examined intra- and interobserver errors in the mastoid process measurements, we found a high level of errors, and this highlights the difficulty involved in intraobserver repeatability and interobserver reproducibility. Our results imply that, in order to achieve reliable results of sex determination using the mastoid process, the measurement methods need to be carefully determined and executed.
1 0 0 0 福島の文学 : 11人の作家
1 0 0 0 東野辺薫著作目録
- 著者
- 福島県立図書館調査相談室[編]
- 出版者
- 福島県立図書館
- 巻号頁・発行日
- 1975
1 0 0 0 和紙 : 東野辺薫作品集
1 0 0 0 カンボジア花のゆくえ
- 著者
- パル・ヴァンナリーレアク著 岡田知子訳
- 出版者
- 星雲社 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2003
1 0 0 0 現代カンボジア短編集
- 著者
- 岡田知子編訳
- 出版者
- 大同生命国際文化基金
- 巻号頁・発行日
- 2001
1 0 0 0 カンボジアを知るための60章
- 著者
- 上田広美 岡田知子 福富友子編著
- 出版者
- 明石書店
- 巻号頁・発行日
- 2023
1 0 0 0 地獄の一三六六日 : ポル・ポト政権下での真実
- 著者
- オム・ソンバット著 岡田知子訳
- 出版者
- 大同生命国際文化基金
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 ナガラワッタ
- 著者
- 坂本恭章 岡田知子訳 上田広美編
- 出版者
- めこん
- 巻号頁・発行日
- 2019
1 0 0 0 カンボジアを知るための60章
- 著者
- 上田広美 岡田知子編著
- 出版者
- 明石書店
- 巻号頁・発行日
- 2006