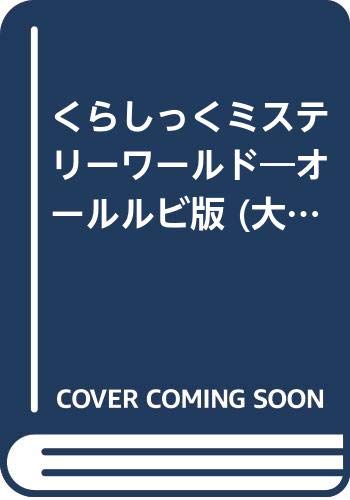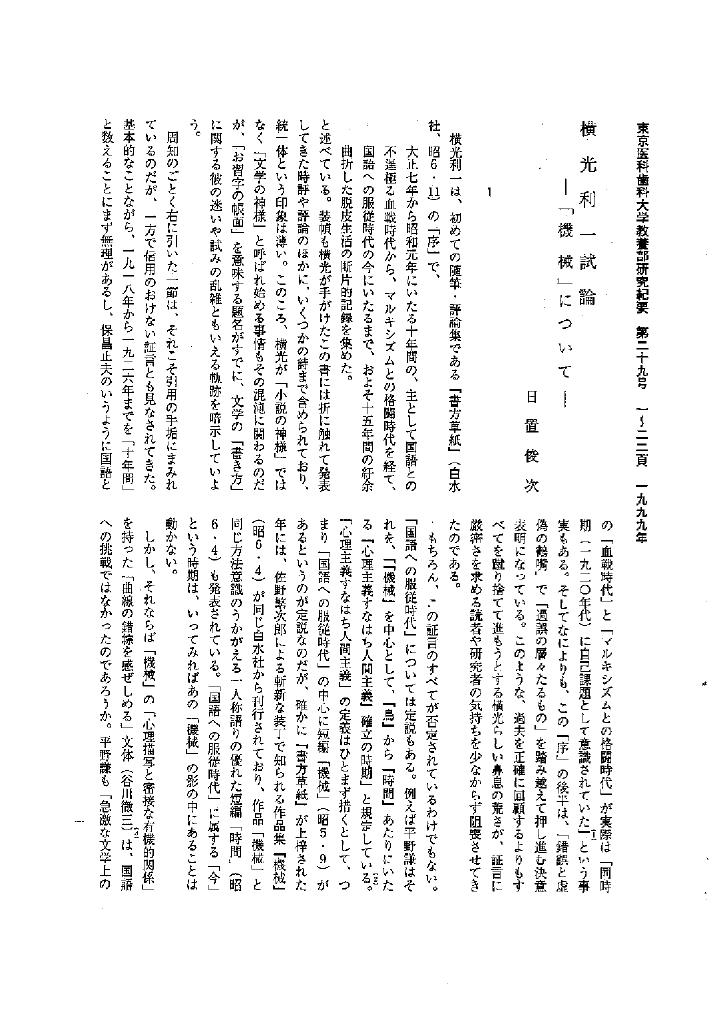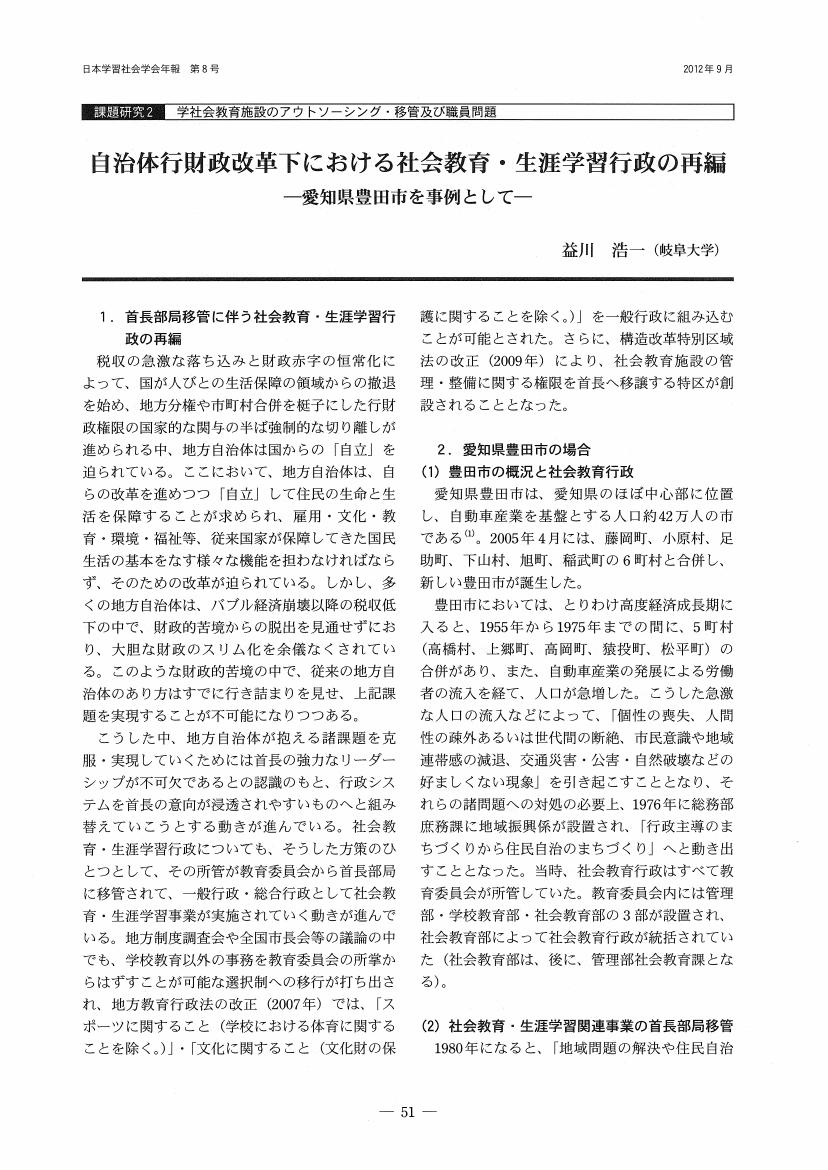- 著者
- Masaya Motohashi Michael F. Wempe Tomoko Mutou Yuya Okayama Norio Kansaku Hiroyuki Takahashi Masahiro Ikegami Masao Asari Shin Wakui
- 出版者
- The Japanese Society of Toxicology
- 雑誌
- The Journal of Toxicological Sciences (ISSN:03881350)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.195-206, 2016-04-01 (Released:2016-03-10)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 14 16
This article was retracted. See the Notification.
- 出版者
- リブリオ出版
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 OA 幣原外交における政策決定
- 著者
- 今井 清一
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.92-112, 1959-03-31 (Released:2009-12-21)
1 0 0 0 OA 横光利一試論 「機械」について
- 著者
- 日置 俊次
- 出版者
- 国立大学法人 東京医科歯科大学教養部
- 雑誌
- 東京医科歯科大学教養部研究紀要 (ISSN:03863492)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.47-68, 1999 (Released:2020-09-28)
1 0 0 0 OA 酸素ガス切断における予熱ガス炎性状と切断性能の関係に関する研究
- 著者
- 大沢 直樹 澤村 淳司 池上 祐一 山口 和恵
- 出版者
- 一般社団法人 溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会論文集 (ISSN:02884771)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.141-156, 2013 (Released:2013-07-23)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2 2
Plate temperature and heat input in oxyfuel gas cutting process with H2/LP gas and LPG flame are calculated by 3-dimensional FE heat conduction analyses. FE analyses are performed by using moving coordinates, and cutting groove temperature is determined by iterative calculation. The 2-dimensional groove temperature distribution determined by Matsuyama's theory is chosen as the initial values in this iterative calculation. The heat transfer properties of the preheating flame are determined by using the GA-based heat transfer estimation technique proposed in the previous report. The validity of the proposed numerical procedure and the accuracy of the determined groove temperature are examined by comparing the calculated and measured plate temperature and HAZ sizes. Heat input due to preheating, qG, and that due to self burning of steel, qB, are estimated in these analyses, and they are compared with the heat inputs estimated by Wells' and modified Wells' equations. The relation between the heat transfer characteristics of the preheating gas flame and plate temperature distribution is examined, and the cutting performance improvement mechanisms of Hydrogen preheating are discussed. As results, followings are found: 1) The 3-dimensional groove temperature distribution can be calculated by performing the iterative analyses procedure proposed in this study; 2) The critical cutting speed can be estimated once the gas heat transfer parameters are known; 3) It is not appropriate to evaluate the magnitude of cutting thermal deformation only from the preheating gas's total calorific value; 4) Under the conditions chosen, the heat generated by self burning is inadequate to maintain the cutting process, and it is essential to supplement heat by preheating; 5) The faster cutting speed and smaller total heat input of H2/LP gas are results of the larger local heat transfer coefficient below the gas ejection hole. It is supposed that the improvement in oxyfuel gas cutting performance can be achieved by modifying the heating apparatus so that the local heat transfer coefficient becomes larger.
- 著者
- 青木 巌
- 出版者
- 日本西洋古典学会
- 雑誌
- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.31-38, 1962
It lias been said that Aristotle, being intent on establishing his own system, was often inaccurate or negligent in his description of the presocratic philosophers He is said to have written about them only for the purpose of either illustrating how they are wrong as compared with his own views, or showing their ideas as confirmations of his own, which are always true He is, after all, not motivated by any historical sense, and turns out to be incorrect and at times unjust in his historical treatment As against him, it is said, Theophrastus, thought not prompted by any different motive, is more impartial and correct concerning the early Greek philosophy There is a third opinion that Theophrastus is in all essentials only repeating interpretations he found in Aristotle and they have, therefore, the same deficiencies, in fine, he too is a biased witness and even less trustworthy than Aristotle In view of these three interpretations, the present writer scrutinizes the problem deliberately confining himself to a single item το απειρον of Anaximander He knows that such a limited method of treatment is inadequate, and may even be dangerous, but he is also convinced that even though he restricts hisv problem to such a small aspect, he can come to a conclusion which has some value In sum there can be no choice between Aristotle and Theophrastus in regard to the presocratic causes in general Sometimes incorrect and inattentive as he is, the former is quite reliable as a historian, and the latter surely follows his master's interpretations faithfully without being blind to the blunders and omissions on his part Any issue has to be solved through consulting both of them together with other sources, and, carefully adopting or rejecting them
1 0 0 0 アリストテレスの様相存在論 : ロゴスとエルゴンの相補的展開
- 著者
- 千葉 惠
- 出版者
- 北海道大学文学研究科
- 雑誌
- 北海道大学文学研究科紀要 = Bulletin of the Graduate School of Letters, Hokkaido University (ISSN:13460277)
- 巻号頁・発行日
- no.150, pp.1-157, 2016
1 0 0 0 OA 自動車事故予防を目指す実験室研究における困難
- 著者
- 藤田 悟郎
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.47-61, 2006 (Released:2008-09-25)
- 参考文献数
- 32
Researchers, who are interested in motor vehicle accident prevention, want their laboratory research outcomes to be utilized in actual prevention measures. However, they sometimes have difficulties in conducting their laboratory research. They are often in trouble when they understand accident statistics. Also, they are often in trouble when the public and program planners did not understand possibilities of the research outcomes, or misunderstand the research results. In this study, several events, which had been occurred in motor vehicle accident prevention and researches in Japan, were analyzed from the viewpoint of techno-science studies and situated cognition theory. Revision of accident statistics, counter measures for older drivers accidents and counter measures of drinking driving were analyzed. Results of this study indicates that observation devices, such as statistic survey sheets or driving simulator are important, not only for reliable measurement but also for cooperation with the publics and program planners. The results also suggest that when researchers design their research method, they should have multi dimensional and macro view in which researchers are able to see not only the qualities of research method, but also social cooperation with program planners.
- 著者
- 山井 洋一 本田 健一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会論文集 (ISSN:13446460)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, pp.192-202, 2023 (Released:2023-08-05)
- 参考文献数
- 30
This paper proposes the evaluation methodology in early design phase for the feasibility of novel instrument layout to be applied for the next generation civil aircraft, based on the MIL-HDBK-46855A human engineering guideline that shows pilot evaluation and analysis method for military system. Airline pilots evaluation on mockup with this method facilitates to identify the critical design issue and its potential resolutions from visibility, its trajectory and crew coordination point of view and mitigate the risk for late finding of issue to avoid redesign in later design phase. The effectiveness of the evaluation method is potentially shown by the trial usage on the conventional instrument layout, and the achieved data can be used for a reference to compare it with the novel instrument layout design.
1 0 0 0 OA 自治体行期政改革下における社会教育・生涯学習行政の再編 ―愛知県豊田市を事例として―
- 著者
- 益川 浩一
- 出版者
- 日本学習社会学会
- 雑誌
- 日本学習社会学会年報 (ISSN:18820301)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.51-55, 2012 (Released:2019-09-09)
1 0 0 0 OA 1.アユの分類学的位置
- 著者
- 岩井 保
- 出版者
- Japanese Society for Aquaculture Science
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.199-200, 1990-06-30 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 生活習慣病治療のパラダイムシフト ―慢性炎症を標的とした治療戦略―
- 著者
- 四方 賢一
- 出版者
- 岡山医学会
- 雑誌
- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.3, pp.197-206, 2011-12-01 (Released:2012-01-04)
- 参考文献数
- 46
1 0 0 0 研究者間の創造的連携を支援する視覚的対話プログラムの開発
本研究は、高度な専門性を持ち、専門領域を超えたコミュニケーションが難しい理系研究者を対象として、領域横断的な研究を進めるための視覚的対話のワークショップのプログラムを開発することを目的とする。このプログラムは、研究者自らが複雑な研究を図解し、図解されたものを用いて対話し、動かし合いを通して、創造的に連携点を見つけ出すことを特徴とする。研究の実施にあたっては、1.視覚的対話の手法の研究者に対する調査、2.WSの実施と分析による創造的連携の理論モデルの構築とツールの開発。3.プログラムの改善とツールと手法の公開 の3つを中心に進める。
- 著者
- 富田 誠 瀧 知惠美 夏川 真里奈 小出 瑠 南斉 規介
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第69回研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.104, 2022 (Released:2022-08-30)
協働研究を行う研究者を対象に、研究者個人の内面、特に内的動機に当てた対話の場をデザインした。その特徴は、客観性や根拠の積み上げを重要視する研究発表の場では語られない、内的動機をなめらかに語り出すことにある。結果、語り出すことを許与する問い、語りを引き込む聞き手、共視される対象が主なアクターとなって研究者の語りを誘出することが示唆された。
1 0 0 0 OA 日本における「生活改善」の思想的射程 1920年代~1930年代
- 著者
- 満薗 勇
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社会経済史学 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.4, pp.467-482, 2018 (Released:2020-02-25)
1 0 0 0 OA 食品中の活性物質
- 著者
- 三浦 孝次
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.137-143, 1976-04-05 (Released:2009-12-11)
1 0 0 0 OA 『マキャベリ的知能』と紛争の実証研究
1 0 0 0 OA 幕末における海外文化の収集活動と翻訳について
- 著者
- 上野 晶子
- 出版者
- 北九州市立自然史・歴史博物館
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2013-04-01
Nederlandsch Magazijn(マガゼイン)を研究の中核として、その翻訳書及び古賀謹一郎による読書録を分析した。具体的には、①マガゼインの項目及び掲載ページをデータベース化し、古賀及び蕃書調所旧蔵本にみられる書込みなどを追加した対応表を作成した。②国内に残存する「和蘭宝凾(蘭人日本之記)」を確認し、その原文である「JAPAN」(Nederlandsch Magazijn 1839年)との比較をおこなった。③マガゼインを底本とする史料を分析し、蕃書調所による「官板 玉石志林」の翻訳作業の過程を考察した。④古賀謹一郎による日誌及び蔵書目録を調査した。
1 0 0 0 OA 混合状態に対する量子情報量とホログラフィー原理
- 著者
- 玉岡 幸太郎 梅本 滉嗣
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.6, pp.335-339, 2020-06-05 (Released:2020-10-14)
- 参考文献数
- 9
時空,そして重力の微視的起源を明らかにすることが,物理学における究極の問いの一つであることは間違いないだろう.近年,この問題を考える上で,量子コンピュータなどの基礎ともなる量子情報科学に基づいたアプローチが重要視されている.この問いは,「重力の量子論がどのように定式化されるか?」と換言できる.重力の量子化は,歴代の物理学者による挑戦を跳ねのけ続けてきた難しい問題だが,この困難を克服できる可能性の一つがホログラフィー原理である.これは,「D+1次元の量子重力理論は,D次元の重力を含まない量子多体系と等価である」という作業仮説である.実際に,量子重力理論の有力候補である超弦理論において,このホログラフィー原理を具現化したAdS/CFT対応が発見された.この具体例を通して,ホログラフィー原理の核心を明らかにすべく,数多くの研究が進められている.この文脈において,昨今では量子情報というキーワードを基にした新しい発展が続いている.その火付け役となったのが,D次元量子多体系のエンタングルメント・エントロピーとD+1次元重力理論のある種の曲面の面積が等しいことを明らかにした,笠–高柳公式である.エンタングルメント・エントロピーは,純粋状態にある2体系の量子もつれ(エンタングルメント)を定量化する情報量である.一方,面積は時空の曲がり方から一意に決まる幾何学量のため,この公式は「量子相関の構造」と「時空の曲がり方の構造」に密接な関係があることを示唆している.ところが,熱状態などの混合状態を考え始めると,エンタングルメント・エントロピーはもはや量子もつれを定量化する情報量ではなくなってしまう.これと対応するように,笠–高柳公式に現れる幾何学量だけでは,時空の計量を完全に決定できないことも知られている.事実,エンタングルメント・エントロピーの混合状態への一般化は量子情報理論におけるテーマの一つであり,これまでも文脈に応じて無数の情報量が提案されてきた.我々は少し見方を変えて,「ホログラフィー原理の観点から“良い”量子情報量は存在するか」という問いを考えた.その結果として,笠–高柳公式の一般化を与えるような“良い”量子情報量の候補を二つ発見した.一つは純粋化量子もつれと呼ばれるよく知られた量,もう一つはオッドエントロピーと呼ばれる新しく導入された量である.どちらの量も,純粋状態に対してはエンタングルメント・エントロピーと等価である.我々は,これらの情報量が,重力理論と等価な量子多体系において,笠–高柳公式に現れる曲面を一般化したもの(エンタングルメント・ウェッジ・クロスセクションと呼ばれる)の面積と等価であることを様々な観点(情報量と幾何学量の満たす不等式の一致や,重力と量子多体系における直接計算の一致など)から示し,一般に成り立つことを予想した.これらの発見は,単なる公式の一般化にとどまらず,従来の予想(重力理論とホログラフィックに等価な量子多体系では,2体量子相関が支配的である)に修正が必要であることを明らかにするなど,前述の「ホログラフィー原理が成り立つ上で何が重要か?」に対して新しい知見を与え始めている.また,このような情報量はホログラフィー原理の理解を超えて,様々な分野で有用である可能性が高く,今後の更なる発展,応用が期待される.