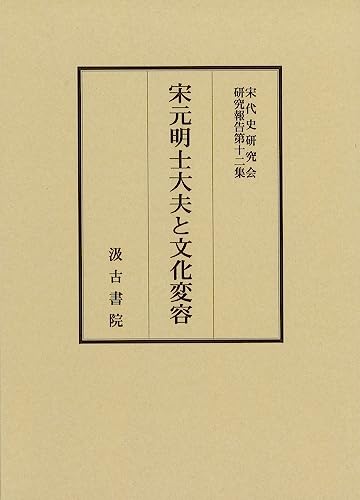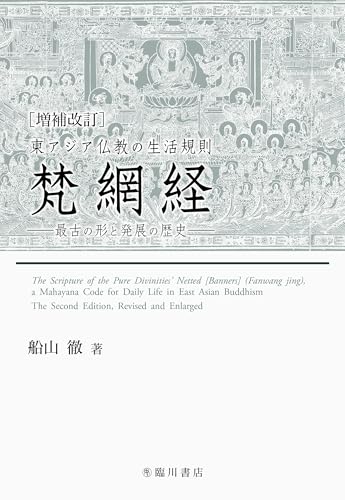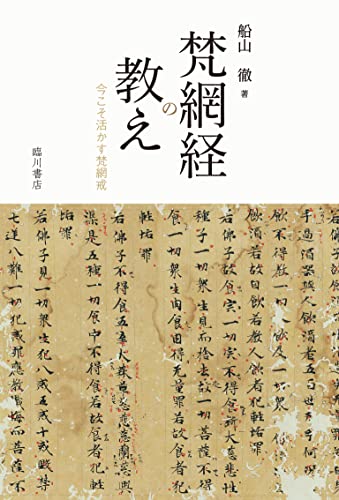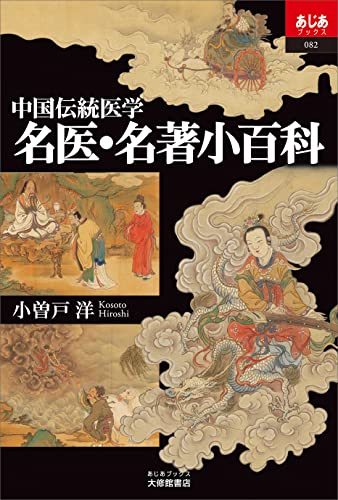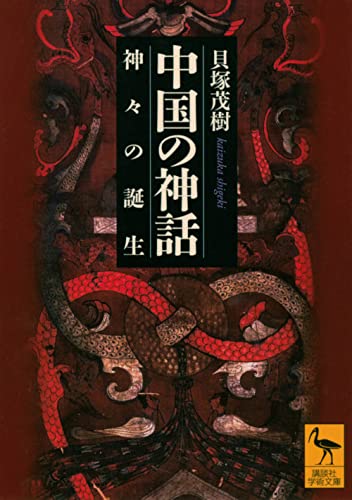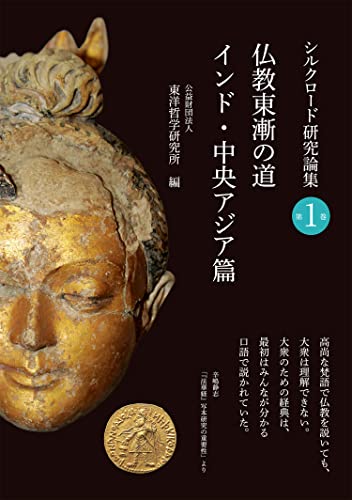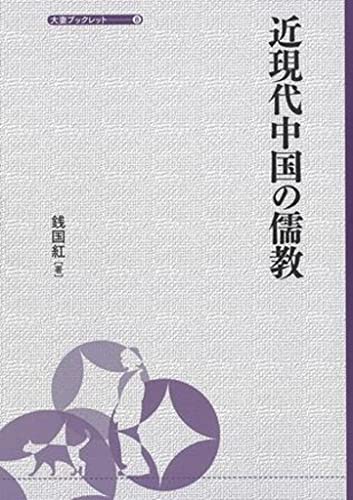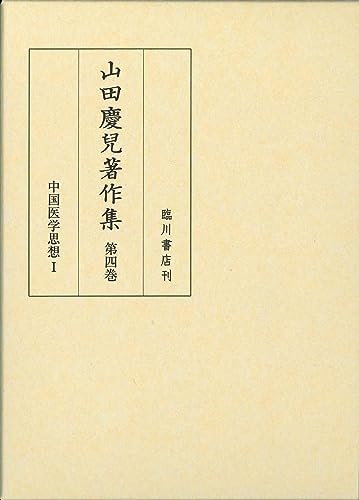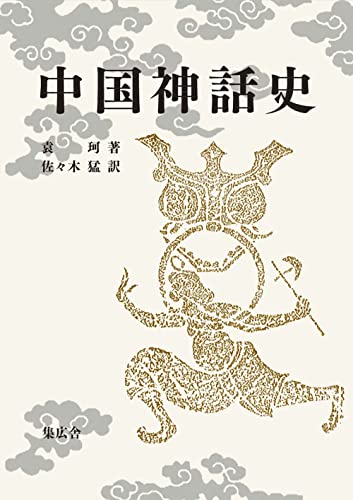1 0 0 0 OA 接着継手の破壊靭性値に与える接着剤層厚さの影響とそのメカニズムについて
- 著者
- 池田 徹 李 徳甫 宮崎 則幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本接着学会
- 雑誌
- 日本接着学会誌 (ISSN:09164812)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.97-105, 2006-03-01 (Released:2014-12-31)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 3 2
接着剤厚みが接着継手の破壊靭性値にあたえる影響についての研究は少なくないが,そのメカニズムはいまだ明らかとは言えない。本研究では,様々な厚みの接着継手中のき裂先端付近の損傷域を光学顕微鏡を用いて観察した。0.7mmよりも薄い接着継手において,界面損傷域が観察された。特に最大の破壊靭性値を示した0.3mmの接着剤層厚みの場合は,大規模な界面損傷域が接着剤層中に観察された。このことより,界面損傷域の応力遮蔽効果がこの接着継手の破壊靭性値を上昇させているものと推定された。接着継手中のき裂先端近傍の損傷を有限要素法にGursonモデルを適用して解析したが,その結果は薄い接着剤層ほど応力と損傷が大きくなるというものであった。このことは,接着剤層が薄くなると単調に破壊靭性値が減少するということを示す。そこで,接着剤層と被着材の界面に人工的な損傷を導入して,有限要素法解析を行ってみた。その結果,約0.3mmの接着剤層厚さで最大の破壊靭性値を示し,界面損傷域の応力遮蔽効果を裏付けるものとなった。
- 著者
- 本多 嘉明 梶原 康司
- 出版者
- The Remote Sensing Society of Japan
- 雑誌
- 日本リモートセンシング学会誌 (ISSN:02897911)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.101-104, 2012-04-20 (Released:2012-11-01)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA 円筒折り紙構造を用いた軽量型ロボットアームの制作評価実験
- 著者
- 楠木 幹也 謝 浩然
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- インタラクション2023
- 巻号頁・発行日
- vol.1B-45, pp.317-321, 2023-03-01
近年,折り紙構造を用いた柔らかいロボットアームの研究が盛んに行われている.本研究では,代表的な円筒折り紙構造による軽量型ロボットアームの制作に着目し,実際の制作コストや体験の評価実験を行う.具体的には,Twisted Tower,吉村パターン,Kreslingパターンの3つの円筒型折り紙構造を手折りしてもらう制作評価実験を実施した.制作評価実験では,それぞれの折り紙構造について,規定時間にわたる制作作業を行ってもらった後,NASA-TLX法を用いたアンケート評価を実施した.実験結果として,Twisted Tower,吉村パターン,Kreslingパターンの順に制作負荷が高いことが明らかになった.
1 0 0 0 OA 豚骨脂培地で生産した酵母菌体の脂肪酸およびアミノ酸組成
- 著者
- 山内 亨 飯田 貢 大武 由之
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.125-133, 1986-02-15 (Released:2009-04-21)
- 参考文献数
- 21
豚骨脂を唯一の炭素源とする培地で,振盪培養によってCandida tropicalis WH 4-2, Candida lipolytica No. 6-20, Candida lipolytica IAM 4947, Candida rugosa JF 101, Candida rugosa JF 114, Cryptococcus albidus IAM 4317, Trichosporon sericeum EP 4-3およびTrichosporon sericeum EP 4-8の8株の酵母を培養した.Cr. albidusとC. lipolytica IMA 4947の菌体生産は良くなかったが,他の6株の酵母は豚骨脂培地で良好に成育した.酵母菌体の脂質含量ならびに脂質の脂肪酸組成は,それそれの菌株で異っていたが,それら脂質は基質に用いた豚骨脂の脂肪酸組成を,かなりよく反映しているところがあると思われた.豚骨脂培地の初発pHを違えて,ジャーファメンターを用いてC. tropicalis WH 4-2とTrichosporon sp. EP 4-8を攪拌,通気培養した.C. tropicalisとTrichosporon sp.をそれぞれの初発pHが6.2あるいは6.3では,初発pHが7.2あるいは7.1のときよりも生育が速やかであった.C. tropicalisの場合は培地の初発pHが6.2のときよりも,初発pH 7.2のときのほうが菌体生産量が多かったが,Trichosporon sp.は培地の初発pHの違いによる菌体生産量に差異がなかった.培地の初発pHと関連して,上記の2株の菌体脂質の脂質画分を調べたが,いずれの酵母にあっても,それぞれの脂質画分の脂肪酸組成は,初発pHの違いで多少の差異は見られるが,特に顕著なものとは考えられなかった.骨脂培地で初発pHを異にして生産したC. tropicalisおよびTrichosporon sp. EP 4-8の酵母菌体は,いずれも基本的には類似したアミノ酸組成を有していて,栄養的価値から見て比較的バランスの良いものと考えられた.
1 0 0 0 宋元明士大夫と文化変容
1 0 0 0 OA 起き上がりの評価とハンドリング実技
- 著者
- 木津 彰斗 石濱 崇史
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.3-10, 2018 (Released:2018-12-20)
- 参考文献数
- 3
To deepen understanding of the normal for sitting from supine, 10 men and women were examined using motion analysis and electromyography. Motion was classified into three categories, namely sitting from supine with arm support on one side, sitting from supine with arm support on both sides, and sitting from supine with the sitting position with extended legs. The muscle activities of the right and left rectus abdominis muscles and right and left abdominal oblique muscle overlapping sites were examined using electromyography. A common feature of the three motions was the absence of rotation or side bending of the trunk. In addition, as segmental rotation and lateral bending of the trunk do not occur, the activities of the upper limbs are suggested to be important with regard to raising and rotating the body.
- 著者
- Misa Miura Ryo Yoshizawa Shigeru Oowada Aki Hirayama Osamu Ito Masahiro Kohzuki Teruhiko Maeba
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- Progress in Rehabilitation Medicine (ISSN:24321354)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.20170008, 2017 (Released:2017-06-15)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 2
Objective: Hemodialysis (HD) patients have lower fitness levels than healthy subjects because of various structural, metabolic, and functional abnormalities secondary to uremic changes in skeletal muscles. Aerobic and resistance exercises are beneficial in improving not only physical function, including maximal oxygen uptake and muscle strength, but also anthropometrics, nutritional status, and hematologic indices. The use of electric ergometers that place light loads on patients has been implemented at many dialysis facilities in Japan. However, reports comparing the effects on body function of electric and variable-load ergometers are few. This study aimed to compare electric ergometers and variable-load ergometers in terms of exercise outcomes in HD patients. Methods: A total of 15 ambulatory HD patients were randomly divided into two groups: the variable-load ergometer group (n=8) and the electric ergometer group (n=7). HD patients exercised at a level based on their physical function three times a week for 12 weeks. Results: After the 12-week intervention period, only the variable-load ergometer group experienced significant increases in lower extremity muscle strength and exercise tolerance. Conclusion: This study confirmed that conventional aerobic training and electric bike exercise during HD were efficacious and safe without causing sudden hypotension or any other side effects. However, exercise using a variable-load ergometer may be more effective than exercise using an electric bike in improving the physical function of HD patients. Exercise using a variable-load ergometer elicited specific whole-body and local effects.
1 0 0 0 OA スポーツ障害の治療―下肢・足―
- 著者
- 入谷 誠
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.129-134, 1998 (Released:2007-03-29)
- 参考文献数
- 5
スポーツ障害の中でも足の障害は最も多く,疹痛を主訴として来院することが多い。足は人間にとって唯一地面に接する部分で,足の異常が近位関節に,また近位関節の異常が足に影響を与え,さまざまな障害を呈してくる。足の障害に対する治療は,足単独の障害として捉えるのではなく,身体全体の障害であるという認識をもたなければならない。そのためには,障害局所の解剖学的な位置の把握,詳細な足の評価を中心とした非荷重下での機能的な評価,身体重心との関連を考察する荷重下での機能的な評価を行う必要がある。そして各々の評価を関連づけて考察し,治療の方向性を探っていくことが大変重要である。
1 0 0 0 東アジア仏教の生活規則梵網経 : 最古の形と発展の歴史
1 0 0 0 梵網経の教え : 今こそ活かす梵網戒
1 0 0 0 OA 尿素樹脂とフェノール樹脂を合成する(5分間デモ実験,実験の広場)
- 著者
- 高木 春光
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.24-25, 2015-01-20 (Released:2017-06-16)
1 0 0 0 OA アメリカ歴史教科書における原爆投下のコンテクスト――第二次世界大戦,冷戦,核時代――
- 著者
- 藤田 怜史
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.127-146, 2012-03-25 (Released:2021-11-06)
This article examines the descriptions of the atomic bombings against Japan in the U. S. history textbooks. In particular, it focuses on historical contexts of the bombings, and clarifies how an understanding of or a debate on the bombings is framed. In order to do that, this study analyzes thirty-nine textbooks that are/were used in American secondary schools.According to the historical research, this article assumes that the historical contexts of the atomic bombings are World War II, the Cold War, and the nuclear age. Most of the history textbooks deal with World War II and the early Cold War in different chapters. On World War II, domestic matters and foreign issues are dealt with in separate sections. On foreign issues, the history textbooks incline to mainly describe military developments on the European front and the Far Eastern front. No history textbook deals with the nuclear age in a single chapter, and some recent textbooks describe it in a section or a head. Based on these facts, this article argues that the U. S. history textbooks in general do not consider the Nuclear Age as an important historical context.Then, where is the description of the atomic bombings placed? Most of the textbooks locate the description in a chapter about World War II and a section about the ending of the war or about the Pacific front, not the Cold War. This is the case with not only the military aspects of the bombings, but also the political aspects. Based on these facts, this article suggests that the history textbooks regard the bombings as a military tactic, and unquestionably connect the bombings with the ending of the war. Some recent textbooks point out the political aspects of the bombings, but they do not provide an adequate context.On the connection between the atomic bombings and the nuclear age, about a half of the textbooks that this article uses say that the bombings ushered the nuclear age. However, as stated above, the nuclear age is not considered as a historical context, and it is only two textbooks that explain the significance of the bombings in the nuclear age. Moreover, almost no textbook clearly connects the destruction of Hiroshima and Nagasaki with the image of the annihilation of the human beings in the nuclear age.As a result of the above analysis this article concludes that the U. S. history textbooks have a tendency to locate the atomic bombings in the context of World War II, especially in a military context. Historian Andrew Rotter points out that there is simplicity in the debate over the atomic bombings in the United States. This study suggests that the bombings in the textbooks reflect and affect this simplicity.
1 0 0 0 OA 覚せい剤の死後体内分布から見えること
- 著者
- 吉留 敬
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第46回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.S12-3, 2019 (Released:2019-07-10)
以前に不整脈治療薬であるフレカイニドの過剰摂取による死亡が疑われた事例を経験し,生前の血中薬物濃度と死体内の薬物濃度の比較を行うことができた。その際,死後の左心血中のフレカイニド濃度は,生前血の17.7倍という著しく高い値を示していた。そこで,動物を用いた実験などを行うことで,フレカイニドは死後その心臓血中濃度,特に左心血中濃度が上昇すること,また,この上昇の原因が,フレカイニドの著名な肺への蓄積と死後の血液の酸性化であることを明らかにした。 ところで,覚せい剤であるメタンフェタミンは心臓血中濃度が死後上昇することが以前より知られており,覚せい剤はフレカイニドと同様に塩基性の薬物であることから,その心臓血中濃度の死後上昇機構はフレカイニドと同様のものであると考えられた。そこで,覚せい剤の検出された剖検事例について,その末梢血中濃度と心臓血中濃度の比較検討を行い,血液の流動性などが,末梢血と心臓血中濃度に影響を与えていることを明らかとしてきた。 その後,死体の各種体液中の覚せい剤濃度の比較を行なったところ,胃内で著しく高濃度を示すことが明らかとなった。覚せい剤は法規制対象の薬物であり,乱用者はしばしば第三者によって飲まされたと主張する。そのような主張を生前にしていた場合,その摂取経路の特定は死者が生前に自ら静注により摂取したのか,それとも経口的に飲まされたのかを鑑別する上で重要なものとなる。そこで,動物実験および事例の検討を行うことで,覚せい剤の摂取経路の鑑別法の構築を行なっている。
1 0 0 0 中国伝統医学名医・名著小百科
1 0 0 0 中国の神話 : 神々の誕生
1 0 0 0 東アジアの思想・芸術と文化交渉
1 0 0 0 中国医学思想
- 著者
- [山田慶兒著] 『山田慶兒著作集』編集委員会編
- 出版者
- 臨川書店
- 巻号頁・発行日
- 2023