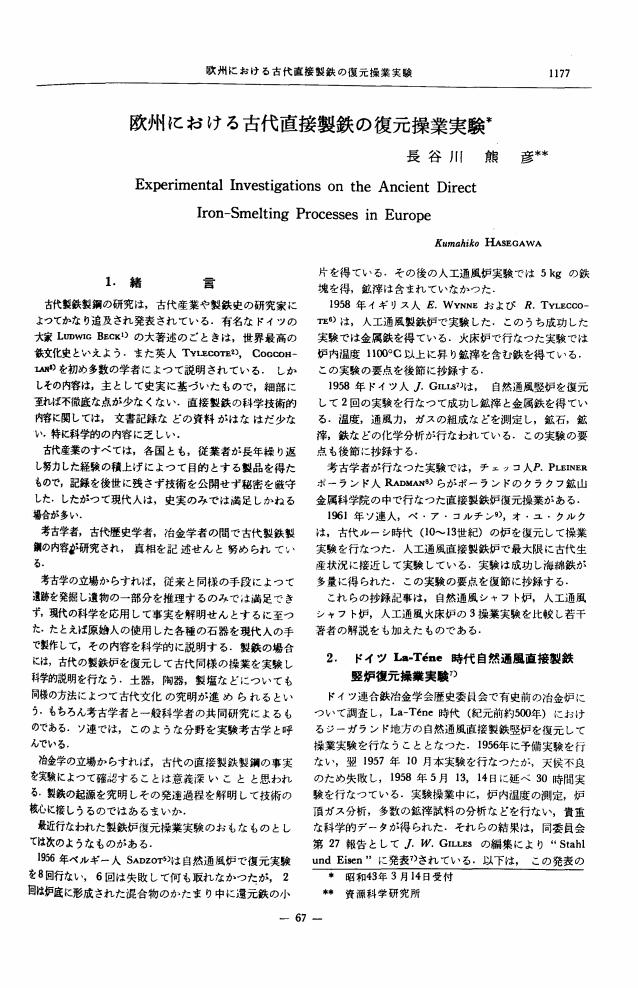1 0 0 0 OA 続·シンクタンク (2) —特殊法人形態のシンクタンク
- 著者
- 小原 満穂
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.11, pp.983-994, 1992-02-01 (Released:2008-05-30)
- 参考文献数
- 1
今後の複雑な国際関係を考えると公的シンクタンクの役割が期待されるとし,特殊法人形態で研究実績を有する「総合研究開発機構」と「アジア経済研究所」をとりあげ事業内容を述べた。前者は行政レベルと政党レベルの要請から設立されたが,政治,経済,社会,国際関係といった広い分野について自主研究,委託研究,助成研究を行うとともに,海外シンクタンクとの国際交流も活発に行い,さらに我が国のシンクタンクを育成している。また後者は,世界の発展途上地域における経済分野の調査研究を行うとともに,海外機関との国際交流や共同研究,情報の収集活動力を注いでいる。また最近人材養成を目的として開発スクールを発足させた。
1 0 0 0 OA 欧州における古代直接製鉄の復元操業実験
- 著者
- 長谷川 熊彦
- 出版者
- The Iron and Steel Institute of Japan
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.11, pp.1177-1192, 1968-09-01 (Released:2010-10-12)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA ポリオウイルスの不顕性感染に関する研究 第2報 麻痺型感染と不顕性感染のウイルス学的比較
- 著者
- 窪田 英夫
- 出版者
- 日本ウイルス学会
- 雑誌
- ウイルス (ISSN:00426857)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.24-32, 1962 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 45
In order to study affecting factors on development of the paralysis in polio patients, feces were collected from six paralytic polio patients and four inapparent infection cases for the virus infection. Ten strains of poliovirus type 2 were isolated from these specimens, and the difference of these strains were compared with each other in the respects of plaque size of the strains, neuroviruleuce to mice when the strains were intraspinally inoculated into mice, and the quantity of poliovirus excreted in those feces, which were indicating respectively the multiplication efficiency, the neurovirulence, and the extent of virus growth in intestinal tract of those polioviruses.The results were as follows:1) The quantity of poliovirus excreted in feces: The quantitative difference did not depend upon the day of illness when the materials were taken and also clinical types of infections: paralytic forms or inapparent infections.2) The measurment of plaque size of the strains: Plaque size of the strains of poliovirus type 2 from the inapparent infections were 5.19±0.37-1.75±0.11(mm), and. that of the paralytic forms were 5.29±0.36-1.66±0.10(mm). These clinical forms did not differ in their range of variation.3) The neuroviruleuce to mice when the strains were intraspinally inoculated into mice: When these viral strains were intraspinally inoculated into mice, there was significant difference between two groups of mice; one group which received viral strains from paralytic polio showed 23.4per cent of mortolity and the other group which was inoculated with viral strains from inapparent infections displayed only 4.3per cent of mortality. The difference can be conciderd significant.From these results mentioned above neurovirulence may play the most important role to convert a poliovirus infection to clinically manifest paralytic form.
1 0 0 0 OA 軌道電子の遷移に伴う原子核の励起とこれを利用した235Uの分離法
- 著者
- 森田 正人
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.118-119, 1973-02-28 (Released:2011-02-17)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 日本・モンゴル関係 ──日本の対モンゴルODAの評価とポストODA
- 著者
- 清水 武則
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.8, pp.8_32-8_37, 2022-08-01 (Released:2022-12-23)
日本のモンゴルへのODAは戦略性を有し、モンゴルのニーズにも合致したものであった。1990年の民主化の翌年には海部総理がサミット国のリーダーとして初めてモンゴルを訪問し、いち早く国際支援国会合の開催など支援策を打ち出し機動性もあった。背景には、ベーカー国務長官(米国)の日本への高い期待があった。日本のODAは90年代の経済危機の時代、2000年代の経済発展段階、2010年頃からの無償卒業国入り以降の新空港建設などの大規模事業への支援を経て、今日新たな段階に入った。無償供与は人道支援以外は基本的に実施困難であり、借款もモンゴルの債務負担能力がネックになっている。ODAの実施を梃子として発展してきた両国関係は、今日、戦略的パートナーシップの段階にあり、モンゴル国民の日本への信頼も良好な発展を示してきたが、ポストODAの時代においては民間交流が重要な役割を果たす必要がある。両国はEPAを締結し2016には発効したが、当初期待したモンゴルの対日輸出の拡大は達成できていない。モンゴルの中国への依存度が高まる中で日本としてできることは産業振興のための技術協力、日本からの観光客の拡大のための協力等が考えられるが、ODAの役割が確実に小さくなっていることだけは間違いない。
1 0 0 0 OA ゆでうどんにおける過酸化水素の殺菌効果
- 著者
- 棚田 益夫 内田 晴彦 井出 知佐子 玉置 幸美 沢 久美子
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.5, pp.437-442, 1973-10-05 (Released:2010-03-01)
- 参考文献数
- 4
The absorption and decomposition of hydrogen peroxide (H2O2) on Japanese noodle was studied in previous papers. The sterilizing effect of H2O2 on Japanese noodle where the residual amount was under 100ppm and the relation between the concentration of H2O2 residue and the viable cell counts in the commercial Japanese noodles were studied in this papers.In case of combined treatment of H2O2 and steaming (100°C, 4 minutes), the satisfying concentration of H2O2 to sterilize the packed 20g of Japanese noodle-paste increased proportionally with the logarithm of the added viable cell counts.The viable cell counts less than 104/g in the most of the commercial Japanese noodles containing more than 20ppm of H2O2.
1 0 0 0 OA 伝統的絵蝋燭の調査研究 : その歴史と図案と製造と利用法について
- 著者
- 内藤 郁夫 昇 愛子 車 政弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.19-28, 2004-07-31 (Released:2017-07-19)
- 参考文献数
- 35
庄内地方(鶴岡と酒田)・会津若松市・長岡市は絵蝋燭の産地として知られている。これらの地域で絵蝋燭業者や技術者に聞き取り調査を行い、伝統的絵蝋燭の図案を中心にその歴史や製造における特徴や利用法を研究した。絵蝋燭は18世紀中頃に庄内地方と会津で開発された。会津若松には3つの絵蝋燭のタイプがあった。一つは、牡丹や菊の絵が描かれた日本画タイプ、一つは、筆・笥・巻物の形に似せた細工蝋燭、あと一つは蒔絵タイプである。庄内の伝統絵蝋燭は御所車の図柄で代表される日本画タイプである。ー方長岡の絵蝋燭は会津若松より伝播したといわれ、牡丹・菊・甕・台の図柄で特徴すけられる。この中で、甕と台は会津若松で忘れられた図柄である。いずれの産地の伝統的絵柄は花篭模様が多<、磁器の影響が示唆される。これらの地域では、江戸時代より仏事に絵蝋燭が使用される。これが絵蝋燭製造の統いた理由である。
1 0 0 0 OA 病院薬剤師のキャリアビジョンに対する意識調査
- 著者
- 河添 仁 土屋 雅美 藤堂 真紀 原 梓 大西 友美子 大里 洋一 堀 里子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.143, no.8, pp.683-691, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)
- 参考文献数
- 10
This study aimed to clarify diverse values toward career visions for hospital pharmacists. A self-administered online questionnaire survey was delivered to live and on-demand release attendees at a symposium about sustainable career paths for pharmacists at the 32nd annual meeting of the Japanese Society of Pharmaceutical Health Care and Sciences between September 23rd and November 14th, 2022. Correspondence analyses of text mining were conducted to assess the association between the participants’ perspectives on career visions and their backgrounds consisting of sex and generation. The recovery rate was 81.9% (136/166). The majority of respondents were women (61.4%), aged ≥40 years (66.1%). Correspondence analysis of career vision for pharmacists showed that respondents who were ≥20–30 years were associated with the research topic, whereas those who were ≥40 years were associated with the director of a pharmacy and worked until retirement age. In contrast, there was no difference in career visions for pharmacists based on sex. The median satisfaction score of the symposium was 6 [interquartile range (IQR): 5–6] in the entire population, as conveyed using a seven-point Likert scale. Interestingly, the median satisfaction scores of the symposium were significantly higher for men in management positions than women in non-management and management positions (p=0.0106 and p=0.0031, respectively). In conclusion, we believe that career support tailored to everyone’s values could enable hospital pharmacists to realize their career visions.
- 著者
- 齋藤 靖弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.143, no.8, pp.623-628, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)
- 参考文献数
- 23
It is difficult to say that pharmacist services in the emergency room (ER) are widespread nationwide. According to a survey of certified emergency pharmacists, the work area they are most commonly engaged in is the intensive care unit. This may be due to the lack of reimbursement for pharmacist services in ERs and the absence of operational guidelines. On the other hand, Sapporo Higashi Tokushukai Hospital has had ER specialized pharmacists (ESPs) since 2016 and has reported on the usefulness of pharmacist services in the ER at conferences and in papers. Among other things, it has been shown that the workload of emergency physicians is reduced by 1.9 h/d through the use of ESPs, and that also contributes to the increase in accurate diagnoses of drug-induced diseases and the treatment of infectious diseases. Reports on the benefits of ESP have also begun to emerge in Japan, including a significant decrease in the number of incident reports. Meanwhile, overseas reports indicate that ESPs have a significant impact on healthcare economics, such as “an annualized cost avoidance effect of more than 400 million yen.” Furthermore, reports of improvements in operational guidelines and patient outcomes that support these guidelines indicate that ESPs in other countries are well-established ahead of their counterparts in Japan. We strongly hope that ESPs will increase in number and distribution in Japan in the future through the evaluation of reimbursement and formulation of operational guidelines.
1 0 0 0 OA 隕石有機物と化学進化(宇宙の化学)
- 著者
- 下山 晃
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.14-18, 2002-01-20 (Released:2017-07-11)
- 参考文献数
- 21
隕石の中でも炭素質隕石は太陽系の原始物質であり, 有機物を含んでいる。隕石アミノ酸が地球起源でなく, 非生物起源であり, このため宇宙起源であることはマーチソン隕石の分析から判明した。同様な結果は南極隕石のアミノ酸分析からも判明し, その種類や存在量, また, 隕石有機物としての特徴もこれらの隕石では共通していた。その後の分析ではジカルボン酸もアミノ酸と類似した特徴をもつことが判明した。隕石有機物の起源については, これまで原始太陽系星雲中や隕石母天体上での成因が提案され, 議論されてきた。近年のH, C, Nの安定同位体比の研究は, 異常に高い同位体比を隕石有機物が示すことから, 先太陽系(つまり星間)での生成が議論され, 起源と成因について新しい展開が見られる。さらに, 個別の同位体比測定が可能になり, 分子の生成経路に関しても考察が可能となった。さらになお, 隕石有機物の化学進化はアミノ酸や核酸の塩基などの生成まで進んだことを示しており, 地球に次いで生体関連有機物が存在する天体が存在することが判明した。
1 0 0 0 OA 『斯波遠説七長臣』考
- 著者
- 小笠原 広安
- 出版者
- 日本近世文学会
- 雑誌
- 近世文藝 (ISSN:03873412)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, pp.45-58, 2023 (Released:2023-07-31)
Shibaensetsu-shichininkarō (published Bunsei 4; 1821) is a “yomihon” of 5 kan / 6 satsu and is an Oie-sōdōmono (stories of feuds within samurai families) based on Sugawara-denju-tenaraikagami, etc. Although its frog monster draws attention, it has received low acclaim to date. However, the true villain is concealed until the last part (kan) of the story, and this device of a surprise ending could be called a new departure in “yomihon”. I investigate how initially, this work was scheduled to be published by a different publisher in a total of 9 kan, and due to the sudden change, the 5 kan were written hurriedly. Next, I focus on the illustration and Chinese poem placed at the beginning of the 4th kan, and demonstrate how the “Sewing corpus” of 7-5 meter is used in the scene that corresponds to the illustration, and how the Chinese poem is cited from Qing poem Nulang-ci, etc., seeing a perspective toward women. The advertisement at the end of the work for “Senjokō” fragrance, of the shop of Ōshima Den’emon, one of the publishers, also suggests an awareness of female readers. It also introduces Tamenaga-Shunsui’s critique of Kokuga, indicating the artistic contact between the two of them. In these ways, I show this work to be an ambitious work by Kokuga seeking new expression, and planning an expansion of readership.
- 著者
- 杉本 菜月 サトウ タツヤ
- 出版者
- 法と心理学会
- 雑誌
- 法と心理 (ISSN:13468669)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.39-46, 2022 (Released:2023-07-31)
1 0 0 0 OA 植物の特性とナトリウム
- 著者
- 間藤 徹
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.8, pp.1395-1398, 1989-08-15 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3 1
1 0 0 0 OA 手掌足底の漂母皮・蝉脱形成からの海中浸水経過時間の推定
- 著者
- 大城 圭太 齊藤 卓也 大和田 幸延 内藤 春顕 松島 裕 磯崎 翔太郎 垣本 由布 大澤 資樹
- 出版者
- 日本法科学技術学会
- 雑誌
- 日本法科学技術学会誌 (ISSN:18801323)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.183-187, 2023 (Released:2023-07-31)
- 参考文献数
- 9
This article aims to evaluate estimation of the postmortem submersion interval (PMSI) for cadavers recovered from the Pacific Ocean in the South Kanto area of Japan. Data were collected from crime scene reports in the 3rd Regional Coast Guard Headquarters over a 11-year period. Approximate time of PMSI was available for 72 cases with the decomposition stage from photo pictures at the scene. No visible changes in the skin of the hands and feet counted from 27 cases, wrinkling and discoloration in 28 cases, and degloving in 17 cases. The average (±S.D.) of accumulated degree days (ADD) was 2.0±3.3, 24.5±19.1, 164.0±112.5, respectively. As minimum ADD, wrinkling and degloving were expected to be formed in 9.4 and 77.8, respectively, which corresponded to a half day and four days at 20°C of sea water temperature. In comparison with other findings, degloving was accompanied by bloated abdomen, sloughing of hairs, and peeling of nails. The characteristic changes of the hands and feet were helpful to estimate PMSI for submerged cadavers. We expect to apply this finding to criminal investigation at the scene.
1 0 0 0 OA 防災ナッジの概念整理- Nudge or Judge?それが問題だ-
- 著者
- 中野 元太 矢守 克也 クラウ ルイザ
- 出版者
- 日本自然災害学会
- 雑誌
- 自然災害科学 (ISSN:02866021)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.23-38, 2022-05-31 (Released:2023-07-31)
- 参考文献数
- 24
ソフトな介入・干渉によって行動変容を促すナッジ論を生産的に防災・避難領域に導入するための方策を提案することが本研究の目的である。ナッジ論は,その概念を突き詰めれば,縦軸に「合理的・意識的人間モデル/本能的・反射的人間モデル」という二項対立軸を置き,横軸に「選択の強制/選択の自由」という二項対立軸を置いた概念図により整理可能である。概念図上方が合理的な選択に基づくジャッジ領域とし,下方をヒューリスティックな選択に基づくナッジ領域と位置づけた。同概念図に基づいて,現在の防災・避難対策をジャッジ領域とナッジ領域とで概観した。その上で,ナッジ論を用いることの批判等も検討しながら,ナッジの有効な活用のためには,介入者と行為当事者との合意形成や,ナッジ領域とジャッジ領域との間の相互利用が重要であることを指摘した。
1 0 0 0 OA 重い障害のある子どもたちの支援を再考する 本人さんはどう思ってはるんやろ…。
- 著者
- 高塩 純一
- 出版者
- 日本重症心身障害学会
- 雑誌
- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.25-31, 2020 (Released:2022-08-03)
- 参考文献数
- 9
Ⅰ.はじめに このたびは、このような機会をいただきましたこと心から感謝しております。私が、重症心身障害児に対する理学療法を教えていただいたのは旭川児童院元副院長の今川忠男先生です。 先生からはハンドリングを含め、多くのことを教わりました。写真1は2007年のヨーロッパのグローニンゲンであったEuropean Academy of Childhood Disability(以下、EACD)の学会でご一緒に行ったときのものです。グローニンゲンまでの列車の中で、なぜ日本の小児リハビリテーションはパラダイムシフトが起こらないのかを熱く語ったことを今でも覚えています。もう一人の恩師は、9月5日に他界された赤ちゃん学会理事長であった小西行郎先生です。小西先生からはGeneral Movements(GMs)の話をはじめ、分野を超えて学ぶことの大切さを教えていただきました。 私はただの臨床家でありエビデンスに基づくような話はできませんのでご了承ください。 では、私がどのような立ち位置でセラピーを行っているのか知っていただくため、私が小学5年生のときに入院していた経験をお話しさせていただきます。 当時、私は右大腿部に痛みがあり3か月間検査入院をしました。入院中はベッドから体を起こすこともできなかったため、私の目の前には天井のパンチングボードの穴。窓からは、いつも東京タワーが見えていました。このとき、私が思っていたことは、このライトアップされた東京タワーは、きっと朝になってもそこにあるのだろうというものでした。入院していた3か月は、まるで時間が止まり、色のない世界であったと記憶しています。これは、第一びわこ学園前園長の高谷清が書かれていた「時刻と時間」を思い出すものでありました。これは、重症心身障害により寝たきりの生活を余儀なくされている子どもにとって時を刻む時計があっても、動かないことによって時間の流れを感じることができないということであります。また、差し込み便器の冷たさ、足を牽引しており、身体を起こすことができないため、絶対にたどり着くことができない廊下。 目を閉じるとぐるぐる回るベッド。鳴り止まない秒針の音。 そこで感じていた世界の空虚感。 小学生のときの自分は、どこか他の人と違うんだな、という異質な感じを持っていました。 私が重症心身障害児(者)のことを知ったのは、東京衛生学園に入学してからでした。当時、東京医科歯科大学の理学療法診療科に丁稚奉公で働かせていただいていたとき、本棚にあった一冊の本が目に止まりました。それが糸賀一雄先生「福祉の思想」であったことは何か運命的なものを感じています。 Ⅱ.人生の岐路で励ましてくれた二人の少女 私が、今の職場に勤め続けられたのも二人の少女との出会いがあったからです。 一人は学生時代に出会った、当時中学2年生の幸子さんです。彼女は白血病に罹っており余命半年といわれていました。彼女が初めて言ったことは、「私はあと半年の命なのに、何をするの?」という言葉でありました。そのような言葉を言われて何も言えなかった当時の自分、毎日消灯まで一緒に遊んだ小児科病棟…。彼女から言われた言葉の一言一言が今でも耳の奥に残っております。今の私にできることがあるとすれば、彼女のことを決して忘れないこと…。 もう一人のお子さんが京大時代に受け持っていた洋香ちゃんです。彼女がいなければ重心の世界に行かなかったと思います。彼女は小さいときから何度も脳腫瘍により手術を受けていました。そのような境遇にもかかわらず他の人たちを気遣う心優しい子でした。彼女が手術後髄膜炎の後遺症により植物状態になったとき、止まらなかった涙とともに、私は何のためにこの仕事をしようと思ったのか、学生時代からどんなセラピストになりたかったのか。 今の私は当時描いていたセラピストになれているのかな…。 Ⅲ.びわこ学園/糸賀一雄/「福祉の思想」 NHKスペシャルのラストメッセージの動画の中で、びわこ学園の創設者である糸賀一雄先生の肉声を聞くことができます。 ビデオの冒頭で糸賀は「本当はこの子も立派に自前で生きているんですよということ。それを私たちは、実は認め合い、それを磨き合って、ということなんです。光ってますよ、この子は、もともと光そのものですよ。ということなんです」 昭和20年敗戦の混乱の中で家族を失い、生きる希望を亡くした子どもたちが街にあふれていました。終戦当時、滋賀県で食糧課長を務めていた糸賀一雄は、こうした子どもたちの状況を目の当たりにしていました。「浮浪児の問題なんていうのをね。国を挙げて『浮浪児狩り』という言葉を使っていましたね。『狩』というのは狩猟の『狩』という字を書くんですよ。これは大変な言葉ですね。考えてみますと大人の責任ですよね、これは。着の身着のままで放り出されたということはね。一つもこの子どもたちの責任じゃないんですよね」 こういう時代があったことを私たちは覚えておかなければいけないと思います。そして、重い障害のある子どもたちに関わる私たちはその根幹に哲学を持たなければならないと思います。 Ⅳ.糸賀思想における発達保障 びわこ学園の創設者の糸賀一雄は、重症児の発達保障のために、「縦軸の発達」に対して、「横への広がり」という考え方を療育の世界に持ち込んだ。 「縦軸の発達」というのは年齢に応じて能力がレベルアップしていく。それに対して「横への広がり」とはいまある能力のままでできることを増やしていく発達だ。 障害によって「縦軸の発達」が難しい子どもであっても「横への広がり」によって、世界は豊かに広がるという。 たとえば自閉症の子どもは同じような絵を描き続けたり、同じような曲を歌い続けたり、同じような文章を書き続けたり、でも、それはその子にとって決して同じことの繰り返しではない。私たち大人が進歩のない繰り返しだと勝手に思い込んでいるだけかもしれない。 それは、健常児の世界であっても、実は同じかもしれない。大人はより早く、より多く、より複雑にと、子どもたちに縦軸の発達を強いるが、本当はいまある能力のままでもっとゆっくりと横軸の広がりを楽しみたいと、子ども自身は思っているかもしれない。 糸賀は障害のある子どもたちと共に暮らす(ミットレーベン)の中でこのような考えにたどり着いたと晩年、鳥取県にある偕成学園での講演の中で述べていた。 よって「この子らを世の光に」というのは、障害のある子どもを救済するための言葉ではなく、糸賀が子どもたちから光をもらったと思えた実体験から生まれた言葉なのである。 這えば立て、立てば歩めではないけれども、正常運動発達をトレースしていくように伸びていくわけではない。縦軸への発達だけではなく、横への広がり、その豊かさも見ていくことが大事なのでは、ないだろうか。 Ⅴ.第一びわこ学園への想い 深夜に入る前に、「ちょっと寝かせて」と受け持っている担当の子の横で一緒に仮眠を取っていた細井ナース。 私は「聴診器より画板とクレヨンを持って仕事をしたい」と言っていた田中ナース。 石川信子先生は 「高塩さん、びわこ学園に何年勤めるの?」と尋ねてくれました。 「私はずっと勤めようと思うんです」と答えると、すると石川先生は笑って「3年務めないとわかんないわよ」と言われました。 夕暮れ時の縁側に腰掛けて園生と食べた柿。こうやって座位訓練をしていた時代があったんですよ。今だったら許されないと思いますが、そんなことをやっていました。 糸賀の言うミットレーベン「共に生きる、共に暮らす」を考えるためには利用者の生活世界をもう一度見てみる必要があるのではないかなと思います。 Ⅵ.“私たちの世界は豊かさに満ちている” 受動的綜合と能動的綜合 私の勤務している重症心身障害児(者)施設びわこ学園医療福祉センター草津の周囲には、もみじの樹がたくさん植えてあります。昨年、永源寺にもみじを見に行った際、初めてもみじの種を知りました。双葉のような葉の中心に種が2つあります。 5月中頃からもみじの葉の一部が赤くなっているのを見たことがある皆さんもいると思います。その赤くなったところにもみじの種があります。60年間、もみじの樹は見てきたはずなのに紅葉に種があることすら知りませんでした。この自我の関与しない無意識的局面をフッサール現象学では、受動的綜合と呼び、これはもみじの種は春から初夏にかけて毎年色づいていることを私は無意識的に見ていたことを意味します。しかし、もみじの種を知り、春なのになぜ、もみじが赤くなっているのだろうと疑問を持ったことで、紅葉を積極的に見ようとした結果、紅葉の種を見つけることができたという能動的綜合が生まれました。私たちが知覚する前には常に環境が発する情報を無意識的に受け止める受動的綜合があります1)。 (以降はPDFを参照ください)
1 0 0 0 OA アイトラッキングシミュレーションツールによる Webページ注視ポイントの解析と改善の試み
- 著者
- 積 高之
- 雑誌
- 経営戦略研究 = Studies in business and accounting (ISSN:1882224X)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.65-80, 2023-02
1 0 0 0 OA 国内野球独立リーグの観戦者に関する調査研究 : 新潟アルビレックスBCを事例として
- 著者
- 本間 崇教 山本 悦史
- 出版者
- 学校法人松商学園松本大学
- 雑誌
- 松本大学研究紀要 = The Journal of Matsumoto University (ISSN:13480618)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.107-113, 2023-03-10
本研究は、学術的な観察対象にされることの少ない野球独立リーグ観戦者を対象とした基礎資料の作成を目的とする。調査対象として、BCリーグに所属する新潟アルビレックスBCを取り上げ、観戦者及び球団のマーケティング施策に関する定量データを収集した。データ収集は新潟アルビレックスBCのホームゲームにて実施し、マーケティング施策の参考となるデータ収集のために、調査前に球団職員へヒアリングを行いながら調査票を作成した。得られたデータを用いて、一部Jリーグ観戦者調査のデータと比較しながら、独立リーグ観戦者調査の特性について明らかにした。その結果、基本属性や行動特性においてJリーグ観戦者とは異なる性質が確認された。
1 0 0 0 OA アカントアメーバ角膜炎の 3 例 —角膜擦過細胞診でのアカントアメーバ原虫の同定—
- 著者
- 堀越 美枝子 石原 力 石井 英昭 伊古田 勇人 山口 由美子 柏原 賢治 城下 尚 村上 正巳
- 出版者
- 公益社団法人 日本臨床細胞学会
- 雑誌
- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.48-52, 2008 (Released:2010-07-14)
- 参考文献数
- 10
背景 : アカントアメーバ角膜炎 (Acanthamoeba keratitis) はコンタクトレンズ装着者に増加傾向がみられる. 原因は淡水, 土壌等に生息しているアカントアメーバ (Acanthamoeba) の感染によるもので, 角膜擦過細胞診標本にて嚢子 (cyst), 培養検査にて原虫の嚢子 (cyst), 栄養体 (trophozoite) を検出できた 3 例を経験したので報告した.症例 : 角膜擦過細胞診で原虫の嚢子が確認できた. パパニコロウ染色ではライトグリーンにより嚢子壁が染色され, 内部は茶褐色あるいは不染性であった. PAS 染色では嚢子壁陽性, 嚢子内部は暗赤色を呈していた. ギムザ染色では嚢子壁が青紫色に好染した. また, 培養により得られた塗抹標本に蛍光染色を施し, 蛍光を発するアカントアメーバの嚢子を検出できた.結論 : アカントアメーバ角膜炎はアカントアメーバ原虫を検出し, 早期に治療することが重要である. 検出方法には病巣擦過物のパーカーインク KOH 法による直接鏡検あるいは培養が代表的な検査方法であるが, 角膜擦過細胞診標本でパパニコロウ染色, PAS 染色, ギムザ染色標本の鏡検によるアカントアメーバ原虫の検出は簡便であり, 早期に治療へ結びつくことができるため, 有用な検査方法である.
- 著者
- Mattia Scandolo Andrea Cavagna Luca Di Carlo Irene Giardina Tomás S. Grigera Stefania Melillo Leonardo Parisi Giulia Pisegna
- 雑誌
- STATPHYS28
- 巻号頁・発行日
- 2023-06-23