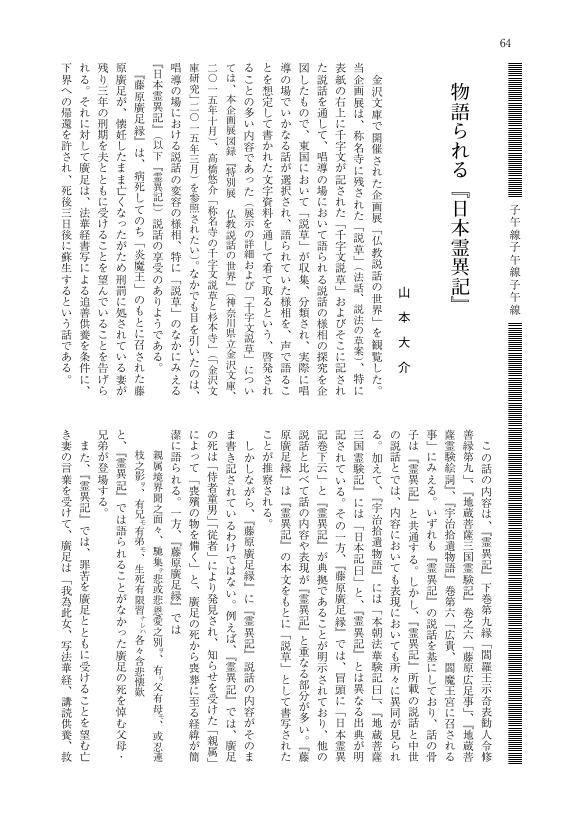- 著者
- Hyung Gon Je Min Ho Ju Chee-Hoon Lee Mi Hee Lim Ji Hye Lee Hye Rim Oh
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.1, pp.54-60, 2019-12-25 (Released:2019-12-25)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
Background:Stroke is a major concern in minimally invasive cardiac surgery, so we investigated the incidence and risk factors of cerebral embolism according to the systemic perfusion strategy under thorough imaging assessment.Methods and Results:Between November 2011 and May 2015, 315 cardiac surgery patients who underwent preoperative computed tomography angiography (CTA) as a routine evaluation were enrolled. The incidence and distribution of cerebral embolism were analyzed with routine postoperative brain diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI) examination. Anterograde perfusion was used in 103 patients (group A), and retrograde perfusion was performed in 212 patients (group R). Operative deaths, incidence of clinical stroke (group A: 0%, group R: 0.5%, P=0.77), and rate of cerebral embolism (group A: 35.9%, group R: 26.4%, P=0.08) were comparable. The median number of new embolic lesions detected by MRI per patient (group A: 2, group R: 2, P=0.16), maximal diameter of the lesion (group A: 6.5 mm, group R: 6.0 mm, P=0.97), and anatomic distribution of the lesion were similar between groups. In the multivariate analysis, hypertension, emergency status, atherosclerosis grade 3 or 4 (intimal thickening >4 mm), and cardiopulmonary bypass time were independent risk factors for postoperative cerebral embolism, but retrograde perfusion was not.Conclusions:According to the results of postoperative DW-MRI, retrograde perfusion itself might not increase the incidence of postoperative cerebral embolism in properly selected cardiac surgery patients undergoing routine preoperative CTA examination.
1 0 0 0 OA 瀬戸内海における津波の波動特性とその危険度の時空間解析
- 著者
- 山中 亮一 上月 康則 田邊 晋 井若 和久 村上 仁士
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.341-345, 2009 (Released:2010-03-05)
- 参考文献数
- 18
Tsunami disaster prevention of Seto Inland Sea is slow to take action for lack of knowledge of generation mechanism of Tsunami damages. According to previous research papers, there is a possibility of appearance of sudden water level raising and long-term water level fluctuation in sympathetic vibration with characteristic vibration in some bay. Therefore, this study focuses on period characteristics and hazardous sea area. As a result of numerical analysis, temporal period characteristics of each sea area, distribution of largest tsunami heights and time of occurrence, distribution of maximum tsunami velocity and time of occurrence and a map of hazardous sea area are clarified. Moreover, generation mechanisms of Tsunami damages are examined.
1 0 0 0 IR 庚申信仰年譜
- 著者
- 窪 徳忠
- 出版者
- 東京大学東洋文化研究所
- 雑誌
- 東洋文化研究所紀要 (ISSN:05638089)
- 巻号頁・発行日
- no.17, 1959-03
Kōshin beliefs still maintained by many people in Tokyo and other parts of the country are believed by Japanese folklorists to be peculiar to Japanese culture.I cannot help casting doubt on this idea, however, since Kōshin beliefs have much in common with San-shih beliefs of Taoism in China.I recently published a small book entitled'Kōshin Beliefs', in which I tried to make a comparative study.In this book, however, I was unable to drive my argument home, because had to be omitted for fear of over-complexity.In this paper I have prepared a chronological table from the original texts giving data concerning the regular functions of Kōshin beliefs as collected from Japanese history books, diaries, poetry, and other sources from the Nara period to the end of Tokugawa era.The paper gives an outline of change in the functions of Kōshin beliefs in Japan, the terminology used, and the manner in which people worship.I have also included three examples of Kōshin monuments, which I think may be of high value in this.Since the documentary sources which I have used are, of course, limited and they leave many points, which I would like to modify later.
1 0 0 0 OA ともに学ぶ教育学(その9)
- 著者
- 荻野 忠則
- 出版者
- 北海道女子短期大学
- 雑誌
- 北海道女子短期大学研究紀要 = Bulletin of Hokkaido Women's College (ISSN:02890518)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.169-184, 1996
1 0 0 0 OA 繊維からみた古代絹
- 著者
- 布目 順郎
- 出版者
- The Society of Fiber Science and Technology, Japan
- 雑誌
- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.P150-P156, 1976-05-10 (Released:2008-11-28)
1 0 0 0 脳波を用いたセルフケアサポートシステム
- 著者
- 吉村 奈津江
- 出版者
- 東京工業大学
- 雑誌
- 戦略的な研究開発の推進 戦略的創造研究推進事業 さきがけ
- 巻号頁・発行日
- 2017
本研究では、心と身体の健康のセルフケアを、脳波を用いたBrain-Machine Interface (BMI)でサポートすることを目的としています。脳活動情報を用いて心の変動や運動調整能力の解読を実現し、自分の心身状態を日々確認することで、普段気がつきにくい心身の異常をいち早く見つけることができると考えています。この心身の状態を自分でモニタリングし、健康指標を提供するシステム構築を目指します。
1 0 0 0 OA 国立公園の研究にみる協働・市民参加の動向に関する試論
- 著者
- 藍場 将司 原田 一宏
- 出版者
- THE JAPANESE FORESTRY SOCIETY
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース
- 巻号頁・発行日
- pp.96, 2022-05-30 (Released:2022-06-21)
日本の国立公園研究における市民参加・協働に関して、「Cinii」に掲載されている先行研究のレビューと、論文本文の文章解析を実施した。日本の国立公園に関する研究のうち本文が閲覧可能であった698件中、138件で政策への提言が確認された。文章解析の結果、年代を問わず自然・利用・地域・保護が頻繫に用いられており、自然の利用と保護の関係に注目した論考が多いと考えられた。一方で年代を経るにつれ管理が頻出することから、研究者の間で自然への人為的介入の必要性が高まっていると考察された。一方で「管理」は多様な文脈で使用されるため、現地での検証も合わせて行われる必要がある。市民参加や連携に関する提言は27件(19.6%)で確認された。1980年代から2000年代前半までは、地域住民の意思を反映させる制度的・行政的仕組みの欠如が指摘されていた。環境省が連携を進める趣旨の提言を公表した2007年以降、国立公園の協働を主たるテーマとして議論する論考が増加し、「協働」の理論モデルの構築や負の側面にふれる論考が確認されるなど、「協働」を軸に市民参加や連携に関する議論が進行したものと考えられる。
1 0 0 0 OA ヴィニィの《牧人の家》について
- 著者
- 田辺(邊) 純夫 Sumio Tanabe
- 雑誌
- 年報・フランス研究 (ISSN:09109757)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.14-31, 1966-11-25
1 0 0 0 OA 『日本霊異記』における仏法
- 著者
- 斎藤 真希
- 出版者
- 静岡大学人文社会科学部
- 雑誌
- 人文論集 (ISSN:02872013)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.A45-A64, 2017-01-31
1 0 0 0 OA 物語られる『日本霊異記』
- 著者
- 山本 大介
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.12, pp.64-65, 2015-12-10 (Released:2021-01-08)
- 著者
- 荻野 良太 福山 将英 川島 英之
- 雑誌
- 研究報告システムソフトウェアとオペレーティング・システム(OS) (ISSN:21888795)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023-OS-158, no.20, pp.1-6, 2023-02-14
本研究では高性能ハッシュ索引である Optimistic Cuckoo Hashing(OCH)をセキュアに実行するために Intel SGX 内部で動作する OCH を提案する.提案手法を設計,実装し,SGX で評価した.その結果,提案手法は 1 スレッド時に 80 万 ops,4 スレッド時に 220 万 ops の性能を示した.しかし,256 スレッド時にはその性能が 40 万opsに低下した.比較のために Enclave を使用しない Optimistic Cuckoo Hashing を評価したところ,1 スレッド時には 50 万 ops,4 スレッド時で 170 万 ops,256 スレッド時で 3300 万 ops だった.この性能劣化の原因を追究すべく mutex,memory access 速度,Enclave へのデータ受け渡し速度等を調査し,Enclave 内での並列メモリアロケーションがボトルネックであることを突き止めた.
1 0 0 0 安全な機能拡張性を持つTEEシェルの実装
- 著者
- 斎藤 文弥 高野 祐輝 宮地 充子
- 雑誌
- 研究報告コンピュータセキュリティ(CSEC) (ISSN:21888655)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023-CSEC-100, no.60, pp.1-8, 2023-02-27
Trusted Execution Environment (TEE) はファームウェアや OS といった基盤システム内の機微情報を保護することを目的とした隔離環境技術である.先行研究では,TEE アーキテクチャの一つである Arm TrustZone をベースとしてメモリ安全性と効果系という概念を主軸に設計した Baremetalisp TEE,およびその TEE の API 定義用言語である BLisp を構築した.さらに作成した BLisp のコードを Coq にトランスパイルし形式的検証も可能な手法を提案した.TEE は他の隔離環境技術である Trusted Platform Module (TPM) 等とは異なりユーザーが自由にセキュリティ仕様を構築できることが特徴として挙げられるが,Baremetalisp では独自の言語 BLisp を用いているため拡張できる機能に制限が存在していた.そこで本研究では Baremetalisp を構成している Rust から関数を BLisp へ組み込み可能にすることによって,柔軟な機能の拡張性を実現した.組み込み関数にも効果系が適用することができ,メモリ安全性と形式的な正しさを保証しつつ安全な機能アップデートが可能な TEE Shell を実現した.
- 著者
- 小森 工 本田 晋也
- 雑誌
- 研究報告システムソフトウェアとオペレーティング・システム(OS) (ISSN:21888795)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023-OS-158, no.16, pp.1-9, 2023-02-14
組込みソフトウェアの大規模化・複雑化に伴い,高い信頼性を保ちつつ豊富な機能を実装する手法が必要とされている.プロセッサごとに機能を分割して実装する方法はコストや面積,電力等の観点から不利であるため,仮想化技術を利用して同一のプロセッサ上で複数のソフトウェアを動作させる試みが幅広く研究されている.特に ARM 社の TrustZone 拡張は仮想化との相性が良く,アプリケーションプロセッサにおいて仮想化に応用した例は多いものの,マイクロコントローラに対して適用した例は少ない.本研究では TrustZone 機能を実装した ARMv8-M アーキテクチャ上で動作する仮想化環境である SafeG-M を提案する.提案手法は既存のリアルタイム OS に小規模な変更を加えることで実現され,評価実験においてわずかなオーバヘッドで動作することが示された.
1 0 0 0 OA 7テスラ超高磁場MRIによる脳イメージング
- 著者
- 福永 雅喜
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.604-607, 2022 (Released:2022-12-27)
- 参考文献数
- 13
The magnetic field strength meant by ultra–high field magnetic resonance imaging (MRI) has been changing with the development of MRI, and in recent years, it is commonly used to refer to scanners with a magnet of 7 tesla (7T) or higher. The resolution of MRI depends on tissue relaxation time and contrast, as well as the signal–to–noise ratio (SNR). Increasing the magnetic field strength not only improves SNR, but also enhancing the tissue contrast. 7T MRI has significant advantages over conventional 3T MRI, including practical sub–millimeter order spatial resolution and improved sensitivity in functional MRI (fMRI). 7T MRI enhances intra–tissue (within gray and white matter) susceptibility contrast. In addition, high resolution of fMRI at 7T provides the opportunity for the separation of input and output information based on layer specific analysis in local brain regions. With the recent development of post–processing techniques, a paradigm shift from conventional macroscopic mapping (gyrus and sulcus) to analysis of function–structure relationships at the individual level is anticipated.
1 0 0 0 OA 高等教育システム改革に関する豪英比較 「二元制」から「一元制」への転換過程
- 著者
- 杉本 和弘
- 出版者
- 日本比較教育学会
- 雑誌
- 比較教育学研究 (ISSN:09166785)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.24, pp.141-160, 1998-06-30 (Released:2011-01-27)
The purpose of this paper is to comparatively examine higher education reforms in Australia and Britain, forcusing on the transformation process from binary systems to unitary ones, and to clarify some factors which brought about such a transformation.
1 0 0 0 OA 春採斜坑の新運炭設備とその効果
- 著者
- 小林 佑司
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 資源と素材 (ISSN:09161740)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.11, pp.779-781, 1989-10-25 (Released:2011-01-27)
1 0 0 0 OA 果菜類の生育とビタミンCの分布 (II) トマト, ピーマン, イチゴ
- 著者
- 北川 雪恵
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.139-143, 1973-12-29 (Released:2009-11-16)
- 参考文献数
- 4
前報に続いて果菜類のトマト, ピーマン (ナス科), イチゴ (バラ科) を用いて生育時期別, 上下部位別, 組織別のV. C量の変化について観察した。1) トマトの果実の生育に伴うV. C量 (mg%) の変化は総C, 還元型Cでは生育につれて増加し, いわゆる収穫期に最高になるが, 完熟期には逆に減少した。 細かく上下部位別の差異を果肉部でみると, 全期間を通じて基部に最も多く, 先端部がこれにつぎ, 中部が最も少なかった。 また組織別では全期を通じて胎座・種子部が果肉部より多く, とくに種子を含むゼリー状部に多かった。なお, 酸化型Cについては未熟期ほど多く, 生育につれて減少したが, 部位別, 組織別には総Cとほぼ同様の傾向がみられた。2) ピーマンの果実の生育に伴うV. C量 (mg%) の変化は総C, 還元型Cでは生育につれて漸増し, とくに完熟期に著しい。 上下部位別の差異を果肉部についてみると, 幼果期には中部に多いが, 収穫期以後は果頂部に最も多かった。 組織別にみると, 全期間を通じて果肉部にとくに多く種子部, 胎座部には少なかった。 また果肉部, 胎座部は完熟期に著しく増加するが, 種子部では反対に減少した。なお, 酸化型Cについては幼果期に多く, 収穫期にやや減少するが過熟期になると再び増加した。また果肉部よりは種子と胎座部に多かった。3) 可食適期のイチゴの場合を上下部位別にみると総C, 還元型Cは果頂部に近いほど多く含まれ基部に最も少なかった。また組織別では皮部にとくに著しく, ついで果肉部に多く含まれ芯部は最も少なかった。酸化型Cについても総Cの場合と同様の傾向が認められた。
1 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症に対する地方自治体および保健所の対応
- 著者
- 白井 千香 内田 勝彦 清古 愛弓 藤田 利枝 上谷 かおり 木村 雅芳 武智 浩之 豊田 誠 中里 栄介 永井 仁美 矢野 亮佑 山本 長史
- 出版者
- 国立保健医療科学院
- 雑誌
- 保健医療科学 (ISSN:13476459)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, pp.292-304, 2022-10-31 (Released:2022-11-18)
- 参考文献数
- 7
保健所は2022年 4 月時点で全国に468か所設置されており,「地域保健法(1994年)」に基づき,健康危機管理の拠点となる役割をもち,災害時や感染症対応には主体的に関わることになっている.新型コロナウイス感染症対応が始まってから,自治体はこの 2 年半,第 1 波から第 7 波の現在に至るまで,流行状況およびウイルス変異及び重症度等に応じて,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき様々な感染症対応に模索を繰り返してきた.基本的には全国的に共通する感染症対応業務(相談,検査,発生届受理,入院調整,患者の移送,健康観察,積極的疫学調査,入院勧告や就業制限通知等)を行うが,都道府県単位で,感染症の発生状況や医療資源の違いもあり,具体的な業務内容や方法は全国一律ではなく,現実的には地域の実情により,それぞれの自治体で工夫されてきた.流行状況を振り返ると,第 1 波,第 2 波,第 3 波は全国的に行動制限を要請され,PCR検査の需要と医療体制の供給がミスマッチであった.新型コロナウイルスは変異以前の特徴として呼吸器機能を低下させる病原性を持ち,有効な薬剤やワクチンがまだ普及せず,診療可能な医療機関も不足していた.第 4 はα株で高齢者の施設内感染で医療提供が困難となり,第 5 波は東京オリンピックの後でδ株の変異ウイルスが主となり,首都圏での流行が目立った.第 6 波および第 7 波はο株が中心で感染性が高く,病原性は低いが感染者数の急増かつ膨大なため,保健所の能力を大きく上回る対応が求められた.全国的にどこの自治体でも保健所の負担軽減策について外部委託も含めて対応するようになった. 2 年半の間に厚生労働省からの通知も多く,全国保健所長会は要望や提言などの意見活動も行った.日本は自然災害の多い国であるが故に,健康危機管理として災害や感染症においては,保健所が平時から備えとしての仕組みづくりや危機発生時の対応,被害からの回復という過程において,主体となることが期待されている.新型コロナウイルス感染症対策で得た教訓を生かしパンデミックとなりうる感染症対策を地域単位で行っていくため,住民の命と健康を維持する「保健所」を,医療機関や福祉施設等と有機的に連携し,持続可能な社会の枠組みとして活かしていくことを提言する.
1 0 0 0 OA 私立大学における非常勤講師の雇用問題に関する試論的考察 : USRの視点から
- 著者
- 小池 裕子
- 出版者
- 日本経営倫理学会
- 雑誌
- 日本経営倫理学会誌 (ISSN:13436627)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.117-127, 2014-02-28 (Released:2017-08-08)
Part-time lecturers represent 57.6% of all the lecturers in Japanese private universities, and a wide gap in working conditions between full-time and part-time lecturers exists. Part-time lecturers, in many cases, are used as cheap labour regardless of their contribution. This paper examines which type of universities depends on part-time lecturers by multi-regression analysis. The results show that the employment of part-time lecturers is not necessarily inevitable by financial reason and there is room to improve the working conditions of such lecturers from the viewpoint of USR (University Social Responsibility).