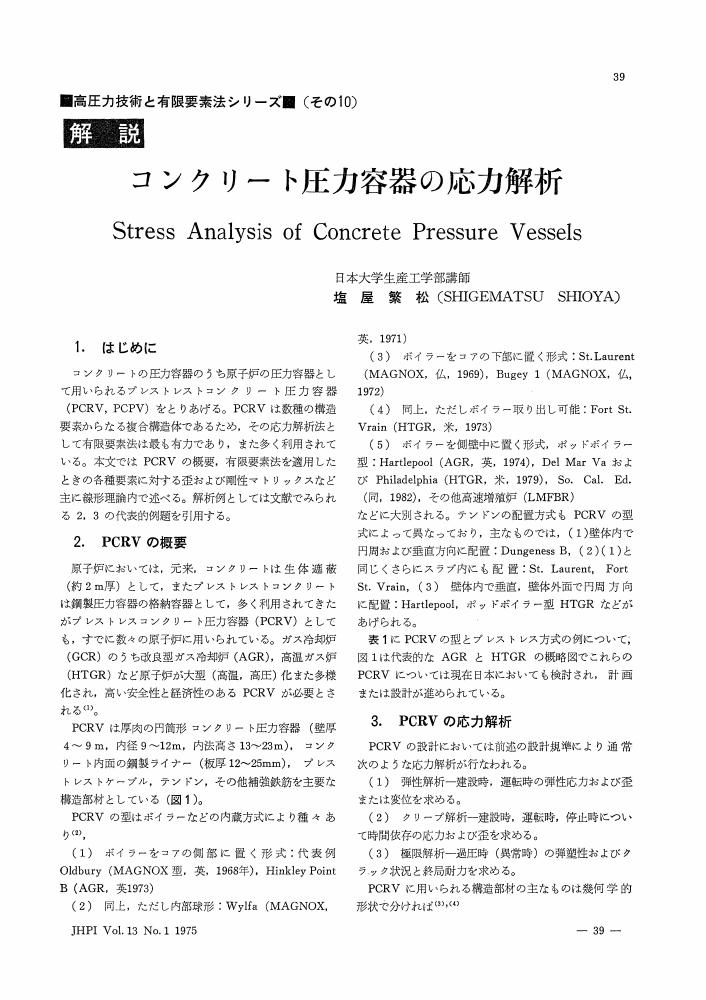1 0 0 0 OA コンクリート圧力容器の応力解析
- 著者
- 塩屋 繁松
- 出版者
- 一般社団法人 日本高圧力技術協会
- 雑誌
- 圧力技術 (ISSN:03870154)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.39-48, 1975-01-25 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 焼酎ブームの論点整理と本格焼酎の生産・流通・消費の特徴
- 著者
- 渡辺 克司
- 出版者
- 鹿児島国際大学経済学部学会
- 雑誌
- 鹿児島経済論集 (ISSN:13460226)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1-4, pp.65-98, 2013-03-06
1 0 0 0 OA 焼酎製造における豪州産大麦の原料事情
- 著者
- 岩見 明彦 大森 俊郎
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.11, pp.784-793, 2004-11-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 1
麦焼酎の原料である大麦は, 国内産では到底まかなえないため, その大部分を豪州産大麦に頼っている。そこで, 豪州産大麦の研究の重要性に鑑み, 筆者等は平成9年より研究を重ねてきた。今回は, 研究成果を基に豪州産大麦の生産状況, 流通の仕組み, 品質・安全性についての報告と, 焼酎用原料としての精麦特性と醸造特性について, SKCSを用いた測定結果が紹介されている。麦焼酎の生産者にとっては, たいへん参考になると思われる。
1 0 0 0 OA III. 焼酎 (その3) 本格焼酎の減圧蒸留について (2)
- 著者
- 宮田 章
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.218-224, 1986-04-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 地域経済に寄与する焼酎製造業の展開条件 : 鹿児島県の芋焼酎産業を事例に
- 著者
- 盧 生奇 白武 義治
- 出版者
- 日本農業市場学会
- 雑誌
- 農業市場研究 (ISSN:1341934X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.33-44, 2005-12-31 (Released:2019-12-08)
The food industry is deemed an important economic sector in Japan. In the case of many remote areas, the food industry, in combination with primary industry activities, has been recognized as a major economic sector, leading regional economies in terms of creating job opportunities. Recently, however, due to the continuing overall economic slump, the food industry in Japan has been facing a sharp reduction in the number of companies and overall labor force. In addition, after joining the WTO in 1995, Japanese food companies have been thrown into severe business competitions in the international markets. Moreover, the LDC might compel the food industry to invest in environmental conservation efforts by 2007. The imo-shochu industry, a traditional Japanese food industry related closely to regional agriculture, stands as a leader in many regional economies, in both production as well as sales. As such, examining the major economic factors by which the imo-shochu industry has maintained such sustainable development is of value. Through use of endogenous development theory, this study empirically identified these factors through an examination of the imo-shochu industry of Kagoshima.
1 0 0 0 OA 要支援・軽度要介護高齢者における抑うつとサルコペニアの関係
- 著者
- 佐藤 稜 沢谷 洋平 柴 隆広 広瀬 環 佐藤 南 石坂 正大 久保 晃
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.5, pp.673-677, 2020 (Released:2020-10-20)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3 3
〔目的〕要支援・軽度要介護高齢者における抑うつとサルコペニアの関係を明らかにすること.〔対象と方法〕通所リハビリテーション利用者,要支援1・要支援2・要介護1の65歳以上の高齢者79名,男性45名,女性34名を対象とした.抑うつの程度におけるサルコペニアの有病率と抑うつの程度における筋力,身体機能,骨格筋量の関係を検討した.〔結果〕男性のみ抑うつの程度とサルコペニアの有病率に有意な関連を認めた.また,男性は抑うつが強くなるに伴い骨格筋量の有意な低下が認められた.女性においては有意差が認められなかった.〔結語〕抑うつとサルコペニア間に,性差が存在し男性要支援・軽度要介護高齢者において抑うつとサルコペニアに関連があることが明らかとなった.
1 0 0 0 OA 会員の声
- 出版者
- 日仏哲学会
- 雑誌
- フランス哲学・思想研究 (ISSN:13431773)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.284-287, 2022-09-01 (Released:2022-10-01)
- 著者
- 丸山 俊明 日向 進
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.535, pp.223-230, 2000-09-30 (Released:2017-02-03)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 3 3
This study aims to clarify the building regulations in agricultural district of Yamashiro province through the Edo period. In Yamashiro province, official notices by Kyoto machibugyosho (magistrate's office) obligated every farmers to present the application forms for building up to Kyoto machibugyosho till 1767. But, in south Yamashiro province, there are some documents prove the existence of buildingregulations by Kyoto daikansho (regional office of administrative official) or Jito (manner's lord ) till the late 1730's. This paper takes up them.
1 0 0 0 OA と畜検査からみた家畜腫瘍の検出状況について
- 著者
- 岩間 公男 宇根 ユミ 吉田 拓郎
- 出版者
- 獣医疫学会
- 雑誌
- 獣医科学と統計利用 (ISSN:18845606)
- 巻号頁・発行日
- vol.1983, no.11, pp.21-28, 1983-12-30 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 5
1962年から1982年の21年間に横浜市食肉衛生検査所で食用としてと殺された牛257, 340頭, 豚2, 408, 286頭, 馬1, 756頭, 緬山羊643頭について, 腫瘍の検出率および発生部位を調査するとともに, 検出された腫瘍 (牛114例, 豚716例) の病理組織学的分類を試みた結果, 次の成績が得られた。1) 牛における腫瘍の検出率 (10万頭あたり) は, 21年間の平均で44.3であったが, 腫瘍の検出されなかった1962, 1963年を除き, 13~102の間で変動した。豚における検出率は, 平均29.7であった。年次別には, それまで20以下であった検出率が, 1974年頃から急速に増加して, 1977年に最高 (104.5) となった後, 35~80の間で変動しながら, 除々に減少の傾向を示した。2) 家畜の種類・用途別にみた腫瘍の検出率は, 牛では乳用種66.9, 肉用種10.0, 豚では, 肥育肉豚14.4, 繁殖豚405.3で, 牛では乳用種, 豚では繁殖豚において検出率が有意に高かった (P<0.05) 。3) 腫瘍の好発器官 (上位5つ) は, 牛では消化器 (9.7) , 造血器 (8.5) , 生殖器 (7.8) および内分泌器 (6.6) , 豚では消化器 (14.3) , 泌尿器 (8.8) , 生殖器 (3.9) および造血器 (1.8) であった。4) 検出された腫瘍は, 病理組織学的に牛では38種類, 豚では25種類, 全体では50種類に分類された。しかし, 1個体に2種類以上の腫瘍が重複して認められた例はなかった。5) 検出頻度の高い腫瘍 (上位5つ) は, 牛では白血病嘲 (8.5) , 顆粒膜細胞腫 (5.8) , 副腎皮質腺腫 (3.1) , 肝細胞癌 (2.3) および肝腺腫 (1.9) , 豚では肝腺腫又は結節性増生 (13.9) , 腎芽腫 (8.7) , 白血病 (1.8) , 卵巣血管腫 (1.7) および子宮平滑筋腫 (1.5) であった。
1 0 0 0 OA 写真感光材料の粒状性
- 著者
- 大上 進吾
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会会誌 (ISSN:18846327)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.38-47, 1959-03-25 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 44
1 0 0 0 OA 二酸化炭素回収型バイオガスPSA技術
1 0 0 0 OA 貸本屋大惣の改装表紙から見る文化・文政・天保期間の合巻の仕入れ
- 著者
- ミギー ディラン
- 出版者
- 人間文化研究機構 国文学研究資料館
- 雑誌
- 第41回 国際日本文学研究集会会議録 = PROCEEDINGS OF THE 41st INTERNATIONAL CONFERENCE ON JAPANESE LITERATURE (ISSN:03877280)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.68-54, 2018-03-28
This paper will examine over 34 different varieties of protective covers used by the Daisō lending library throughout the nineteenth century, categorizing them according to pattern. When cross-referenced with the publication dates of the book on which they appear, these covers yield a consistent data set for dating the acquisition of individual books—something that has not been possible previously due to the absence of detailed house records.The Daisō lending library operated for nearly 150 years in castle town of Nagoya and at its height was regarded as the largest commercial lender in all of Japan. While there has been extensive research on the history of the firm, as well as a full bibliographic survey of its extant books, to date very little is known about its day-to-day operations, given the dearth of house records about its acquisition and lending practices. Accordingly, this paper will seek to model a new approach for dating the acquisition of Daisō books, based on a cross-referencing of cover varieties with publication data.The practice of fitting heavily circulating gōkan with protective covers appears to have begun at the Daisō around Bunka 8 (1811), when the first proprietor, Ōnoya Sōhachi I (Tojirō) passed away and was succeeded by his son Seijirō. This practice continued for at least fifty years, with evidence of newly fitted covers dating to Bunkyū 1 (1861) and later. The covers themselves appear to have been intended to minimize wear and tear on the lavishly illustrated gōkan, whose brilliant nishiki-e covers were an object of interest for lending library readers. The covers featured a different design each year, beginning with relatively simple brushstroke designs in the 1810s and 1820s, and progressively moving to more complex abstract (stripes, lattices, and swastikas) and figural patters (seashells, animals, etc.).This paper proposes that the Daisō alternated varieties of protective covers from year to year and fitted them on books that circulated heavily soon after acquisition. By cross-referencing the annual varieties of covers with the publication dates of the books on which they appear, it is possible to estimate the year of acquisition. At the same time, this material enables us to create windows for estimating the production of manuscript books and paratextual materials like ads for Daisō brand medicines and cosmetics.
1 0 0 0 OA 〈論文〉新型コロナウイルス感染症禍の社会と人権―情報リテラシー・差別・政治の視点で―
- 著者
- 北口 末広
- 出版者
- 近畿大学人権問題研究所
- 雑誌
- 近畿大学人権問題研究所紀要 (ISSN:18808417)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.1-28, 2021-03-31
- 著者
- 長野 伸彦
- 出版者
- 日本大学医学会
- 雑誌
- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.237-241, 2022-08-01 (Released:2022-09-27)
- 参考文献数
- 33
- 著者
- 合谷 祥一 村上 敦 佐藤 桂子 稲積 佐代子 山野 善正
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.9, pp.679-684, 2000-09-15 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 11
疎水基であるトリテルペノイド基にカルボキシル基が結合したムクロジサポニン(SS)の界面活性,乳化性,クリーミング安定性およびゼータ電位に対するpHの影響を調べ,特にクリーミング安定性とゼータ電位についてSoyasaponin I (SI)によるエマルションと比較した.(1) 界面生成直後の界面張力は,pH 7以下でほぼ一定であり,pH 8以上で大きく増大し,pH 9で一定になった.界面生成3時間後では,pH 5以下で,界面に不溶性の膜が観察された.(2) SSはpH 6未満でそれ以上よりも低い乳化性を示した.(3) SSのエマルションのクリーミング安定性はpH 6以下で低くなり,乳化性と一致した傾向を示した.pH 7以上では,SIよりも平均粒径が低いにも関わらず,高い水相分離率を示した.(4) ゼータ電位は,pH 6から8にかけて増大し,pH 8.5以上でほぼ一定になった.また,どのpHにおいてもSIエマルションのゼータ電位よりも低い値を示した.
細胞内寄生性細菌である肺炎クラミジア(我々が同菌日本株の全ゲノムを初めて解読し、種々のユニークな機能を解明)は、肺炎の主要原因菌で動脈硬化病変部にその感染がほぼ100%検出される。クラミジアは約3日間の生活環で動物細胞内で、封入体を形成した後、細胞外へ放出されることから、その生活環とアポトーシスとの関係も解明が期待される。また、同菌は感染細胞内で封入体膜を形成して、数日のlife cycleを経て増殖し細胞外に放出されるが、これまでに我々はアポトーシス制御因子Apaf-1欠失細胞ではクラミジア増殖が高度促進されており、この封入体膜タンパクの1つIncA2(カスパーゼをリクルートするドメインCARDを持つ)がcaspase-9の活性を増強したり、ミトコンドリアタンパクとの相互作用により宿主細胞アポトーシスを制御して菌の増殖を制御していることを発見している。21年度では封入体膜タンパクIncA2がApaf-1やcaspase-9などからなる宿主アポトゾームをいかなる機構により制御されていることがわかった。すなわちApaf-I欠失細胞で肺炎クラミジア感染増幅、caspase9欠失で感染低下があり、caspase9阻害剤による肺炎クラミジア増殖抑制機序の解明ができた。また、クラミジア封入体膜・IncA2と宿主アポトソームの相互作用も確認できた。22年度はさらにApaf-1のクラミジア感染抑制に機能するドメインの同定を試みたが、とくに特定の部位としてクラミジアに特異的に作用するものではなく、Apaf-1のもつカスパーゼ活性化の制御によるアポトーシスの制御によってクラミジアの増殖が影響されることが解明された。またクラミジア封入体内にcaspase9の存在が形態的にとらえることができ、クラミジアが増殖にcaspase9を利用しているか、細胞質内のcaspase9を減少させてアポトーシスを制御することがクラミジアの増殖に関係していることが示唆された。caspase3やcaspase8の変化は2時的なものでクラミジアの増殖に直接的に関与するものでないことも示された。
1 0 0 0 OA PRESERVATION OF STREPTOMYCETES
- 著者
- MONIKA ZIPPEL MARLIES NEIGENFIND
- 出版者
- Applied Microbiology, Molecular and Cellular Biosciences Research Foundation
- 雑誌
- The Journal of General and Applied Microbiology (ISSN:00221260)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.7-14, 1988 (Released:2006-08-18)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 7
Three methods for preserving 16 Streptornyces strains were tested: lyophilization on soil and storage in frozen glycerol medium (-20°C), and in liquid nitrogen (-196°C) in the presence of dimethyl sulfoxide. The viability, stability of auxotrophic markers, antibiotic production, and resistance to their own antibiotics for a period up to one year were studied. No variations in the production of and resistance to antibiotics or accumulation of revertants of mutants were evident during the toral preservation time in all three storage methods. A drastic decrease in viable counts was observed after lyophilization on soil. Viability of strains frozen in glycerol and after storage in liquid nitrogen was similar and ranged from 2.3% to 36.6%.Storage of streptomycetes in frozen glycerol is recommended as a quick and reliable method for frequent studies in the laboratory. Storage in liquid nitrogen is recommended as a long-term preservation method.