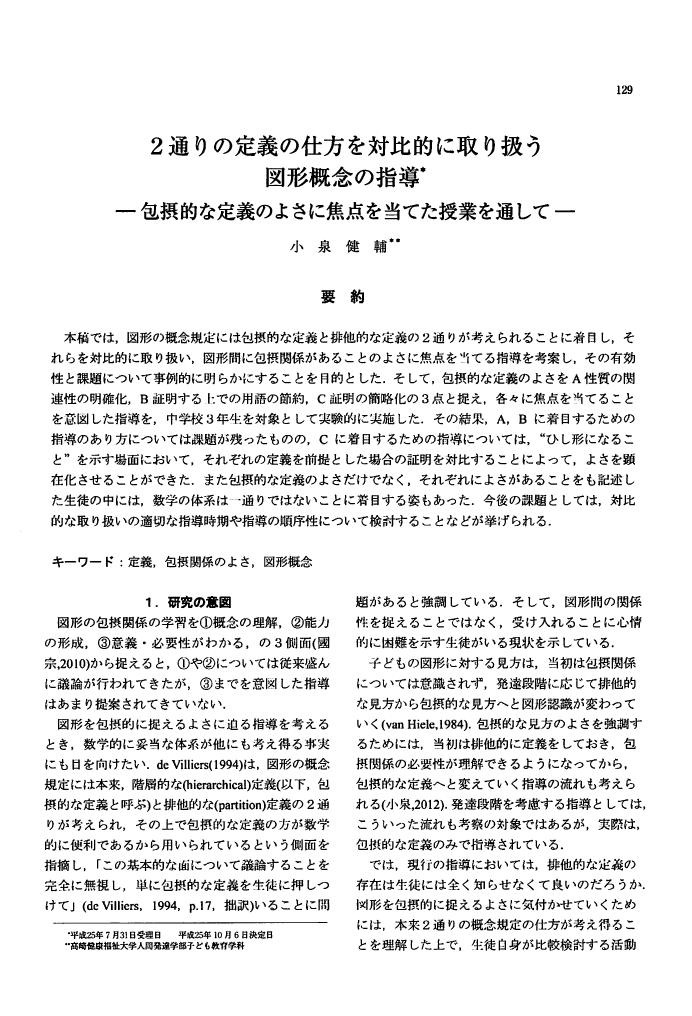1 0 0 0 OA 修身教授及訓練法 : 実験立案
1 0 0 0 OA 看護の場にある「身体」の捉え : 研究の必要性と課題
- 著者
- 伊藤 祐紀子
- 雑誌
- 北海道医療大学看護福祉学部学会誌 = Journal of School of Nursing and Social Services, Health Sciences University of Hokkaido
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.5-13, 2010-03-31
1 0 0 0 金沢医科大学十全会雑誌
1 0 0 0 OA 花田清輝の共同制作論
- 著者
- 石井 伸男
- 出版者
- 社会文化学会
- 雑誌
- 社会文化研究 (ISSN:18842097)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.16-28, 1997 (Released:2019-07-25)
1 0 0 0 塗装と塗料 = The finish & paint
- 出版者
- 塗料出版社
- 巻号頁・発行日
- no.171, 1969-05
- 著者
- 奥村 直史
- 出版者
- 山梨大学教育人間科学部
- 雑誌
- 山梨大学教育人間科学部紀要 = 山梨大学教育人間科学部紀要 (ISSN:18825923)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.45-51, 2016-03-04
1 0 0 0 蹴鞠技術変遷の研究
1.研究の目的:平安時代から江戸時代に至る蹴鞠技術の変遷を総合的に考察するため、(1)文献の研究および翻刻、(2)現在まで蹴鞠の技法を伝承している団体である蹴鞠保存会の会員を対象にした、技法の調査や練習法の聞き取り調査、(3)鞠の復元製作とこれを利用した実技再現、を行なう。2.研究成果の概要:(1)蹴鞠関係の文献は、宮内庁書陵部・国立公文書館内閣文庫・国立国会図書館など各所に所蔵されるが、ここでは天理大学付属天理図書館・滋賀県大津市平野神社の2箇所に所蔵されるものに重点を絞って調査した。天理図書館は、かつて蹴鞠保存会にあった文献200余点を一括収蔵する。その中から今年は27点の調査を行なった。平野神社は、江戸時代に飛鳥井家と並ぶ蹴鞠道家(家元)であった難波家の史料を一括収蔵する。江戸時代中期の難波家当主がまとめた『蹴鞠部類抄』など他所にはない文献も多く、写真によって逐次解読作業を進めている。以上の調査を踏まえて、鎌倉時代初期に成立したと考えられる『蹴鞠口伝集』と、鎌倉時代末頃にまとめられた『内外三時抄』の2点を翻刻した。(2)実技の調査は、蹴鞠保存会の練習日に合わせて2度京都まで出張したが、いずれも豪雨となり、実現しなかった。やむなく聞き取り調査のみを行なった。(3)鞠の復元は、各所に問い合わせてみたが研究費の範囲では実現不可能との返事で、断念せざるをえなかった。ただ蹴鞠保存会が行なった鞠の「突直し」(補修)は見学することができた。3.研究発表:スポ-ツ史・日本史・日本文学などの研究者に呼び掛け、東京および京都で研究会を行なった。特に京都では蹴鞠保存会会員の参加があり、鞠・装束・沓などを実見出来た。報告書は、研究報告(3編)・文献研究(2編)・文献の翻刻・参考文献・平野神社所蔵史料目録など、計388ペ-ジとなっている。
1 0 0 0 OA 量的緩和政策 : 2001年から2006年にかけての日本の経験に基づく実証分析
- 著者
- 本多佑三
- 出版者
- 財務省
- 雑誌
- フィナンシャル・レビュー
- 巻号頁・発行日
- no.99, 2010-02
1 0 0 0 OA 2型糖尿病モデルマウスのアディポカインに対するアントシアニンの作用
- 著者
- 坂崎 文俊
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.259, 2020 (Released:2020-03-01)
- 参考文献数
- 3
健康食品市場は拡大の一途である.日本の公的な健康食品制度に機能性表示食品が加わり,機能性表示食品は特定保健用食品に比べて届出のハードルが低いため,実にたくさんの届出が行われている.昭和46年(1971年)厚生省薬務局長通知(通称「ヨンロク通知」)により毒性の強いアルカロイドを健康食品の関与成分にできないこともあり,機能性表示食品の関与成分にはポリフェノール類が多い.ポリフェノール類は,酸化ストレスに対して防御機能を有すると考えられる.酸化ストレスは体の様々な部分で悪影響を及ぼすため,抗酸化物質の利用は多様な健康効果があると期待される.最近,心血管障害および高血圧に対するポリフェノール類の作用について,ヒトを対象とした疫学研究のシステマティック・レビューが報告された.食物摂取頻度調査票とアメリカ合衆国農務省の作成する栄養成分データベースから食品成分の摂取量を計算した前向きコホート研究6報を総合した結果,ポリフェノール類の分類の中でもアントシアニン類の効果が統計的に有意のようである.ここで紹介する論文は,2型糖尿病モデルマウスに,アントシアニンを豊富に含有するタルトチェリーの抽出物を投与した結果,炎症性アディポサイトカインの産生を抑制したとの報告である.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Del Bo’ C. et al., Nutrients, 11,1355(2019).2) Godos J. et al., Antioxidants, 8,152(2019).3) Nemes A. et al., Nutrients, 11,1966(2019).
1 0 0 0 ビルマの夜明け : バー・モウ(元国家元首)独立運動回想録
1 0 0 0 OA 古文書時代鑑
- 著者
- 東京帝国大学文学部史料編纂掛 編
- 出版者
- 東京帝国大学文学部史料編纂掛
- 巻号頁・発行日
- vol.上, 1928
本研究は、「地域包括ケア」「地域共生社会」が目指される時代に、地域において障害や病い、または、生きづらさなどを抱える人たちがどのように支援と関わりながら日常生活を送り、それを支える人たちがどのように支援実践や居場所を形成してきた/いるのかを、領域横断的な研究者の経験的調査によって明らかにする。この作業を通じて、現在、政策目標とされている地域包括ケアや地域共生社会に向けた課題の明確化を目指す。中心となる研究領域は認知症ケアおよび障害者支援であり、これらの研究を中核として、さらに他領域の支援実践に関する研究の知見を付き合わせていく。
1 0 0 0 OA 無彩色系金属上への染料による着色電着塗装
- 著者
- 黒田 孝一 柴田 清勝 桑原 博昭
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 金属表面技術 (ISSN:00260614)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.62-66, 1986-02-01 (Released:2009-10-30)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 小泉 健輔
- 出版者
- 公益社団法人 日本数学教育学会
- 雑誌
- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.RS, pp.129-136, 2013-11-16 (Released:2021-04-01)
1 0 0 0 OA キャリアデザイン談話室(11) 悩んだら思考をやめて行動する
- 著者
- 西川 宗
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.198-199, 2022 (Released:2022-07-25)
- 参考文献数
- 2
- 著者
- 山本 勝則 守村 洋 河村 奈美子
- 出版者
- 札幌市立大学
- 雑誌
- 札幌市立大学研究論文集 = SCU Journal of Design & Nursing (ISSN:18819427)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.53-59, 2013-03-31
本論文の目的は,精神看護学におけるシミュレーション教育の動向を概観し,シミュレーション教育に関する我々の取り組みを報告し,今後の教育方法の開発計画を提示することである.国内ではシミュレーション教育あるいはOSCE(Objective Structured Clinical Examination)を用いて精神看護学教育を体系的に行っている報告はほとんど見当たらず,国外でも取り組み始めたばかりである.文部科学省と厚生労働省は,看護教育における実践能力の育成・向上を主要課題の一つとしている.この課題に取り組む方策の一つとして,OSCEなどのシミュレーションを取り入れた看護教育が活発に行われている.しかし,精神看護学教育においては,シミュレータの開発が困難であることや看護技術が状況依存的であり評価が困難なことなどにより,導入が遅れている.そのような状況の中で,米国等では模擬患者(SP)を導入したシミュレーションや,シミュレータを用いた教育などの新たな展開がみられるようになった.「リアリティの高い学習への移行」を目指して精神看護教育を行っていた我々は,OSCE,SP(Simulated/Standardized Patient)参加型シミュレーション演習と,順次シミュレーション教育を導入してきた.精神看護学におけるシミュレーション教育への学生の評価は概ねポジティブである.基本的なコミュニケーション技術が獲得されていることも確認できた.今後,特に重要なこととして,①シナリオの開発,②教育全体の洗練(効率化とさらなる工夫の導入),③対外的発信がある.また,この教育方法が学生に自信を与える影響も評価する必要がある.
- 著者
- 甲斐 勝二 Kai Katsuji
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.1283-1320, 2021-03