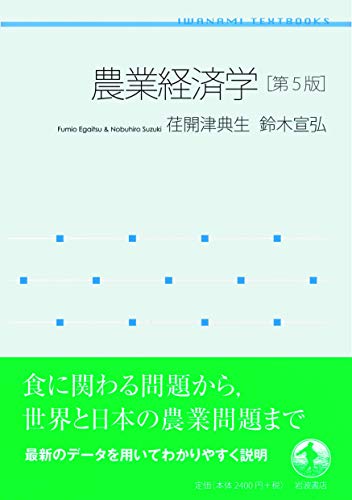1 0 0 0 農業経済学
- 著者
- 荏開津典生 鈴木宣弘著
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 2020
1 0 0 0 OA 頚肋を伴う非特異的両上肢痛の1症例
- 著者
- 西 啓太郎 江原 弘之 岩﨑 かな子 内木 亮介 中西 一浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.7, pp.157-160, 2022-07-25 (Released:2022-07-25)
- 参考文献数
- 9
頚肋を有し,他院で胸郭出口症候群と診断された20代男性に対して,医師と理学療法士が協働して上肢痛の治療選択をした.その結果,頚肋による神経および血管の圧迫の可能性が低く,非特異的上肢痛であり,運動器リハビリテーションの適応があると判断した.10回のリハビリテーションとデュロキセチンの内服により,123日目に症状が改善した.集学的な評価が侵襲的治療を最小限に抑えることに有効であった.
1 0 0 0 OA 保険市場における情報の非対称性 ―実証研究のサーベイ―
- 著者
- 斉藤 都美
- 出版者
- 公益財団法人 損害保険事業総合研究所
- 雑誌
- 損害保険研究 (ISSN:02876337)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.147-174, 2011-05-25 (Released:2020-07-18)
- 参考文献数
- 41
- 著者
- かながわ考古学財団 [編]
- 出版者
- かながわ考古学財団
- 巻号頁・発行日
- 1995
1 0 0 0 OA 熱の流れを等価回路で考える 缶ビールは何分で冷える?
- 著者
- 長坂 雄次
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.10, pp.703-706, 1997-09-20 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 逆説の自律神経学
- 著者
- 田村 直俊
- 出版者
- 日本自律神経学会
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.64-69, 2019 (Released:2019-07-01)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 1
自律神経学を構築したLangleyとCannonの論述には疑問がある.(1) 自律神経と情動:JamesとLangeは自律神経活動が情動を惹起するとし,Cannonは情動が自律神経に影響を及ぼすとしたが.後者の見解は末梢神経だけを自律神経と定義したLangleyに由来する誤解である.情動の主座の間脳は中枢自律神経線維網の一部である.(2) 脊髄副交感神経:Langleyは胸・腰髄から起始する副交感神経を否認したが,呉らはイヌの脊髄後根を切断し,中枢側断端で変性を免れた遠心線維(脊髄副交感神経)を証明した.(3) 脱神経過敏:Eppingerらは交感神経緊張症でadrenalineに対する臓器反応が亢進すると主張した.この見解は脱神経過敏の法則(Cannon)に反すると批判されたが,Eppingerらの症例は自律神経不全症ではないので,脱神経過敏の観点からこの学説を批判するのは見当違いである.
1 0 0 0 OA ラスクの改訂「法律哲學」
- 著者
- 和田 小次郎
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稲田法学 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-56, 1929-02-20
1 0 0 0 イスラームの革命と国家 : 現代アラブ・シーア派の政治思想
- 著者
- ムハンマド・バーキル・アッ=サドル ムハンマド・フサイン・ファドルッラー著 小杉泰編訳
- 出版者
- 国際大学中東研究所
- 巻号頁・発行日
- 1992
- 著者
- 山田 裕一 宮崎 康支
- 出版者
- 松本短期大学
- 雑誌
- 松本短期大学研究紀要 (ISSN:09107746)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.49-60, 2022-03
幼児教育・保育者向け指南本(いわゆる「ハウツー本」)のテクスト分析を通して、障害児教育・保育における環境づくり、言葉がけ、そして人間関係についての射程を明らかにした。一般の幼稚園・保育園において障害児や医療的ケア児等の受入を一般化しようという社会的潮流と、それに伴う制度的変遷などを受け、保育所・幼稚園の保育者においては障害児保育等に関する学習やスキル向上の必要性に駆られている。研修以外の有力な学習方法の選択肢として指南本があり、その分析を通して伝達されうるメッセージを検討した。特に国が示すあるべき保育のあり方や障害者権利条約および障害者差別解消法施行に伴う、障害の社会モデルの考え方がどのように反映されているのかについて、2冊各2版の指南本において環境づくり・言葉がけ・人間関係に関する論点について分析・検討した。その結果、指南本における指導の射程として保育の多様性や子どもの理解、そしてユニバーサルデザイン等の理念を掲げて伝達されていた。一方で、個別の言語・図像表現と全体的な内容が子どもの医学的・個人的理解に傾斜しているように読み取れた。これはイラストや図を用い、わかりやすさや手に取りやすさを重視した指南本の限界である可能性がある。今後の研究課題としては、こうした指南本に幼児教育・保育の政策がどのようにして言語・図像において表現され、それが如何にして読者に解釈されうるか、また指南本では伝わりにくい子どもの多様性を大切にする保育のあり方や社会モデルの哲学・理念をどう伝えていくかという点になる。(著者抄録)
1 0 0 0 OA 精密水準測量概説 —火山活動に伴う微小な地盤上下変動の検出を目指して—
- 著者
- 山本 圭吾
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.221-231, 2022-06-30 (Released:2022-07-28)
- 参考文献数
- 13
- 著者
- 青山 裕
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.171-193, 2022-06-30 (Released:2022-07-28)
- 参考文献数
- 86
Volcanoes in Hokkaido had vigorous eruption histories in the last 400 years. Especially in the southern Hokkaido, Hokkaido-Komagatake, Usuzan, and Tarumaesan, reawakened in the 17th century after the long-dormant period and vigorous magmatic eruptions of VEI5 class have been recorded in the historical literature and also in geological layers. Contrary to these volcanoes, we have documented histories only after the 20th century for Tokachidake and Meakandake. Continuous volcano monitoring has been performed in major active volcanoes in Hokkaido since 1960s. In the 1970s, with the increase in seismic activity of Tokachidake, sponsored research from Hokkaido Government to Hokkaido University began to establish disaster management plans for future eruptions of active volcanoes in Hokkaido, and research reports was edited by Hokkaido University. Although 50 years have passed since the publication of the first report on Tokachidake, the reports of the research on active volcanoes are still one of the first documents to be referred when investigating the past activities of volcanoes in Hokkaido and the results of old scientific surveys. In addition, the reports include interdisciplinary contents for that time such as prediction of future eruptive activities and disaster prevention measures. The sponsored research by Hokkaido Government has continued to the present, and a new report on Tokachidake was published in 2014. The compilation of such research reports is very effective for volcano researchers and for relating field to share their awareness of the problems of volcanoes beyond their individual fields of expertise. Monitoring network around the active volcanoes in Hokkaido has been remarkably improved for these 20 years by Japan Meteorological Agency (JMA), Hokkaido University and other relating institutions. Recent data exchange in real-time among different organizations reduces duplication of monitoring resources and increases multi-parameter monitoring ability. The improved volcano monitoring network is expected to detect precursory activities of future magmatic eruptions concerned at the major volcanoes. Looking back on the eruption in the 20th century in Hokkaido, small phreatic eruptions preceded magmatic vigorous eruptions in many cases. Not only mountaineers but also tourists and citizens can easily approach the crater area without any special equipment at several active volcanoes, so even a small eruption can lead to severe volcanic disaster. (View PDF for the rest of the abstract.)
- 著者
- 宇田川 光弘
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.186, pp.186_113-186_128, 2017-01-30 (Released:2017-04-07)
- 参考文献数
- 38
After 60 years of the history of Japan’s official development assistance (ODA), two approaches stand out as the main philosophy of Japan’s foreign aid – aid for developing nations’ self-help and human security, as recently expressed in the Development Cooperation Charter of 2015. While ‘self-help’ was much emphasized around the 1990s, when Japan emerged as a top donor, ‘human security’ has been regarded as more important element since the early 21st century.This essay argues that the relationship between self-help and human security has been ambiguous in Japan’s aid policy. While self-help is one of the key concepts in the analysis of the realist approach (such as Kenneth Waltz) in the theory of international politics, human security is in the more liberal or humanitarian tradition. Furthermore, it does not clear who makes ‘self-help’ efforts in economic development. Japan’s aid philosophy assumes that the developing state (or government) makes efforts toward development, but in reality, the government of developing states may not work for the interests of its peoples. In this case, the self-help efforts of individuals may end up with no returns for them. It is pointed out that Japan, relatively homogeneous, regards nation’s self-help as natural and normal, but the introduction of two level analysis – state level and person level – makes clear that many developing states have divisions within the state, and self-help efforts by all sectors of the state rarely happen.In recent years, Japan has more emphasized the importance of ‘human level’ in development, by adopting human security in its development aid. However, there is no coherent explanation or examination how this notion of human security relates to self-help efforts. Human security has become more important in recent years, because the state itself can become the source of threat to peoples, or the state cannot protect its peoples from the various threats, such as infectious diseases, financial crisis, terrorism, and refugees. Despite the fact that Japan introduced human security in its aid policy in the late 1990s, Japan’s contributions to human security area has not been adequately recognized, because the majority of Japan’s aid money is still spent for the establishment of economic infrastructure, and given in the form of yen loan.Emerging donors, including China, often take a similar approach to international aid, emphasizing the respect for recipient countries’ right to independently select their own path of development. It seems odd for Japan to stick to the aid principle similar to that of undemocratic emerging donors, particularly with regard to the fact that Japan’s political relations with China, which received substantial amount of Japanese aid, have been more tensional in recent years.
1 0 0 0 OA <フォーラム2.>ドラヴィダ言語学の立場から
- 著者
- 児玉 望
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.231-222, 1996-03-31
筆者は十五年間、ドラヴィダ語学を学んできた。そこでドラヴィダ言語学の立場から、大野説を検討した結果、次のような問題点が明らかとなった。
1 0 0 0 OA マルチエージェントモデルを用いたオオカミ再導入によるニホンジカの植生影響緩和効果の分析
- 著者
- 古林 知哉 松井 孝典 宮内 達也 町村 尚
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第28回 (2014)
- 巻号頁・発行日
- pp.1B2OS02a5, 2014 (Released:2018-07-30)
日本ではニホンジカの増加や生息域拡大により,生態系や農林業への被害が増加している.アメリカではオオカミの再導入により植生の回復がみられたが,日本での活用のために定量的な解析が必要である.本研究ではマルチエージェント化した個体群動態モデルと生態系プロセスモデルBiome-BGCの結合し,ニホンジカの採食がC3grass植生へ与える影響の緩和に対してオオカミ再導入が与える効果を定量的に評価した.
1 0 0 0 OA 放射線照射後1年以上が経過した頭頸部がんサバイバーの晩期有害事象と社会的困難との関連
- 著者
- 源河 朝治 神里 みどり
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.87-96, 2022 (Released:2022-07-28)
- 参考文献数
- 37
【目的】放射線療法後の頭頸部がんサバイバーにおける晩期有害事象と社会的困難との関連を明らかにする.【方法】照射後1年以上が経過した頭頸部がんサバイバーの症状を既存の疾患特異的QOL尺度の一部で評価した.分析は記述統計を行い,社会的困難と晩期有害事象および基本的属性との関連を検討した.【結果】対象者は73人(回収率70.8%)であった.晩期有害事象は口腔乾燥の有症率および重症度が最も高かった(79.5%).また,社会的困難は会食時の困難の有症率が最も高く(87.7%),会話困難の重症度が最も高かった.照射後5年以上経過した群は症状の重症度が高く,社会的困難と晩期有害事象には有意な正の相関がみられた.社会的困難は嚥下障害と唾液異常,手術歴と関連していた.【結論】頭頸部がんサバイバーは長期にわたり複数の晩期有害事象と社会的困難を有していた.今後は外来にて包括的なアセスメントとケアを行う必要がある.
1 0 0 0 OA 嚢胞内乳癌の臨床病理像
- 著者
- 山下 晃徳 吉本 賢隆 岩瀬 拓士 渡辺 進 霞 富士雄
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.11, pp.2726-2731, 1994-11-25 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 5 4
われわれは嚢胞内乳癌の臨床病理学的特徴をあきらかにする目的で,嚢胞内乳癌と嚢胞内乳頭腫の鑑別診断の可能性,嚢胞内乳癌の嚢胞周囲の乳管内進展を含めた病理組織学的特徴について検討した. 嚢胞内乳癌と嚢胞内乳頭腫との鑑別の可能性は,嚢胞内乳癌31例,嚢胞内乳頭腫23例を年齢,腫瘍径,超音波像などについて比較してみた.嚢胞内乳癌の乳管内進展については, 5mm幅の全割病理組織切片を作成して,癌の広がりをマッピングした. 嚢胞内乳癌は嚢胞内乳頭腫に比べ高齢者に多く, 60歳以上の嚢胞内腫瘍は癌である場合が多かった.また超音波像での両者の鑑別には,嚢胞内の腫瘤の辺縁の形状が大切で,辺縁の不整なものは癌に多いことが分かった. また嚢胞内乳癌は非浸潤癌が多く,腋窩リンパ節への転移も少ないが,乳管内の進展についてみると,約4割の症例が嚢胞壁より2cm以上乳管内を進展していた.
1 0 0 0 OA 居住環境と心の健康
- 著者
- 一番ヶ瀬 康子
- 出版者
- 日本精神衛生学会
- 雑誌
- こころの健康 (ISSN:09126945)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.17-25, 1988-05-15 (Released:2011-03-02)
1 0 0 0 OA 声門開大術の種類と方法
- 著者
- 杉山 庸一郎
- 出版者
- 日本喉頭科学会
- 雑誌
- 喉頭 (ISSN:09156127)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.01, pp.16-20, 2021-06-01 (Released:2021-09-17)
- 参考文献数
- 22
Bilateral vocal fold immobility influences not only vocal function but also the airway tract, possibly resulting in dyspnea. Pathophysiological diagnosis using electromyography of laryngeal muscles is also critical for patients with bilateral vocal fold immobility to optimize the surgical procedures. Vocal fold lateralization, transverse cordotomy, and arytenoidectomy can be utilized for bilateral vocal fold paralysis and posterior glottic stenosis depending on the severity of stenosis and mobility of cricoarytenoid joints. A unilateral approach should be recommended for the initial surgery to reduce the risks of aspiration and hoarseness. Laryngofissure with cartilage grafting and T-tube stenting may be performed for severe posterior glottic stenosis, often coinciding with subglottic stenosis. Laryngeal stenosis due to the bilateral vocal fold immobility should be carefully evaluated and treated with appropriate surgical technique, thereby keeping adequate airway space with preventing severe postoperative swallowing and phonatory dysfunction.
1 0 0 0 OA ウイルス種内の遊離塩素耐性分布幅が全体不活化率の推定に及ぼす影響
- 著者
- 鳥居 将太郎 片山 浩之
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.7, pp.III_423-III_429, 2020 (Released:2021-03-17)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1 1
ウイルスの遊離塩素耐性は水質に依存し,不活化に必要なCT値が水温,pHごとに定められてきた.近年,同じウイルス種内でも塩素耐性に違いがあることが示された.本研究は,高耐性株の存在が実際の浄水の塩素処理効率に及ぼす影響を評価することを目的とした.多摩川,相模川のF特異RNA大腸菌ファージGI型の塩素耐性を評価し,同種内の遊離塩素耐性のばらつきを考慮した不活化モデルを作成した.GI型野生株の86%(30/35株)で,実験室株MS2, frより塩素耐性が高かった.また,MS2の8 log不活化が期待できるCT値では,GI型野生株の全体不活化率が,5.3-5.6 logにとどまると算定された.環境水中におけるウイルスの消毒効果の推測では,実験室株によって代替するのではなく,種内の遊離塩素耐性のばらつきを算入した不活化モデルを採用すべきである.