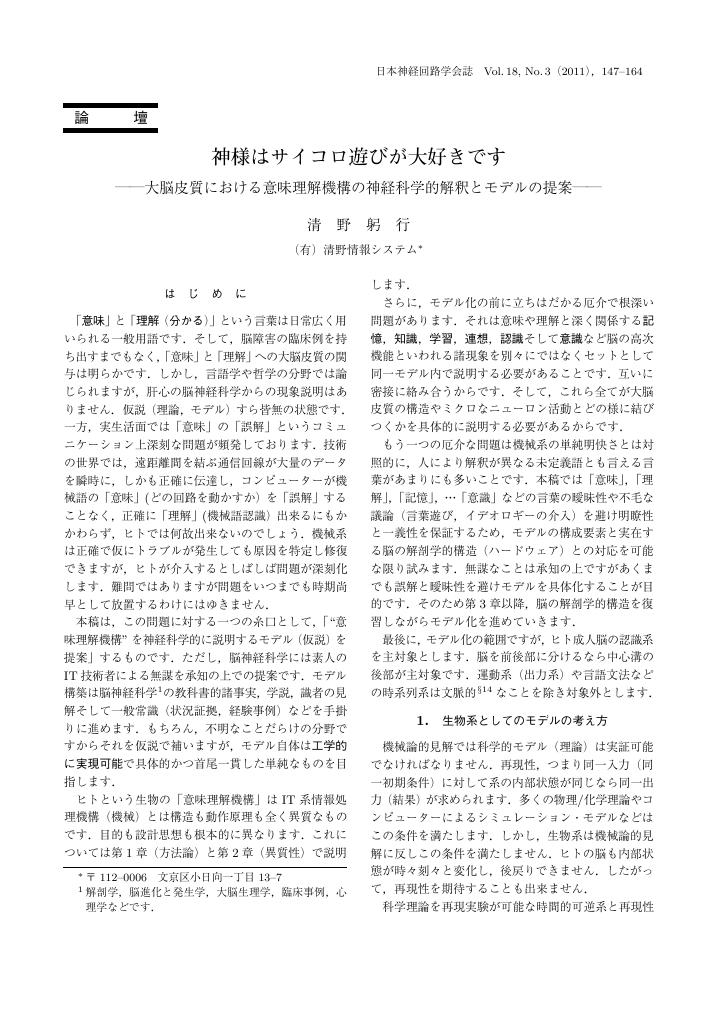9 0 0 0 OA 黒潮およびその周辺海域における仔稚魚の成長活性
- 著者
- 眞子 裕友 小針 統 一宮 睦雄 小森田 智大 幅野 明正 東 隆文 久米 元
- 出版者
- 日本プランクトン学会
- 雑誌
- 日本プランクトン学会報 (ISSN:03878961)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.93-101, 2022-08-25 (Released:2022-09-17)
- 参考文献数
- 53
It has been thought that food availability for fish larvae was poor in the Kuroshio because of the low standing stocks of plankton in the oligotrophic conditions under thermal stratification throughout the year. Despite a potential risk or disadvantage for larval survival and growth, Kuroshio and its neighbouring waters are nursery grounds for the early life stages of various fishes. Here, we compared the growth activity of fish larvae among 15 taxonomic groups, including 11 families in the Kuroshio and its neighbouring waters, based on protein synthetase activity and protein contents. Protein-specific (spAARS), individual-based aminoacyl tRNA synthetase activities (iAARS), and protein contents (PRO) of fish larvae ranged from 2 to 232 nmol PPi mg protein−1 h−1, from 1 to 21 μmol PPi ind−1 d−1, and from <1 to 26 mg ind−1, respectively. spAARS, iAARS and PRO were variable among the taxonomic groups and were not classified between mesopelagic groups and the others. Compiling these measurements among all taxonomic groups, a significant negative correlation was found for spAARS to PRO. The correlation showed no significant difference between the Kuroshio and its neighbouring coastal waters, indicating that growth activities to fish larvae body mass were comparable in the Kuroshio and its neighbouring waters. Based on nonmetric multidimensional scaling on spAARS, iAARS and PRO among 15 taxonomic groups, two different groups were classified for fish larvae, represented by the high iAARS under the high PRO but low spAARS (Group 1) and the low iAARS under the low PRO but high spAARS (Group 2), representing the different life strategies for larval growth among the taxonomic groups. The present findings suggest that these biochemical indices are useful for evaluating the growth activity of fish larvae among various taxonomic groups and that food availability is not poor enough to support larval growth in the Kuroshio and its neighbouring waters.
- 著者
- Yuta Sawabe Daiki Chiba Mitsuaki Akiyama Shigeki Goto
- 出版者
- 一般社団法人 情報処理学会
- 雑誌
- Journal of Information Processing (ISSN:18826652)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.536-544, 2019 (Released:2019-09-15)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2
Currently, many attacks are targeting legitimate domain names. In homograph attacks, attackers exploit human visual misrecognition, thereby leading users to visit different (fake) sites. These attacks involve the generation of new domain names that appear similar to an existing legitimate domain name by replacing several characters in the legitimate name with others that are visually similar. Specifically, internationalized domain names (IDNs), which may contain non-ASCII characters, can be used to generate/register many similar IDNs (homograph IDNs) for their application as phishing sites. A conventional method of detecting such homograph IDNs uses a predefined mapping between ASCII and similar non-ASCII characters. However, this approach has two major limitations: (1) it cannot detect homograph IDNs comprising characters that are not defined in the mapping and (2) the mapping must be manually updated. Herein, we propose a new method for detecting homograph IDNs using optical character recognition (OCR). By focusing on the idea that homograph IDNs are visually similar to legitimate domain names, we leverage OCR techniques to recognize such similarities automatically. Further, we compare our approach with a conventional method in evaluations employing 3.19 million real (registered) and 10, 000 malicious IDNs. Results reveal that our method can automatically detect homograph IDNs that cannot be detected when using the conventional approach.
- 著者
- 田中 淳子
- 出版者
- 大阪府立大学
- 雑誌
- 社會問題研究 (ISSN:09124640)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.79-99, 2008-03
9 0 0 0 OA 有機顔料講座 (6) その他の有機顔料
- 著者
- 橋爪 清
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.11, pp.552-561, 1967-11-30 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1 1
9 0 0 0 OA 対話における間接的応答と直接的応答からなる言い換えコーパスの構築と分析
- 著者
- 高山 隼矢 梶原 智之 荒瀬 由紀
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.84-111, 2022 (Released:2022-03-15)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1
人間は対話においてしばしば相手の質問や発話に対して間接的な応答をする.例えば,予約サービスにおいてユーザがオペレータに対して「あまり予算がないのですが」と応答した場合,オペレータはその応答には間接的に「もっと安い店を提示してください」という意図が含まれていると解釈できる.大規模な対話コーパスを学習したニューラル対話モデルは流暢な応答を生成する能力を持つが,間接的な応答に焦点を当てたコーパスは存在せず,モデルが人間と同様に間接的な応答を扱うことができるかどうかは明らかではない.本研究では既存の英語対話コーパスである MultiWoZ を拡張し,71,498 件の間接的応答と直接的応答の対からなる対話履歴付きパラレルコーパスを構築した.また,間接的な応答を扱う能力を評価するための 3 つのベンチマークタスクを設計し,最新の事前学習済みモデルの性能を調査した.さらに,ユーザーの間接的な発話を事前に直接的な発話に変換することで対話応答生成の性能が向上することを確認した.
9 0 0 0 IR 植物民俗学における植物をめぐる迷信
- 著者
- 植 朗子
- 出版者
- 京都府立大学
- 雑誌
- 京都府立大学学術報告. 人文 (ISSN:18841732)
- 巻号頁・発行日
- no.69, pp.67-75, 2017-12
9 0 0 0 ECMPの拡張によるハードウェアロードバランサの提案
本研究では,Equal Cost Multi-path (ECMP) を拡張することで既存の ECMP の欠点を解消した新しいロードバランス手法を提案する.一般的なハードウェアルータの持つ ECMP 機能はトラフィックをフローごとに複数のネクストホップに分散することができる.つまり ECMP をそのままロードバランサとして利用できれば,専用の機材を導入するのと比較してコスト面,運用面における負荷が少ない.しかし ECMP は,フローのハッシュ値とネクストホップ数によってパケットの転送先を決定するため,ネクストホップとなるサーバの数が増減した場合,既存のコネクションが異なるサーバに届き切断されるという問題がある.本研究では,この問題を解決するため ECMP を拡張した ECMP with Explicit Retransmission (ECMP-ER) を提案する.ECMP-ER は Layer-3 の ECMP を基礎としており,既存の経路制御プロトコルで動作する.その上で ECMP-ER では,ルータが ECMP の経路について,現在のネクストホップに加えて過去のネクストホップ情報も保持する.サーバの増減時に異なるサーバに届いたフローのパケットは,サーバがルータへ再送し,さらにルータが過去のネクストホップを参照して再送することで最終的に適切なサーバへ転送される.本研究では ECMP-ER を P4 スイッチを用いて試作し評価した結果,ECMP では 20% 以上のコネクションが切断される状況においても,ECMP-ER は全てのコネクションを維持したままトラフィックを分散できることを確認した.
9 0 0 0 OA 甲状腺乳頭癌におけるBRAF (VE1) 蛋白発現の臨床病理学的検討
- 著者
- 沖野 和麿 塩沢 英輔 佐々木 陽介 田澤 咲子 野呂瀬 朋子 本間 まゆみ 矢持 淑子 楯 玄秀 瀧本 雅文
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.35-42, 2016 (Released:2016-11-26)
- 参考文献数
- 20
BRAF (V600E) 遺伝子変異に基づくBRAF (VE1) 蛋白発現は甲状腺乳頭癌において予後不良因子と報告される.BRAF (V600E) 遺伝子はRAS-RAF-MARKシグナル伝達を介し細胞増殖を制御する.BRAF分子標的療法は悪性黒色腫で実用化されている.甲状腺癌とホルモン作用に関する研究において,甲状腺癌発生にエストロゲン, プロゲステロンの関与が示唆される.われわれは甲状腺癌について,BRAF (VE1),Estrogen Receptor (ER),Progesterone Receptor (PgR) の蛋白発現の臨床的意義を検討した.昭和大学病院において病理診断された甲状腺乳頭癌59例,甲状腺濾胞癌3例,甲状腺低分化癌3例,甲状腺未分化癌4例,腺腫様甲状腺腫46例を用いた.パラフィン包埋切片に抗BRAF (V600E) 抗体,抗ER抗体,抗PgR抗体を用いて免疫染色を行った.BRAF (VE1) 発現は甲状腺乳頭癌では40例 (68%) に認められた.腺腫様甲状腺腫にはBRAF (VE1)発現は見られなかった.BRAF (VE1) 陽性群と陰性群で性別,腫瘍径に有意な差は見られなかったが,発症年齢45歳以上に有意に多かった(P=0.017).PgR発現は甲状腺乳頭癌では陽性32例 (54%),陰性27例 (46%) だった.腺腫様甲状腺腫は陽性12例(26%),陰性34例(74%)だった.甲状腺乳頭癌におけるPgR陽性例は,女性に多い傾向が見られた (P=0.057).甲状腺乳頭癌におけるBRAF (VE1) 発現とPgR発現に相関は見られなかった (P=1.000).BRAF (V600E) 遺伝子変異に対するBRAF (VE1) 蛋白発現は相関性が示されており,腫瘍のBRAF (VE1) 蛋白発現を検討することで,BRAF (V600E) 遺伝子変異の状態を評価することが可能である.腺腫様甲状腺腫ではBRAF (VE1) 陽性例は認められず,甲状腺乳頭癌におけるBRAF (VE1) 免疫染色陽性は,腺腫様甲状腺腫ではなく,乳頭癌と判断できる所見といえる.甲状腺乳頭癌において45歳以上でBRAF (VE1) の発現が有意に多く,予後不良因子である年齢 (45歳以上) との統計学的な相関が見られたことは.BRAF (VE1) 発現が臨床的予後因子である発症年齢と相関し,予後を規定する因子である可能性が示唆された.BRAF分子標的療法の適応拡大が期待される中,BRAF (V600E) 遺伝子変異とそれに伴うBRAF (VE1)蛋白発現を伴う甲状腺乳頭癌は,その有力な候補と考えられる.今回の検討で,BRAF (VE1) 蛋白発現は甲状腺乳頭癌のおよそ7割に認められる特異的所見であることが明らかとなり,甲状腺癌へのBRAF分子標的療法の拡大のための基礎的研究として,臨床病理学的に有用な知見であると考えられた.
9 0 0 0 女子高校生における『援助交際』の背景要因
- 著者
- 櫻庭 隆浩 松井 豊 福富 護 成田 健一 上瀬 由美子 宇井 美代子 菊島 充子
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.167-174, 2001-06
本研究は, 『援助交際』を現代女子青年の性的逸脱行動として捉え, その背景要因を明らかにするものである。『援助交際』は, 「金品と引き換えに, 一連の性的行動を行うこと」と定義された。首都圏の女子高校生600人を無作為抽出し, 質問紙調査を行った。『援助交際』への態度(経験・抵抗感)に基づいて, 回答者を3群(経験群・弱抵抗群・強抵抗群)に分類した。各群の特徴の比較し, 『援助交際』に対する態度を規定している要因について検討したところ, 次のような結果が得られた。1)友人の『援助交際』経験を聞いたことのある回答者は, 『援助交際』に対して, 寛容的な態度を取っていた。2)『援助交際』と非行には強い関連があった。3)『援助交際』経験者は, 他者からほめられたり, 他者より目立ちたいと思う傾向が強かった。本研究の結果より, 『援助交際』を経験する者や, 『援助交際』に対する抵抗感が弱い者の背景に, 従来, 性非行や性行動経験の早い者の背景として指摘されていた要因が, 共通して存在することが明らかとなった。さらに, 現代青年に特徴的とされる心性が, 『援助交際』の態度に大きく関与し, 影響を与えていることが明らかとなった。
- 著者
- 清野 躬行
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.147-164, 2011-09-05 (Released:2011-10-28)
- 参考文献数
- 38
- 著者
- 鶴田 幸恵
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.21-36,157, 2004
The past studies on passing practice have accounted for the interaction about ones appearance and recognition of it. But these studies started their argument from the point that one already has a "normal appearance," and did not account for how it is accomplished that one has a "normal appearance" in the viewers recognition. The aim of this article is to argue that such a way of accounting of past studies can not adequately account for passing practices of transgenders who intend to accomplish being a "normal natural female," using the transcript data from interviews of Male-to-Female transgenders, because accomplishing that appearance is the most important problem for them. For this, I focus on "viewing" as an action. First, I discuss the logic used in Goffmans Stigma and Garfinkels famous paper on "Agnes," who is transgender. Through this work, it is found that the person who is passing is categorized in two ways. One is "categorization at a glance" which is an immediate and spontaneous practice. The other is "categorization from inductive judgment," which is conscious judgment by clues in ones appearance. Second, it is found from data that the person who is passing refer to "categorization from inductive judgment" to accomplish being categorized as "normal" with "categorization at a glance." Third, it is only when the question for instance, "Is that person is male or female?" is relevant that "categorization from inductive judgment" usually arises. So, for transgenders, to be categorized with the way of "categorization from inductive judgment" is to fail passing. This means that accounting for achievement or failure in passing must distinguish two ways of categorization. Through that consideration, I conclude that being categorized as a "normal natural female" with the way of "categorization at a glance" is necessary for transgenders to pass as normal. That is, on the one hand, the first step to passing, and on the other hand, the endless practice for transgender people.
9 0 0 0 IR 福岡大学病院における性同一性障害治療の現状と症例の特徴について
9 0 0 0 OA COVID-19における凝固異常と血栓症
- 著者
- 射場 敏明 比企 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.600-603, 2020 (Released:2020-12-14)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 2
9 0 0 0 OA ジーン・シャープの戦略的非暴力論
- 著者
- 中見 真理 ナカミ マリ Mari NAKAMI
- 雑誌
- 清泉女子大学紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.163-184, 2009
- 著者
- Takeru Takahashi Yasuharu Goto
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- BPB Reports (ISSN:2434432X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.21-23, 2022 (Released:2022-04-05)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
Fluconazole and dihydropyridine calcium channel blockers (DCCBs) are simultaneously used in clinical practice. Although fluconazole can increase the blood levels of DCCBs by inhibiting CYP3A4, there are only a few reports regarding the effects of interaction of these drugs on blood pressure. Based on electronic medical records, we conducted a retrospective study of blood pressure in hospitalized patients treated with fluconazole while receiving amlodipine and nifedipine. The mean blood pressure over 3 days, specifically 2 days before starting fluconazole treatment and the first day of fluconazole treatment (day 1), was used as the reference value to compare the mean blood pressure calculated every 3 days after day 1 until day 13. Most of the 26 patients included in the study had underlying hematologic malignancies. The average age of patients was 71.8 years. Twenty-one patients received amlodipine and five received nifedipine. The combination of DCCBs and fluconazole was associated with a significant decrease in blood pressure on day 11–13 (p < 0.01). The mean difference in overall systolic blood pressure was −15.8 mmHg (95% CI: −21.1 to −10.4). Therefore, the combination of fluconazole and DCCBs might potentiate the antihypertensive effect of DCCBs, and caution should be exercised when using them for lowering blood pressure.
- 著者
- 湯浅 誠
- 出版者
- 日本社会事業大学社会福祉学会
- 雑誌
- 社会事業研究 (ISSN:02884828)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.4-19, 2010-01
9 0 0 0 OA 脱植民地と在日朝鮮人女性による攪乱 ――「解放」後の濁酒闘争からみるジェンダー――
- 著者
- 李 杏理
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.37-53, 2017-10-20 (Released:2018-11-01)
- 参考文献数
- 39
本稿は、在日朝鮮人による濁酒闘争について、1930-40年代の史的・政策的背景を踏まえてそのジェンダー要因を探る。在日朝鮮人女性の存在形態は、植民地期から6割を超える不就学と9割を超える非識字により底辺の労働にしか就けない条件下にあった。日本の協和会体制下では日常にも帝国権力が入り込み濁酒を含む生活文化が否定された。それでも朝鮮人女性が濁酒を「密造」したという個別の記録があり、小さな抵抗は積み重ねられてきた。「解放」を迎えた朝鮮人女性たちは、いち早く女性運動を組織し、ドメスティック・バイオレンスの解決や識字学級、脱皇民化・脱植民地の新たな生を歩み始めた。ようやく自由に朝鮮語や歴史を学び、自分たちが置かれてきた境遇を知ることが可能となった。しかし、日本の敗戦と「解放」は在日朝鮮人にとって失職を意味し、恒常的な食糧難と貧困をもたらした。日本の民衆だれもがヤミに関わって生きるなか朝鮮人に対していっそう取り締まりが強化された。在日朝鮮人が濁酒をつくる背景には、①朝鮮人の貧窮と生計手段の少なさ、②朝鮮人にとっての酒造文化と植民地「解放」のインパクト、③検察・警察による朝鮮人の標的化、④ジェンダー要因があった。在日朝鮮人運動の男性リーダーは、「解放民族として」濁酒をやめるべきだとした。それでも女性たちは濁酒をつくり続け、生きる術とした。女性たちが濁酒闘争の先頭にたち、女性運動団体は交渉現場にともに立った。地域によって警察に謝罪を表明させたり、職場を要求し斡旋の約束を取り付けたりもした。濁酒闘争は、植民地「解放」のインパクトの中で、民族差別とジェンダー差別を生み出す旧帝国日本の権力に異議申し立てをし、生活の現実とジェンダー差を明るみにしたという意味で、「脱帝国のフェミニズム」を思考/ 志向する上での重要な参照項となりうる。
- 著者
- 露崎 弘毅
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会
- 雑誌
- JSBi Bioinformatics Review (ISSN:24357022)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.33-46, 2022 (Released:2022-11-01)
- 参考文献数
- 81
生命科学分野で取得されるデータ集合は、雑多(ヘテロ)な構造になり、ヘテロなデータ構造を扱える理論的な枠組みがもとめられている。本連載では、汎用的なヘテロバイオデータの解析手法である行列・テンソル分解を紹介していく。第4回では、これまで扱ってこなかった質的データ、距離、グラフといった特殊なデータに対して適用できる行列・テンソル分解を紹介する。
9 0 0 0 その健康保険証は適切か
2017年1月6日の産経新聞に「国保悪用の外国人急増 留学と偽り入国,高額医療費逃れ 厚労省,制度・運用見直し検討」という記事が掲載された.2016年に筆者が参加した外国人患者受け入れ体制整備関連のセミナーでも,「健康保険証の不適切な使用事例がある」というフロアからの同様の指摘があった. 外国人に限らず,健康保険証の偽造や不適切な使用による診療報酬詐欺といった事件は,メディアでも何度も報じられている.外国人患者が増えると,このような問題が増えるのではないかという指摘は当初からあった.在留・訪日外国人が増えるなかで,今後,医療機関が経験するかもしれない健康保険証をめぐる問題のパターンとその対処について紹介したい.