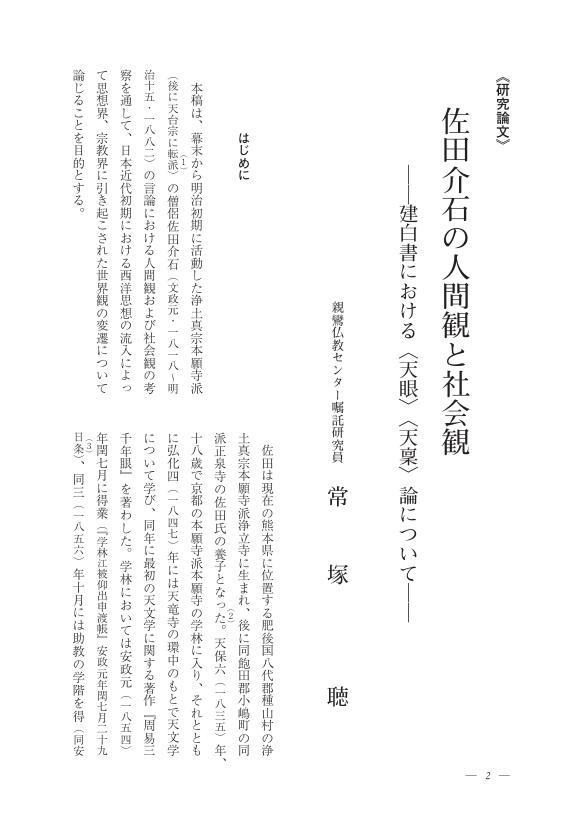- 著者
- BAUM Harald
- 出版者
- 日本比較法研究所
- 雑誌
- 比較法雑誌 (ISSN:00104116)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.41-79, 2014
When it comes to regulating capital markets in the European Union, the most important legislative instrument is the Markets in Financial Instruments Directive, the so-called MiFID. The Directive primarily promotes market integration by granting market access and market integrity by regulating market supervision. As part of this it also emphasizes investor protection as a regulatory goal in its own right. To achieve this goal MiFID sets out "conduct of business rules" in its Articles 19 to 24 that postulate a number of transparency, information, and fiduciary obligations for investment firms when doing business with customers. From the traditional German point of view, this regulatory regime qualifies as a regulation that falls into the domain of public law - as opposed to that of private law. The EU, however, does not know such a clear distinction. The central question that arises here is whether the conduct of business rules do actually create civil law effects. The MiFID is - somewhat surprisingly - quiet on these matters. The European Court of Justice ruled in 2013 that the Member States are free to decide whether or not they want to implement civil law sanctions against a violation of conduct of business rules.Germany implemented the conduct of business rules into national law in the year 2007 by amending Articles 31 to 37 of the Securities Trading Act. Insofar as these provisions deal with the contractual relationship between an investment firm and its customers, they can be qualified as "functional civil law." This newly created investor protection sharply contrasts with the arcane case law developed by the German courts over the past decades on the basis of general private law. The later ensures a much more dogmatically refined, nuanced, and systematically coherent regime of investor protection than the one that the rather crude EU regulations can provide because these are shaped by diverse legal traditions and political compromise. A hotly debated question is how the interaction of supervisory law and civil law can be managed as both are only partly overlapping and partly leading to different, sometimes even contradictory obligations for investment firms. This unsolved fundamental issue permeates all capital market regulation at present.The German Federal Court of Justice postulates a strict primacy of the general civil law in relation to the conduct of business rules of the Securities Trading Act. According to this view, the conduct of business rules as part of public law can - at most - play only an indirect role in the context of interpreting already existing contractual and pre-contractual obligations. They can, however, not create any kind of obligation beyond those already established under private law. A second opinion, diametrically opposed to the first one, emphasizes an unrestricted primacy of the "functional" civil law of the Securities Trading Act over the general civil law. In this view, due to the principle of full or at least maximum harmonization in the field of investment services by MiFID, the German courts may no longer enforce those parts of their case law that are based on contractual or pre-contractual duties that are stricter than the conduct of business rules. A third view builds a compromise between the two contradictory views: it does not claim a primacy of public law in the form of "functional" civil law, but much more modestly assumes a "diffusion"-"Ausstrahlung"- of the pertinent public law rules into the general civil law and its application. This is probably the leading opinion in German academia today.
- 著者
- 小野 幸一 孫 珠煕 宮武 恵子
- 出版者
- ファッションビジネス学会
- 雑誌
- ファッションビジネス学会論文誌 (ISSN:13489909)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.57-66, 2010-03
ファッションを学んでいる女子学生を対象に意識・行動に関してアンケート調査を行い分析した結果、名古屋、京阪神、九州の3地域には地域性があることが明らかとなった。1)一か月のこづかいは、名古屋、京阪神では約4万円であるが、九州では約2万5千円である。被服費として名古屋、大阪で約半額の2万円、九州では約1万円支出している。2)定期購読ファッション雑誌では、名古屋はギャル系ファッション志向が強い。京阪神、九州は元祖赤文字系、ストリート、モード系の各志向の雑誌が読まれている。九州での1位はヤングベーシック系non-noである。名古屋、九州での憧れの女性有名人第1位はギャル系の象徴である浜崎あゆみであるが、九州ではTOPlOには入っていない。3)好きなへアースタイルでは名古屋がボリュームのあるゴージャスなスタイルの割合が高い
1 0 0 0 OA 佐田介石の人間観と社会観 ――建白書における〈天眼〉〈天稟〉論について――
- 著者
- 常塚 聴
- 出版者
- 宗教法人 真宗大谷派 親鸞仏教センター
- 雑誌
- 現代と親鸞 (ISSN:13474316)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.2-33, 2012 (Released:2018-10-31)
1 0 0 0 IR 音響式炭面計によるユニット方式チューブミルの給炭自動制御法
- 著者
- 中富 葆造 岩水 哲夫
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 鹿児島大学工学部研究報告 (ISSN:0451212X)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.89-100, 1962-09
Since the thermal Power Plants in the Kyushu Districts are obliged to use low quality coal for fuel, they have no alternative but to utilize combustion of pulverized coal. The Unit System Tube Mill is a low costing Pulveruzer, but this system has its difficulties with automatic coal feeding. The reason being that as the feed control is carried out by interlinking the draft of the exhauster which blows the pulverized coal into the furnace with the feed rate of the coal feeder, after operation over a long period,excessive quantities of coal accumulates within the mill causing Mill-over or shortage of pulverized coal comes about decreasing the load of the Power Plant. With such difficulties constantly happening, perfect automatic combustion cannot be obtained. These defects can be corrected by disconnecting the interlink between the coal feeder and the exhauster, and controlling the feed rate of the coal feeder so that a fixed quantity of coal is constantly retained within the Tube Mill. Since a detector is necessary to determine the quantity of coal retained in the Tube Mill, the Author has invented and developed an Electro-acoustic Mill Level Meter which is quick responding and enables the operator to accurately detect the quantity of coal retained within the Mill. Recently the Unit System Tube Mill coal feeding system of the No. 2 Minato Power Plant of the Kyushu Power Company was completely switched to automatic operation by the use of this invention. Following this, the same automatic coal feeding system was installed at the Ainoura Power Plant which brought about excellent operating results. This thesis reports on the outline of this Invention.
1 0 0 0 OA ミトコンドリアと葉緑体の分裂は古代からの同じリングによって支配されている
- 著者
- 黒岩 常祥
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本小児血液・がん学会
- 雑誌
- 日本小児血液学会雑誌 (ISSN:09138706)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.128-136, 2003-06-30 (Released:2011-03-09)
- 参考文献数
- 18
真正粘菌でミトコンドリア核を発見したことによって, ミトコンドリアの分裂は, ミトコンドリア核分裂とミトコンドリア基質の分裂 (ミトコンドリオキネシス) に分けて研究することが可能となった.ミトコンドリオキネシス, いわゆるミトコンドリアの分裂機構は, 主にミトコンドリアの分裂が同調化できる原始紅藻Cyanidioschyzon merolaeで解析された.その結果, ミトコンドリアは, 古代からのFtsZリング, 内外のMDリング, そしてダイナミンリングの四重のリングを順次に使って分裂していることが明らかとなった.驚くことに, ほとんど同じリングが, 植物の機能の現場である葉緑体 (色素体) の分裂にも使われていた.これは偶然であろうか.ミトコンドリアと色素体の起源が同じであるという視点からも真核細胞誕生の謎を考察する.
1 0 0 0 日付のある耳--大伴家持の歌の世界性 (特集・古代文学の世界性)
- 著者
- 猪股 ときわ
- 出版者
- 古代文学会
- 雑誌
- 古代文学 (ISSN:02881284)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.2-11, 1999-03
1 0 0 0 OA 嬉遊笑覧 : 12巻附1巻
1 0 0 0 IR オット・ヴァイニンガー『性と性格』 : 翻訳と解題
- 著者
- ヴァイニンガー オット 白坂 彩乃 大川 勇
- 出版者
- 京都大学人間・環境学研究科ドイツ語部会
- 雑誌
- ドイツ文学研究 : 報告 (ISSN:04195817)
- 巻号頁・発行日
- no.66, pp.1-86, 2021
1 0 0 0 IR リルケ訳『マリアナ・アルコフォラードの手紙』 : 翻訳と解題
- 著者
- リルケ ライナー・マリーア 白坂 彩乃 大川 勇
- 出版者
- 京都大学人間・環境学研究科ドイツ語部会
- 雑誌
- ドイツ文学研究 : 報告 (ISSN:04195817)
- 巻号頁・発行日
- no.65, pp.1-66, 2020
1 0 0 0 OA 千曲之真砂 : 10巻 附録1巻
1 0 0 0 IR 『猟奇』総目次
- 著者
- 原 卓史
- 出版者
- 尾道市立大学芸術文化学部
- 雑誌
- 尾道市立大学芸術文化学部紀要 = Bulletin of Onomichi City University, Faculty of Artistic Culture (ISSN:21873550)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.49-75, 2016
- 著者
- 増田 一世
- 出版者
- 全国障害者問題研究会
- 雑誌
- 障害者問題研究 = Japanese journal on the issues of persons with disabilities (ISSN:03884155)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.272-277, 2019-02
- 著者
- 田中 真秀 佐久間 邦友 山中 信幸
- 雑誌
- 川崎医療福祉学会誌 (ISSN:09174605)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.17-26, 2021
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経ビジネス = Nikkei business (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.2111, pp.10-15, 2021-10-11
このため20年、政府は12兆円超を一気にばらまくという事態になった。コロナで失業した困窮者も富裕層も関係なく、1人10万円をもらえた特別定額給付金だ。本来なら減収世帯にしぼって30万円を給付するはずだった。
1 0 0 0 IR コリエンテスにおけるハチドリの行動生態及び訪花に関する調査研究
- 著者
- 上里 健次 Schinini Aurelio Nunez R. Eduardo Uesato Kenji
- 出版者
- 琉球大学農学部
- 雑誌
- 琉球大学農学部学術報告 (ISSN:03704246)
- 巻号頁・発行日
- no.59, pp.29-34, 2012-12
アルゼンチン北東部のハチドリの生息地に2ヵ年滞在して、ハチドリの行動生態に関する現地調査と写真撮影を行った。とりわけ魅力的で空飛ぶ宝石とも呼ばれるハチドリの飛翔姿態については、著者のみならず、何人にも認められる自然の宝物のひとつである。着任後しばらくはハチドリの飛翔を目にしても、写真撮影のチャンスは治安の悪化情勢もあって、全く考える余地はなかった。その中で専門分野の熱帯花木の開花状況を調査中に、合わせてハチドリの飛翔習性の把握にも努めた。生息する数種のハチドリの一種、コモンハチドリ一種が留鳥として、冬季間も飛来活動を続けることの知見が得られたことも幸運であった。飛翔習性と冬季に開花する植物との関連性の理解、花蜜でない昆虫捕食の活動についても目視できた。これらの現地調査の結果、各植物の花とホバリングの組合わせ、昆虫の空中での捕食、巣と卵の確認などそれぞれに貴重な記録が得られた。留鳥か渡りかの周年の動き、生息するハチドリの種の違いなどにも知見が得られた。ハチドリは鳥類の中では最小最軽量、胸筋が発達して飛翔能力に優れていることから、空中飛翔時に停止後退が可能で、そのことによる飛翔姿態の優雅さが注目される特別の野鳥である。まさしく生きた宝石で、最も魅惑的な野鳥として評価されることは当然である。ハチドリのホバリング撮影は難事なだけに、少なくとも中南米旅行でそのチャンスがあれば留意を望みたい。
- 著者
- 泉谷 直木
- 出版者
- 日経BP社 ; 2002-
- 雑誌
- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.12, pp.34-37, 2015-11
ビール系飲料市場で5年連続シェアトップのアサヒグループホールディングス。社長の泉谷直木さんが若手時代から20年以上、愛用しているのが「能率手帳」だ。泉谷さんは手帳を、単なるスケジュール管理の道具ではなく「常に行動を共にする"相棒"」と語る。
- 著者
- 熊倉 永子
- 出版者
- 国立研究開発法人建築研究所
- 雑誌
- 若手研究
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-01
本研究では、人々が生活の中で感じる温冷感を対象とした新たな指標の開発を目指している。都市生活者が投稿したジオタグ付きTweetデータの中から、暑さや涼しさを表現した短文や写真データを抽出し、投稿された場所や時間の特徴を明らかにする。また、投稿が集中する場所について、実測とシミュレーションによる物理的な熱環境の実態や、空間用途及び人口統計データ等との関係から、都市生活者が感じる暑さや涼しさとの相違を分析する。その結果をもとに、都市生活者が感じる暑さや涼しさのパターンを明らかにし、暑熱に対する適応策を検討する。
1 0 0 0 熱中症性脳症におけるHMGB1の関与と病態の解明
本研究は次の二つの事項を達成する.1:地上気象ビッグデータ取得デバイスの開発,2:地上気象ビッグデータの数値気象モデルへの同化手法の構築,および計算精度の向上性の評価.それぞれについて今年度の実施状況は以下の通りである.1.地上気象ビッグデータ取得デバイスの開発:3つの球形温度センサを用いた気象3変数逆同定システムであるグローブ風葬放射センサを従来の直径12 mmから4 mmまでダウンサイズすることに成功した.また,同定する3気象変数として,風速・日射・輻射熱の組み合わせから風速・日射・気温の組み合わせを逆同定するシステムを新たに構築した(Globe Radio-anemo Thermometer; GRaT).GRaTとすることで,正確な気温測定に必要であった強制通風筒が必要なくなるため,システム全体の低消費電力化,さらなる小型化が可能となった.GRaTに関して特許の出願を行った.加えて,PM2.5を測定する簡易・小型測定デバイスを開発した.2.地上気象ビッグデータの数値気象モデルへの同化手法の構築:地上気象ビッグデータの気象シミュレーションへのデータ同化インパクトを評価するため,オープン気象モデルWRFの3Dvarを用いたデータ同化数値実験を行った.夏の晴天日を対象としたシミューレーションにより地上気象データの同化が上空の気象解析値を有意に修正させることが確認された.一方で,精度の向上は確認されておらず,2020年度は4dvarを用いた同化数値実験を行う.上記に加え,上空風速の簡易・安価な測定原理であるCIV(Cloud Image Velocimetry)の開発,および羽田・成田空港を離発着する航空機から排出される排熱・排ガスのメソ気象用データベースの構築を行なった.