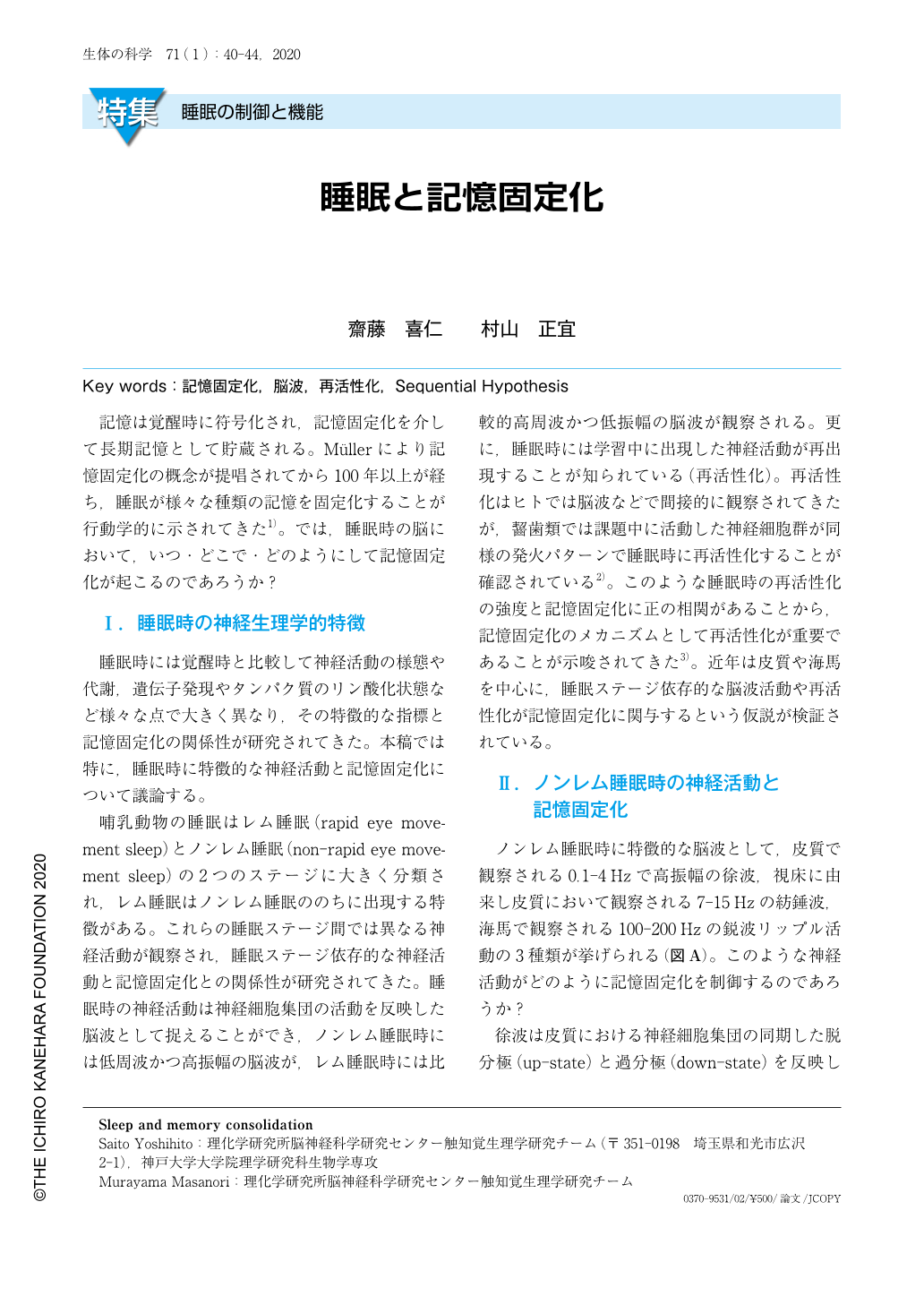1 0 0 0 OA アトピー性皮膚炎94症例における新中医薬処方「複方苦参」の治療効果
- 著者
- 李 頌華 王 如偉 田丸 直美 都 仁哉 岩崎 純夫 小林 裕太 奥西 秀樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本炎症・再生医学会
- 雑誌
- 炎症・再生 (ISSN:13468022)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.55-59, 2004 (Released:2006-10-25)
- 参考文献数
- 13
There has been considerable interest in traditional Chinese herbal therapy as a novel treatment for atopic dermatitis (AD). To investigate the efficacy and safety of formulas of traditional Chinese herbal medicine, Kujin-Plus, 94 AD patients received oral administration of the formula, Kujin-Plus I, containing 10 herbs, combined with a lotion, Kujin-Plus II, containing 7 herbs, and an ointment, Kujin-Plus III, containing 8 herbs as an open trial. The severity of the disease (clinical score; 0-4) and the severity of pruritus (pruritus score; 0-4) were judged by standardized scores. Both scores were significantly improved at the end of the treatment (p < 0.01;nonparametric test). The blood eosinophil ratio and serum IgE levels were high in AD patients and they were significantly reduced at the end of the treatment (p < 0.001). Of 94 AD patients with traditional Chinese herbal therapy, 32 were markedly improved, 59 were improved, 3 were slightly improved and none was ineffective. There was no remarkable evidence of renal or hepatic toxicity or another severe adverse effects. Thus, the present study confirmed that this herbal treatment is clinically efficacious on AD with a significant reduction in blood eosinophil ratio and serum IgE level.
1 0 0 0 睡眠と記憶固定化
- 著者
- 齋藤 喜仁 村山 正宜
- 出版者
- 金原一郎記念医学医療振興財団
- 巻号頁・発行日
- pp.40-44, 2020-02-15
記憶は覚醒時に符号化され,記憶固定化を介して長期記憶として貯蔵される。Müllerにより記憶固定化の概念が提唱されてから100年以上が経ち,睡眠が様々な種類の記憶を固定化することが行動学的に示されてきた1)。では,睡眠時の脳において,いつ・どこで・どのようにして記憶固定化が起こるのであろうか?
- 著者
- KUMI ASHIZAWA NORIKO TANAMACHI SUMIYO KATO CHIYOKO KUMAKURA XIA ZHOU FENG JIN YULING LI SHUNHUA LU
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- Anthropological Science (ISSN:09187960)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.1, pp.67-76, 2008 (Released:2008-04-26)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3 3
A number of papers on the growth of Chinese children have been published in local journals in China in the Chinese language. However, we noticed that height and weight are the main focus of these studies. Because leg length relative to height is of interest in human biology, the current study focuses on the growth of this proportion. Two groups of Chinese children were investigated: 587 boys and 625 girls in Beijing in 1997 aged 6–18 years, and 579 boys and 615 girls in Xilinhot, Inner Mongolia, in 2005 aged 7–18 years. Height and leg length (iliospinal height) were measured, and the ratio of leg length to height was calculated for each child. Mean distance curves and spline-smoothed yearly increment curves were obtained. In order to clarify the difference between the two groups of Chinese children, data from Japanese children were adopted as a control. The Beijing children were taller than the Xilinhot children, but no difference was detected in leg length between them. The ages at ‘take-off’ and ‘peak’ obtained on the yearly increment spline-smoothed curve of height in the Xilinhot children boys were 1.2–1.8 years earlier, respectively, than those of the Beijing boys. In the girls, these two ages were almost the same in the two cities, although the ‘peak’ was 1.8 cm greater in the Xilinhot girls. Leg length in the boys was almost the same in both Beijing and Xilinhot. In the girls of the Xilinhot group, leg length was greater after puberty. Consequently, the ratio of leg length to height was greater in the Xilinhot children than the Beijing children. It is suggested, in China, that socioeconomic factors influence growth of height to a greater extent than growth of leg length, and that leg length and leg length relative to height might be controlled by a genetic factor.
1 0 0 0 OA 現代ロシア語における〈格の融合〉と〈格の階層〉の相関性
- 著者
- 野口 卓眞
- 出版者
- 日本ロシア文学会
- 雑誌
- ロシア語ロシア文学研究 (ISSN:03873277)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.26-34, 2007 (Released:2019-05-07)
- 著者
- 安元 悠子
- 出版者
- 国立大学法人 琉球大学島嶼地域科学研究所
- 雑誌
- 島嶼地域科学
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.97-116, 2021
本稿では,琉球諸語から日本語標準語への言語シフトの過程を経験した個人の言語レパートリーに影響を及ぼした言語イデオロギーの記述・分析をおこなう。琉球諸島における「離島」で生まれ育った琉球諸語の話者は,人生において拠点の移動を経る中で,「中央へのまなざしと周縁性の自覚」,「言語の階層性」といった標準語イデオロギーと対峙しながら,「地域基準」「社会基準」にもとづいた言語使用をおこなっていることが明らかになった。言語的多様性を特長とする琉球諸語において,個人の言語体験に注目し詳細を記述することは,言語の衰退プロセスを紐解く鍵となり,今後の言語維持継承の一助になると考える。
1 0 0 0 明治後期の沖縄における感染症流行と衛生
- 著者
- 前田 勇樹
- 出版者
- 国立大学法人 琉球大学島嶼地域科学研究所
- 雑誌
- 島嶼地域科学
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.41-61, 2021
本稿は,明治後期(1890~1910年代)の沖縄での感染症流行と,それに対する防疫対策や衛生対策について新聞資料および松下禎二(京都帝大教授)による衛生視察記録を中心に分析を行ったものである。明治期の沖縄では感染症流行に対する前近代的な慣習や患者の隠蔽などが根強い一方で,この時期になると基礎的な防疫対策(清潔法と隔離)の浸透が見受けられる。その背景には,日清戦争後から始まる沖縄の同化政策の本格化と新聞による情報の流布が挙げられる。また,近代日本の植民地となった台湾との間での人の移動の活発化は,沖縄の感染症対策に大きく影響を及ぼすものであった。
- 著者
- 佐藤 崇範
- 出版者
- 国立大学法人 琉球大学島嶼地域科学研究所
- 雑誌
- 島嶼地域科学
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.183-197, 2021
- 著者
- トッピング マシュウ・W
- 出版者
- 国立大学法人 琉球大学島嶼地域科学研究所
- 雑誌
- 島嶼地域科学
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.79-96, 2021
本研究は,参加型アクション・リサーチ(PAR)の方法論を適用した質的実践研究である。本稿ではパーソナルインタビューおよび消滅危機言語継承活動の観察を通して沖縄県石垣市の2つの地域において,八重山地方の伝統的な「しまくとぅば」に対して研究参加者が持つ言語イデオロギーと活動の実践方法を詳述する。継承活動として「マスター・アプレンティス語学学習」という危機言語再活性化の手法を応用している。また,PARは社会科学研究の協調性を強調するため,本研究の方法論として採用した。本稿を含む調査結果は,八重山諸島や琉球諸島をはじめ,世界の他の地域の消滅危機言語再活性化への示唆があるといえよう。
1 0 0 0 近世琉球における人口推移の地域性について
- 著者
- 比嘉 吉志
- 出版者
- 国立大学法人 琉球大学島嶼地域科学研究所
- 雑誌
- 島嶼地域科学
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.19-39, 2021
琉球史における人口研究は,18世紀後半以降の総人口の減少と,一貫した町方人口の増加という特徴を挙げてきた。しかし,本稿はこれら先行研究のもとになった史料の数字を批判的に再検討するものである。具体的に,「琉球一件帳」や「中頭方取納座定手形」を取り上げ,従来の数字の解釈を批判的に検討し,総人口と地域人口の推移を整理した。 18世紀後半以降の琉球の人口推移は,総人口で増加傾向にあったが,町方人口は一貫して増加ではなかった。沖縄島で大きな人口増加が見られる一方,離島地域は人口の減少と停滞が顕著だった。このように,近世琉球の人口は多様な地域性をはらんで推移していったのである。
- 著者
- 宮里 厚子
- 出版者
- 国立大学法人 琉球大学島嶼地域科学研究所
- 雑誌
- 島嶼地域科学
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-17, 2021
19世紀中頃に琉球王国に滞在した8人のフランス人宣教師の中で,ルイ・テオドール・フュレ神父は6年3か月の最も長い期間琉球で過ごした。本来の目的であるキリスト教の布教活動ができない状況の中,フランス人宣教師たちは後の日本上陸に向けて語学学習に励んだが,フュレ神父はそれ以外にも学術的関心を持って多岐にわたる活動を行い,その資料や記録を残している。本稿では,まずフュレ神父の気象学,地震学,民俗学等における学術的活動の記録を紹介する。次に6年以上に渡る滞在中,フュレがどのように琉球王府との良好な関係作りに腐心していたかをパリ外国宣教会に残る手紙から読み解き,その滞在における方策を明らかにする。
1 0 0 0 IR 音楽療法における数学的パラダイムに関する研究
- 著者
- 上垣 渉 根津 知佳子 Wataru UEGAKI Chikako NEZU
- 出版者
- 三重大学教育学部
- 雑誌
- 三重大学教育学部研究紀要 (ISSN:18802419)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.41-60, 2013
本論文の目的は,音楽療法における数学的パラダイムの構造を明らかにすることである.そのために,古代ギリシアにおける音楽理論の形成過程と,その特徴及び人間への影響の仕方を考察した.古代ギリシアの音楽理論はオリュンポスによって創始され,テルパンドロスによってオクターブ的7 音音階が成立した.ピュタゴラスはそれを改革して8 音音階を完成させ,数比(ラチオ)にもとづく音楽理論を展開した.一方,アリストクセノスは音楽理論における数比主義を排除して,調和(ハルモニア)を求める聴覚に依拠した知覚主義的音楽理論を唱えた.これら2 つの音楽理論の統一を図ろうとしたのがプトレマイオスであった.音楽の世界と数学の世界を結びつけるのは比例(アナロギア)であり,比例によって音律論は強固な数学的基礎を獲得したのである.音楽は人間の精神に対して倫理的・教育的な作用力を発揮するが,本論文では,そのような音楽の特性を「音楽のエートス」と名づけた.プトレマイオスは,エートスの発生はトノスの転位の結果であると考え,7 種のオクターブ形式を定式化した.この7 種の形式が人間の精神に対して勇気,悲哀など種々の影響をもたらすのである.以上の考察から,数学的パラダイムはラチオとハルモニアを核とし,アナロギアを介して,音楽的エートス論を形成するという構造を持っていることを明らかにした.
1 0 0 0 OA 啓蒙の政治学 : 前期ハーバーマスの哲学と政治
- 著者
- 大村 一真 Kazuma Omura
- 出版者
- 同志社法學會
- 雑誌
- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.8, pp.3099-3175, 2021-03-31
研究ノート(Note)
1 0 0 0 啓蒙の政治学 : 前期ハーバーマスの哲学と政治
- 著者
- 大村 一真
- 出版者
- 同志社法学会
- 雑誌
- 同志社法学 = The Doshisha law review (ISSN:03877612)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.8, pp.3099-3175, 2021-03
1 0 0 0 OA 常用新薬集
- 著者
- 日本新薬株式会社新薬部 編纂
- 出版者
- 日本新薬新薬部
- 巻号頁・発行日
- 1940
1 0 0 0 IR 『オイディプス王』を読む(2)
- 著者
- 丹下 和彦
- 出版者
- 大阪市立大学
- 雑誌
- 人文研究 (ISSN:04913329)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.1115-1140, 2000
VI. 第2スタシモン(863~910行) : 四つのスタンザからなる。まずストロペー1では人知によらぬオリュンポスを父とする天上の掟の存在が告げられ, その掟に従って言動いずれも清らかに過ごす定めが我とともにあるようにと歌われる。……
1 0 0 0 OA クエン酸シルデナフィル (バイアグラ)
1 0 0 0 OA へき地における特別支援教育の課題と展望 地域型インクルーシブ教育を目指して
- 著者
- 二宮 信一
- 出版者
- 北海道教育学会
- 雑誌
- 教育学の研究と実践 (ISSN:13498266)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.41-50, 2021 (Released:2021-07-24)
- 著者
- 朴 璨旴
- 出版者
- 朝鮮学会
- 雑誌
- 朝鮮学報 = Journal of the Academic Association of Koreanology in Japan (ISSN:05779766)
- 巻号頁・発行日
- vol.256, pp.1-31, 2020-12