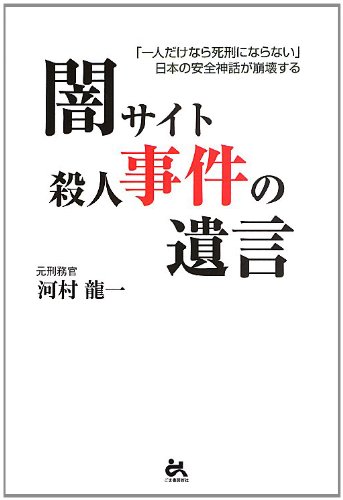- 著者
- 面田 雄一 中島 求
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- Dynamics & Design Conference
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, pp._706-1_-_706-6_, 2004
The objective of this study is to clarify the principle of the most stable position in the skydiving freefall. As the first step, the simulation method to analyze the dynamic behavior for freefall has been developed by the authors. In this report, an optimizing calculation to maximize an objective function with respect to the stability in the freefall is conducted. It is found that the most stable position becomes arched one. Next, the simple configuration that consists of 20 cylinders is optimized, and the angle to maximize restoring moment about each cylinder element is calculated and compared with optimized angle.
1 0 0 0 OA 力の概念の理解に関する一考察
- 著者
- 岡田 順一
- 出版者
- 南山大学
- 雑誌
- アカデミア. 人文・自然科学編 = Academia. Humanities and natural sciences (ISSN:21853282)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.47-60, 2012-01-30
- 著者
- 中島 求 面田 雄一
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 B編 (ISSN:03875016)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.734, pp.2010-2017, 2007
The objective of this study was to develop a simulation method for analysis of body behavior in skydiving freefall and to clarify the most stable body position during the freefall. The details of the developed simulation method were firstly described. Using the simulation method, we conducted an optimizing calculation to maximize an objective function with respect to the stability in the freefall. It was found that the most stable position became arched one. In order to clarify the reason why the most stable position became arched, optimization with respect to a simple shaped object which consists of 20 cylinders was conducted. Then the angle to maximize the restoring moment for each cylinder element was analytically calculated and compared with the optimized angle. From the results, we conclude that the most stable position becomes arched mainly since the restoring moment at each part itself becomes maximum at that angle. We also conclude that the magnitude of the arch in the most stable position is determined by the ratio of the normal and tangential drag coefficients.
1 0 0 0 OA 前線への移動 ──日本統治下時代の外地花街の元芸妓の 聞き取りを中心に──
- 出版者
- 日本オーラル・ヒストリー学会
- 雑誌
- 日本オーラル・ヒストリー研究 (ISSN:18823033)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.101, 2016 (Released:2018-12-26)
1 0 0 0 序文
- 著者
- 木下 秀文 佐藤 文憲
- 出版者
- 日本泌尿器内視鏡学会
- 雑誌
- Japanese Journal of Endourology
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.115, 2017
<p> 尿膜管は膀胱から臍にいたる管腔であるが, 臍から膀胱頂部までの様々な部位で, 拡張した管腔が遺残する場合がある. 部位により, urachal cyst, urachal fistula, urachal sinus, urachal diverticulumなどと呼ばれる. これに感染などを伴うと, 疼痛や発熱, 臍からの膿の流出, 血膿尿などの症状が現れ, 症候性 (感染性) 尿膜管疾患として治療される. 急性期は一般的に, 抗菌薬などの治療が中心となるが, 再発することもあり, 外科的な治療が考慮される.</p><p> 従来は開腹手術により遺残尿膜管を摘出していたが, 腹腔鏡下尿膜管摘除術が保険収載され, より低侵襲な外科的治療として普及してきている. しかしながら, 手術症例自体がさほど多くないため, 術式についてコンセンサスは得られておらず, 施設ごとに様々なアプローチがなされているのが現状である. 経験の多い施設でも, 年間に数例程度の手術症例数であろう. 手技自体は, 比較的容易であり, ほとんど経験のない施設でも比較的導入しやすい手術であると思われる.</p><p> 本稿では, 腹腔鏡下尿膜管摘除術の変遷と今後の方向性を佐藤先生に概説していただき, 基本的な術式 (側方アプローチ) を荒木先生に解説していただいている. もう一つの基本的なアプローチとして, 正中アプローチがある. この術式は, 臍の部分からopen laparotomyでカメラポートを挿入し, 左右の傍腹直筋レベル (臍よりやや尾側) に術者の左右のポートを置く術式である. 近年, このアプローチの発展型として, 単孔式腹腔鏡下尿膜管摘除術を行う施設も増加してきており, 矢西先生, 石井先生, 金先生には単孔式の術式について解説していただいている. また, 臍は腹部に位置する唯一の"チャームポイント"であり (あくまで個人的な意見です), 臍をどのように扱うかには, 各施設・各術者で様々な考えがあると思われる. 金先生には特に臍形成の工夫について解説していただき, 矢西先生には, 本術式の整容性について, データを示していただいている.</p><p> 本稿が, これから腹腔鏡下尿膜管摘除術を導入する先生方および単孔式手術に移行しようとされている先生方の一助になれば幸いである.</p>
1 0 0 0 OA シロオビアゲハのベイツ型擬態を司る分子基盤の解明
- 著者
- 西川 英輝 藤原 晴彦
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.1, pp.1_5-1_12, 2016 (Released:2017-10-10)
- 参考文献数
- 20
- 著者
- 若林 哲朗
- 出版者
- 社団法人 日本騒音制御工学会
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.73-76, 1991
1 0 0 0 OA 標的型敵対的攻撃による巻き込み現象の検出と可視化
- 著者
- 藤堂 健世 安田 翔也 山村 雅幸
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.3Rin469, 2020 (Released:2020-06-19)
機械学習における敵対的攻撃が注目を集めている。ブラックボックスなニューラルネットに対する普遍的かつ標的型の敵対的攻撃は困難と言われており、これを利用したニューラルネットの構造解析の知見は未だ十分とは言えない。本稿では,ブラックボックス・普遍的・標的型攻撃のための画像ノイズを遺伝的アルゴリズムによって作成し、これを適用した他クラスサンプルの圧縮空間上での遷移挙動から,ニューラルネットワークの特徴量構造の特性を調査した.その結果、あるクラスに対する標的型ノイズが、他クラスのサンプルに特徴的な遷移を誘導する「巻き込み」現象が観察された。巻き込みの発生度合いはクラスごとに異なったため、クラスごとに敵対的攻撃に対する耐性が異なることが示唆された。これらはクラスの距離に対応する何らかの指標と解釈することができ,ひいては特徴量空間の解析の糸口になると考えられる.
1 0 0 0 OA 階級鬪爭の必然性と其の必然的轉化
1 0 0 0 OA 地域施設としての火葬場と都市計画規制に関する研究
- 著者
- 浅香 勝輔
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文報告集 (ISSN:09108017)
- 巻号頁・発行日
- vol.421, pp.83-94, 1991-03-30 (Released:2017-12-25)
In this paper, a side view of the present-day crematoria has been investigated, by directing attention to the facilities which had already existed before zones were decided for use inside a city planning area, and by casting light on the problems encountered in the cities having such crematoria. As examples with very interesting characteristics, cities of Sakai and Higashi-Osaka in Osaka Prefecture as well as Nagoya in Aichi Prefecture have been dealt with.
1 0 0 0 OA 中世の未来記と注釈
- 著者
- 小峯 和明
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.29-37, 1999 (Released:2018-02-09)
1 0 0 0 OA 肩甲骨骨折の治療成績 ―肩甲帯部合併損傷の取り扱い―
- 著者
- 仲川 喜之 梅垣 修三 尾崎 二郎 富田 恭治 中垣 公男 桜井 悟良 松倉 光晴 建道 寿教
- 出版者
- 日本肩関節学会
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.110-115, 1994-09-01 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this report is to evaluate the results of treatment for fractures of the scapula with associated injuries. This study was composed of 123 patients (130 fractures). One hundred and seven were males and 16 were fenales. Their average age was 44.8 ranging from 3 to 84. The fractures were divided into four types as follows; scapular body: 54 cases, scapular neck: 40 cases, coracoid process: 18 cases, acromion or scapular spine: 18 cases. Seven cases had fractures in more than one location. Eighty-one of the 123 cases (66%) had assoceated injuries. Ninety-four cases were treated conservatively and 29 cases surgically. The results of the treatment were evaluated by the J.O.A.score.The results of cases without any nerve injuries were judged as excellent (mean score of conservative cases: 92.3 points, surgical cases: 97.1 poinys). Cases with nerve injuries had poor results (mean score of the conservative cases: 80.3 points, surgical cases: 85.7 points).An association between scapular fractures and fractures of the ribs is common. In those cases, a pneumothorax may not develop immediately after a traumatic episide, but it may occur after a few days. An acromioclavicular dislocation is apt to be associated with a fracture of the coracoid process, in which case, surgical treatment is indicated. A displaced fracture of the scapular neck associated with a clavicular fracture on the same side is unstable, in which case, surgical treatment is indicated. A rotator cuff tear is apt to be associated with a fracture of the scapular body or but it is often overlooked, Associated nerve injuries have a great inflvence on the results. It is important to examine an associated nerve imjury and to start rehabilitation as soon as possible. neck, very
1 0 0 0 OA 胸背部への持続的圧迫刺激による自律神経活動,体表温度および胸背部硬度の変化
- 著者
- 中元 唯 岡 真一郎 高橋 精一郎 黒澤 和生
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48101553, 2013 (Released:2013-06-20)
【はじめに、目的】疼痛は,組織破壊よる自発痛と,潜在的な組織障害および不快な感覚が絡み合った慢性疼痛がある.慢性疼痛は,自律神経反応との関連が深いことから交感神経の抑制を目的とした星状神経節や胸部交感神経節ブロック,星状神経節に対する直線偏光近赤外線照射などが用いられている.一方,理学療法においては,胸椎のマニピュレーションが指先の皮膚温を上昇させ,軽微な圧迫刺激が遅く鈍い痛みを特異的に抑えることから,胸背部への体性感覚入力が自律神経系に影響を及ぼす可能性がある.本研究の目的は,胸背部に対する持続的圧迫刺激が自律神経活動,末梢循環動態におよぼす影響について調査することとした.【方法】対象は,健常成人男性10 名(22.2 ± 1.2 歳)とした.測定条件は,室温25°前後で対象者を背臥位とし,メトロノームを用いて呼吸数を12 回/分で行うよう指示した.測定項目は,胸背部硬度,体表温度,心拍変動解析とした.胸背部への徒手的圧迫刺激は,簡易式体圧・ズレ力同時測定器プレディアMEA(molten)を用い,右第2 −4 胸椎棘突起の1 横指下外側に圧力センサーを接着して50mmHgに調整した.胸背部硬度は,生体組織硬度計PEK-1(井元製作所)を用いて右第2 −4 胸椎棘突起の1 横指下外側をそれぞれ3 回測定した.体表温度は,防水型デジタル温度計SK-250WP(佐藤計量器製作所)を用い,右中指指尖を1 分ごとに測定した.心拍変動解析は,心拍ゆらぎ測定機器Mem-calc(Tawara)を用いて心電図R-R 間隔をTotal Power(TP),0.04 〜0.15Hz(低周波数帯域,LF),0.15 〜0.40Hz(高周波数帯域,HF)として行った.自律神経活動の指標は,自律神経全体の活動をTP,副交感神経活動をHFn(HF/(LF+HF)),交感神経の活動をLF/HFとした.測定プロトコールは,圧迫前の安静10 分(以下,圧迫前),胸背部圧迫10 分,圧迫後の安静10 分(以下,圧迫後)とした.統計学的分析はSPSS19.0Jを用いて,圧迫前後の比較を対応のあるt検定およびWilcoxon符号順位和検定を行い,有意水準を5%未満とした.【倫理的配慮、説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき,対象者には研究内容を十分に説明し書面にて同意を得た後に測定を実施した.【結果】TPは圧迫前後で有意差がなかった.胸背部硬度は,圧迫前57.0 ± 4.3 から圧迫後55.8 ± 3.7 と有意に低下した(p<0.01).体表温度は,圧迫前33.8 ± 0.6℃から34.4 ± 0.6℃と有意に上昇した(P<0.05).心拍数は,圧迫前70.1 ± 12.9bpmから圧迫後67.6 ± 11.5bpmと有意に低下した(p<0.05).HFnは,圧迫前10.0 ± 4.7 から圧迫後13.0 ± 4.3 と有意に増加した(p<0.05).LF/HFは,13.5 ± 7.1 から圧迫後10.1 ± 5.4 と有意に低下した(P<0.05).【考察】胸背部硬度は圧迫後に有意に低下した.皮膚の静的刺激を感知する受容器は順応が遅く,持続的な圧迫刺激により皮神経支配領域のC線維を抑制すると報告されている.また,皮神経支配領域における求心性線維の興奮は,軸索反射により求心性神経終末から血管拡張物質を放出させる.胸背部硬度の低下は,圧迫刺激による皮膚受容器の順応,C線維の抑制と血管拡張に起因すると推察された.胸背部圧迫後のHFnは有意に上昇し,LF/HFは有意に低下した.ラットによる先行研究では,後根求心性線維への刺激は逆行性に交感神経節前ニューロンにIPSPを引き起こすとともに,脊髄を上行し上脊髄組織で統合されて交感神経節前ニューロンに投射し,副交感神経の興奮と交感神経の長期抑制を起こす.HFnの上昇とLF/HFの低下は,胸背部への圧迫刺激が副交感神経の興奮と交感神経の抑制を引き起こしたと考えられる.さらに,皮膚血管は交感神経性血管収縮神経によって支配されており,交感神経の抑制が皮膚血管を拡張させたため右中指体表温度が上昇したと考えられる.胸背部圧迫後の心拍数は有意に低下した.Miezeres(1958)は,犬の胸部交感神経節機能は左右差があり,右側が心拍数,左側が伸筋収縮力を増加させると報告している.本研究における圧迫後の心拍数の減少は,右胸部交感神経節の活動が抑制されたためと考えられる.胸背部への持続的圧迫刺激は,交感神経を抑制し,副交感神経を興奮させることが示された.上脊髄組織は,交感神経の長期抑制させることから胸背部圧迫刺激の持続性について検討する必要がある.【理学療法学研究としての意義】胸背部への軽度な持続的圧迫刺激は,慢性疼痛を有する患者の治療法のとして有用な可能性がある.
1 0 0 0 OA 竹富島方言アクセント(2)
- 著者
- ローレンス ウエイン
- 出版者
- 法政大学沖縄文化研究所
- 雑誌
- 琉球の方言 (ISSN:13494090)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.97-129, 2019-03-31
- 著者
- 福島 尚
- 出版者
- 中央図書出版社
- 雑誌
- 国語国文 (ISSN:09107509)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.9, pp.p21-40, 1988-09
1 0 0 0 IR 北海道東部川流布K/T境界試料の花粉学的検討
- 著者
- 高橋 清 山野井 徹
- 出版者
- 〔長崎大学教養部〕
- 雑誌
- 長崎大学教養部紀要 自然科学篇 (ISSN:02871319)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.p187-220, 1992-01
The junior author, Yamanoi, collected and analyzed 22 siltstone and claystone samples from the Katsuhira Formation spanning the Cretaceous/Tertiary (K/T) boundary in Kawaruppu area of eastern Hokkaido. The K/T boundary was decided on the basis of planktonic foraminifera by Saito et al. (1986). Recently, the senior author, Takahashi, has examined 66 slides which were prepared by Yamanoi and recognized 64 triprojectate, 6 oculata, and 14 other pollen grains which are palynostratigraphically useful (Tables 1 and 2). However, a remarkable palynofloral change at/near the K/T boundary in Kawaruppu afea is not recognized. Especially, many kinds of the triprojectate-oculata pollen did not disappear at the K/T boundary. On the other hand, the major palynofloral change at the K/T boundary in western North America occurred, including the abrupt disappearance of all species of Aquilapollenites except A. spinulosus, as well as the disappearance of Wodehouseia spinata, Cranwellia striata, Proteacidites spp., and others. They are replaced by such species as Wodehouseia fimbriata, Alnus trina, and Carpinus subtriangula (Lerbekmo et al., 1979). In this region the palynomorph break takes place a few meters above the highest occurrence of dinosaur bones, notably Triceratops. In short, the K/T boundary in this region is defined by the palynofloral change. A climatic condition of biotic change at Kawaruppu in eastern Hokkaido may be different from that in western North America. This problem must be solved in the near future.
1 0 0 0 OA アニメ産業における制作者のキャリアとジェンダーに関する質的研究
- 著者
- 松永 伸太朗 永田 大輔
- 出版者
- 長野大学
- 雑誌
- 長野大学紀要 = BULLETIN OF NAGANO UNIVERSITY (ISSN:02875438)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.71-72, 2020-11-30
1 0 0 0 特別講演2 患者の底力
- 著者
- 本間 りえ
- 出版者
- 日本重症心身障害学会
- 雑誌
- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.198, 2015
私の息子は特に障害もなく生まれすくすくと成長していました。しかし、6歳になるころから「何か変だ」と思うことがありその頻度はしだいに多くなってきました。いろいろ病院をめぐり最終的に副腎白質ジストロフィー(ALD)いう希少難病であることが知らされました。そのときを境に、息子の宇宙飛行士になりたいという夢は断たれました。また、私も、それまでの人生設計とは異なる別の人生を歩むことになりました。 ALDの唯一の治療法は造血幹細胞移植です。しかし、発症早期に移植を行わないかぎり、その効果は限定的です。息子は、症状がかなり進んでから診断されたこともあり、造血幹細胞移植のお蔭でいのちは取り留めましたが、いまは寝たきりです。息子がALDと診断され、造血幹細胞移植というつらい治療を受け闘病生活を送っているときは、本当につらい日々でした。しかし、日々つらい治療に耐え「いのち」を一生懸命に生きている息子の姿を見たとき、息子が私のもとに生まれてきてくれたことに対する感謝の気持ちがわいてきました。 患者会を作ろうと決意したのは、同じ疾患の宣告を受けた家族を知りお互いに助け合う関係を築きたいという気持ちからでした。この患者家族の絆は、いまでは日本全国だけでなく海を越え世界にまで及んでいます。ALDは、発症前あるいは発症早期に治療することにより、患者の生活の質が大きくかわる疾患です。患者会では、早期発見のために、この疾患の存在を医師だけでなく一般の人にも知ってもらいたいという思いで疾患啓発にも力を入れています。 息子の介護と患者会の活動との両立は決して容易なものではありません。しかし、患者会の仲間や家族、そして何より病を持ちながら輝く命を送っている息子の支えがあり、私は毎日充実した日々を送っています。 そうです。患者とその家族には力があるのです。略歴1984年結婚後、長男・長女に恵まれ、ごく普通の専業主婦としての生活を送る。1995年長男のALD発症を機に、初めての介護生活を経験。2000年1月 「ロレンツォのオイル」の連絡網を元に、ALD患者の家族会「ALD親の会」を発足。会長就任。2006年全国から5家族が集い、顧問医を囲んだ第1回交流会を開催。2007年8月 東京慈恵会医科大学にて、「ALD親の会」主催第1回勉強会を開催。以降、毎年、全国(東京、大阪、名古屋、岐阜、鹿児島、北海道)で定期勉強会や、映画 <ロレンツォのオイル~命の詩~>上映会を開催。2010年8月 「ALD親の会」創設10周年記念勉強会を開催。2010年11月 雑誌STORY(光文社)11月号連載<私の服にはストーリーがある>にて、特集記事6ページ掲載。2010年12月 BS日テレ<よい国のニュース>にて密着特集放映。2012年4月 「ALD親の会」を母体として、「特定非営利活動法人ALDの未来を考える会(A-Future)」を設立。理事長就任。以降、全国の医療施設、大学医学部、セミナー等で、ALD啓発・介護意識向上・医療従事者育成のための講演多数。