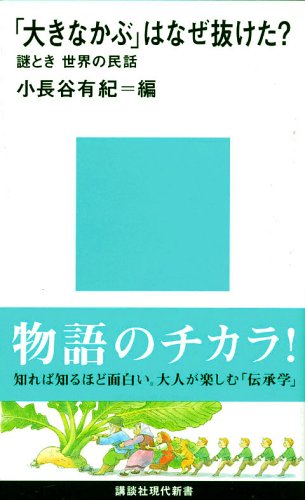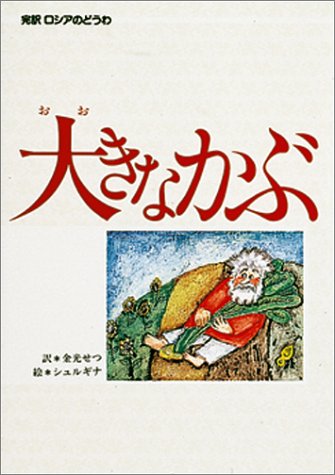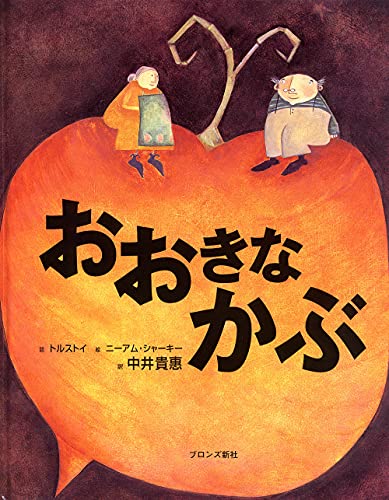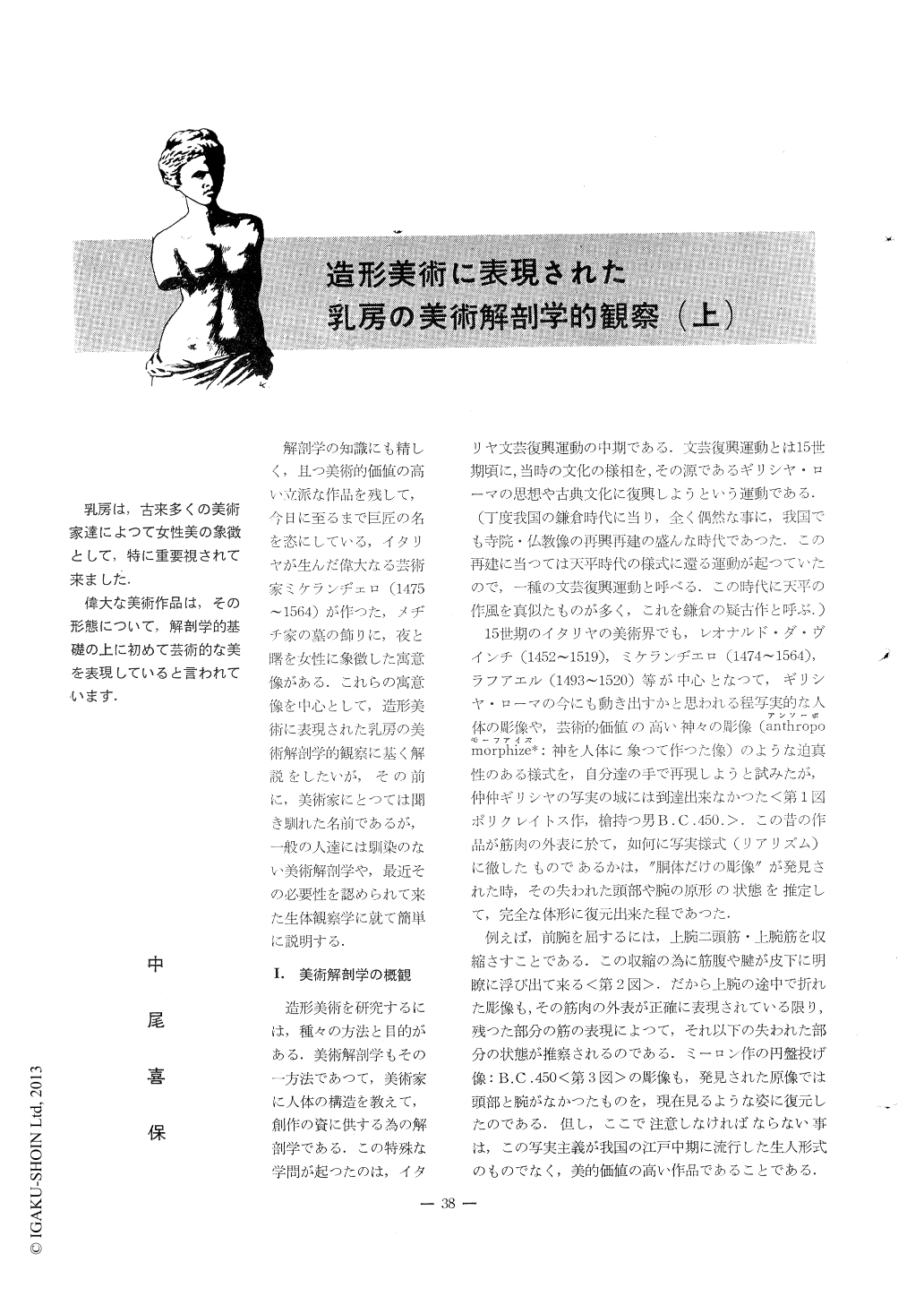1 0 0 0 OA 協会だより/編集後記
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.8, pp.437-438, 2020-08-01 (Released:2020-08-01)
1 0 0 0 OA 「東アジアの人文・社会科学における研究評価―制度とその変化―」佐藤幸人 編
- 著者
- 孫 媛
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.8, pp.436, 2020-08-01 (Released:2020-08-01)
1 0 0 0 共起性の分析:共著分析を中心として
- 著者
- 芳鐘 冬樹
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.8, pp.425-427, 2020-08-01 (Released:2020-08-01)
- 著者
- 今満 亨崇
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.8, pp.391, 2020-08-01 (Released:2020-08-01)
本特集ではRDF(Resource Description Framework)/SPARQL(SPARQL Protocol and RDF Query Language)による検索と可視化について特集しますが,特集の紹介をする前にまず弊誌がこれまでRDF/SPARQLについてどのような特集記事を掲載してきたか振り返ってみたいと思います。RDFについては当初から扱っており,1999年には当時W3Cにて検討中だったRDFについて,Dublin Coreのメタデータ記述と関連付けて紹介しています1)。時代が進むにつれ,身近なシステムがRDFデータを提供する動きが出てきました。2014年の特集「Web API活用術」2)ではCiNiiにおけるRDFデータの提供やその活用事例を紹介する記事を掲載しています。システム側での提供が増えると,それを利活用する動きも活発となり,2017年の特集「つながるデータ」では古崎晃司氏がLOD(Linked Open Data)活用コミュニティの取り組みの中でRDFにも言及していたり3),神崎正英氏の記事ではIIIF(International Image Interoperability Framework)のデータ構造がRDFでモデル化されていること等が紹介されています4)。ここに挙げたものに限らず,RDFについてはこれまで様々な記事を掲載してまいりました。一方SPARQLについてはどうでしょうか。2011年頃から言及する記事自体は複数掲載していますが,その利用方法などについて具体的に言及しているのは神崎正英氏ら5)の記事や,古崎晃司氏の記事6)に留まります。近年ではWeb UIでSPARQLの入力を受け付けるサービスも増えつつあり,インフォプロがRDF/SPARQLを利用する機運が高まっています。そこで本特集ではインフォプロが主体的にRDFデータを収集・利活用することを想定しました。まずはライフサイエンス統合データベースセンターの山本泰智氏にRDF/SPARQLの概要を非常に分かりやすくまとめて頂きました。次に,ゼノン・リミテッド・パートナーズの神崎正英氏に,様々なWebサービスにおけるSPARQLでの検索クエリ,及び得られるRDFデータについて概観して頂きました。個々のWebサービスからデータを得られるようになった次のステップとして,大阪電気通信大学の古崎晃司氏には得られるデータをいかにしてつなげるか,その作成方法についてご解説頂きました。ところでRDF/SPARQLはその性質上,複数ソースのデータをつなげて大規模なデータセットを作成することが可能ですが,そのままでは役に立ちません。可視化することの重要性について,コミュニケーションの媒介としての観点からノーテーションの矢崎裕一氏にご解説いただきました。最後は多摩美術大学の久保田晃弘氏に,可視化された複雑なデータの分類について人間の認知と関連付けてご紹介頂くとともに,大量かつ複雑で一貫性に欠ける現実の情報の世界にシステム的な共通の枠組みを適用する方法として圏的データベースをご紹介頂きました。最近はデータ駆動型社会の到来などと言われております。インフォプロがそのような社会を生き抜くための資料として,本特集をご活用いただけますと幸いです。(会誌編集担当委員:今満亨崇(主査),炭山宜也,野村紀匡,海老澤直美,水野澄子)参考文献1) 杉本重雄.〈特集〉メタデータ:メタデータについて:Dublin Coreを中心として.1999,vol.49,no.1,p.3-10.2) 情報科学技術協会.情報の科学と技術64巻5号.2014.3) 古崎晃司.〈特集〉つながるデータ:コミュニティ活動を通したLOD活用の“つながり” -LODハッカソン関西を例として-.2017,vol.67.no.12,p.633-638.4) 神崎正英.〈特集〉つながるデータ:リンクの機能を柔軟に生かすデータのウェブ.2017,vol.67,no.12,p.622-627.5) 神崎正英,佐藤良.〈特集〉典拠・識別子の可能性:ウェブ・オントロジーとの関わりの中で:国立国会図書館の典拠データ提供におけるセマンティックウェブ対応について.2011,vol.61,no.11,p.453-459.6) 古崎晃司.〈特集〉ウェブを基盤とした社会:ウェブの情報資源活用のための技術:ナレッジグラフとしてのLOD活用.2020,vol.70,no.6,p.303-308.
1 0 0 0 「大きなかぶ」はなぜ抜けた? : 謎とき世界の民話
1 0 0 0 大きなかぶ
- 著者
- トルストイ再話 金光せつ訳 リディア・シュルギナ絵
- 出版者
- 偕成社
- 巻号頁・発行日
- 1989
1 0 0 0 おおきなかぶ
- 著者
- トルストイ話 ニーアム・シャーキー絵 中井貴惠訳
- 出版者
- ブロンズ新社
- 巻号頁・発行日
- 1999
1 0 0 0 OA 元気な食品小売店に学ぶ,売れない時代の販売戦略
- 著者
- 小山 周三
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.12, pp.900-907, 2012 (Released:2017-12-18)
消費者との接点に立つ小売店の販売状況について解説をお願いした。地域に密着した専門小売店の状況は大変厳しい時期が続いている。その中で,スーパーやコンビニエンスストアと異なる販売戦略で「元気のいい地域小売店」の状況を,「優良経営食料品小売店頭表彰事業(全国コンクール)」を通して,具体的に見ていく。その結果,消費者と「きずなづくり」に欠かせない経営観が見えてくるが,個別の例の中から共通して見えてくるポイントを提示していただいた。当誌の読者の多くがメーカー側の立場におられると思うが,消費者に直接サービスを提供する立場をより理解することにより,「元気のいい地域小売店」へのメーカー側の販売戦略に参考になると考える。
1 0 0 0 造形美術に表現された乳房の美術解剖学的観察(上)
1 0 0 0 探究的学習を支援する浮世絵鑑賞システムの構築
- 著者
- 早野 瑞季 時井 真紀
- 雑誌
- 第82回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.1, pp.545-546, 2020-02-20
美術鑑賞において、鑑賞経験の少ない初心者は博物館リテラシーが不足していることが問題とされている。この背景をふまえて、絵画作品の注目すべき鑑賞ポイントを探る力、作品を関連付けて鑑賞する力が必要であると考えた。そこで本研究の目的は、視点の広がりをもって鑑賞することができる浮世絵を題材とし、Kinectを用いた体験型の浮世絵鑑賞を行うことである。システムでは、作品の鑑賞ポイントや複数の作品間のつながりを提示することで鑑賞体験を印象付けてユーザーの鑑賞視点を広げ、その後の積極的な美術鑑賞の支援を目指した。このシステムを用いた実験を行い、被験者の作品の理解と探究的学習への効果を調査した。
1 0 0 0 OA 200 ml献血と採血基準
- 著者
- 室井 一男 浅井 隆善 竹下 明裕 岩尾 憲明 梶原 道子 松崎 浩史
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.19-23, 2015-02-27 (Released:2015-03-23)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 3 3
1 0 0 0 OA 歯科を受診したSUNCTの1例
- 著者
- 樋口 景介 千葉 雅俊 山口 佳宏 高橋 哲
- 出版者
- 日本口腔顔面痛学会
- 雑誌
- 日本口腔顔面痛学会雑誌 (ISSN:1883308X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.37-42, 2017 (Released:2019-04-24)
- 参考文献数
- 10
症例の概要:症例は69歳の女性.約1か月前より左眼窩〜側頭部の発作痛を繰り返すようになった.某病院脳神経外科を受診し,頭部CTとMR検査で異常は認められなかったため,歯科疾患と考え,東北大学病院歯科顎口腔外科を初診来院した.発作痛は1日10回程度,2〜3分間の電撃痛(VAS:75)で,診察時に確認できなかったが左眼に流涙を伴うとのことだった.三叉神経・自律神経性頭痛(TACs)を疑い,インドメタシンファルネシル(400mg/日)を7日間投与したが痛みに変化はなかった.発作性片側頭痛を除外し結膜充血および流涙を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNCT),または頭部自律神経症状を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNA)を疑い,当院神経内科を紹介した.神経内科で発作中の左側結膜充血および流涙が確認され,SUNCTと確定診断された.クロナゼパムおよびガバペンチンによる薬物療法を受け,発作痛は改善した.考察:SUNCTは一側性の眼窩部,眼窩上部または側頭部の激痛発作で,同側の結膜充血および流涙を伴うことを特徴とするTACsである.TACsはタイプ診断に,発作痛の持続時間とインドメタシンの有効性を評価することが重要である.TACsなどの頭痛患者は歯科を受診する可能性があるため,一般歯科医でも頭痛の知識が必要と考えられる.特に,口腔顔面痛専門医はTACsを正しくタイプ診断できる必要がある.結論:歯科医も頭痛の知識を持つことが重要であると考える.
1 0 0 0 MUSE信号ディジタル記録・再生システム
- 著者
- 大澤 洋仁
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.50, pp.25-29, 1989
1 0 0 0 OA 東京高等蚕糸学校五十年史
- 著者
- 東京高等蚕糸学校 編
- 出版者
- 東京高等蚕糸学校
- 巻号頁・発行日
- 1942
- 著者
- 金井 克子 名倉 加代子
- 出版者
- いんなあとりっぷ社
- 雑誌
- Talk talk (ISSN:13409344)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.64-70, 2000-07
- 著者
- 内田 隆
- 出版者
- 東京薬科大学
- 雑誌
- 東京薬科大学研究紀要 = The Bulletin of Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences (ISSN:13438956)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.1-14, 2020-03-31
- 著者
- Yuji Matsuda Takashi Ashikaga Taro Sasaoka Yu Hatano Tomoyuki Umemoto Tetsumin Lee Taishi Yonetsu Yasuhiro Maejima Tetsuo Sasano
- 出版者
- International Heart Journal Association
- 雑誌
- International Heart Journal (ISSN:13492365)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.665-672, 2020-07-30 (Released:2020-07-30)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
Clinical outcomes after percutaneous coronary intervention (PCI) for severely calcified lesions remain poor. The purpose of this study was to investigate the neointimal response after everolimus-eluting stents (EES) for severely calcified lesions treated with rotational atherectomy (RA) using optical coherence tomography (OCT).We retrospectively analyzed 34 lesions in which PCI was performed with EES deployment following RA and OCT was performed immediately after PCI and at follow-up (nine months). The EES was either durable-polymer (DP) EES (22 lesions) or bioabsorbable polymer (BP) -EES (12 lesions). Strut coverage and malapposition were evaluated at 1-mm intervals of cross-section (CS) by serial OCT analysis. Malapposed strut was defined as having the distance from luminal border > 100 μm.A total of 11,823 struts immediately after PCI and 11,720 struts at follow-up were analyzed. Immediately after PCI, the strut-level analysis showed no significant differences in the percentage of malapposed struts between the DP-EES group and the BP-EES group. At follow-up, the BP-EES group showed a more prevalent covered strut compared with the DP-EES group (strut-level analysis: 95% versus 97%, P = 0.045; CS-level analysis: 97% versus 100%, P < 0.01; lesion-level analysis: 27% versus 83%, P < 0.01, respectively).In severely calcified lesions requiring RA, the BP-EES group achieved better neointimal coverage than the DP-EES group at nine months. Additional prospective studies are needed.
1 0 0 0 6.小児における糖尿病と肥満度との関連について
- 著者
- 岡田 知雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.7, pp.441-444, 2020-07-30 (Released:2020-07-30)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 日本人の精液性状の変化に関する基礎的研究
本研究費の援助を受けた平成10年度より平成13年2月末(本報告書記述時点)までに東京・九州・四国地区でそれぞれ100名以上、全国で400名以上の調査を終えている。その結果、精液性状に関しては、精子濃度の平均値は1ミリリットルあたり1億個弱と問題のある数値ではないものの、精子運動率が30%未満と世界保健機関(WHO)の基準値である50%を下回っていること、さらに精子濃度には地域差(九州>東京・四国)と年代差(20歳代<30歳代)が存在することなどを明らかにした。また、精液採取条件が精液性状に及ぼす影響を検討し、採取場所は精液性状に影響を与えないことを示した。現在、精液性状の個人変化および季節変動を検討する目的で、10人程度のボランティアから定期的に精液の提供を受けて検討を進めている。さらに、精子の質的変化をとらえる方法として精子染色体の蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)法による分析に取り組み、X、Y両性染色体性と18番染色体を対象とし染色体異数性と精液性状あるいは妊孕性等との関連を検討し、妊孕性の確認された健常人の精子染色体異数性の基礎的データを求めた。なお、精液性状の変化の要因に関しては、影響を与える因子は、ストレス、温度、食生活、大気汚染、薬物摂取など多く存在すると考えられており、その因子の一つとして、内分泌撹乱化学物質(いわゆる"環境ホルモン")の関与が推定されているのが現状で、化学物質と精液性状の関連については推測の位置をでていない。現在、今回の研究で収集した精漿試料中の各種化学物質の検討を進めており、来年度の早い時期には一定の結果が出るものと期待される。以上の成果について、関連学会の招請講演、一般講演などで発表し、総説を書くことで啓蒙活動を行った。現在、研究成果は外国雑誌への投稿を終えたものもあるが、一部は投稿準備中である。
- 著者
- 久保田 信 北田 博一 菅野 和彦
- 出版者
- 日本生物地理学会
- 雑誌
- 日本生物地理学会会報 = Bulletin of the Biogeographical Society of Japan (ISSN:00678716)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.219-222, 2018-01-20
Aberrant female and male medusae of Turritopsis rubra and T. sp. (most frequently those with three oral lips and three gonads, but with normal four radial canals) were found (c 13% incidence in female of both species, n = 107, 85) in November, 2016 from Iwaki City, Fukushima Prefecture, Japan. In both species, parasitic trematoda was found; in T. sp. maximally eight individuals/normal medusa and five ones/aberrant medusa. Moreover, in the same place in Fukushima Prefecture and in the other place in Ibaragi Prefecture aberrant Turritopsis rubra mature medusae without oral lips or with 1, 2, 3, 5 oral lips, were also found (18.3 %, n = 142 in Otsu harbour in Ibaragi Prefecture) in October, 2017