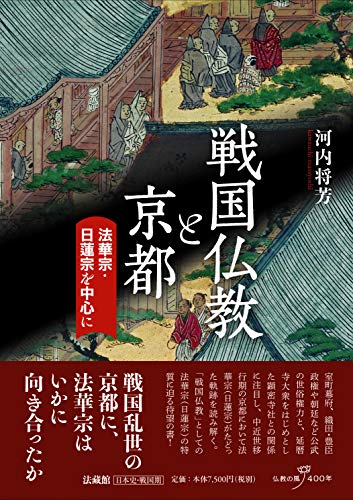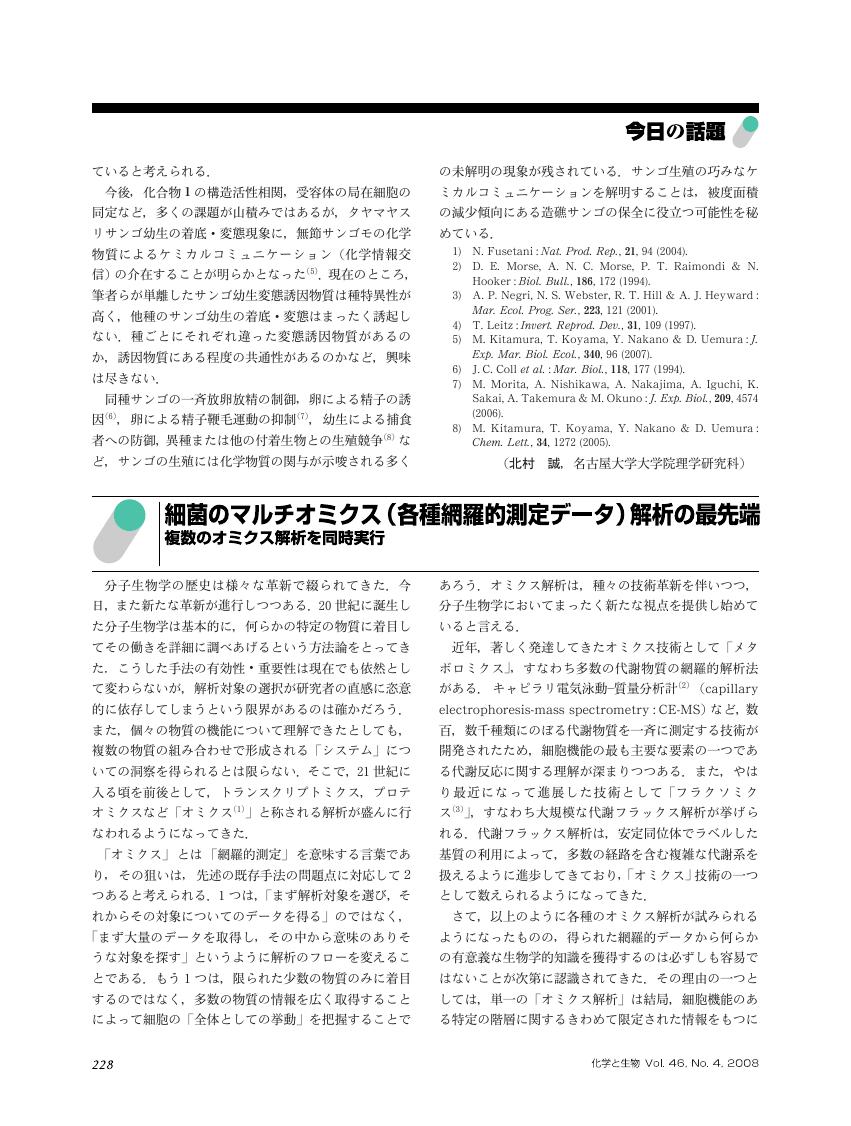1 0 0 0 OA 混合製剤中の塩酸キニーネの定量
- 著者
- 立沢 政義 中山 修二 大河原 晃
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.6, pp.761-766, 1970-06-05 (Released:2010-01-15)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 7 6
キニーネ塩は酸性(pH6.2)でプロムフェノールブルーと反応させると赤色を呈し,これはベソゼン-クロロホルム混合溶媒(1:1)で抽出すると585mμに吸収の極大を示す.通常色素法による塩基の定量はpH4.2で行なっている.この条件では反応に選択性がないため同一系成分共存では利用できないが,pH6.2においてブロムフェノールブルーはキニーネ塩に対する選択性が大である.混合製剤中のキニーネ塩の定量にこの反応を利用した比色定量法を確立した.
1 0 0 0 OA pH試験紙
- 著者
- 及川 五郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.169-172, 1952-11-30 (Released:2009-03-16)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 戦国仏教と京都 : 法華宗・日蓮宗を中心に
- 著者
- Jean Anne Zollars Patricia A. Burtner Gail Stockman Prisca Werbelow Jessie Swartzentruber Jean R. Lowe
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.7-15, 2020 (Released:2020-01-22)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 4
[Purpose] As an alternative to manual stretching, the aim of this study was to investigate the feasibility of using neural/visceral manipulation as a safe and effective intervention to increase neck range of motion of infants with congenital muscular torticollis. [Participants and Methods] Ten 4-month old infants with congenital muscular torticollis received eight sessions of neural/visceral manipulation administered for 30–50 minutes without observed pain. Specific palpation techniques addressed restricted tissue areas of neck, head, trunk and extremities. Neck rotation and lateral flexion were assessed by still photography and a computer program calculating ROM angles before, immediately following, and 4 months post intervention. Motor development and social competence were monitored over time using the Alberta Infant Motor Scale and Bayley-III Social Emotional Scale. [Results] Results of analysis of variances revealed significant improvements in passive and active neck rotation and lateral flexion. Significant increases were also found on the Alberta Infant Motor Scale and Bayley-III Social-Emotional scale. [Conclusion] Neural/visceral manipulation can be used safely in infants with congenital muscular torticollis to improve neck range of motion.
- 著者
- 菅谷 和宏
- 出版者
- 公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構
- 雑誌
- 年金研究
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.2-60, 2017
<p> 本稿では1991年の第1回調査から2016年の第6回調査までの25年間におけるサラリーマンの生活と生きがいの変化について追う(第1節)。生きがいの保有率は、第2回調査の78.4%から一貫して減少し、第6回調査では初めて5割を切り43.6%(前回比▲12.3%)まで低下した。生きがいの意味合いとして、「生きる喜び」「生活の活力」「生きる目的」「自分自身の向上」が減少し、「生活のリズム」「心のやすらぎ」が増加している。生きがいを感じる事柄は、「仕事」が32.5%から18.0% に減少し、「ひとりで気ままにすごす」が7%から17.5%に増加している。くわえて、心の安らぎが得られる場が減少し、「どこにもない」とする人が増えている。生きがいを得られる場は「仕事」から「家庭」に移る一方で、「家族の理解・愛情」は減少している。さらには、自ら他人とのつながりを求めない人が増えている。新たな生きがいの場を自ら見い出す積極性も持たず、ただ、生きがいの喪失に繋がる現状が浮かび上がる。</p><p> このような中、団塊の世代が本格的に就業から引退し、高齢者の仲間入りを始める。そこで、次に第1回調査(40~44歳)から第6回調査(65~69歳)まで団塊世代の生活と生きがいの変化を追ってみた(第2節)。驚くことに、他の世代とは異なり、生きがいの保有率は第1回調査から第6回調査では59.0%と同じ水準を維持していた。定年退職後も「経済的ゆとり」を持ち、仕事に代わる「趣味」などに生きがいを見い出している団塊の世代がいる。 生きがいの意味や内容は年齢と共に変化し、男女では生きがいの意味や内容が異なっていた。 人口減少による労働力不足が懸念される中、高齢者の知識と経験を社会へ活用することが求められる。また、雇用形態が多様化する中、生きがいを持ち続けられるような社会の仕組み作りが必要で あり、今後の日本の超高齢化社会への対応と活性化に繋がるものと考える。</p>
1 0 0 0 OA 蛍光灯の光
- 著者
- 森 礼於
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.205-207, 1993-04-01 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- by Mildred Rose Meili
- 出版者
- University of Texas
- 巻号頁・発行日
- 1970
1 0 0 0 OA 高度負荷土壌での植物の生存戦略
- 著者
- 橋床 泰之
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.7, pp.434-441, 2003-07-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 Provinz Posen, Ostmark, Wielkopolska : Eine Grenzregion zwischen Deutschen und Polen 1848-1914
- 著者
- Thomas Serrier
- 出版者
- Herder-Institut
- 巻号頁・発行日
- 2005
1 0 0 0 OA 廃硫酸処理
- 著者
- 若江 一男
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 実務表面技術 (ISSN:03682358)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.9, pp.435-439, 1971-09-01 (Released:2009-10-30)
1 0 0 0 IR 伊東忠太の建築理念と設計活動に関する研究
1 0 0 0 破傷風及瓦斯壞疽能働免疫に關する研究
1 0 0 0 IR テレビコマーシャルの食シーンに見る女たち
- 著者
- 今泉 容子
- 出版者
- 筑波大学文藝・言語学系
- 雑誌
- 文芸言語研究 文芸篇 (ISSN:03877523)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.124-86, 2001
食べる女。飲む女。料理する女。女が日本のテレビコマーシャルのなかでクローズアップされるとき、それが食のシーンであることが多い。女は長いあいだ料理をつくるひとであり、その材料を買いに行くひと ...
- 著者
- 瀬川 夏代
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- Aspekt : 立教大学ドイツ文学科論集 (ISSN:03876861)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.368-374, 2002
1 0 0 0 體育原理
- 著者
- 可兒徳 飯塚晶山共著
- 出版者
- 淺見文林堂 (発賣)
- 巻号頁・発行日
- 1935
1 0 0 0 OA フィリピン国カガヤン川中流域水害地形分類図と治水計画への応用
- 著者
- 大矢 雅彦 松田 明浩
- 出版者
- The Tohoku Geographical Association
- 雑誌
- 季刊地理学 (ISSN:09167889)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.139-150, 2002-08-26 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 6
カガヤン川流域はフィリピン最大の平野であるにもかかわらず, 激しい洪水のため持続的開発が進まず, 国全体からみても経済開発の立ち遅れた地域となっている。筆者らは洪水対策の基礎資料となる, カガヤン川中流部の水害地形分類図を作成した。その結果, 調査地域には, 熱帯特有の環境によって形成されたと考えられる高位沖積面と低位沖積面が分布している事が判明した。主な集落は自然堤防, 高位沖積面上にある。水害地形分類図から, 上流側の地域IIIでは網状流がみられ, 拡散型洪水を繰り返したことがわかる。中核都市ツゲガラオ市付近の地域IIでは, 連続性のよい大規模な自然堤防および高位沖積面がみられ, 下流部ほど蛇行は著しくない。氾濫範囲がほぼ一定の洪水が流下していたと考えられる。北部の狭窄部に近い下流側の地域Iでは河川が蛇行を繰り返し, 大きく湾曲した旧河道や三日月湖が分布する。洪水の型は, 河岸侵食が著しい集中型である。カガヤン川中流部では, 堤防などの治水施設は皆無に等しい。その治水計画は全面的に日本に任されており, 現在ハード面とソフト面の治水案が立てられつつある。本図はその基本図として, 様々な場面で有効に活用できる。
1 0 0 0 OA 細菌のマルチオミクス(各種網羅的測定データ)解析の最先端
- 著者
- 石井 伸佳 曽我 朋義 冨田 勝
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.228-229, 2008-04-01 (Released:2011-02-05)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA ソ連の中近東政策 -イランに対するソ連外交-
- 著者
- 岡部 三郎
- 出版者
- 財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.12, pp.53-67, 1960-05-15 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 48
1 0 0 0 OA 映画関連企業資料の現状と問題点
- 著者
- 加藤 厚子
- 出版者
- 日本アーカイブズ学会
- 雑誌
- アーカイブズ学研究 (ISSN:1349578X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.21-39, 2008-03-31 (Released:2020-02-01)
映画は芸術作品であると同時に、企業により販売され世界規模の市場で消費される商品である。近年、映画は文化財・歴史資料として研究されているが、映画に関わる企業の企業資料については看過されてきた。映画という商品の特性や、企業における保存意識の低さから、映画関連企業資料の実態は明らかではない。その一方で、世界では企業資料を含む「映画遺産」の保存意識が高まっている。本稿では、映画関連企業資料の特徴を分析し問題点を指摘した上で、資料管理の観点から大手映画会社の歴史を概観し、企業資料の現況把握を試みる。そして関連機関によるアーカイブの取り組みを検討し、映画関連企業資料の調査・保存・公開における問題点を指摘し考察を行う。