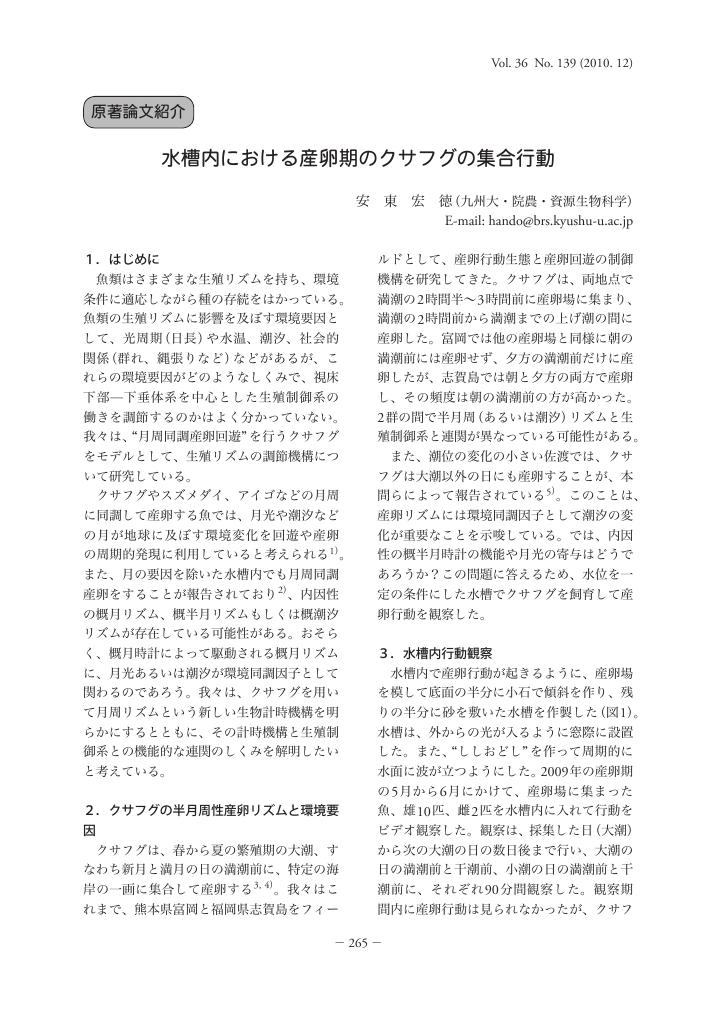1 0 0 0 OA 病院経営におけるコスト構造の定量分析
- 著者
- 下村 欣也 久保 亮一
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療・病院管理学会
- 雑誌
- 日本医療・病院管理学会誌 (ISSN:1882594X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.129-136, 2011 (Released:2011-09-16)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
本論文は,独立行政法人国立病院機構の財務諸表データを用いながら,黒字病院グループ(N=57)と赤字病院グループ(N=44)におけるコスト構造に差があるのかどうかを定量的に分析した。その結果,(1)保険査定・(2)給与費・(3)材料費・(4)診療材料費・(8)設備関係費・(9)減価償却費・(10)経費・(11)支払利息の項目で2グループ間に差があることが明らかになった。本論文の示唆として以下の点を上げることができる。第1に,定量的な分析手段を用いて,病院経営におけるコスト効率の重要性を検証していることである。第2に,黒字病院と赤字病院の境界線を分かつ可能性のある費用項目を具体的に明示したことである。第3に,病院経営においてコスト集中戦略が有効である可能性をデータ分析により示したことである。
1 0 0 0 OA 文献紹介
- 著者
- 和泉 広恵
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.97, 2003-07-31 (Released:2009-08-04)
1 0 0 0 OA 「非当事者」にできること : 東日本大震災以後の文学にみる被災地と東京の関係
- 著者
- 加島 正浩 KASHIMA Masahiro
- 出版者
- 名古屋大学大学院文学研究科附属「アジアの中の日本文化」研究センター
- 雑誌
- JunCture : 超域的日本文化研究 (ISSN:18844766)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.180-193, 2017-03-17
The purpose of this article is to determine the significance of literature on the Great East Japan Earthquake written by authors who do not belong to one of the affected parties. It does so by analyzing a novel depicting the Great East Japan Earthquake, focusing on the relationship between Tokyo and the affected area. Immediately after the earthquake, when the threat of radioactive substances spreading to Tokyo loomed large, the author of this novel was able to write as one of the affected. However, later it became difficult for the author to write about the disaster as the impact of such first-hand accounts began to wear thin. This was due to consideration for the affected parties, who continued to live in Fukushima after the disaster. However, as this article argues, excessive consideration for the affected parties distracts people from realizing the true state of affairs in Japan, and when those other than the affected parties are discouraged from speaking out, it causes feelings of indifference and accelerates the “wearing thin” of the impact, ultimately forcing the affected area to take care of the problem on its own. The affected parties, who had to focus on restoring their everyday lives after the disaster, could not fight against this “wearing thin” of the impact. However, others could. Thus, writers who write about the earthquake disaster with due care are fulfilling their part.
1 0 0 0 OA 抗ウイルス薬の耐性出現メカニズムの研究
- 著者
- 佐藤 彰彦
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第41回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.MS3-2, 2014 (Released:2014-08-26)
1988年に塩野義製薬 医科学研究所が発足し,抗ウイルス薬研究を開始した.抗HIV薬研究の中で,我々が見出し,臨床試験入りした化合物として,NNRTI(非核酸系逆転写酵素阻害剤)のS-1153(Capravirine)をはじめとして,多くのINI(インテグレース阻害剤)を見出した. 抗HIV薬では,薬剤を長期に投与することから,薬剤耐性ウイルスの出現を克服することが最重要課題であり,耐性の出現メカニズムを詳細に研究し,その基礎研究を基にした創薬をすることが必要である.S-1153(Capravirine)の研究・開発時から,既存の抗HIV薬の耐性プロファイリングから,耐性ウイルスの克服を目標にした研究を続けてきた.我々は,安定して耐性ウイルスを分離する方法を見出し,このin vitroでの培養手法を用いることで,臨床試験と同じ耐性ウイルスが分離できることがわかった. この手法を用いて,薬剤耐性ウイルスの出現機構を考察したところ,耐性ウイルスの出現時期,頻度,変異部位は,ウイルスの変異率,変異ウイルスの増殖性,薬剤の抗ウイルス効果(選択性)に依存しており,薬剤濃度を高く維持できれば,耐性ウイルスの出現を抑えることができることを理論的に証明し,ウイルスの耐性出現をコントロールできるノウハウを習得した.この理論から,既存の耐性変異に対して活性が低下しない化合物を目標にして,多数の骨格をデザインし,長期培養しても高度耐性ウイルスが分離できない優れた特徴を持つ化合物群を見出した. 我々は,抗インフルエンザウイルス薬の研究も進めてきており,インフルエンザウイルスのin vitro試験での耐性ウイルス出現過程は,HIVと同じ傾向であるが,急性感染症であるインフルエンザ感染の場合は,耐性ウイルスに対するin vitroとin vivo効果は,HIVとは異なり,必ずしも一致しないことがわかってきている.各ウイルスの耐性出現理論について紹介したい.
1 0 0 0 OA リマウント調整による総義歯装着者の咀嚼能力の改善
- 著者
- 河原 英雄 成松 由香 小松 亜希子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会
- 雑誌
- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1-2, pp.17, 2016-04-25 (Released:2019-07-30)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
義歯をリマウントして,咬合調整によりフルバランスの咬合を与えると,「すっきりした」「かめるようになった」など患者の満足を得ることができる.筆者は,リマウント調整後のフードテストの様子を映像で記録することにより,個別的に咀嚼能力の回復を評価してきた.このリマウント調整による咀嚼能力の回復を客観的に確認するため,リマウント調整をした総義歯装着者の70 人(男性23 人,女性47 人,平均年齢75.8 歳)を被験者としてリマウント調整の前と後に咀嚼能力検査を行った.咀嚼能力測定には咀嚼試料中に溶出するグルコース濃度を測定する市販キットを用いた.その結果,92.8%の被検者でリマウント調整後に10%以上の溶出グルコース濃度の向上が得られ,平均41.8%の溶出グルコース濃度の改善をみた(調整前に咀嚼能力の低かった上下総義歯群では68.1%改善した).リマウント調整により高い確率で咀嚼能力が改善することが客観的に確認できた.この事実は,一般に使われている総義歯は,無歯顎者の咀嚼能力を十分に回復しておらず,改善の可能性があることを示している.【顎咬合誌 36 (1 ・2 ): 1 7 - 2 4 ,20 1 6 】
1 0 0 0 OA 女性とインターネット 女性がよく見るサイト、よく使うネットワークサービス
- 著者
- 伊藤 淳子
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.48(2001-GN-040), pp.1-6, 2001-05-24
パソコンとインターネットの普及により、女性のネットワーク利用者が急増している。なかでも20代と30代をあわせると全体の80%以上になり、既婚者とシングルマザーが半数以上を占める。よって、関心のあるコンテンツやテーマもセグメントされ、「妊娠出産・子育て」「SOHO」などが定番テーマとなっている。しかし、多くの「女性サイト」のなかでも人気があるサイトは、情報配信以上に情報交換や情報共有といったコミュニケーションが重視されている。こうした現状と、今後のネットワーク利用への期待について、女性のネットワークに着目し、利用と活用について調査を行った。
1 0 0 0 OA チンパンジーの社会関係と長期的なストレス:研究領域としての動物福祉
- 著者
- 山梨 裕美
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.23-32, 2019-06-20 (Released:2019-07-12)
- 参考文献数
- 71
Both general and academic attention toward animal welfare has been increasing and the importance of scientific investigation into welfare states of captive animals is being recognized. One of the big questions in scientific studies of animal welfare is how we can assess animal welfare in an objective manner, and this is an intensively debated topic. In this paper, I reviewed the studies on captive chimpanzees (Pan troglodytes) in order to discuss the methodologies used to assess welfare states and introduce studies that have investigated how social environments affect chimpanzee welfare by combining behavioral and hair cortisol (HC) measurements. Recently, cortisol accumulated in the hair of animals has been considered as an indicator of the long-term hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis. From a welfare perspective, long-term stress is more problematic than acute stress as it is challenging for animals to experience distress over a long period and long-term activation of the HPA axis can result in overall health deterioration. A series of studies on captive chimpanzees show that HC is useful for monitoring the long-term stress levels in captive chimpanzees. Furthermore, using the novel measure of long-term stress, I found that the stress level of male chimpanzees is affected by social variables and that male chimpanzees use social play as a means to reduce social tension. Although scientific investigation of animal welfare is still not a prevalent practice in Japan, it is a promising area of study both for improving animal welfare and deepening our understanding about animals.
1 0 0 0 OA 個人の人格的尊厳の憲法的保護 : ドイツにおける名誉保護をめぐる憲法論議を素材に
- 著者
- 濱口 晶子 Hamaguchi Shoko
- 出版者
- 名古屋大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 名古屋大學法政論集 (ISSN:04395905)
- 巻号頁・発行日
- vol.215, pp.165-209, 2006-12-25
1 0 0 0 OA 自己鏡映像認知への温故知新
1 0 0 0 OA 伝藤原為家筆『道真集』断簡
- 著者
- 久保木 秀夫
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館紀要 = National Institure of Japanese Literature (ISSN:03873447)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.171-192, 2005-02-28
国文学研究資料館蔵の伝藤原為家筆歌集断簡は、有吉保氏によって現存するいずれの系統とも異なる『道真集』と指摘された伝冷泉為相筆断簡(MOA美術館蔵手鑑『翰墨城』所収)のツレである。書写年代は鎌倉時代後期頃。ほかに個人蔵のもう一葉のツレが知られる。記載歌はすべて他文献にも見出されるが、断簡独自の内容もあり、他文献からの単なる抜粋などではなさそうである。従来『新古今集』ほかの出典となった道真の家集の存在が想定されており、あるいは当該断簡はそれに該当するかもしれない。また藤原定家自筆『集目録』記載「菅家」との関連も注目される。The National Institute of Japanese Literature collects a fragmentary manuscript of the collection of 31-syllable Japanese poems. This material may correspond to "Michizane Shu" which became the source of "Shin Kokin Waka Shu" and has been lost now.
1 0 0 0 OA 口蓋弓鉤
- 著者
- 久保 猪之吉
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療機器学会
- 雑誌
- 医科器械学雑誌 (ISSN:00191736)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.10, pp.511-512, 1932-04-20 (Released:2020-01-17)
- 著者
- 林 勇樹
- 出版者
- 日本生物工学会
- 雑誌
- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.1, pp.15-20, 2016
1 0 0 0 OA 聴診器と打診器に就て : 並に余の考案せる聴診器と打診器
- 著者
- 松田 勝一
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療機器学会
- 雑誌
- 医科器械学雑誌 (ISSN:00191736)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.12, pp.552-556, 1933-06-20 (Released:2020-01-20)
- 著者
- 戸田 聡
- 出版者
- 立教大学キリスト教学会
- 雑誌
- キリスト教学 = Christian studies (ISSN:03876810)
- 巻号頁・発行日
- no.59, pp.65-84, 2017
1 0 0 0 OA ヒト肺肥満細胞のアセチルコリンに対する反応性に関する検討 : 好塩基球との相違について
- 著者
- 高橋 清 宗田 良 岸本 卓巳 松岡 孝 前田 昌則 荒木 雅史 谷本 安 河田 典子 木村 郁郎 駒越 春樹 谷崎 勝朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.6, pp.686-692, 1992-06-30 (Released:2017-02-10)
自律神経系の機能異常に基づく各種アレルギー性肺疾患病態における肺肥満細胞の役割を解明する目的で, 酵素処理法, percoll遠心法, 付着細胞除去法によって得られた高純度ヒト肺肥満細胞のアセチルコリンに対する反応性を, ヒスタミン遊離率を指標として検討した. その結果, 肥満細胞からのヒスタミン遊離はアセチルコリンの濃度に依存し, 10^<-5>で有意に亢進していた (p<0.05). また, アセチルコリンは抗ヒトIgE家兎血清によるヒスタミン遊離を相対的に増加させた. なお, かかるヒスタミン遊離はアトロピンでは部分的にしか抑制されなかった. 一方, ヒト末梢血好塩基球はかかるアセチルコリンに対する反応性が認められなかった. 以上の結果より, ヒト肺肥満細胞はIgE受容体のみならず, アセチルコリン受容体を介する反応により自律神経系の標的細胞として各種アレルギー性肺疾患の発症機構の一端を担っていることが示唆された.
1 0 0 0 OA 水槽内における産卵期のクサフグの集合行動
1 0 0 0 空間デザインの原点 : 建築人間工学
- 著者
- 岩中 貴裕 高塚 成信
- 出版者
- The Japan Society of English Language Education
- 雑誌
- 全国英語教育学会紀要 (ISSN:13448560)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.121-130, 2007 (Released:2017-04-27)
This study aims to investigate how noticing forms in relevant input presented immediately after output encourages learners of English to take lexical items into their IL systems. Twenty nine university students, classified into 3 proficiency levels, took part in an experiment, in which they worked on guided composition, and then took notes of what forms they had noticed in looking at relevant input presented immediately after output. The participants were asked to work on the same guided composition in the following week to examine how they retained lexical items from the relevant input. The results are: 1) The output-input process leads advanced learners to retain more lexical items; 2) The uptake is promoted when: i) the participants analyze a form in the relevant input syntactically, and/or ii) the participants perceive a form in the model as being in contrast with its counterpart in their own output and realize ungrammatical or less appropriate status of the latter; and 3) The output-input process helps learners gain lexical knowledge on use.
- 著者
- 野地 雅人 稲垣 浩 遠藤 聡 常松 尚志
- 出版者
- 日本脊髄外科学会
- 雑誌
- 脊髄外科 (ISSN:09146024)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.80-86, 2017 (Released:2017-07-08)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
Cervical angina is a pathological condition characterized by angina-like paroxysmal precordial pain caused by a lesion in the proximity of the cervical spine without cardiovascular abnormality. The symptom cannot be alleviated even with nitroglycerin administration. Although various reports have suggested possible causes, no report has identified the definite etiology of the disease. We report a rare case with frequent chest pain attacks, which completely disappeared after anterior cervical decompression and fusion and cervical calcified disc herniation. In addition, we compared the present case with previously reported cases. The patient was a 78-year-old woman who complained of pain in the left chest and back area. Her symptoms worsened in August 2007. She was then hospitalized after undergoing medical examination in the emergency department, with the following results: ST segment depression (+), horizontal down-sloping V4-V6 on electrocardiography, and troponin (−). On the basis of these results, she was diagnosed as having unstable angina. Later, we conducted a cardiac catheter test and found 99-100% stenosis for #6 and 99% stenosis for #13 periphery. Percutaneous coronary intervention (PCI) for #6 was performed with a favorable collateral circulation. The patient did not have any symptoms during treadmill exercise and was discharged from the hospital. Although she repeatedly visited the emergency department every 2 or 3 months because of the pain in her left chest and back area, ischemia findings at the time of electrocardiography and blood test results were always negative. In March 2012, the symptom persisted even with PCI for #13. In June 2014, an acetylcholine prorocation test was conducted for suspected vasospastic angina, but the result was negative. As the patient occasionally had numbness and pain in both upper extremities, which worsened, she underwent a medical examination in our clinic in February 2015. Midline calcified hernia at C3/C4 and spur at C4/C5 were found on magnetic resonance imaging and computed tomographic myelography. Anterior decompression and fusion (C3/C4 and C4/C5) were conducted with a cylindrical cage in June 2015, and the postsurgical pain in the chest and back area completely resolved. A philological study showed that the affected segment often indicated symptoms associated with radiculopathy at the C6 or C7 myotome areas, but our case was considered a spinal segment disorder or sympathetic involvement.
1 0 0 0 IR 科学者と治癒者--『豊饒』『壊滅』における医療哲学
- 著者
- 林田 愛
- 出版者
- 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会
- 雑誌
- 慶応義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文学 (ISSN:09117199)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.131-153, 2009
序I: 精神病治療と外科手術II: パターナリズムの文学的表象 : 戦略としての「情報の操作」III: 疾患ではなく患者をIV. 慈父と医師むすびMélanges dédiés à la mémoire du professeur OGATA Akio = 小潟昭夫教授追悼論文集