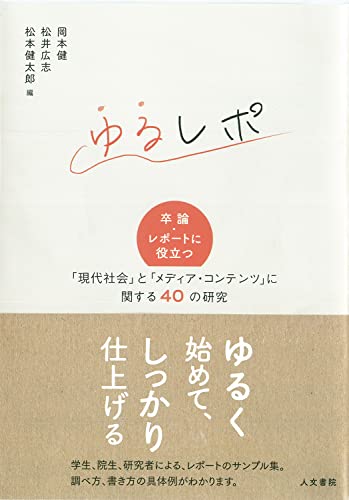6 0 0 0 OA 光を用いた空中可聴音の計測技術
- 著者
- 矢田部 浩平 及川 靖広 石川 憲治
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.8, pp.450-457, 2020-08-01 (Released:2021-02-01)
- 参考文献数
- 30
6 0 0 0 OA 音の物理量と心理量
- 著者
- 二階堂 誠也
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.325-332, 1980-03-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 19
- 著者
- 長谷川 真司 高石 豪 岡村 英雄 中野 いく子 草平 武志
- 出版者
- 山口県立大学
- 雑誌
- 山口県立大学学術情報 (ISSN:18826393)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.125-133, 2016-03-31
矯正施設に福祉の支援を必要とする高齢受刑者・障害受刑者が多くいることが認識されるようになり、彼らが出所し地域で生活を送るうえで退所後適切な福祉サービスにつながらない事や、住居の確保や就労の場がないまま出所する等ソーシャルワークの支援が乏しいため再犯に至るリスクが高い事が問題になっている。そのため、司法と福祉をつなぐ地域定着支援センターが設立され、実践を積み重ねている。本研究では、地域定着支援センターが支援を行った事例について当事者及び関係機関の専門職にヒアリングを行い、福祉の支援が必要な矯正施設出所者が地域生活を円滑に送ることが出来るようにするための要因について明らかにする。It is recognized that there are many elderly and handicapped convicts at correctional institution, and there are high risks at returning to correctional institution without appropriate social work support. Thus, the Japan Council of Regional Sustained Community Life Support Centers for the Elderly and Handicapped Ex-offenders is established to connect social work and justice, and many practices have been carried out to support community life for ex-offenders. In this case study, interview was conducted for clients and professionals at related organizations. Then, it is clarified the factors to transfer the life smoothly from corrective institution to community for ex-offenders whoneed supports from social us
6 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1941年08月02日, 1941-08-02
6 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1931年03月09日, 1931-03-09
- 著者
- Masanori Nonaka Takeshi Hayashibara
- 出版者
- The Japanese Society of Systematic Zoology
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.297-342, 2021-10-14 (Released:2021-10-14)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 2
Investigations were carried out on 22 deep-water octocoral specimens in the family Coralliidae sampled from the Emperor Seamounts during 2009 to 2012. The specimens were collected from 350–1100 m deep, mostly from the southernmost region of the Emperor Seamounts. Colonies were identified by visual and microscopic observation of standard morphological characters (colony size, diameters of colony base and branches, diameter and height of autozooid mound, thickness of coenenchyme and sclerite sizes, etc.) along with supporting information from molecular DNA analysis. Half of the 22 specimens were identified as Pleurocorallium cf. pusillum (Kishinouye, 1903), suggesting that the species called “Mid” that was once harvested dominantly in this area was this species. The remaining 11 specimens were identified as genus Hemicorallium Gray, 1867. These were identified as belonging to the following species: one previously described species [H. laauense (Bayer, 1956)], three similar species [H. cf. abyssale (Bayer, 1956), H. cf. regale (Bayer, 1956), H. cf. sulcatum (Kishinouye, 1903)] and three new species (H. kaiyo sp. nov., H. muzikae sp. nov. and H. tokiyasui sp. nov.).
- 著者
- 三浦 しをん 金田 淳子
- 出版者
- 青土社
- 雑誌
- ユリイカ (ISSN:13425641)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.7, pp.8-29, 2007-06
6 0 0 0 OA 生命倫理学の立場から見た子宮移植の論点
- 著者
- 高島 響子
- 出版者
- 一般社団法人 日本移植学会
- 雑誌
- 移植 (ISSN:05787947)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.37-43, 2022 (Released:2022-05-19)
- 参考文献数
- 23
Uterus transplantation (UTx) has become a new potential option for women with absolute uterine factor infertility (UFI), who desire to give birth to their own children. In UTx, organ transplantation from living or deceased donors is used under the goal of assisted reproductive technology. In July of 2021, the commission for ethical issues on UTx under the Japanese Association of Medical Sciences published the report, and allowed the conducting of clinical research on UTx with a limited number of patients. This article discusses bioethical considerations of UTx. Transplantation from a living donor is an exceptional procedure which does not fulfill ethical principles of non-maleficence nor justice. Autonomy is also affected because the national guideline requires that a donor should primarily be a family member of the recipient and it raises a concern whether both a donor and a recipient feel pressure. Transplantation from a living donor is accepted because beneficence (saving a patient’s life) surpasses the other principles. This formula cannot be applied to UTx from living donors because the uterus is not a vital organ, and it is difficult to ethically justify such a transplantation. The interest of children is another important ethical issue. From a research ethics perspective, UTx is an unproven intervention to achieve the clinical goal for UFI women. Implementing UTx not as treatment but as clinical research first is supported by the standard of research ethics today. However, allowing clinical research embraces the practice of UTx itself, while unresolved ethical considerations are left behind. Continuous discussion open to public, review of institutional systems including legislation reform, and wholistic care and support for UFI women are needed.
- 著者
- 岡本健 [ほか] 編
- 出版者
- 人文書院
- 巻号頁・発行日
- 2021
6 0 0 0 OA 日本全国諸会社役員録
6 0 0 0 OA 兵庫県会社一覧
- 著者
- 兵庫県総務部調査課 編
- 出版者
- 兵庫県総務部調査課
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和15年12月末日現在, 1941
6 0 0 0 政治改革をめぐる政治過程の研究
1 1996年度に引き続き、政治改革に関する一次資料を収集・複写し、目録を作成した。本年度は、とくに国会審議関係の資料、第八次選挙制度審議会関係の資料、マスコミ関係の資料、および政治改革推進協議会(民間政治臨調)関係の資料を充実させることができた。その結果、昨年度以来収集した資料は約1000点に達した。これらの資料は、現在「政治改革ア-カイヴ」として東京大学法学部研究室内に暫定的に保管してある、今後、最終的な収納先および公開方法について検討する予定である。2 上記ア-カイヴを主たる素材として、政治改革に関する政治過程の分析を行うための「政治改革研究会」が、研究分担者・および8名の研究協力者(飯尾潤、岩井奉信、野中尚人、岩崎健久、濱口金也、内山融、岩崎正洋、川人貞史の各氏、順不同)を得て組織された。具体的な研究項目は、竹下〜海部内閣・宮澤内閣・細川内閣の時系列的部分と、自民党・野党・政治改革推進協議会・労働界・マスコミ・選挙制度・政治資金および腐敗防止などのテーマ別部分からなり、それぞれの項目について論文が提出されている。3 研究会の成果を社会化するため、『政治改革の記録(仮称)』編集委員会を断続的に開催し、1998年秋の公刊を目指して作業が進められている。現在は出版社との調整、提出済み論文の検討作業、および掲載資料の編集・インタビュー調査の準備を行っているところである。
- 著者
- 北川 朋子
- 出版者
- 聖トマス大学
- 雑誌
- サピエンチア : 英知大学論叢 (ISSN:02862204)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.74-95, 2013-03
6 0 0 0 OA オーストラリア・ビクトリア州における 自発的幇助自死法の成立と特徴
- 著者
- 南 貴子
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.40-48, 2018-09-29 (Released:2019-08-01)
- 参考文献数
- 20
オーストラリア・ビクトリア州において、2017年11月29日にVoluntary Assisted Dying Bill 2017(自発的幇助自死法案)が議会を通過し、2019年6月19日までに施行されることになった。ビクトリア州に住む18歳以上の成人で、意思決定能力があり、余命6か月以内の末期患者に対して、自ら命を絶つために医師に致死薬を要請する権利が認められる。オーストラリアでは、北部準州において1995年に世界で初めての「医師による患者の積極的安楽死並びに自殺幇助」を認める安楽死法Rights of the Terminally Ill Act 1995(終末期患者の権利法) が成立したが、施行後9か月で無効となった。その後20年の歳月を経て、ビクトリア州で幇助自死を認める安楽死法がオーストラリアで唯一成立したことになる。 Andrews政権が「世界で最も安全で最も抑制のきいたモデル」と評するビクトリア州の「自発的幇助自死 法」の成立と特徴について、そのセーフガードに焦点を当てつつ、他国の安楽死・幇助自死法との比較も踏まえながら分析する。
6 0 0 0 OA 敦煌毛詩音残巻反切の研究 (上)
- 著者
- 平山 久雄
- 出版者
- 北海道大學文學部
- 雑誌
- 北海道大學文學部紀要 (ISSN:04376668)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.1-243, 1966-03-26