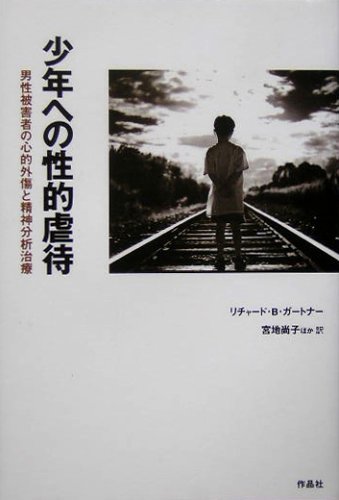- 著者
- 田島 悠来 タジマ ユウキ Tajima Yuki
- 出版者
- 同志社大学社会学会
- 雑誌
- 評論・社会科学 = Social science review (ISSN:02862840)
- 巻号頁・発行日
- no.119, pp.19-40, 2016-12
論文(Article)本稿では、「ご当地アイドル」のパフォーマンスを事例に、住民主体の地域振興のあり方について探究した。その際、パフォーマンス研究という枠組みを用い、「ご当地アイドル」のメンバーおよび運営にまつわる関係者に対して実施した聞き取り調査の結果をもとに、メンバー(=パフォーマー)にとってパフォーマンスがどのような効果を発揮し、それが地域振興とどのように関わっていったのかを、シェクナー(2006)が提唱したパフォーマンス機能の類型を参照しながら考察した。以上の結果、「ご当地アイドル」のパフォーマンスは、パフォーマーにとって、娯楽、アイデンティティの確認・変更、共同体の構築・維持、教育・説得という主として4つの機能を持つことで、若い世代が主体となる地域振興の可能性を提示していることが導き出せた。This paper examines the regional revitalization as an empowerment by local residents, through a case study about the activities of regional idols in Japan. In this article, I discuss what impacts were had on the members of idol groups (performers) and how their performances were related to regional promotion, using the framework of performance studies and having semi-structured interviews with regional idols and their stakeholders. Refer to Schechner's theory about the functions of performance (2006), the performances of regional idols have mainly four functions for performers: to entertain, to mark or change identity, to make or foster community, and to teach, persuade, or convince. At the same time, this implies the potential for the empowerment of young generations.
6 0 0 0 OA 電車内痴漢の分類とその特徴 -新聞報道を用いた探索的分析-
- 著者
- 大髙 実奈
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 雑誌
- 東洋大学大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School, Toyo University (ISSN:02890445)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.65-85, 2021-03-15
6 0 0 0 IR 幼児期における恐怖対象の発達的変化
- 著者
- 富田 昌平 TOMITA Shohei
- 出版者
- 三重大学教育学部
- 雑誌
- 三重大学教育学部研究紀要. 自然科学・人文科学・社会科学・教育科学・教育実践 = BULLETIN OF THE FACULTY OF EDUCATION MIE UNIVERSITY. Natural Science,Humanities,Social Science,Education,Educational Practice (ISSN:18802419)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.129-136, 2017-03-31
本研究では、幼児期における恐怖対象の発達的変化について検討した。研究1では、保育園年中児29名、年長児26名を対象に、恐怖対象の有無やその内容と理由、5つの一般的な恐怖対象(お化け、動物・虫、暗闇、幽霊、注射)に対する感情評価について尋ねた。その結果、子どもの恐怖対象の数は加齢に伴い減少すること、女児は男児よりも恐怖対象を持つ傾向にあることが示された。研究2では、幼稚園児の保護者66名を対象に、子どもの恐怖傾向とその強さ、恐怖対象の内容と発達的変化について尋ねた。その結果、恐怖対象の発達差や性差に関して、研究1の結果が概ね繰り返された。また、内容的には年齢や男女問わず、お化け、動物・虫、幽霊、暗闇、1人でいることなどが多く挙げられ、加齢に伴い想像的なものに対する恐怖が増加することが示唆された。考察では、幼児期における恐怖対象とその発達的変化を踏まえた上で、「怖い」を楽しむ実践を育児や保育においてどのように位置づけ、展開していくかが議論された。【キーワード】恐怖対象、想像、幼児
6 0 0 0 IR いのちの尊厳へのまなざし : 精神障害者福祉の歴史と現状を踏まえて
- 著者
- 田村 綾子
- 雑誌
- 聖学院大学総合研究所紀要
- 巻号頁・発行日
- no.64, pp.328-362, 2018-03-31
6 0 0 0 OA 炭焼き加熱特性の解析 (第2報)
- 著者
- 石黒 初紀 阿部 加奈子 辰口 直子 蒋 麗華 久保田 紀久枝 渋川 祥子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.95-103, 2005-02-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
一般には炭火で調理されたものがおいしいと評価されることは多いがその根拠は明らかにされていない.そこで, 伝熱量および放射の割合を同等にした数種の熱源で鶏肉を焙焼し, 官能検査, においの成分分析を行った.さらに, 試料を焙焼する熱源から発生する燃焼ガスの成分分析を行った.官能検査の結果, においと総合的評価は[炭火焼き]と[ガス網焼き]を比較すると, 有意差は認められなかったが[炭火焼き]が好まれる傾向がみられ, さらにその匂いの差は識別できるものであった.そこで, においについて機器測定を行った.その結果, エレクトロニック・ノーズによる分析結果からセンサーが測定できるにおい成分の量は[ガス直火焼き], [ガス網焼き], [ヒーター焼き]は同等であるが, [炭火焼き]は他の熱源のものより低いことがわかった.このため, 炭火加熱により生じたにおいに何らかの違いがあることが考えられた.また, GCMSによる分析結果から, 官能検査により炭火加熱をした鶏肉の方が好まれた要因は, 香気成分組成において好ましくないにおいを持つ脂肪族アルデヒド類の割合が焼き網に比べ少なく, 香ばしい香りを有するピラジン類やピロール類の割合が多いためと考えられた.鶏肉の焙焼香の違いの原因は, 燃焼ガスにあるのではないかと考え, 燃焼ガスの測定を行った.その結果, 炭の燃焼ガスには, 焼き網よりも還元性の強い一酸化炭素や水素が多く含まれ, 酸素の含有量が少なかった.なお, この燃焼ガスの組成の違いと香気成分の生成との詳細な関連についてはさらなる検討が必要である.
6 0 0 0 IR ある精神障害者のライフストーリーにみるリカバリー
- 著者
- 寺澤 法弘 Terazawa Norihiro
- 出版者
- 大阪府立大学人間社会システム科学研究科 人間社会学専攻社会福祉学分野
- 雑誌
- 社會問題研究 (ISSN:09124640)
- 巻号頁・発行日
- no.68, pp.69-82, 2019-02-28
6 0 0 0 アンダークラス言説再考 : 再分配のための「承認」に向けて
- 著者
- 堅田 香緒里
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.16-28, 2005
「脱工業化」社会の貧困の多くも,従来の貧困同様,社会的要因に起因するものであるが,それへの社会的対応の一つとしての再分配が十全には行われていない.こうした状況が許される背景として,特定の言説の影響が考えられる.本稿ではまず,そうした言説の一つとしてアンダークラス言説を取り上げ,それが再分配に与える影響について考察している.その結果,アンダークラス言説は,アンダークラスをアブノーマルなものとして構成することによって,再分配を脱正当化しているということが明らかになった.続いて,今日,十全な再分配を要求し得るアプローチの一つとして,ナンシー・フレイザーの「再分配と承認」アプローチを検討している.その結果,彼女のアプローチは,経済的な再分配と象徴的な承認という二側面を包含している点および承認の対象を地位に求めている点において,十全な再分配の要求ないし貧困の政治にとって有用であることが確認された.
- 著者
- 藤田 秀樹
- 出版者
- 富山大学人文学部
- 雑誌
- 富山大学人文学部紀要 (ISSN:03865975)
- 巻号頁・発行日
- no.68, pp.109-123, 2018
『ジョーズ』においては,三人の白人男性が,具体的には地元の警察署長,サメの捕獲に執着する漁師,そしてサメを専門に研究する海洋学者が,この役割を果たす。生業も年恰好もパーソナリティもそれぞれ異なるこれら三人の関係性は,当初は友好的とは言い難いものだが,次第に彼らの間に男同士の絆とでも言うべきものが醸成されていく。そして彼らは団結して,怪物のように巨大で狡猾なサメと対決する。かように『ジョーズ』は,大災害映画であると同時に,男同士の絆を描くバディ映画(buddy film)としての佇まいをも併せ持つ。レスター・D・フリードマンによれば,「スピルバーグ映画の多くは,初めのうちは張り合うが,最終的にはお互いを理解し敬意を払い,共通の敵を打ち破るために団結するようになる男たちを機軸に展開する」のであり,「『ジョーズ』は,スピルバーグ映画において男同士の絆を最も明確に表現したもののひとつであり続けている」。災厄が起こるまでは互いに接点も接触もなく,急遽寄せ集められたという観すらあり,サメに関する経験的知識や科学的知識という強みだけでなく,水恐怖症という弱みやサメとの過去の忌まわしい因縁をも抱えた男たちが,それぞれの個性をぶつけ合わせながらも結束しカタストロフィに立ち向かっていくさまに,この映画の大きな興趣があるのではなかろうか。以上のようなことを念頭に置きつつ,『ジョーズ』という映画テクストを読み解いていくことにする。
6 0 0 0 OA 参加民主主義のすすめ : 逆転型全体主義から自由と平等を守る
- 著者
- 浜野 研三 Kenzo Hamano
- 雑誌
- 人文論究 = Jimbun ronkyu : humanities review (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.73-95, 2018-05-20
6 0 0 0 IR 脱物質主義の労働観 : 合理化から再魔術化へ
- 著者
- 寺崎 正啓
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 鶴山論叢 (ISSN:13463888)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.83*-97*, 2009-03
6 0 0 0 OA 地球意識計画
- 著者
- ネルソン ロジャー・D 小久保 秀之
- 出版者
- International Society of Life Information Science
- 雑誌
- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.185-192, 2014-09-01 (Released:2018-10-13)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3
地球意識計画(GCP)と呼ばれる長期継続実験は、同期的に生成されたランダムデータの流れの中から、大規模な出来事によって生じるランダムでない構造を探索する。地球規模の乱数発生器(RNG)ネットワークが、最多で世界65箇所の並列ランダムデータの系列を記録し、「世界的な出来事(素晴らしい祝典や悲劇に対する広範囲の精神的・感情的な一時的反応と定義)」が起こっているときに期待値からデータが偏るという仮説を厳密な実験で検証する。現在進行中の再現実験は、指定された出来事の期間、ネットワーク中の相互作用を測定する。そして過去15年以上にわたる450件以上の公式仮説の結果は十分に期待値から離れており、帰無仮説に対して1兆分の1以下である。対照実験によって従来の物理学的説明や実験エラーは除外され、また実験計画法によって解釈が制限される。実験結果は、ある種の人間の意識が効果の源として含まれていることを示唆している。ランダムデータの微かな構造化は、人間の可干渉な注目と感情が物質世界に効果をもたらすことを示している。
6 0 0 0 OA 19世紀末イギリスの服飾観―ダンディと新しい女
- 著者
- 佐々井 啓
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.6, pp.262-271, 2015 (Released:2015-06-18)
- 参考文献数
- 48
6 0 0 0 OA 城跡の公園化と歴史的環境の整備
- 著者
- 田畑 貞寿 宮城 俊作 内田 和伸
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.169-174, 1989-03-30 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 7
本研究では, わが国の近世城郭跡の保存と活用を目的とした公園化による環境整備がどのようにすすめられているのかを明らかにし, 史跡保存のため新たな史跡公園化の方途を探ることを目的とした。国内90ケ所の城址公園を対象として行った調査により, 多くの事例において史跡指定→指定地内の土地公有化→施設の移転→遺構の発掘調査→復元整備→史跡公園化といった事業のプロセスが確認された。
6 0 0 0 OA 対立する情報との接触が態度に及ぼす効果 ―対立の種類に着目した研究レビュー―
- 著者
- 小林 敬一
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.143-161, 2016 (Released:2018-04-13)
- 参考文献数
- 96
In our society, exposure to conflicting information concerning public issues is the norm rather than the exception. Despite this, to date there has been no comprehensive assessment of studies examining the effects of exposure to conflicting information on attitude formation and change. Therefore, the present article reviewed empirical studies across three relevant research areas: social network heterogeneity, competitive framing, and attitude polarization. Synthesis of these findings suggest that exposure to conflicting information weakens the strength of preexisting attitudes, encourages the formation of moderate attitudes, enhances the impact of a frame (a stronger frame, an antecedent frame, or a subsequent frame) on attitude formation, or leads to perceived attitude polarization. As a unified explanation of these effects, a model is presented. This model posits that a certain aspect of conflicting information communicated, including a conflict of claims, arguments, and frames, is highlighted by moderating factors (e.g., the presence or absence of social network as an information source, the accessibility of preexisting attitudes), thereby bringing about different exposure effects. Finally, some directions for future research are proposed.
6 0 0 0 OA 群発頭痛に対して選奇湯の頓用が著効した1例
- 著者
- 森 裕紀子 五野 由佳理 及川 哲郎 小田口 浩 花輪 壽彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.274-279, 2016 (Released:2016-11-22)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1 1
群発頭痛の発作軽減に選奇湯の頓用が奏効した症例を経験した。症例は46歳女性で,30歳頃より季節の変わり目に群発頭痛の発作があり,症状は3日間持続した。発作時トリプタンや消炎解熱鎮痛剤は無効で,その発作の持続時間が長く頻回となったため漢方治療を希望し来院した。瘀血と気鬱より随証治療で通導散料を処方して頭痛の頻度と程度は軽減したが,鎮痛剤が無効な頭痛発作は生じた。そこで眉稜骨(眼窩上縁)内側の圧痛を認め,痛みの範囲が眉稜骨周囲のため頭痛時に選奇湯を頓用としたところ,最近1∼2週間持続した発作が30分で消失した。一般に構成生薬が少ない漢方薬ほど切れ味がよいとされる。選奇湯は黄芩を含む5味と構成生薬が少なく,頓用での効果が期待できる。眉稜骨周囲の痛みに対して,特に眉稜骨内側の圧痛を認める場合は選奇湯の頓用は試みるべき処方の1つである。
6 0 0 0 OA 開鼻声の定量的評価法に関する研究
- 著者
- 片岡 竜太
- 出版者
- 一般社団法人 日本口蓋裂学会
- 雑誌
- 日本口蓋裂学会雑誌 (ISSN:03865185)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.204-216, 1988-12-26 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 3
臨床応用可能な開鼻声の定量的評価法を確立するために,口蓋裂あるいは先天性鼻咽腔閉鎖不全症による開鼻声患者18例と健常人17例の発声した母音/i/について声道伝達特性を観察するためにケプストラム分析を行い,得られたスペクトルエンベロープに1/3オクターブ分析を加え,開鼻声の周波数特性を求めた.次に20人の聴取者による開鼻声の聴覚心理実験を行い,得られた主観評価量と声道伝達特性を表わす物理量の関連を検討したところ次の結果が得られた.1)開鼻声のスペクトルエンベロープの特徴は健常音声のスペクトルエンベロープと比較して第1,第2フォルマント間のレベルの上昇と,第2,第3フォルマントを含む帯域のレベルの低下であった.2)開鼻声の聴覚心理実験を行い得られた5段階評価値を因子分析したところ,開鼻声を表現する2次元心理空間上に2つの因子が存在し,第1因子は全聴取者に共通した聴覚心理上の因子であり,第2因子は聴取者間の個人差を表わす因子であると考えられた.そのうち第1因子を主観評価量とした.3)開鼻声の主観評価量と1/3オクターブ分析から得られた物理量の相関を検討したところ,第1フォルマントの含まれる帯域から2/3-4/3オクターブ帯域の平均レベル(物理評価量L1)および第1フォルマントの含まれる帯域から9/3-11/3オクターブの帯域の平均レベル(物理評価量L2)と主観評価量に高い相関が認められた.
- 著者
- 田中 耕一郎
- 出版者
- 北星学園大学
- 雑誌
- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 = Hokusei review, the School of Social Welfare (ISSN:13426958)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.91-114, 2016-03
6 0 0 0 少年への性的虐待 : 男性被害者の心的外傷と精神分析治療
- 著者
- リチャード・B・ガートナー著 宮地尚子ほか訳
- 出版者
- 作品社
- 巻号頁・発行日
- 2005
6 0 0 0 OA マルチモーダル情報に基づくグループ会話におけるコミュニケーション能力の推定
- 著者
- 岡田 将吾 松儀 良広 中野 有紀子 林 佑樹 黄 宏軒 高瀬 裕 新田 克己
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.AI30-E_1-12, 2016-11-01 (Released:2016-11-02)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 6
This paper focuses on developing a model for estimating communication skills of each participant in a group from multimodal (verbal and nonverbal) features. For this purpose, we use a multimodal group meeting corpus including audio signal data and head motion sensor data of participants observed in 30 group meeting sessions. The corpus also includes the communication skills of each participant, which is assessed by 21 external observers with the experience of human resource management. We extracted various kinds of features such as spoken utterances, acoustic features, speaking turns and the amount of head motion to estimate the communication skills. First, we created a regression model to infer the level of communication skills from these features using support vector regression to evaluate the estimation accuracy of the communication skills. Second, we created a binary (high or low) classification model using support vector machine. Experiment results show that the multimodal model achieved 0.62 in R2 as the regression accuracy of overall skill, and also achieved 0.93 as the classification accuracy. This paper reports effective features in predicting the level of communication skill and shows that these features are also useful in characterizing the difference between the participants who have high level communication skills and those who do not.
6 0 0 0 OA 脳卒中治療ガイドライン2021におけるリハビリテーション領域の動向
- 著者
- 松野 悟之
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.129-141, 2022 (Released:2022-02-20)
- 参考文献数
- 6
本稿は,改訂された脳卒中治療ガイドライン2021について,リハビリテーション領域に関連する内容を中心に紹介し,新たな治療や既存治療のエビデンスレベルの向上などを理解することで,医療従事者が脳卒中患者に対する適切な評価および治療の選択の一助となることを目的とした.今回の改訂では,脳卒中治療ガイドライン2015と比べて,リハビリテーション領域の治療において,反復性経頭蓋磁気刺激や経頭蓋直流電気刺激を用いた治療の推奨が増加した.既存の治療においても,その有効性を検証する研究が実施され,エビデンスレベルが向上したものもある.一方で,今回の改訂で削除された内容もみられる.ガイドラインを踏まえた指針や判断基準を土台にして,臨床現場における個々の患者に対する柔軟な対応の両面が重要だと考える.