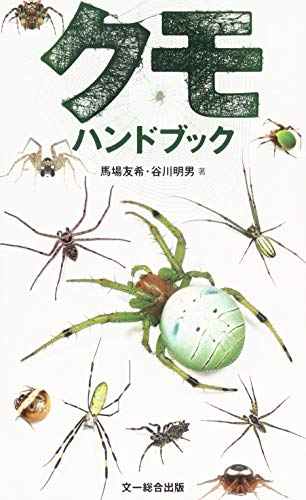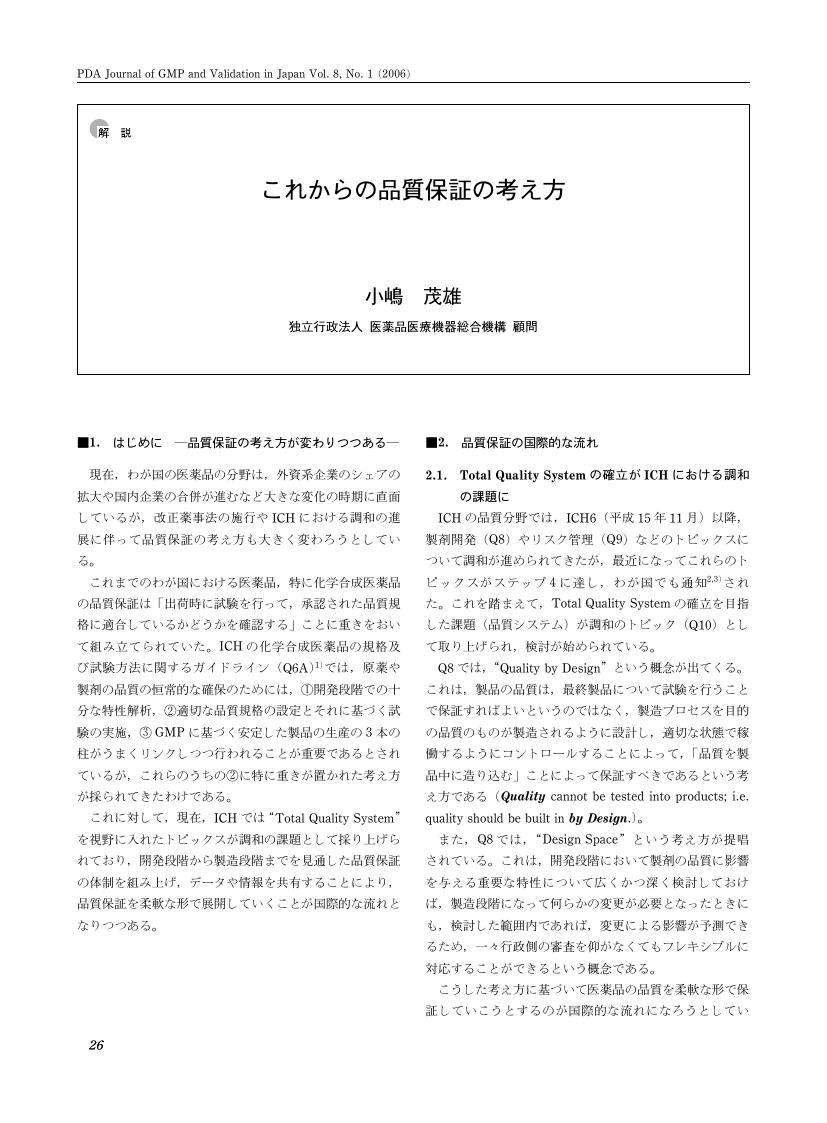1 0 0 0 OA 外国人外出一件 2巻
- 出版者
- 写
- 巻号頁・発行日
- vol.[1],
1 0 0 0 OA 課題解決力強化のための大学生対象のAL活動
- 著者
- 櫻井 敬三
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.910-913, 2017-10-28
一般講演要旨
1 0 0 0 OA 教育連携と人材育成取り組みにおける考察
- 著者
- 若月 聡
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.906-909, 2017-10-28
一般講演要旨
1 0 0 0 OA 七つ意呂婆東都布地尽 み 浦橋八十之助実者十太丸・つるみのふし
1 0 0 0 クモハンドブック
- 著者
- 馬場友希 谷川明男著
- 出版者
- 文一総合出版
- 巻号頁・発行日
- 2015
1 0 0 0 OA 逸脱管理に関する事例研究</br> ~よりよい逸脱管理のために~
- 著者
- 竹澤 健一 片山 博仁 田中 広徳 田村 圭史郎 中村 みさ子 三宅 正一 室井 哲夫 百永 眞士 山岡 尚志 涌田 俊哉
- 出版者
- 一般社団法人日本PDA製薬学会
- 雑誌
- 日本PDA学術誌 GMPとバリデーション (ISSN:13444891)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.78-86, 2006 (Released:2007-05-10)
In the revised “GMP Ministerial Ordinance on Drugs and Quasi-drugs” announced by MHLW in December 2004, “deviation control” was stipulated. In response to this, Manufacturer needs to prepare SOPs to control and handle deviations appropriately and any deviation has to be documented. When critical deviation is occurred, impact assessment on the quality has to be also performed. If the deviation may have quality impact, the deviation has to be notified to Licensed Marketing Approval Holder of the product. Therefore, manufacturing unit or quality unit in manufacturer is required to have sufficient knowledge and ability to execute root cause analysis, impact assessment and corrective action/preventative action (CAPA). In this article, by taking up the following three cases, how to handle deviations such as root cause analysis, impact assessment of quality and CAPA has been discussed. 1) Deviation from the standard operating procedure in granulation process 2) Deviation from the specification in pharmaceutical water 3) Deviation from the humidity limit in stability chamber In each case, insufficient handling example is first introduced and then desirable way of thinking is shown along with appropriate example. Points to be considered are also discussed for a more appropriate handling.
1 0 0 0 OA これからの品質保証の考え方
- 著者
- 小嶋 茂雄
- 出版者
- 一般社団法人日本PDA製薬学会
- 雑誌
- 日本PDA学術誌 GMPとバリデーション (ISSN:13444891)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.26-38, 2006 (Released:2007-05-10)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 伊藤 史人 九鬼 孝夫 濱住 啓之
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会冬季大会講演予稿集 2014 (ISSN:13434357)
- 巻号頁・発行日
- pp.1-2-1_-_1-2-1_, 2014-12-17 (Released:2017-06-05)
1 0 0 0 OA 薬物療法の予想される変化と対応すべく品質保証のあり方
- 著者
- 西畑 利明
- 出版者
- 一般社団法人日本PDA製薬学会
- 雑誌
- 日本PDA学術誌 GMPとバリデーション (ISSN:13444891)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.18-25, 2006 (Released:2007-05-10)
- 参考文献数
- 5
遺伝子解析の著しい進歩,薬理ゲノミクスの治療および新薬開発への積極取り込みなど,科学技術の著しい進歩の中で,既存の医薬品の服用のあり方や新たに世の中に出てくる医薬品の機能は変化する兆しがあり,この変化は加速すると予想できる。この変化の向かっているところは,個々の患者に“最も適した医薬品は?”や“最も適した服用量は?”であり,本来の目標である患者本位の薬物治療を実施することにある。医薬品の服用のあり方や新たに世の中に出てくる医薬品の機能がどのように変化しようとも,製造販売承認を受けた医薬品を“製造・品質管理し,世の中に供給する使命”を遂行する上で,企業が遵守しなければならに絶対要件は“承認時の約束ごとである承認事項で決められた品質を医薬品が確保していること”である。この医薬品の保証の原点は企業の品質管理システムの内容と運用に依存するところが大きく,品質管理システムは科学技術・管理手法の進歩により変化することも認識する必要がある。医薬品の出荷基準に係わる品質保証を達成する手法として,品質管理システムの一つとしてのリスクマネジメント手法の導入・運用が重要となり,高度のリスクマネジメントを達成するための製造工程の Process Analytical Technology 手法の積極的活用が推奨されている。
1 0 0 0 OA 自己理解を促す保健指導が児童のレジリエンスに与える影響の検討
- 著者
- 原 郁水 古田 真司
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告. 教育科学編 (ISSN:18845142)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.53-59, 2016-03-01
1 0 0 0 OA 東海道五十三次の内 浜松 毛剃九右衛門
- 著者
- 豊国
- 出版者
- 辻岡屋
- 雑誌
- [役者見立東海道五十三駅]
1 0 0 0 OA 世界の泥火山研究レビュー(無機化学編)
- 著者
- 土岐 知弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第124年学術大会(2017愛媛) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.087, 2017 (Released:2018-03-30)
1 0 0 0 OA 切り花生産のための花序の発達機構 : シュッコンカスミソウを例にして
- 著者
- 札埜 高志
- 出版者
- 一般社団法人植物化学調節学会
- 雑誌
- 植物の生長調節 (ISSN:13465406)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.114-119, 2012-12-20 (Released:2017-09-29)
- 参考文献数
- 32
Inflorescence characterized by clusters of florets, rather than simple flowers, is often used as cut flowers. The number of florets and the shape of inflorescence have a significant impact on the quality and price of cut flowers, and therefore, controlling these characters is crucial in cut flower production. The mechanism of inflorescence architecture development appears to intricately change depending on the hereditary factors and cultivation conditions, but it has some regularity, too. In this paper, it is explained that the mechanism of inflorescence architecture development for the purpose of stable production of cut flowers, especially of Gypsophila paniculata using a term of "regularity" as a keyword.
- 著者
- 土井 元章 森田 隆史 武田 恭明 浅平 端
- 出版者
- 園藝學會
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.795-801, 1991
- 被引用文献数
- 1 2
シュッコンカスミソウの生育開花に関する低温要求性の異なる品種, 系統を用い, 冬期の低温に遭遇した後の株において, シュートの種々の生育段階における高温遭遇がロゼットの形成および奇形花の発生に及ぼす影響について検討した.<br>その結果, シュートが栄養生長段階である3月31日から4月10日に昼温30°C (6:00~18:00) 夜温25°Cの高温処理を施すと, 低温要求性の大きい'パーフェクタ', 'ブリストル•フェアリー'20系統では, その後生育, 開花に好適な条件下で栽培してもすべてのシュートがロゼットを形成した. これらの品種, 系統についで低温要求性の大きい'ダイヤモンド', 'ブリストル•フェアリー'03系統においても高温遭遇後は半数のシュートがロゼットを形成した. 一方, 低温要求性の小さい'フラミンゴ', 'レッド•シー', 'ブリストル•フェアリー'08系統では, ロゼットを形成することなく, 開花に至った.<br>花芽形成開始直後に処理した高温は, 開花時の花茎を短くし, 主茎上の下位節での花芽形成を抑制した以外, 形態的な変化をもたらさなかった.<br>頂花における雄ずい形成期である4月30日前後に高温を処理すると, 奇形花が発生した. 奇形花の形態的な観察を行ったところ, 奇形花は, 各小花が雄ずい形成期ごろに高温に遭遇することにより, その後雄ずい原基の細胞分裂活性が長期にわたり維持されるようになり, 雄ずいの花弁化が異常に進み, 花弁数が増加するとともに分裂部を中心に花弁塊が形成される結果, 発生するものと考えられた. また, 高温による奇形花の発生は, 低温要求性の大きい品種, 系統ほど著しい傾向にあった.<br>以上の結果より, 低温遭遇後に高温に遭遇すると, 高温が低温の効果を打ち消し, 生理的にロゼット化を誘導する結果, 分裂組織における生育がより栄養生長的となり, 形態的にロゼットや奇形花を形成するようになることが考察された.
1 0 0 0 OA [豊田天功書簡]
- 著者
- [豊田天功] [著]
- 巻号頁・発行日
- vol.[84], 1800