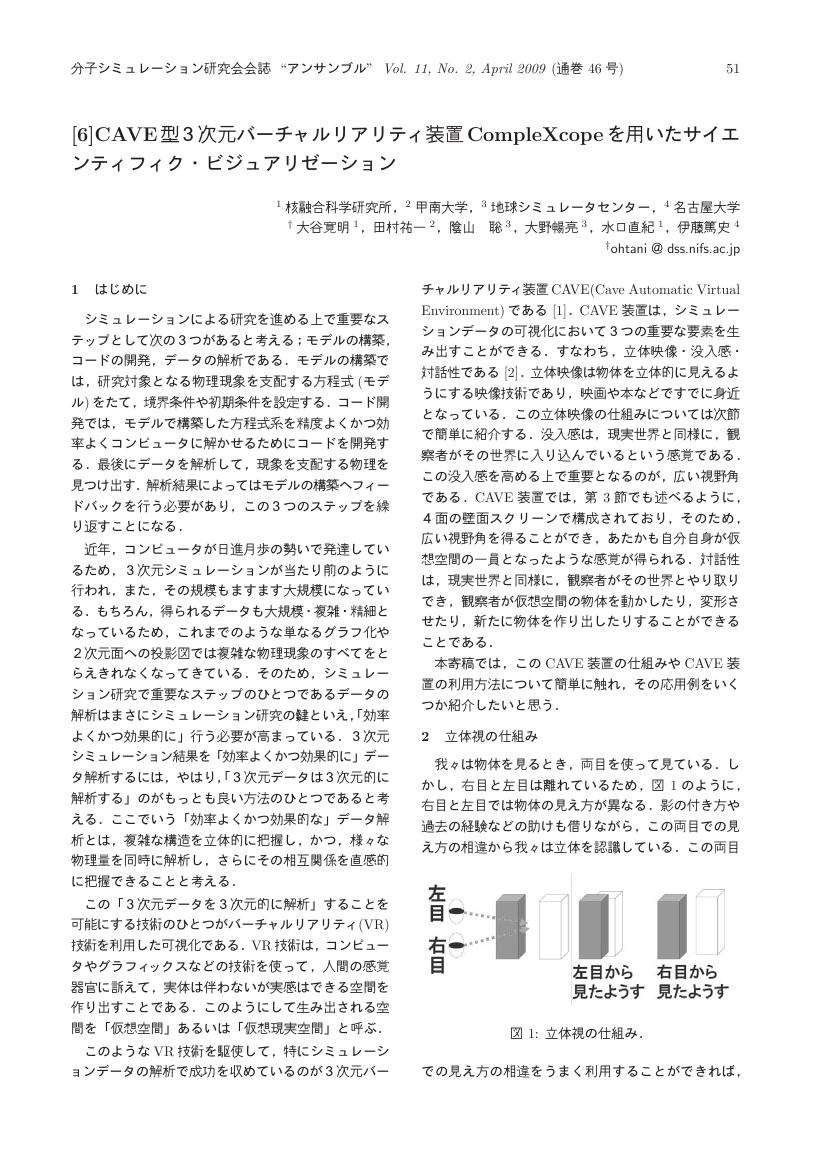- 著者
- 飯倉 義之
- 出版者
- 比較日本文化研究会 ; [1994]-
- 雑誌
- 比較日本文化研究
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.53-63, 2012-09
1 0 0 0 IR 古典ラテン語の散文における名詞句の分離配置について
- 著者
- 樋元 祥太郎 ヒモト ショウタロウ HIMOTO Shotaro
- 出版者
- 東京外国語大学地域文化研究科・外国語学部記述言語学研究室
- 雑誌
- 思言 : 東京外国語大学記述言語学論集 (ISSN:18844391)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.143-150, 2017-12-08
1 0 0 0 ラテン語の名詞フレーズの分離配置について
- 著者
- 寺門 伸
- 出版者
- 獨協医科大学語学・教養科目紀要編集委員会
- 雑誌
- 語学・教養科目紀要 (ISSN:18815405)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.17-37, 2013-12
1 0 0 0 OA 部分文字列増幅法による共通パターン発見アルゴリズム
- 著者
- 池田 大輔 山田 泰寛 廣川 佐千男
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用(TOM) (ISSN:18827780)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.SIG2(TOM11), pp.56-66, 2005-01-15
本論文では,複数の文字列に共通な部分を見つける問題を考察する.まず,この問題をパターンから生成された文字列の集合が与えられたときに,そのパターンの定数部分を見つける問題(テンプレート発見問題)として定式化する.パターンとは定数と変数からなる文字列で,パターンが生成する語は変数を定数文字列で置きかえて得られる.置きかえに用いられる文字列中の部分文字列の頻度分布はベキ分布に従うことを仮定し,高確率でテンプレート発見を解くアルゴリズムを構築する.共通部分の発見問題の1 つである最長の共通部分列を探す問題はNP 完全であることが知られているが,問題の再定式化,部分文字列の集合による定数部分の表現方法,部分文字列の頻度と総出現数から共通部分を発見する手法により,テンプレート発見問題は高確率でO(n) 時間で解けることを示す.ここで,n は入力文字列の長さの和である.さらに,このアルゴリズムがノイズに対し頑健であることと,複数のテンプレートが混在する場合でも有効であることを,Web 上の実データに適用することで実証する.
1 0 0 0 OA 児童の逸脱行動が問題視される学級集団特性の分析
- 著者
- 弓削 洋子 後藤 倫美
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告. 教育科学編 (ISSN:18845142)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.25-31, 2018-03-01
1 0 0 0 中国語固有名詞の中日表記対応辞書とその知的検索支援システムの構築
本研究は当初の計画に従い以下の研究成果を得た。1.中国語音節片仮名表記法(jピンイン)の最適化中国在住の中国語母国語話者を対象とする聴取実験により、中国語音節の日本語仮名表記法(jピンイン)を体系として最適化した。なお、以下の研究成果はこの成果に基づき実現されたものである。2.日中対応表記辞書のコンテンツの作成と評価一般旅行者用観光ガイドブックの索引情報や中国資料集を素材として、一般観光客に有用な地名(観光地名477個、都市名80個)および主要な人名(姓51個、名45個)を網羅的に収集し、データベースシステムACCESS2000に格納した。また、学術的観点・実用的観点からの妥当性を確認した。3.知的検索支援システムの実装と評価中国語未学習の日本人でも比較的容易に入力できるように、ピンイン入力、偏や旁さらには画数による文字候補限定による入力の他に、図形的類似に着目する「日中類似変換」方式を提案し、知的検索支援システムとして実装し、学術的観点・実用的観点から妥当性を確認した。4.日中表記対応辞書のシステムとしての評価上記の中日表記対応辞書と知的検索支援システムとをHTML、php、VB、MySQLにより作成し統合した。中国語(GB2313コード)入力に関しては既存の日本語用IME(4,402文字)と上記4の方法(2,361文字)を併用する方式を採用した。5.Webサーパーの構築とWeb化の実験上述の成果をWeb形式で公開するためにWebローカルなサーバーを構築し、マニュアルのオンライン化を含めWeb化実験を行ない、初の計画通りの動作を確認した。6.システムの総合的評価最終年度統合した辞書・検索システムをアンケート形式で総合的に評価し、表示画面の構成、操作性、機能性に関し概ね良好であることを確認した。
1 0 0 0 OA コミュニケイション的法治国家の人権制約理論
- 著者
- 西原 博史
- 出版者
- 早稲田大学社会科学学会
- 雑誌
- 早稲田社会科学総合研究 = Waseda studies in social sciences (ISSN:13457640)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.1-17, 2000-07
論文
1 0 0 0 OA 真澄遊覽記
- 著者
- [菅江真澄] [著]
- 巻号頁・発行日
- vol.第16冊, 1910
1 0 0 0 OA 高齢者拘束性肺疾患への対処
- 著者
- 石崎 武志
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.217-222, 2008-12-29 (Released:2016-12-28)
- 参考文献数
- 11
高齢者拘束性肺疾患では,種々の並存疾患や吸気制限のため最適の薬物療法の維持や呼吸リハビリテーションおよびHOT療法の継続が困難の場合がある.家族の理解と社会の支援も求められるが,医療従事者としては上記治療法と生活指導を通して,高齢者拘束性肺疾患患者がかかえる諸問題に真摯に対応し,ADLとQOLを維持改善することを目的としたい.
1 0 0 0 OA 振動触覚を用いた情報提示のための仮現運動と刺激条件
- 著者
- 丹羽 真隆 伊藤 雄一 岸野 文郎 野間 春生 柳田 康幸 保坂 憲一 久米 祐一郎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.223-232, 2009-06-30 (Released:2017-02-01)
- 参考文献数
- 30
In this paper, we explore the use of tactile apparent motion at different patterns and speeds for information displays. As the first step, we investigate stimulus conditions and the number of tactors to build information displays. As the second step, a prototype of tactor array consisting of five tactors, which is mounted on the upper arm of subjects, was constructed. In order to evaluate the system, experiments to measure the performance of users' ability to distinguish between multiple kinds of stimuli were conducted for two levels: physical level and semantic level. For the physical level, users' ability to distinguish four motion patterns at three different speeds was tested. For the semantic level, users' ability to identify four kinds of messages with three levels of importance, each of which corresponds to the combination of specific motion pattern and speed, was tested. In both experiments, users had little trouble with pattern and speed identification. Several ideas for future exploration of tactile apparent motion for general-purpose information displays are presented.
- 著者
- 大谷 寛明 田村 祐一 陰山 聡 大野 暢亮 水口 直紀 伊藤 篤史
- 出版者
- 分子シミュレーション研究会
- 雑誌
- アンサンブル (ISSN:18846750)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.2_51-2_57, 2009 (Released:2011-09-01)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 文化人類学からみた食文化
- 著者
- 野林 厚志 Nobayashi Atsushi ノバヤシ アツシ
- 出版者
- 弘文堂
- 雑誌
- 新・食文化入門. 森枝卓士, 南直人編. 弘文堂, 2004, p.134-151
- 巻号頁・発行日
- pp.134-151, 2004-10-15 (Released:2017-03-06)
新・食文化入門
1 0 0 0 OA 障害のある学生の特性に着目したICT活用の卒業研究指導
- 著者
- 針持 和郎
- 出版者
- 一般社団法人 CIEC
- 雑誌
- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.32-37, 2016-06-01 (Released:2016-12-01)
広島修道大学は5学部・4大学院研究科からなる学部生・院生数約6,000名の文科系私立大学である。本稿では,本学の障害学生支援環境を述べるとともに,与えられた学習教育環境と障害学生支援体制の中で,英語英文学科の発達障害のある学生がコンピュータを単なる清書マシーンとしてのみ使用するのではなく,インターネットを通じて信頼するに足る試料を取得し,コンコーダンスプログラムで試料を加工し,スプレッドシートを用いて統計処理を行い,ワードプロセッサで論述を展開するまでのプロセスの報告を通して,ICTの利用が発達障害のある当該の学生にとってどのようにメリットがあったかを述べる。
1 0 0 0 OA 大学における情報基礎教育の教示方法に関するアンケートから検討する「学びのスタイル」
- 著者
- 篠田 有史 鳩貝 耕一 岳 五一 松本 茂樹 高橋 正 河口 紅 吉田 賢史
- 出版者
- 一般社団法人 CIEC
- 雑誌
- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.67-72, 2016-06-01 (Released:2016-12-01)
より学習者に適応した教示の実現を目指して,取り上げる題材の難易度の調整を行うのではなく,学習者の個性豊かな学びに寄り添うという取り組みが行われている。学習者の好む教示方法や学び方を調査するため,本研究では「学びのスタイル」アンケートを提案し,主成分分析と決定木構築手法を組み合わせて分析する。情報基礎教育科目の授業に参加した学習者を対象にアンケート調査を実施し,取り上げた授業における学習者の学び方がどのようなものであるかを,取り組みを通じて明らかにする。
1 0 0 0 OA 大学生の情報モラル教育における体験重視型指導の効果
- 著者
- 西川 幸太 山岸 芳夫
- 出版者
- 一般社団法人 CIEC
- 雑誌
- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.79-84, 2016-06-01 (Released:2016-12-01)
近年,いわゆる「バカッター」に代表される,情報モラルの欠如が招くトラブルは社会的問題となっており,注目を集めている。そのため,現在は情報モラルの効果的な指導法の模索が急務とされている。我々は従来通りの指導方法である,知識や実例を紹介する事例紹介型指導と,学習者に実際に体験させながら指導する体験重視型指導の二つの指導法について,出来る限り学習因子を一致させた上で教材およびカリキュラムを作成し,大学1年生と3年生の参加者に対し指導を実践,教育効果の差を検証した。その結果,事例紹介型指導を行なった参加者には,事前と事後のテスト結果に有意差はなかったが,体験重視型指導の参加者の結果には有意差が認められた。実験後の参加者による内省文の内容についても,体験重視型指導の参加者の方が学習内容についての記述が多く見受けられた。