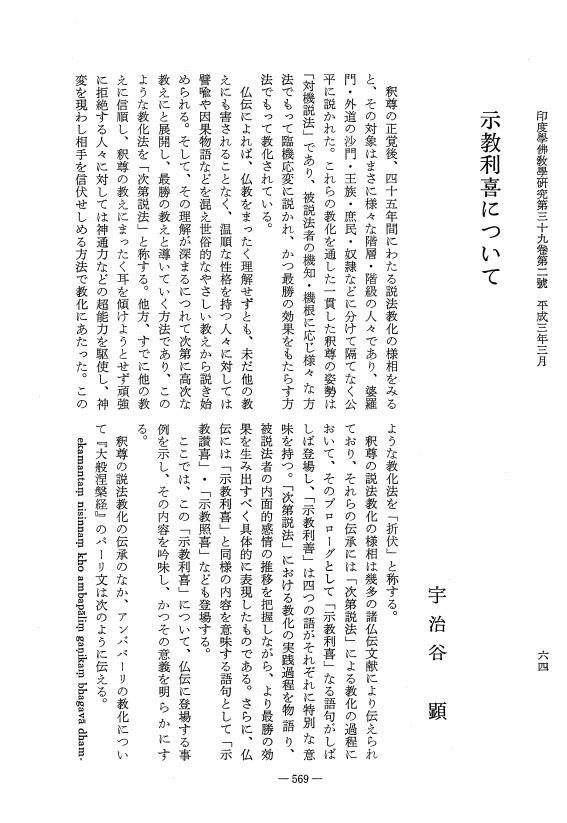- 著者
- Josep Antoni ALCOVER Pere DOVER
- 出版者
- 日本熱帯生態学会
- 雑誌
- Tropics (ISSN:0917415X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.189-201, 2000 (Released:2009-01-31)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 5 6
MyotragusbalearicusBate1909 は地中海Baleares 諸島(スペイン領)の媛小化した偶締類ウシカモシカの一種で, 4500 年前に絶滅してしまった。その先祖は,約570 万年前の,地中海の乾燥気候時にBaleares 諸島を取り囲んだ塩性砂漠を横切ってMallorca 島に移入・定着した。その島峡型進化に沿って,Myotragus は大変に特殊で,派生した特徴を獲得した。このMyotragus は,比較的小型(成獣でも肩高約50cm) で,大変にたくましい四肢ー短い掌骨と指骨,ステレオスコープのように,見えることを容易にした前方に位置する眼寓,さらにその成獣では大変長冠歯で,常に成長を続ける犬歯を具えていた。Myotraglls の移動運動は,本土のウシ類のそれとは根本的に異なっていた。それは,ある限定された関節の形状にある。これらの解剖学的形状のために,それぞ、れ異なった骨と骨(大腿骨と腔骨,上腕骨と接骨,掌骨と指骨)の関節面での動きはかなり制限されていた。つまり,現在の本土の牛科の,食肉類の攻撃に対しての,逃れるためのジグザグの動きはbaleariclls では限られていたか,全く出来なかった。足根骨と中足骨との融合は,ジグザグの動きには不適である。更新世のBalearic 諸島における食肉類の不在は,Myotragus の運動システムの島棋的進化を明らかにする鍵となる。この成獣の個々の歯の中で,常に成長をつづける1 本の犬歯の存在は,この種の最も特徴的なところである。この犬歯は最近まで第2 乳門歯(dI2) であると解釈されてきた。しかし,その成獣における存在は,ネオテニーの過程で、起こった。未成熟のこの動物は,他の初生的犬歯を有する。第2 乳門歯(dI2) は,恐らくは,最初第1 乳門歯科(dI2) の脱落後に萌出し,誕生後の数週間,未成熟の歯列中に存在する。また未成獣においては,脱落する犬歯(dC) ,下顎第3 前臼歯( dP3) ,上額第2 乳臼歯(dP2) を具えている。これら3 つの歯は,二次的永久歯の生え変わりもなく,脱落する。Myotragus におけるこのように高度に改変された歯の獲得は,鮮新世に始まり,それは気候変化と植生変化に関係してきた。M.balearicus は大変有効な草食者で,硬い植物を食べることが出来た。糞石の花粉研究から,この動物は約98%) はツゲ属の一種Buxus balearicus を食べていた。今日,この植物はBaleares 諸島における遺存種的な分布をしている。しかし,後期更新世には, Mallorca 島とMenorca 島で、は普通であった。この植物は葉に大量のbuxine alkaloid を含むために,今日のウシ類にとっては大変有毒な種である。M.balearicus の絶滅は, Baleares 諸島への人類の到達後とみなされる。確固たる原因はわからないが,それは人類到達と関係があるに違いない。
1 0 0 0 OA ビールの泡立ちとおいしさの関係 : ビールのおいしさの材料的要因について
- 著者
- 久保 英俊 寺内 文雄 久保 光徳 青木 弘行 鈴木 邁
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 45
- 巻号頁・発行日
- pp.284-285, 1998-10-30 (Released:2017-11-08)
The purpose of this paper is to clarify the effect of material of a beer cup on its taste from the view point of the froth on beer. First, the height of froth layer of beer had been measured in the two cups made of glass and ceramic respectively, after it had just poured into a cup. Next, the taste of beer were evaluated with five kinds of cup : each cup was made of different material. Two kinds of beer was also evaluated to examine the influence of material by a kind of beer. It was suggested the difference of material of cup affects to frothing because of the surface property and the taste of beer depends on the kind of not only material but also beer.
1 0 0 0 OA 自然と創造 : ポール・ヴァレリーの芸術観の基底
- 著者
- 黒田 愛
- 出版者
- 静岡大学人文学部
- 雑誌
- 人文論集 (ISSN:02872013)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.A203-A220, 2000-01-31
1 0 0 0 IR PISA型「落書き」問題の解答に見る大学生の読解力の傾向
- 著者
- 妹尾 知昭
- 出版者
- 筑波大学大学院人間総合科学研究科学校教育学専攻
- 雑誌
- 学校教育学研究紀要 (ISSN:18838839)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.37-56, 2010
1 0 0 0 OA スマートフォンアプリケーションの動作状況を利用したフォレンジック手法の検討
- 著者
- 諏訪部 功吉 田中 英彦
- 雑誌
- 第79回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.1, pp.535-536, 2017-03-16
多くのスマートフォンにはGPSセンサーや加速度センサー、温度センサー等の各種センサーが搭載されている。またこれらのセンサーを活用するアプリケーションも日々増えており、これらのアプリケーションは所有者の様々な情報を適宜取得して活用している。スマートフォンを持っている人が増えたことで、様々な場面でモバイル・フォレンジックを行う機会も増えているものの、パソコンやサーバに対するフォレンジックとモバイル・フォレンジックとは大きく異なる。本研究では、 スマートフォンにインストールされたアプリケーションが記録したデータに着目して行うモバイル・フォレンジックの手法を提案する。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)
- 巻号頁・発行日
- no.384, pp.59-61, 2005-09-23
羽田空港の再拡張事業で,PFI(民間資金を活用した社会資本整備)を採用した国内最大規模のプロジェクトが,事業者選定の段階に入った。なかでもエプロン部分は,土木工事主体のPFIの先例として注目を集めている。 2005年7月に国土交通省が,エプロン部分の事業者の募集要項を公表。9月に一次審査の資料提出を締め切り,二次審査を経て,2006年4月に事業者を決定する予定だ。
1 0 0 0 IR 日本農業の抱える諸問題の一考察 : 減反政策と米の生産性
- 著者
- 天尾 久夫
- 出版者
- 作新学院大学 作新学院大学女子短期大学部
- 雑誌
- 作大論集 (ISSN:21857415)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.311-334, 2015-03
[要約] 前民主党政権で交渉参加表明のあったTPP(Trans-Pacific Partnership:環太平洋戦略的経済連携協定)1)も現在最終局面を迎えている。地元メディアで注目されていないが、実は北関東地域の農業に大きな衝撃を与えると予想される。しかし、ミクロベースで見たとき、個々の農業従事者はそれほど騒ぐことも少なく、淡々と日常の農業に従事している。その格差に関心を持ったのが、本論文の執筆動機であった。 私の世代で「農業経済学」という分野は一昔前の旧いイメージが付きまとい、私もその誤った感覚から、この分野の議論・研究を控えていた感がある。TPP交渉の国内発表で、官庁の提示するTPPの参考資料を散見すれば、例えば、国内の農産物の需給推計の手法など、あまり経済学の知見は活かされていないように思う。これは、農業向けの給付や補助金を予算編成のため推計するので、逆算して数量の推計が行われたいたようにも思う。言い換えれば、数字に「政治・行政」の差配が色濃く表れている。そうした資料提出の姿こそ、現行の日本の農業政策の姿が色濃く反映しているのかもしれない2)。 さて、農業経済学の先行研究では、農業問題は経済学の議論として極めて簡明な施策を提示している。◦生産性の低い農業従事者とりわけ兼業農家をどう扱うのか◦農業の生産性をどのように向上させるのか(減反政策との整合性)◦主要産品の米の生産調整をどうするのか(減反政策) すべての農業従事者に手厚い助成を与える施策は、政・官に魅力的な利益を供与することにつながる。本稿では、今でも、農業政策の基本政策である「減反政策」が、零細農家に補助金事業を含め所得補償し、日本に永続的に小規模農家(小規模農業経営体)を存続させるという意味で有効な政策と指摘できる。本論で指摘する結論は、政策目的の経年変化を通じて、農業政策の抱える問題を明示することを目論んだものである。 さて、TPPの締結で農業問題が、急に大問題として浮かび上がったかのように錯覚を起こす者も多かろう。しかし、実際には、日本が自由貿易の利益を享受するため、国際間の貿易協定を締結する度に、日本の農業は協定に沿って変化しただけなのである。 本稿の結論だけを述べれば、減反政策は米の生産性、特に収穫減を引き起こすということにほとんど影響していないことが分かる。言い換えれば、日本国内の米の保護政策のため、食用米以外の目的の米を作れば、転作助成金が得られるため、減反すれど米の供給量は減らないだけでなく、規模の経済性による生産性上昇の妨げになっている。 本稿では、日本の農業政策の時系列の変化から3期間、1960年代から70年中盤、70年代後半~80年代、90年~2010年までに分けて、現在の農業政策で、「減反政策」が収穫量(生産)に及ぼす効果を簡単な計量経済学モデルで分析することにした。生産関数は、一般に土地という生産要素を考慮しないが、農業では「土地」は生産要素として重要な役割を担うので、作付面積を加えて生産関数を推計することにした。その効果の経済学的解釈については異論はあろうが、私は農業技術が土地の増産効果に含まれると解釈している。これについては更に研究の深化が求められる。 結論だけを述べれば、高齢化が進む日本の農業の姿がモデルにも現れている。労働・資本の投入により、農業の生産性(収穫量)はわずかだが上昇するが、その効果は近年落ち込んでいることが分かる。また、減反は生産性(収穫量)を押し下げる効果がある期間に顕著に現れている。なお、農業に係わるデーターは農林水産省の発表した数値(総務省のe-stat)から推計を行った。本稿では極力、日本全体の米生産に関する生産関数の基本的な形状を簡便に示すことに努めた。 私の従来の専門は地域金融機関の研究なのであるが、農業への資金の貸出、決済などの業務はJA(農協)の独占状態となっている。この研究の最終目的は、JAの考察にあり、このまま歴史的優位性と農業の特殊性に甘えて、独占的な立場であり続けることが、日本の農業にとっても、日本の金融にとって相応しいことなのかという疑問も心中に残っている。少なくとも、私は、JAが金融機関であるならば、国内の農業事業をどのように審査し、与信業務を行うかについて明確にすることが必要と考えている。それが農業に関わる金融の未来像を描くことになると考えているからである。最後に、あえて注意を喚起しておくが、本稿で私はJA組織を非難するといった意図は全くないことを、議論する前に述べておく。1) TPP(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership AgreementまたはTrans-Pacific Partnership)は環太平洋戦略的経済連携協定と言い、日本国は2010年10月に参加を検討すると表明した。もともと、2005年シンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4ヶ国間で始まり、調印し、2006年発効したものであった。2011年にアメリカ、オーストラリア、ベトナム、マレーシア、ペルー、カナダ、メキシコが加盟交渉国として、原加盟国との拡大交渉会合に加わった。そして、日本も2013年にTPPに参加し、現在、12ヶ国で交渉となった。この交渉は2014年内の加盟国で最終交渉、妥結を目指し、現在に至っている。これは性質上、多角的な経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)と呼ぶこともできる。2) 農林水産省[5]、[6]、[7]、[8]参照。これらの報告書は農林水産省のホームページより入手できる(2014年12月現在)。
- 著者
- 森田 儔 斉藤 明彦 影山 智津子
- 出版者
- THE KANTO-TOSAN PLANT PROTECTION SOCIETY
- 雑誌
- 関東東山病害虫研究会年報 (ISSN:03888258)
- 巻号頁・発行日
- vol.1985, no.32, pp.74-75, 1985
1 0 0 0 OA 示教利喜について
- 著者
- 宇治谷 顕
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.569-573, 1991-03-20 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 IR BOOK REVIEW : Homecomings : The Belated Return of Japan's Lost Soldiers : By Yoshikuni Igarashi
- 著者
- NISHINO Ryota
- 出版者
- International Research Center for Japanese Studies
- 雑誌
- Japan review : journal of the International Research Center for Japanese Studies (ISSN:09150986)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.211-213, 2017
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1904年03月25日, 1904-03-25
1 0 0 0 OA 冠辭考 10巻
- 著者
- 賀茂真淵 [著]
- 出版者
- 伊丹屋善兵衛 [ほか9名]
- 巻号頁・発行日
- vol.[5], 1800
- 著者
- 青木 義明
- 出版者
- 静岡大学
- 雑誌
- 法經論集 (ISSN:09132910)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.79-84,A1-A22, 1990-11
- 出版者
- 新潮社
- 雑誌
- 芸術新潮 (ISSN:04351657)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.7, pp.28-33, 1998-07
- 著者
- 村上 明子
- 出版者
- 北海道大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- 經濟學研究 (ISSN:04516265)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.329-348, 2013-02
1979年の革命以降, イランではイスラームを主体とした独自の社会統合論理が掲げられた。1990年代後半から2000年代初めにかけては自由化が模索されるも, 2005年に発足したアフマディネジャード政権下では, 現在に至るまで革命理念への回帰が謳われている。本稿では2005年以降の同国労働市場の状況について, まずは, 法制度を元に性別役割規範の基本構図を紐解きつつ, 人口圧力の高まりや経済制裁等, 労働市場を取り巻く課題とその対応策のあり方を確認した。加えて, 革命理念が労働現場に与える影響についても注目した。以上について, 現地における雇用者側へのインタビュー調査より, 1)革命後に示された労働者保護方針と労働需給の逼迫とが相まって労使双方が猜疑心を抱く状況を生み出していること, 2)革命後, 内外の変動が激しい同国では社会的紐帯が企業活動においても重視されていること, 3)イスラーム的価値観や同国におけるジェンダー認識が女性への労働需要に寄与する側面を有すること, 4)経済制裁への対応の結果, 取引チャンネルに変化が看取されること, --こうした事実が明らかとなった。今後は, 対外関係の改善と, 企業の公正な競争を担保する制度の拡充が望まれる。
1 0 0 0 OA 小学校ベースボール型授業事例の批判的検討 ─対案としてのバランスボール・ベースボール─
- 著者
- 森 勇示
- 出版者
- 愛知教育大学保健体育講座
- 雑誌
- 愛知教育大学保健体育講座研究紀要 (ISSN:13468359)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.1-6, 2017-03-23
1 0 0 0 OA 研究者が知っておくべき研究倫理と著作権制度
- 著者
- 山本 順一
- 出版者
- 桃山学院大学
- 雑誌
- 桃山学院大学経済経営論集 = ST.ANDREW'S UNIVERSITY ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW (ISSN:02869721)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.21-62, 2017-07-20
This paper deals with necessary knowledge about copyright law, and inaddition related important ethics which all researchers have to learn. Atfirst, it explains the outlines of Japanese Copyright Act of 1970, andfollowing revised acts. Researchers never fail to understand the realmeaning of legal citation doctrine. They necessarily should make sense ofthe way to lawfully and ethically reuse their own academic papers. Whenthey are working at national laboratories, or famous universities, they hadbetter know something about trademark, besides patent system. Thispaper also tells about what authorship ought to be. And other topics, forexample self-archiving, institutional repositories, creative commons license,and the usage of copyright-free illustrations are discussed. This paper isdedicated to young generation researchers including my students.