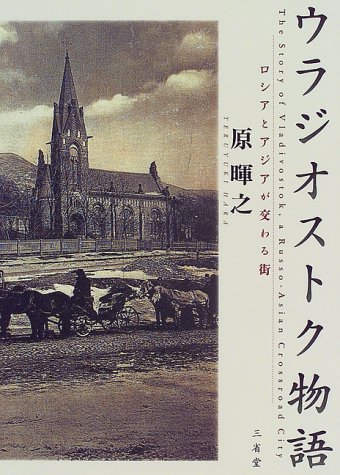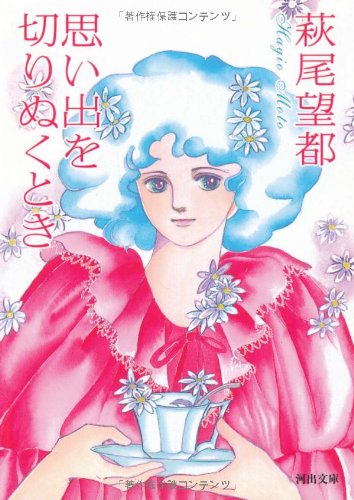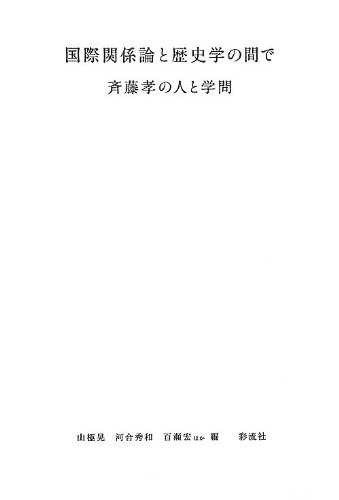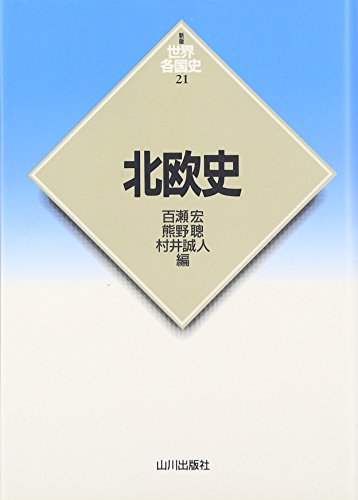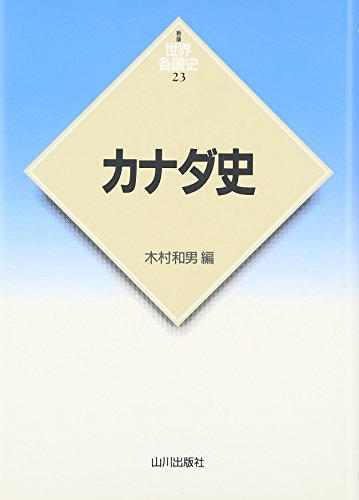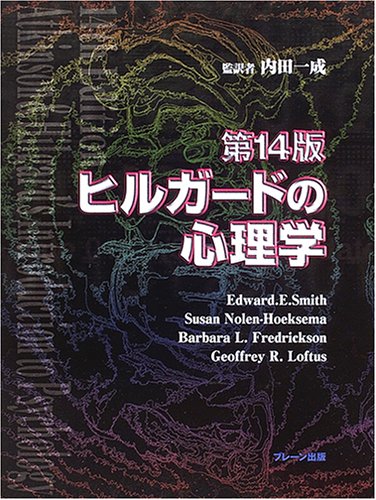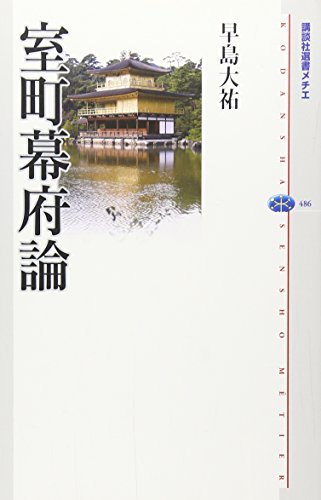1 0 0 0 ウラジオストク物語 : ロシアとアジアが交わる街
1 0 0 0 インプラント再建乳房における超音波検査の有用性の検討
- 著者
- 石神 弘子 阿部 麻由奈 織田 典子 妹尾 有夏 海老名 祐佳 赤羽 和久 坂本 英至
- 出版者
- 一般社団法人 日本超音波検査学会
- 雑誌
- 超音波検査技術抄録集 第42回日本超音波検査学会―学会プログラム・講演抄録集―
- 巻号頁・発行日
- pp.S285, 2017-06-01 (Released:2017-06-15)
1 0 0 0 思い出を切りぬくとき
1 0 0 0 日本人論 : 明治から今日まで
1 0 0 0 国際関係論と歴史学の間で : 斉藤孝の人と学問
- 著者
- 山極晃 河合秀和 百瀬宏ほか編
- 出版者
- 彩流社
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 北欧史
- 著者
- 百瀬宏 熊野聰 村井誠人編
- 出版者
- 山川出版社
- 巻号頁・発行日
- 1998
1 0 0 0 ミチューリン生物学研究
- 著者
- 日本農業生物学研究会
- 巻号頁・発行日
- 1965
- 著者
- 吉田 丈人
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.208-216, 2007-07-31 (Released:2016-09-15)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
個体群動態は、生態学者が古くからその理解に取り組んできた課題である。数理モデルを使った理論研究は質的に異なる様々な動態を予測し、実証研究はそのような動態が現実の個体群で見られることを示してきた。しかし、動態がどのように決まるかについて特定の説明が与えられ「理解」された野外個体群はほとんどない。また、動態に影響を与える新しい要因が、今なお発見され続けている。私たちは、モデル系として非常に単純な捕食者-被食者系を使い、その個体群動態を室内実験で詳細に調べることにより、野外個体群の動態を理解するのに資する知識を得ようと試みてきた。捕食者-被食者のモデル系としてワムシ(Brachionus calyciflorus)とその餌である藻類(Chlorella vulgaris)を用い、これらの生物をケモスタット(連続培養装置の一つ)で飼育して個体群動態を観測した。それと共に、個体群動態を説明する機械論的な数理モデルを得ようと取り組んできた。これまでに、ワムシと藻類の機能的反応と数量的反応・ワムシ個体群の齢構造と老化・藻類個体群の遺伝的多様性と迅速な進化が、この系の動態を説明するのに必要な要因であることを明らかにした。本論文では、ここまでの理解に至る過程を解説し、理論研究と実証研究がどのように有効に連携できるかについて一例を紹介したい。
1 0 0 0 ヒルガードの心理学
- 著者
- Edward E. Smith [ほか] 著
- 出版者
- ブレーン出版
- 巻号頁・発行日
- 2005
- 著者
- 高畑 明尚 Takahata Akihisa
- 出版者
- 琉球大学法文学部
- 雑誌
- 琉球大学経済研究 (ISSN:0557580X)
- 巻号頁・発行日
- no.56, pp.109-127, 1998-09
1 0 0 0 病気になるということ--「病気たかり」から死へ
- 著者
- 折橋 豊子
- 出版者
- 國學院大學伝承文化学会
- 雑誌
- 伝承文化研究 (ISSN:13487825)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.75-87, 2007-03
1 0 0 0 OA 4-2光学像記録のシステム化
- 著者
- 村松 克峙
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン (ISSN:18849644)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.11, pp.861-866, 1973-11-01 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 大学院に求める
- 著者
- 中野 政詩
- 出版者
- 社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.103-104,a1, 1997-02-01 (Released:2011-08-11)
大学院の重点化の社会的意義が次世代の生活様式の加速度的向上に即するためのものであり, したがって重点化された大学院での教育・研究が社会の形態や事業にそのまま直結するものを目指していると分析して, 大学院で教育を受ける者にとってのメリットの幾つかを挙げ, 大学院の側から進学希望者および進学者に期待する準備や研さんの姿勢について述べた。
- 著者
- 津田 博幸
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.11-20, 1999
六国史に歴史叙述の一環として描かれたシャーマニックな出来事と、歴史叙述の担い手たる古代の史官たちの知の世界との関わりについての考察。具体的には、前兆と結果を記述しつつ展開する歴史叙述の方法を取り上げて分析する。前兆を知り結果を予期することはシャーマニックな知に属するが、その知を史官たちの知と分断してとらえず、両者を地続きのものと考え、そこから歴史叙述が生成するダイナミズムを描くことを目指した。
- 著者
- 内田 順子
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.21-31, 1999
憑依によって発せられた不完全な神託が、次第に固定化・様式化されたものが共同体で伝承される神歌である、という文芸史観がある。そのために、神歌前史として「憑依の神託」が常に想定され、現在伝承されている神歌の諸表現は、いにしえの憑依表現の残存としてとらえられることになる。しかしわれわれが前提とできるのは、演唱されることによってのみ現存する神歌だけである。憑依はそれに先駆けては現存しない。われわれはここから出発し、神歌と憑依との関係を根底から探求しなおすことを試みる。
1 0 0 0 メタモルフォーシスの人類学
- 著者
- 石井 美保
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.147-147, 2008
本分科会では、憑依・夢・癒し・出産・老いを事例として、身体の規範化と偶発性の間を揺らぐ〈身体-自己〉のあり方を多面的に検討する。身体変容の経験を形成する言語行為や、日常と非日常の臨界における間身体的な共同性の生成とその破綻に着眼することを通して、日常的な秩序のコードから外れつつも、他との関係性の中で独自の健全さを模索する〈身体-自己〉の可能性を提示したい。
- 著者
- 山内 大典 渡辺 孝夫 奥寺 俊允 川口 和子 高橋 常男
- 雑誌
- 日本口腔インプラント学会誌 = Journal of Japanese Society of Oral Implantology (ISSN:09146695)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.460-469, 2010-09-30
- 参考文献数
- 29
1 0 0 0 OA 小児の発達障害の評価と支援に視能訓練士と言語聴覚士の連携が必要であった症例
- 著者
- 星原 徳子 岡 真由美 山本 真代 金永 圭祐 森 壽子 長島 瞳 河原 正明 藤本 政明
- 出版者
- 公益社団法人 日本視能訓練士協会
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.59-65, 2013 (Released:2014-03-13)
- 参考文献数
- 29
【目的】発達障害の早期発見は、社会生活での自立の促進において重要である。視能訓練士(以下CO)は小児の視覚だけでなく他機能との関わりにも注目し、成長発達の支援に関わる必要がある。今回、COと他院耳鼻科言語聴覚士(以下ST)が連携し、発達障害の評価と支援が可能であった症例を報告する。【対象・方法】2004年6月~2012年6月にK眼科で弱視または斜視と診断された18歳未満の症例412例中、発達障害を疑いSTが所属する専門医療機関への受診を促した12例であった。症例は未就学児8例(2歳5か月~5歳8か月)、就学児4例(6歳6か月~14歳3か月)であった。発達評価には遠城寺式・乳幼児分析的発達検査表、同旧版(以下遠城寺式発達検査表)を使用した。【結果】生活年齢に相応した視機能検査ができなかったのは5例であった。発達障害を疑った視機能検査時の特徴は、発音不明瞭6例、多動4例、クレーン現象1例、コミュニケーション不良2例であった。12例全例の親が現状を否定する言動をし、ペアレントトレーニングを要した。STによる積極的訓練を開始できたのは7例、STによる6か月毎の経過観察を要しているものが2例だった。ST受診を拒否または一度受診したが訓練拒否したものが3例であった。【結論】遠城寺式発達検査表の項目を考慮して視機能検査を施行することは、小児の発達状態の評価に有用であった。COがSTと連携することで発達障害児の早期発見と就学前後での支援につながった。