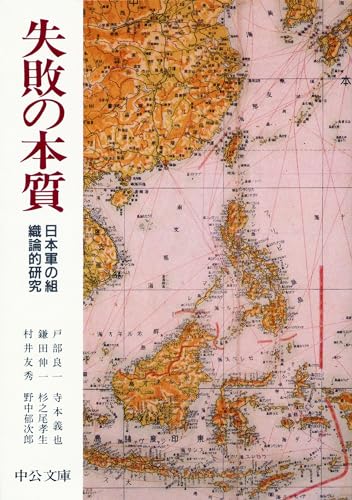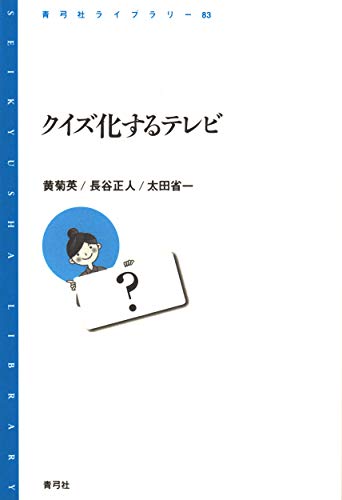- 著者
- 赤堀 薫子
- 出版者
- 名古屋大学学生相談総合センター
- 雑誌
- 名古屋大学学生相談総合センター紀要
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.32-36, 2001
- 著者
- 中野 俊光
- 出版者
- 筑波大学倫理学原論研究会
- 雑誌
- 倫理学 (ISSN:02890666)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.29-45, 2009-03-20
- 著者
- 井上 昌彦
- 出版者
- 日本図書館協会
- 雑誌
- 現代の図書館 = Libraries today (ISSN:00166332)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.28-33, 2017-03
1 0 0 0 IR 藤原光頼(桂大納言入道)出家後の動向 ―藤原惟方『大納言入道灌頂記』の紹介―
- 著者
- 藤原 重雄 Shigeo Fujiwara
- 雑誌
- 日本古写経研究所研究紀要 = Journal of the Research Institute for Old Japanese Manuscripts of Buddhist Scriptures (ISSN:21897662)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.35-46, 2016-03-01
- 著者
- 渡 浩一
- 出版者
- 明治大学国際日本学部
- 雑誌
- 明治大学国際日本学研究 (ISSN:18834906)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.59-74, 2013
1 0 0 0 OA 小林清親の「光線画」をめぐって : その表現の成立と展開の一試論
- 著者
- 田淵 房枝 Fusae Tabuchi
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.64/65, no.4/1, pp.59-77, 2015-05-20
1 0 0 0 IR 「イソップ寓話」翻訳・翻案の特異性 : "蟻と蟬の事"の事例検証から
- 著者
- 谷出 千代子
- 出版者
- 仁愛大学
- 雑誌
- 仁愛大学研究紀要. 人間生活学部篇 (ISSN:21853363)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.78-86, 2013-03-31
イソップ寓話「蟻と蟬の事」,または「蟻と螽蟖の事」など底本とする原話によって表記やプロットの展開が異なるこれらの話は,日本に最も早く入ってきた外国の物語である. そこで,天草本,古活字本,影印本などと称される底本としてのイソップ寓話の特色がどのように時代と共に流布し人々に扱われてきたか,さらには読者層の相違によって翻訳者はいかに翻刻を重ねたか,翻訳のもつ役割を吟味してきたかなど,文章表現と絵画描写(挿絵)を通して,入手,管見の可能となった明治期,大正期発刊本に限って分析検証してきた. 結果として,翻刻や翻訳にこだわりを持ち,用語使用に対しても厳しい態度で臨んでいると思われる物語に向き合うことができた.文化的には日本という国柄の精神性を重視し,大和魂に固守する余り,今日的時代性から判断すると,諧謔的な想像性と創造性に拘りと時代性を受容できた検証であった.
1 0 0 0 OA デンマークでの研究生活
- 著者
- 龍崎 奏
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.8, pp.473-474, 2012-08-10 (Released:2012-08-23)
- 著者
- 江口 真規
- 出版者
- 筑波大学比較・理論文学会
- 雑誌
- 文学研究論集 (ISSN:09158944)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.25-40, 2015-02-26
1 0 0 0 失敗の本質 : 日本軍の組織論的研究
- 著者
- 戸部良一 [ほか] 著
- 出版者
- 中央公論社
- 巻号頁・発行日
- 1991
1 0 0 0 クイズ化するテレビ
- 著者
- 黄菊英 長谷正人 太田省一著
- 出版者
- 青弓社
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 OA あんぽんたんの記 (六)
- 著者
- 藥酒狂
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.9, pp.341-342, 1953-09-15 (Released:2011-11-04)
1 0 0 0 OA ドーナツにおける亀裂とその材料配合及び品質評価との関係
- 著者
- 長尾 慶子 横川 知子 畑江 敬子 島田 淳子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.25-30, 1994-02-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 4
Crack is often observed during deep-frying at the inside, outside and/or upside of hard doughnuts and sometimes impairs the appearance. Experiments were carried out to know the effect of the proportion of ingredients and the preparation condition on the appearance of the doughnuts.Multiple regression analysis showed that the increasing rate of the weight and volume of fried doughnuts were affected by sugar and butter content. The recipe without butter resulted in the doughnuts without outside crack. The more the sugar content was, the smaller the outside crack was. When the sugar and butter content was high, the upside crack was large. To leave the dough sample at 4°C before frying made the volume and the weight of the doughnut large and the upside crack small.Panel members judged the doughnuts to be most preferable when the small crack at the upside was observed. We divided the sample doughnuts into two groups in terms of the ratings of the overall appearance, namely, preferable group and not preferable group. Then we ran a discriminant analysis. The recipes of the preferable group contained more sugar and egg and less butter than those of the other group.
1 0 0 0 OA 走査電子顕微鏡法(4)
- 著者
- 木村 利昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.86-93, 2000-02-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 設立中の株式会社の活動範囲
- 著者
- 北沢 正啓
- 出版者
- 日本私法学会
- 雑誌
- 私法 (ISSN:03873315)
- 巻号頁・発行日
- vol.1955, no.14, pp.61-82, 1955-10-30 (Released:2012-02-07)
- 著者
- 臼井 幸弘 高橋 寛幸 吉開 範章
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SITE, 技術と社会・倫理 : IEICE technical report (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.505, pp.19-24, 2002-12-06
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 11
ネットワーク上でのコミュニティ活動を活性化する上で、信頼形成のための評判システムが重要であることを示す。そして、ネットコミュニティの中でも信頼形成が重要となるネットオークションについて、評判システムを組み込んだ実験結果を示す。まず、ネットコミュニティの形成・運用のための要件を挙げ、それに必要となる、コミュニティが持つべき機能をまとめ、信頼形成が重要であることを示す。そして、ネットオークションに、信頼形成の手段として評判システムを取り入れた実験で、評判システムがある場合とない場合での比較を行い、取引商品価値の変動等から、評判システムが市場の活性化に効果を持つことを示す。
- 著者
- ボガート アン 目黒 条
- 出版者
- 舞台芸術財団演劇人会議
- 雑誌
- 演劇人
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.82-89, 2003
1 0 0 0 IR 反復で読み解くグリム童話入門(第2章)西洋人は首狩り族
- 著者
- 高橋 吉文
- 出版者
- 北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 = Research Faculty of Media and Communication, Hokkaido University
- 雑誌
- メディア・コミュニケーション研究 (ISSN:18825303)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.1-53, 2009
グリム童話は、ある特定の記号(コード)の反復から組み立てられていることが基本であるが、そこにおいてとりわけ際だつもののひとつが、〈切断〉コードの反復である(第1章)。しかし、記号という一見人工的にみえるものの基底には、古代や太古の昔に遡りうる民俗的・神話的な思惟がとぐろを巻いている。その〈切断〉コードとも深く関わる人頭・生首信仰もその一例である。本論第2章では、人頭崇拝の普遍的広がりの確認を導入として、西洋文化の二大源流地中海とケルト等に顕著な人頭崇拝例と、西洋世界におけるその強靱な呪縛系譜(西洋人=首狩り族)を示す。その後、口承世界における生首嗜好の世界的広がりをまずは示した上で、頭部に呪力を感じる神話的思考の存在、及び口承物語におけるその展開を継承した民衆昔話のひとつ『子どもと家庭のための昔話集(グリム童話集)』(KHM)において、〈斬首〉コードがどのように反復され、メルヘンを構成しているかを確認する。KHM47「ねずの木」では〈斬首〉コードの反復とシンメトリー構成を簡潔に示し、斬首され門壁に釘で打ち付けられた馬頭が王女と言葉をかわすKHM89「鵞鳥番のむすめ」では、その〈斬首〉コード反復が、古代ゲルマン人の馬頭信仰という歴史的事実や神話的思惟にいかに強く裏打ちされていたかを明らかにする。Die Grimmschen Märchen sind aufgrund der Wiederholungen halbsemiotisch zu analysieren. Im 1. Kapitel dieser Einführungsserie habe ich die symmetrische und halbsemiotische Erzählstruktur der Grimmschen Märchen, welche die Brüder Grimm in der tieferen Erzählschicht bewusst und insgeheim gestalteten, an dem KHM21 "Aschenputtel" auf die werkimmanente Weise klargemacht, indem ich mich an der Wiederholung eines "Fuß-Abschneidung"-Kodes orientierte. Im vorliegenden 2. Kapitel handelt es sich als Verstärkung der Analyse anhand vom "Abschneidung"-Kode um eine skizzierende Auflistung und Zitate aus den volkskundlichen Materialien, die den Kult des Kopfes und des Köpfens seit Alteuropa bezeugen, und ferner um die Feststellung der Europäer als Kopfjäger, an deren verborgenen Tradition sie immer noch unbewußt, aber stark festhalten. Solch eine Neigung findet sich auch in europäischen Überlieferungen wie Volksmärchen. Die Grimmschen Märchen machen dort keine Ausnahme. Bei KHM47 "Van den Machandelboom" lässt sich der "Haupt-Abhauen"-Kode, in verschiedenen Brechungen transformiert, vielmals und symmetrisch wiederfinden. Dasselbe trifft für KHM89 "Die Gänsemagd" zu, wobei man nicht nur den den Lesern sichtbaren Wiederholungen des abgehauenen Pferdekopfes, sondern auch den uns scheinbar unsichtbaren eines rollenden Huts (=Kopfes) wie der kriechenden Haltung (beim Köpfen)der Königstochter begegnet, die sich zunächst am Wasser zweimal, dann am Ende im Eisenofen bäuchlings legt. Hier im 2. Kapitel werden auch Belege in Bezug auf germanische Kulte und Sitten des abgehauenen Pferdekopfes zitiert. Die Auflistung, die die Notwendigkeit des "Kopf・Haupt-Abhauen"-Kodes historisch begründet,soll die halbsemiotische Analyse des Grimmschen Märchens KHM89 "Die Gänsemagd", die ich im 3. Kapitel auszuführen vorhabe, vorbereiten und für die Gültigkeit der Methode garantieren.
- 著者
- 千田 芳樹
- 出版者
- 東北哲学会
- 雑誌
- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.15-30, 2012