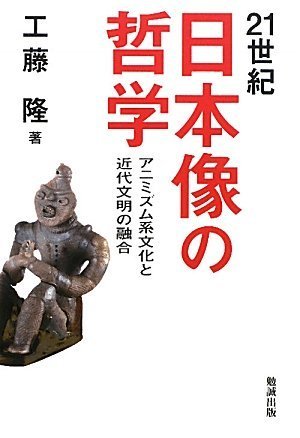1 0 0 0 OA 機械構造用非調質鋼の降伏強さ向上に関する研究
1 0 0 0 相関行列共通型CDMA基地局用アダブティプアレーアンテナ
- 著者
- 原 嘉孝
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. B, 通信 (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.7, pp.1329-1343, 2001-07-01
- 被引用文献数
- 22 4
高効率な信号処理に基づくCDMA(Code Division Multiple Access)基地局用アダプティブアレーアンテナを提案する。本方式では, SMI(Sample Matrix Inversion)アルゴリズムに基づきウエート制御を行うが, 逆拡散前の信号に対して相関行列演算を行うことにより, ユーザ間で相関行列の共通化を実現している。このような構成により基地局でのウエート演算量を低減できる。また, チップごとに相関行列演算を行えるため, 従来型SMI方式以上の高速ウエート制御も可能となる。性能評価の結果, 提案方式は演算量とBER(Bit Error Rate)特性の両面で従来方式よりもよい性能が得られることが明らかとなった。また, 提案方式では相関行列をチップ非同期のユーザ間で共有するが, チップ非同期による性能劣化はほとんど生じないことを確認した。
1 0 0 0 「ボランティアを通して学ぶ」ことをどうみるか
- 著者
- 広田 照幸
- 出版者
- 日本福祉教育・ボランティア学習学会
- 雑誌
- 日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.27-36, 2013-06-20
1 0 0 0 戰時住職手帖
- 著者
- 眞宗大谷派教化研究院編
- 出版者
- 眞宗大谷派戰時對處事務所實踐局
- 巻号頁・発行日
- 1942
- 著者
- 山田 理恵 渡辺 融
- 出版者
- 社団法人日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- no.59, 2008-09-09
1 0 0 0 IR 新入生歓迎特集 「滋賀大生のそこが知りたい! : 滋賀大フリートーク」
- 著者
- 滋賀大学
- 出版者
- 滋賀大学広報委員会
- 雑誌
- しがだい : 滋賀大学広報誌
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.10-11, 2002-04
1 0 0 0 21世紀日本像の哲学 : アニミズム系文化と近代文明の融合
- 著者
- 杉田 利男 高橋 宜博 吉田 巖
- 出版者
- The Crystallographic Society of Japan
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.107-110, 1993
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 農業用トラクタヒッチ点位置制御による牽引車両の追従性向上の検討
目的:一般に、トラクタで牽引車両を牽引する場合は、旋回時にトラクタ走行軌跡と牽引車両の走行軌跡に内輪差が生じることが避けられない。この内輪差が作業に影響を与え、時には事故の発生にもつながり安全性の面からも改善が求められている。本研究では、トラクタ前輪の操舵角度に合わせて、ヒッチ点位置を横方向に移動制御する方式によって内輪差の減少させることすなわち牽引車両の追従性の向上を図ることにより、トラクタの牽引作業の作業性、安全性の向上を目的としている。これまで試作機を製作し追従性向上のための実験を行ってきたが、更なる追従性の向上のため作動部分およびプログラムを改良して実験を行った。研究方法:農林技術センター所有のトラクタで牽引車両を牽引して、トラクタ後輪車軸中心部および牽引車両車軸中心部から水滴をたらしながら走行し、水滴跡をそれぞれの走行軌跡とし、軌跡差を計測した。試作機ぞを作動させずヒッチ点を中心に固定した状態(以後、非作動時)とヒッチ点を移動させた場合(以後、作動時)の軌跡差を比較した。研究成果:トラクタ前輪操舵角度を一定に保ち旋回のみを行った結果、操舵角度30度での軌跡差は非作動時の最大64cmに対し、作動時は最大5cmと大幅に減少した。次に、実作業時にも頻繁に行われるU字ターン行った。U字ターンでは、これまでの実験からトラクタの速度に応じて作動の時間を遅延させることにより軌跡差が減少することが解っているため時差をつけた作動試験を行った。また、本試作機では、最大ヒッチ移動量が60cmであるが操舵角度30度で最大移動量を超えるため、操舵角度25度と最大移動量を超えた操舵角度33度の軌跡差を測定した。その結果、非作動時では、ターン頂点とターン終了の中間付近の軌跡差が最も大きく70cmほどであった。操舵角度25度作動時では、最大軌跡差がターン開始付近の6cm。操舵角度33度作動時では、最大軌跡差がターン終了付近の11cmとなった。8の字にターンを行った場合もほぼ同様の結果となり、それぞれの操舵角度で最大軌跡差が2cm大きくなった程度であった。以上の結果から、本方式により追従性が確実に向上することが確認できた。これにより、作業性・安全性の向上が図られるものと考える。
1 0 0 0 神経ブロックのためのクロワッサン型傾斜枕
1 0 0 0 ヴォルテール-6-
- 著者
- 福鎌 忠恕
- 出版者
- 政治公論社
- 雑誌
- 政治公論 (ISSN:04881052)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.66-99, 1955-04
1 0 0 0 OA これまでの常識を上回る精度を実現する画像からの幾何学量推定方法の研究
1 0 0 0 光磁気ヘッドの非点隔差補正
- 著者
- 松井 勉 藤村 雄己
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会秋季大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.2, 1994-09-26
光ディスクレコーダは、高密度化と高速転送レート化の2つの方向で高性能化を目指して開発が行われている。高密度記録再生特性を左右するのは光ヘッドであり、集束ビームを絞りこみ、光学変調度を大きくとることが大きな課題である。レーザ波長=0.68μm、対物レンズ開口数=0.55のとき、レーザ波長の1/2以下のピット長の高密度記録を達成するには、C/N比(CNR)が最良になるようにフォーカスオフセットを調整する必要がある。このとき、トラッキング誤差信号(TE)が劣化し、トラッキングサーボが不安定になることがあった。これは集束ビームの非点隔差に起因し、対策として、光磁気ヘッドの非点隔差を補正する光学系を実現したので報告する。
1 0 0 0 アジリジン誘導体を合成素子とする連続的開環-環化反応の開発
昨年度に引き続き,各種グアニジン誘導体より,窒素上にアリル置換基を有するアジリジンを合成し,熱的,および光条件による環化付加反応を検討した.しかしながら,いずれの場合も目的の環化体を得ることができなかった.一方,四酸化オスミウムを用いるジヒドロキシル化については,アリル置換基上でのみ酸化が進行した所望のジヒドロキシル体を与えた.今後,ここで生じたジオール部位に対して更なる変換を行い,C3単位ををアジリジンに組み込んだヘテロ環合成へと変換する予定である.また,アジリジン環に対する反応性を調査する上で,有機銅試薬による開環反応,有機ホウ素試薬によるシグマトロピー型反応などの検討を行ったが,所望の環化付加体を得ることはできなかった.その検討の過程において,塩化インジウムを用いた場合にtransアジリジンからcisアジリジンへの異性化反応が効率よく進行することを見出した.この異性化はこれまでに例がなく,特にcisアジリジンを部分骨格に有するマイトマイシンCなどの天然物合成への展開が期待される有用な反応であり,これらの事項についてHeterocycles誌に投稿した.一方,アジリジンを一旦フェニルゼレン試薬で開環してβ-ゼレノアミンとした後,アリルスズ試薬を用いたラジカル型炭素-炭素結合反応によりアリル基の導入に成功した.今後このアリル基を足がかりとした環化反応に展開していく予定である.
- 著者
- 徳山 道夫 川崎 恭治
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:05272997)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.58-62, 1984-11-20
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
1 0 0 0 βカテニンとPAR-3複合体の接着非依存的相互作用の解析
平成20年度にはカドヘリン分子と相互作用せずにPAR-3複合体とのみ相互作用する特殊なβカテニン・カドヘリン融合タンパク質の作製に成功した。本年度はこの融合タンパク質の性質とこの分子がPAR-3複合体とカドヘリン・カテニン複合体の相互作用を阻害するドミナントネガティブ因子として機能できるかどうか、解析を進めた。先ずこの融合タンパク質はカドヘリン非存在下でも内在性のαカテニンの発現増強を行うことを明らかにした。野生型のβカテニンではこの発現増強は見られず、融合タンパク質内のカドヘリン細胞質領域、特のそのC末端領域がαカテニンの発現状況であることも明らかにした。次ぎにこの融合蛋白質を通常の培養細胞に発現させたところ、目立った異常は見られなかった。しかし、上皮分化誘導をかけると上皮細胞接着装置複合体形成に微妙に影響を与える可能性が示唆された。より高い発現状態で上皮組織構築における影響を調べるために、ニワトリ初期胚においてこの分子の過剰発現を試みた。その結果、神経管上皮組織構築に異常が見られた。現在これが融合タンパク質によるドミナントネガティブ効果であるかどうか、詳細な検討を進めている。miRNA依存的な遺伝子発現抑制をカドヘリン、PAR-3などについて試みた。しかし用いたF9細胞では有効な発現抑制効果が見られなかった。miRNAの発現量が低い可能性が考えられるが、発現量を上げる手だてがなく、この計画は中断している。
1 0 0 0 機械の分解組み立てを通してのものづくり基礎教育に関する研究
- 著者
- 上野 孝行
- 出版者
- 鹿児島工業高等専門学校
- 雑誌
- 奨励研究
- 巻号頁・発行日
- 2011
研究目的多くの高専において"ものづくり"が教育目標として掲げられており,もの作りの教育方法について講義や実習などで多角的に検討されている.本校においても,学生のモチベーションをいかに向上させ,維持させるかということが問題視されている.近年,学生の成長過程での周辺環境がIT技術の発展により劇的に変化している.このような背景から,日常生活環境から機械装置が電子装置に置き換わりメカニカルな装置が身の回りにないため,分解してメカニズムを知る楽しみを知らない学生が増えてきている.機械工学科の学生にいたっても,そのようなことに興味を持たない学生も少なからず存在する.このことは創造力の養成に対する動機にも影響している.そこで4輪バギーの操舵部分を対象とした分解組み立ての実習を取り入れる.実用車であるため機械工学科の学生の興味を惹く題材を用いることで,その教育効果を検討する.研究方法(1)現有の4輪バギーを分解し,構造について特にサスペンションのアライメントの理論を学習するための方案を洗練するとともに,他の教科との関連や実習の効果を検討する.(2)また,学生への動機付けの成否を,アンケートや実習を通した学生からの聞き取りで行う.(3)効率よく実習を行うために,実習用のバギーを1台追加する(購入申請).(4)毎実習終了後にアンケートを取り,実習の内容の改善点についてフィードバックを行いながら更に適したテキスト,サブノート,教材の開発を行う.(5)その教育効果をさらに高めるために,補助教材の製作を行う.(6)以上に加えて学生の意識調査を聞き取り方式で行い,実習方案の完成度を高めていく.研究成果(1)4輪バギー保有台数が増えたことにより少人数教育を行うことができた.(2)(1)の結果,実習時間にゆとりが生まれ,新たな分野について授業で取り上げることができた.(3)学生からの聞き取り調査により、すべてにおいて教育効果が高まったことが確認できた.
1 0 0 0 摂食試験によって判明した天蚕(ヤママユ)の食性と適性飼料樹
- 著者
- 寺本 憲之
- 出版者
- 滋賀県農業総合センター農業試験場
- 雑誌
- 滋賀県農業総合センター農業試験場研究報告 (ISSN:13470035)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.32-52, 2001-03
- 被引用文献数
- 1
天蚕の野外における食樹調査と室内における摂食試験による飼料適性調査を滋賀県において実施した. 野外調査によって,ブナ科に属するナラガシワとバラ科に属するカマツカの2種を天蚕食樹として新しく記録した.また,室内調査によって,ブナ科に属するイチイガシ,イタグリ,シイグリおよびブナ,カバノキ科のイヌシデ,クマシデ,アカシデ,サワシバ,ヤシャブシおよびシラカンバ,ヤマモモ科のヤマモモ,ニレ科のムクノキ,バラ科のヒメリンゴおよびアンズ,そしてマンサク科のアメリカフウおよびフウ,合計16種を新室内飼育記録として追加した.今回の新記録を追加して天蚕の食樹記録の整理検討を行ったところ,野外食樹記録が13種,室内飼育記録が19種,併せて,天蚕幼虫が摂食してほぼ正常に成育できる樹種は32種と判断された.摂食試験の結果から,天蚕の最適性飼料樹としてクヌギ,アベマキ,アラカシ,ブナ(ブナ科)およびアメリカフウ(マンサク科)の5種を選定した. 以上の結果と既知食樹記録を総括して天蚕の食性に関する再検討を行ったところ,天蚕はブナ科に属する植物を中心に食するが,植物分類学上から考察すると,ブナ目群(ブナ目ブナ科・カバノキ科,ヤナギ目ヤナギ科,イラクサ目クワ科・ニレ科)およびバラ目群(バラ目バラ科,マンサク目マンサク科,ムクロジ目カエデ科)の2植物目群,すなわち植物分類学上で類縁関係が高い,まとまった植物群に属する植物の葉を食することが明らかになった.また,天蚕の食性には個体あるいは系統変異があり,個体選抜による育成によって,本種の食性は上記の植物科に属する植物の範囲内で拡張できる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 生殖器官形成における糖鎖修飾の意義
高等生物は管腔様構造の臓器ネットワークを有しており、形成過程での破綻はヒトにおいてもよく見られるが、その原因は遺伝的要因と環境的要因とが交差しており不明な点が多い。申請者はCelsr1欠損マウスが生殖器系管腔様構造の形成不全を呈し、この表現型が糖転移酵素Fringeの欠損マウスの表現型と酷似することを発見した。Celsr1蛋白質は2箇所のEGF-like motifにおいてO-フコシル化かつFringe修飾され、細胞内分布が制御された。以上の結果から「翻訳後の糖鎖修飾がCelsr1蛋白質の局在を制御する」ことが明らかとなり、管腔様構造の形成に特異的な、糖鎖修飾による制御機構が明らかとなった。
1 0 0 0 ソ連における歴史認識と政治
- 著者
- 立石 洋子
- 出版者
- 北海道大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2012-08-31
フルシチョフ期のソ連における自国史像の変遷を分析課題とした。なかでも歴史家の関心を集めた1)北カフカース史の描写をめぐる議論と、2)歴史家の論争の中心となった学術誌『歴史の諸問題』誌の活動を中心に検討を進めた。1)に関する研究成果まず、同時期の政治改革の過程では共産党史だけでなく自国史の解釈も大きな論争点となったこと、特に北カフカースを中心とする非ロシア人地域の歴史とロシア史との関係が歴史家の議論を集めたことを明らかにした。そのうえで、19世紀の北カフカースで起こった対ロシア蜂起であるシャミーリの反乱について、1953年のアゼルバイジャン共産党第一書記バギーロフの逮捕が歴史家の論争の始まりの契機となったこと、また1957年のチェチェン・イングーシ自治共和国の再建が、この史実に対する公式見解の方向性を決定づける重要な要因となったことを明らかにした。2)に関する研究成果『歴史の諸問題』誌の活動を、1953年に編集長となった歴史家パンクラ―トヴァの活動を中心に分析した。まず、1953年の編集部の改組が科学アカデミーの決定に基づくものであったことを指摘し、そのうえで同誌編集部が、読者会議の開催や討論用論文の掲載を通じて歴史家と社会の論争を促していった過程を分析した。これに加えて、共産党中央委員であり、最高会議代議員でもあったパンクラートヴァのもとには、スターリン時代に政治的抑圧を受けた多数の知識人の名誉回復と釈放を求める市民からの訴えが多数寄せられていたことを明らかにした。さらに、社会に対して公的歴史像の変遷を説明する役割を担った彼女が、スターリン期の歴史学の役割に対する社会からの批判と、政治指導部に対する市民の批判の高まりを警戒した党指導部による統制の狭間で苦悩するさまを跡付け、従来の研究が着目してこなかったソヴィエト体制下の知識人の一側面を指摘した。