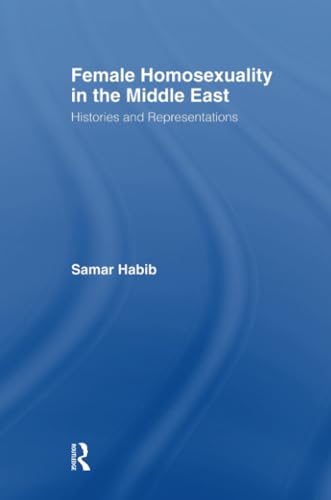5 0 0 0 源順と和歌 : 源順集を手がかりとして
- 著者
- 原田 真理
- 出版者
- 福岡女子大学
- 雑誌
- 香椎潟 (ISSN:02874113)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.37-51, 1987-09-25
5 0 0 0 タヌキのタメフンについて(生態学・行動学)
- 著者
- 山本 伊津子 日高 敏隆
- 出版者
- 社団法人日本動物学会
- 雑誌
- 動物学雑誌 (ISSN:00445118)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.4, 1981-12-25
- 著者
- 相澤 真一 小山 裕 鄭 佳月
- 出版者
- ソシオロゴス編集委員会
- 雑誌
- ソシオロゴス (ISSN:02853531)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.65-89, 2013
5 0 0 0 OA 「場」の概念からみた図書館における来館を促す建築的魅力に関する研究
1市6町が合併した東近江市の7図書館での調査から、各館が施設サービスに特徴を持っているため、各館のサービスをきちんと理解して6割近い利用者が複数の館を使い分けて利用するなど、従来までの近い・多いだけではない各館のサービスを熟知した「相対的な使い分け利用」が具体的に確認できた。ラーニングコモンズなどの設置が増えてきた大学図書館では、着座行為率(着座人数/滞在者数)が90%を超えるなど着座に対する要望が高く、座席選択は公共図書館では窓からの眺望などが理由として挙げられるが、大学図書館では集中して作業できることが優先されるなど利用意識はかなり異なることが分かった。
5 0 0 0 OA 記号的統計モデリングの世界を探る
- 著者
- 佐藤 泰介
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.3_33-3_36, 2008-07-25 (Released:2008-09-30)
5 0 0 0 目標フレーミングが感情情報の自動的な処理に与える影響
- 著者
- 竹橋 洋毅 唐沢 かおり
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.50-57, 2008
Guided by the regulatory focus theory (Higgins, 1997), this study examined the effects of goal framing on the subjective feeling of affect and the automatic processing of affective information. After the manipulation of goal framing (promotion focus vs. prevention focus), 32 participants were asked to indicate their affective state and to engage in a modified Stroop task. Results indicated that goal framing did not influence subjective feeling but influenced the speed of color naming in the Stroop task; participants in the prevention condition responded more slowly toward loss-related words (quiescence and agitation) than gain-related words (cheerfulness and dejection), whereas participants in the promotion condition responded toward gain-related words as slowly as toward loss-related words. These results suggest that goal framing heightens the activation of particular affective representations and the activations influence performance on a Stroop task automatically. The effects of automatic processing of affective information on subjective feeling and the process of self-regulation are discussed.
- 著者
- 高橋 尚也
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.97-108, 2010
In Japan, activities to prevent crime by citizens have been encouraged, but are not developing well. Two studies were carried out to examine factors regulating citizen participation in activities to prevent crime in Edogawa ward. In a survey interview of 15 leaders of activity to prevent crime (Study 1), it was suggested that attachment to city, attitude towards activities to prevent crime, indirect support from administration, and mutually beneficial relations with administration led to development of these activities. In a survey of 141 randomly sampled adults (Study 2), people who participated in activities to prevent crime accounted for 14.2% of the total. Among men, participation was determined by the number of organizational affiliations in the community. Intention to participate was promoted by advanced age and high levels of political interest. In women, participation was determined by youth, number of schoolchildren in the family, and communication with neighbors. Intention to participate was restrained by low levels of political interest and absence of high-school children in the family. Implications for activities to prevent crime were discussed from the viewpoint of gender and benefit from activity.
5 0 0 0 OA 〈論説〉 立憲主義の源流 : 合理主義的啓蒙思想か、スコットランド啓蒙思想か
- 著者
- 阪本 昌成
- 出版者
- 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻
- 雑誌
- 筑波ロー・ジャーナル (ISSN:18818730)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.65-100, 2011-03
- 著者
- 大杉 昭英
- 巻号頁・発行日
- 2015-03
目次第Ⅰ部 中央政府決定型 第1章 ドイツ …………………………………………………………………………………… 13 1.教育行財政の仕組み,教職員の任用,職務のあらまし 2.教職員数の算定方式 3.若干の考察 4.ドイツの事例が示唆するもの 第2章 フランス ………………………………………………………………………………… 21 1.国の予算における教職員数 2.中等教育 3.初等教育 4.フランスの事例が示唆するもの 第3章 オーストラリア ………………………………………………………………………… 35 1.教育行財政の仕組み,教職員の任用,職務のあらまし 2.教職員数の算定方式と学級規模の決定方式 3.各効果測定の指標,推進の根拠 4.教員数の算定方式のメリット・デメリット 第4章 シンガポール …………………………………………………………………………… 45 1.教育行財政の仕組み,教職員の任用,職務のあらまし 2.教職員数(国全体の教職員数の総和)の算定方式と学級規模の決定方式 3.それぞれの効果の指標,推進の根拠(理念など) 4.国からの資源配分(教員・予算)の在り方と考え方 5.教員数の算定の際に考慮されるファクター 6.教員数の算定に関する政策形成の際に重視される指標 7.教員数の算定方式のメリットとデメリットの考察及びシンガポールの事例が示唆するもの第Ⅱ部 地方政府(学校)決定型 第5章 アメリカ ………………………………………………………………………………… 55 1.教育行財政制度の仕組み 2.教職員の任用と教職員数の算定方式 3.学級規模の決定方式 4.アメリカの事例が示唆するもの 第6章 イギリス ………………………………………………………………………………… 71 1.教育行財政制度の仕組み 2.教職員の任用及び職務 3.教職員数の算定方式と学級規模の決定方式 4.教職員数及び学級規模の効果検証の指標 5.教職員定数及び学級規模に関する議論 6.イギリスの事例が示唆するもの 第7章 フィンランド …………………………………………………………………………… 79 1.教育行財政の概要と教職員の任用・職務 2.教職員数の算定方式と学級規模の決定方式 3.フィンランドの事例が示唆するもの 第8章 カナダ ………………………………………………………………………… 87 1.オンタリオ州とその教育行政のシステムと教員配置 2.オンタリオ州の少人数学級政策の実施 3.カナダの事例が示唆するもの 第9章 中国 …………………………………………………………………………… 101 1.国からの資源配分(教員・予算)の在り方と考え方 2.教員数の算定の際に考慮されるファクター 3.教員数の算定に関する政策形成の際に重視される指標 4.教員数の算定方式のメリットとデメリットの考察及び中国の事例が示唆するもの第Ⅲ部 中央政府算定・地方政府決定型 第 10 章 日本 ………………………………………………………………………… 115 1.国からの資源配分(教員・予算)の在り方と考え方 2.教員数の算定の際に考慮されるファクター 3.教員数の算定に関する政策形成の際に重視される指標 4.教員数の算定方式における特徴 第11 章 韓国 ………………………………………………………………………… 127 1.教育資源の配分の原則 2.教職員数の推移と現況 3.学級規模の決定の仕組み 4.教職員定数の算出 5.教職員配置政策の背景要因 6.韓国の事例が示唆するもの巻末資料
5 0 0 0 メタスタージオのオペラセリアにおけるアリアの劇的効果
- 著者
- 上西 明子
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.37-59, 1997
<p>Noi ricordiamo Pietro Metastasio (1698-1782) come il librettista che porto a compimento la riforma dei libretti delle opere iniziata da Apostolo Zeno (1668-1750). Per quasi tutto il secolo diciottesimo itesti di Metastasio vennero musicati e rappresentati, a differenza dei giorni nostri, molto spesso in tutta l'Europa. Egli restitui dignita letteraria all'opera, espellendo dall'opera seria ogni elemento comico, e costitui uno schema fisso di scena drammatica, separando l'azione affidata a recitativi dall'effusione lirica, confinata nelle arie conclusive. Tale schema condusse alla stilizzazione dell'opera seria, verso cui la generazione seguente assunse un atteggiamento critico. Si puo dire che la storia dell'opera sia quella del cambiamento dell'equilibrio fra musica e parole. Un determinato equilibrio in un'epoca puo apparire sorpassato agli occhi della generazione seguente. Da questo punto di vista, entrambe le riforme, cioe la riforma metastasiana e quella successiva a Metastasio, possono essere meglio intese. In altri termini, una parte della critica verso le opere metastasiane puo essere stata dovuta alla differenza di equilibrio nelle due epoche. Ora il Settecento el'Ottocento sono entrambi ricordi gia lontani. Soltanto adesso possiamo rivedere le opere di Metastasio e capire la ragione della grandissima popolarita di cui godette nel suo tempo, tenendo conto dell'ambiente culturale e sociale del tempo quando la gente si godeva le opere come puro divertimento (parlando e mangiando e divertendosi se non ascoltando le arie dei cantanti popolari). In questo studio ho cercato di analizzare l'effetto drammatico delle arie nelle opere metastasiane, essendo queste il punto essenziale della sua riforma e anche l'oggetto della critica del tempo seguente. L'opera qui scelta e Adriano in Siria (Adriano in breve), messa in scena per la prima volta a Vienna nel 1732 nella sua eta d'oro. Secondo il suo schema, e normale che nei recitativi l'azione proceda e nelle arie conclusive (cioe l'effusione lirica alla fine di una scena) si fermi, e che dopo avere cantato le arie i cantanti escano di scena. Seguendo il costume del suo tempo, l'aria e "da capo aria", e si compone di due strofe, la prima delle quali e ripetuta dopo la seconda. Adesso vediamo come si realizza lo schema in Adriano. Per prima cosa, quasi tutte le arie sono composte di due strofe, adatte alla struttura di"da capo aria". Inoltre, dopo quasi tutte le arie, i cantanti escono di scena. Quindi il pubblico aspetta naturalmente l'uscita del cantante dopo ogni aria. La sola eccezione e l'aria di Aquilio (3-2), dopo la quale Aquilio nell'allontanarsi incontra Adriano, la cui comparsa deve essere inaspettata non solo per Aquilio ma anche per il pubblico. In terzo luogo, la maggior parte delle arie appartiene al tipo che non fa procedere l'azione. Nelle arie tipiche come queste, spesso con metafore, gli affetti dei personaggi fanno presa direttamente sul pubblico. Tale alternanza dei recitativi delle arie crea un ritmo di tensione e rilassamento. Certamente questo ritmo, diverso da quello dei drammi moderni, e difficile per noi capirlo. Ma una volta accettatolo, potremo goderne cosi com'e. Bisogna riconoscere qualche merito in questo tipo di aria, presentata con metafore o espressioni comuni. Alcune arie sparse in atti diversi possono dare rilevanza al tema o all'opera (p. es. le arie di 2-12, 3-6, 3-7). Inoltre, le arie potrebbero dare ai poeti la misura di comunicazione diretta dal palcoscenico alla sala. Oltre a cio, Metastasio tenta talvolta di lisciare l'alternanza fra i recitativi e le arie inserendovi parole comuni. Parliamo ora delle arie non tipiche, quelle che non fermano l'andamento del dramma. In Adriano, quasi un quarto di tutte le arie appartengono a questo gruppo.</p><p>(View PDF for the rest of the abstract.)</p>
- 著者
- Samar Habib
- 出版者
- Routledge
- 巻号頁・発行日
- 2009
- 著者
- 吉田 陽祐 多田 昌裕 野間 春生 野田 賢
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.20, pp.5-8, 2011-05-20
近年,自動車や道路に対して様々な改良がなされた結果,交通事故件数は減少傾向にあるが,依然として高い水準を保っている.これに対し筆者らは,装着型センサで計測した運転行動データに加え,交差点のもつ地形的特性や周辺交通状況をも考慮した運転技能評価手法により,ドライバーの安全意識の向上を図るアプローチを提案している.今回,予防安全面から見て提案手法による評価がどの程度意味のあるものなのか,その有用性を調べるため,教習所指導員による主観的な技能評価との比較を行った.38人のドライバーを被験者とした公道走行実験の結果,安全運転の専門家である指導員の評価結果と相関係数0.71の関連がある事を示し,提案手法の予防安全面での有用性を確認した.
5 0 0 0 OA エイコサペンタエン酸の連用が喘息患者白血球のロイコトリエン産生能に及ぼす影響
- 著者
- 榊原 博樹 廣瀬 邦彦 松下 兼弘 中村 慎吾 佐藤 元彦 加古 恵子 末次 勸
- 出版者
- The Japanese Respiratory Society
- 雑誌
- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.395-402, 1995-04-25 (Released:2010-02-23)
- 参考文献数
- 20
気管支喘息患者10名にエイコサペンタエン酸エチルエステル (EPA-E) 製剤 (MND-21) を1日2.7g, 12週間投与した. この間, 喘息症状, 血清の脂肪酸濃度, および calcium ionophore A23187で刺激された白血球のロイコトリエン (LT) 産生能を測定した. コントロールとして, EPA-Eを内服していない39名の気管支喘息患者から得られた白血球を使用した. LT産生量は逆相高速液体クロマトグラフィーにより測定した. EPA-Eの内服で血清中のEPA濃度は3.3倍に増加した. EPA-E内服4週間後の白血球のLTC4およびLTB4産生量 (それぞれ53.5±23.3ng/107cellsと24.9±12.4ng/ao7cells) はコントロール (それぞれ124.4±91.6ng/107cellsと58.3±34.8ng/107cells) と比べて有意に減少した. 4週間のEPA-E内服で有意なLTC5, およびLTB5の産生が認められたが僅かであった (それぞれ6.5±1.9ng/107cellsと4.6±2.7ng/107cells). 臨床症状の改善はEPA-E投与2ヵ月後に認められたが, その効果は一時的であった.
- 著者
- 余頃 祐介
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.43-52, 2016-04-01 (Released:2016-04-01)
- 参考文献数
- 8
2015年のDOIアウトリーチ会議は,ジャパンリンクセンターのホストにより東京で2015年12月3日に開催された。そこでは,「研究データへのDOI登録実験プロジェクト」の最終報告に加えて,海外のDOI登録機関から日本のコミュニティーに対して,そのユースケースを交えたDOI登録のメリット,DOI登録対象の多様性について紹介があった。
5 0 0 0 昭和41年「丙午」に関連する社会人口学的行動の研究
- 著者
- 坂井 博通
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.29-38, 1995
近年「丙午」研究の範囲が広がり, 1906年と1966年以外の「丙午」にも明かりが投げかけられると同時に1966年の「丙午」に関しては,ミクロデータを用いて出生間隔の研究もなされ始めた。しかし,今までの「丙午」研究は,次の3つの視点(1)「丙午」の影響が及んだ範囲, (2)「丙午」生まれの子ども側から見た特徴, (3)「丙午」が与えた社会人口学的影響,が欠けていると考えられるために, 1966年の「丙午」を例に検討を行った。「丙午」の影響が及んだ範囲に関しては,主に人口動態統計を用いて,「丙午」を含む前後20年の出生数,出生性比の動向を観察した結果, (1-1)在日韓国・朝鮮人や在日中国人, (1-2)外国在住の日本人, (1-3)非嫡出子に関しても「丙午」の影響が見られたことを確認し,「丙午」迷信の内容が,マスコミだけでなくパーソナルな伝播により普及した可能性が大きいことを示唆した。また,「丙午」の影響測定には,出生数と出生性比の両方を検討する必要を述べた。「丙午」生まれの子ども側から見た特徴に関しては,主に厚生省人口問題研究所が1985年に行った「昭和60年度 家族ライフコースと世帯構造変化に関する人口学的調査」(サンプル数7,708)の全国調査の分析により,他の年次生まれの子どもと比較して,「丙午」生まれの子どもは, (2-1)父方のおじ,おばは多くないが,母方のおじ,おばが多く,その母親の出産意欲に母親自身の兄弟姉妹数が正の影響を及ぼした可能性のあること, (2-2)特に第2子の場合,男女とも兄弟姉妹数が多いこと, (2-3)父がホワイトカラーの割合が大きく,迷信から自由な出産が多かった可能性があること, (2-4)「丙午」前後生まれの者も含めて「丙午」の迷信をよく知り,さらに,自分も「丙午であっても出産した」と答える割合が大きい,という知見を得た。「丙午」と関連する社会人口学的影響に関しては,人口動態統計と人口移動統計により,「丙午」の年において, (3-1)例年より低い3月の出生性比と例年より高い4月の出生性比, (3-2)低い移動性比, (3-3)女子の自殺の増加,自殺率の上昇, (3-4)母子世帯の増加と翌年の減少,「丙午」と翌年の性病罹患数の増加,を見出した。その原因に関しては,それぞれ,「丙午」と関連させて,「丙午」年度生まれの女子を忌避する届出操作,出産を控えた女子の人口移動の活発化,女性の価値の低下,家庭内禁欲に伴う家庭外性行動の活発化の観点から論じた。
5 0 0 0 低線量放射線の生物影響とトリチウム研究
- 著者
- 田内 広 馬田 敏幸 立花 章
- 出版者
- プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 = Journal of plasma and fusion research (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.2, pp.119-124, 2012-02-25
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
核融合炉で利用されるトリチウムの量は少なくないことから,低濃度かつ少量のトリチウムによって生物が影響を受けるのか,そしてもし影響が出るのであれば,それはどのくらいの量(線量率)を超えれば生じる可能性があるのか,ということを科学的データによって明らかにすることが求められている.低線量放射線被ばくによる生体影響研究の現状と,これからのトリチウム生物学の方向について概説する.
5 0 0 0 OA 表紙生成エンジンを用いた二次元配置型 Web キュレーションシステムの開発
- 著者
- 重田 桂誓 松村 敦 宇陀 則彦
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.609-623, 2013-02-15 (Released:2013-03-04)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
現在,Web コンテンツを対象としたキュレーションが注目されている.キュレーションとは,あるテーマに対して人が独自の視点でコンテンツを取捨選択し,1つにまとめることである.キュレーションにおいては,このようなコンテンツを解釈する視点であるコンテキストが重要とされている.しかし,Naver まとめをはじめとする既存サービスでは,多様なコンテキストを表現できない.さらに,コンテキストの直感的な把握ができないため,試行錯誤しながらよりよいキュレーションを行うことが困難である.この問題を解決するために,本研究では表紙生成エンジンを用いた二次元配置型 Web キュレーションシステムを開発した.二次元配置は Web コンテンツの自由なレイアウトやキュレーションされたページ全体の俯瞰を可能にする.一方,Web ページの表紙は,画像やテキスト,色を組み合わせて生成するため,個々のページの内容やコンテキストの直観的な把握を助ける.本システムの有効性を評価するため,学生 16 名を対象に Naver まとめとの比較実験を行った.その結果,本システムの方が多種多様な表現によるキュレーションが行われ,また,まとめたページに含まれる視覚的要素の割合も高かった.さらに,本システムの方がコンテンツの見た目や直観性を意識してキュレーションする傾向も確認できた.
5 0 0 0 OA 教皇レオ9世と聖職者「独身」制
- 著者
- 尾崎 秀夫
- 出版者
- 神戸海星女子学院大学
- 雑誌
- 神戸海星女子学院大学研究紀要 (ISSN:13468154)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.31-49, 2006
5 0 0 0 IR 新潟市の女性シャーマンとその依頼者について
- 著者
- 佐藤 憲昭 サトウ ケンショウ Sato Kensho
- 出版者
- 駒澤大学総合教育研究部文化学部門
- 雑誌
- 駒澤大学文化 = Komazawa University culture (ISSN:02896613)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.1-26, 2016-03